先日は「義理と人情」について記事を書きました。
きょうは「義理」について考えてみたいと思います。
またしても、今回は「義理」を「義」と「理」とに分けて考えてみましょう。
「義」とは何でしょうか?
いま、手元にある漢和辞典を見てみましょう。
「義」の言葉には「正義、義務、忠義、義侠、義兄」などの熟語があります。
そして、この言葉にはいくつかの意味がありましたが、その中で次のように説明されたものがありました。
「②正しい、正しいすじみち、③ みち、人として行わなければならない道」などとあったのです。
任侠映画で主人公が単身で敵陣に乗り込む行動を支える原理は何だろうかと、先日の記事で問いました。
この場合、相手に非があると感じた主人公が取る行動には、二つの選択肢があります。
相手の非を公権力により裁定してもらう方法がまず考えられます。
市民生活の中では通常の市民のとる態度がそれにあたります。警察や裁判所に相手を訴えることです。
しかし、映画の中の主人公はなぜか、それをしません。
それには次の理由が考えられます。
それは、自分が世話になった人には、公(おおやけ)の力ではなく自分自身が恩を返さなければならないという不文律の世界に彼がいることを自覚しているからなのです。
主人公は「義理」の中の「義」を「理」として悟ったから、敵陣に単身で乗り込むように自分を駆り立てたのだと考えることが出来ます。
このことは何を意味しているのでしょうか?
まずは、「個と公権力との関係」と考えてみましょう。
原初的な「共同体」が「市民社会と公権力」とにはっきりと分離されるようになったのは、近世以降になってからの事です。
社会の中での個人間または集団間でのトラブルが起きた時,その解決方法を、それらの個人や集団の成員が自分たちの手で解決すのではなく、お互いが納得できる規範に基づく方法により解決するようになっていきます。
「共同的な意思に基づく規範」はその後、「法律」となってゆくのです。
そして、自分たちが作り出した「規範」は作り出した本人たちの行動をも制約してゆくようになります。
自分たちが作り出したものに自分たちが縛られる状態となっていったのです。
市民社会での「私怨」を市民個人が解決しようとすることが、公権力により制限されていったのです
個人の恨みを個人が晴らすことが出来なくなっていったのです。
その代替え策として、その権利を公権力に委ねる方法として、法の整備が行われたと考えられます。
江戸時代の「大岡裁き」や「水戸黄門」などの行動がそれらの「公権力の行使」になるのでしょう。
この観点からすると、映画の中の主人公は公権力の行使に違反をしているのですが、そもそも「公と私」との区別の外側にいる人にとっては、権力は自ら作り出さなければならない事になるわけです。
そのよう考えると「任侠映画」でとる主人公の行動も理解可能となります。
「任侠映画」をこのように観る人などはおそらく少ないとは思いますが、任侠映画の観方の一つと考えられます。
きょうは「義理」について考えてみたいと思います。
またしても、今回は「義理」を「義」と「理」とに分けて考えてみましょう。
「義」とは何でしょうか?
いま、手元にある漢和辞典を見てみましょう。
「義」の言葉には「正義、義務、忠義、義侠、義兄」などの熟語があります。
そして、この言葉にはいくつかの意味がありましたが、その中で次のように説明されたものがありました。
「②正しい、正しいすじみち、③ みち、人として行わなければならない道」などとあったのです。
任侠映画で主人公が単身で敵陣に乗り込む行動を支える原理は何だろうかと、先日の記事で問いました。
この場合、相手に非があると感じた主人公が取る行動には、二つの選択肢があります。
相手の非を公権力により裁定してもらう方法がまず考えられます。
市民生活の中では通常の市民のとる態度がそれにあたります。警察や裁判所に相手を訴えることです。
しかし、映画の中の主人公はなぜか、それをしません。
それには次の理由が考えられます。
それは、自分が世話になった人には、公(おおやけ)の力ではなく自分自身が恩を返さなければならないという不文律の世界に彼がいることを自覚しているからなのです。
主人公は「義理」の中の「義」を「理」として悟ったから、敵陣に単身で乗り込むように自分を駆り立てたのだと考えることが出来ます。
このことは何を意味しているのでしょうか?
まずは、「個と公権力との関係」と考えてみましょう。
原初的な「共同体」が「市民社会と公権力」とにはっきりと分離されるようになったのは、近世以降になってからの事です。
社会の中での個人間または集団間でのトラブルが起きた時,その解決方法を、それらの個人や集団の成員が自分たちの手で解決すのではなく、お互いが納得できる規範に基づく方法により解決するようになっていきます。
「共同的な意思に基づく規範」はその後、「法律」となってゆくのです。
そして、自分たちが作り出した「規範」は作り出した本人たちの行動をも制約してゆくようになります。
自分たちが作り出したものに自分たちが縛られる状態となっていったのです。
市民社会での「私怨」を市民個人が解決しようとすることが、公権力により制限されていったのです
個人の恨みを個人が晴らすことが出来なくなっていったのです。
その代替え策として、その権利を公権力に委ねる方法として、法の整備が行われたと考えられます。
江戸時代の「大岡裁き」や「水戸黄門」などの行動がそれらの「公権力の行使」になるのでしょう。
この観点からすると、映画の中の主人公は公権力の行使に違反をしているのですが、そもそも「公と私」との区別の外側にいる人にとっては、権力は自ら作り出さなければならない事になるわけです。
そのよう考えると「任侠映画」でとる主人公の行動も理解可能となります。
「任侠映画」をこのように観る人などはおそらく少ないとは思いますが、任侠映画の観方の一つと考えられます。



















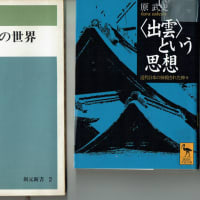








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます