世の中にあるものは、一部の例外を除いては立体として存在しています。
ヒトや人が造った人工物などや自然そのものも立体的に存在していると考えるのが自然です。
ところが絵画や写真は立体物を描写するのには、平面的にしか描けない訳です。
アルタミラの洞窟に描かれた動物の絵は足が4本とも平面的に描かれていますね。
幼い子供に犬や猫の絵を描かせてみるとやはり動物の足を4本とも平面的に描くことがあります。
このことは何を意味しているのでしょうか。
それはまず、地面上を動く哺乳動物には4脚の足がある事を観察者が認識している事が必要です。
動物に正対している時や真横から観察している時には、2本にしか足が見えない時がありますが、観察者は動物には足が4本ある事を知っているのです。
ですから、古代人や幼い子供が動物を描く時に、足が4本の絵を描いてしまうのです。
このことは、それを観察している人の認識が正しくない事を意味している訳ではありません。
むしろ、正しい認識なのかも知れません。
私たちは、それらの動物を絵に描く時には、一般的には立体的に表現しようと意図的に遠近法で絵を描きます。
このことは、物を見た時には、物には立体感がある事を、認識しているからなのです。
しかし、そのことは人が生まれつき持っている物の見方ではなく、学習により獲得した能力のように思われるのです。
物を立体としてとらえることは、観察と学習を繰り返すことにより備わってきた能力のように思われるのです。
絵画や写真をいかにも立体的にそこに在るかのように表現する仕方は、古代人や幼い子供にはまだ備わっていないから、と考えることが出来ます。
さて、わたくしは趣味で写真を撮ることがあります。
肉眼で見た光景とそれが写真としてプリントされた時の印象が違って感じることがあります。
これは、ヒトの眼が2眼であり、しかも平面的に両目の位置が離れている事に原因があります。
ヒトの眼は、初めから立体視が可能なようになっているのです。
それに対してカメラのレンズは一眼なのです。
はじめからカメラは立体視出来るようには、なっていない訳です。
ですからカメラで風景を立体的に撮ろうと思えば、それなりの工夫が必要になってきます。
遠近感を出すために工夫を凝らさなければならないのです。
近くにあるものをはっきりとさせ、遠くにあるものをぼんやりと撮るテクニックがそれです。空気遠近法と呼ばれている遠近技法です。
これは、元々は絵画での表現技法のひとつでした。それを写真を撮る人は意識しないで、利用しているのです。
写真展などで風景を撮った作品を見れば、上位に選ばれる作品には意図的に遠近法を取り入れたものが多いのも、納得できるのです。
つたない写真ですが、わたくしが昨年撮った山の写真を見ていただきます。
菜の花畑の向こうに、鳥海山が写っているものです。

撮った本人は好みではないのですが、どうゆう訳かこの写真を地元の観光協会主宰のコンテストに出したところ、入選してしまったのです。
観光ポスターにでも使うことが出来るだろうとの判断なのかも知れませんね。
風景写真は立体的に撮る方法としては、先に述べた遠近法が使えますが、人物写真の場合は簡単にはいきません。
明かりが少ない室内でストロボ光を直接対象の人物に当てると、必ずと言って良いほど平面的な描写の写真になってしまいます。
色んな事を考えるのは、老化の防止にも役立つだろうと始めた写真ですが、何をするにせよ簡単にはいかないものですね。
ヒトや人が造った人工物などや自然そのものも立体的に存在していると考えるのが自然です。
ところが絵画や写真は立体物を描写するのには、平面的にしか描けない訳です。
アルタミラの洞窟に描かれた動物の絵は足が4本とも平面的に描かれていますね。
幼い子供に犬や猫の絵を描かせてみるとやはり動物の足を4本とも平面的に描くことがあります。
このことは何を意味しているのでしょうか。
それはまず、地面上を動く哺乳動物には4脚の足がある事を観察者が認識している事が必要です。
動物に正対している時や真横から観察している時には、2本にしか足が見えない時がありますが、観察者は動物には足が4本ある事を知っているのです。
ですから、古代人や幼い子供が動物を描く時に、足が4本の絵を描いてしまうのです。
このことは、それを観察している人の認識が正しくない事を意味している訳ではありません。
むしろ、正しい認識なのかも知れません。
私たちは、それらの動物を絵に描く時には、一般的には立体的に表現しようと意図的に遠近法で絵を描きます。
このことは、物を見た時には、物には立体感がある事を、認識しているからなのです。
しかし、そのことは人が生まれつき持っている物の見方ではなく、学習により獲得した能力のように思われるのです。
物を立体としてとらえることは、観察と学習を繰り返すことにより備わってきた能力のように思われるのです。
絵画や写真をいかにも立体的にそこに在るかのように表現する仕方は、古代人や幼い子供にはまだ備わっていないから、と考えることが出来ます。
さて、わたくしは趣味で写真を撮ることがあります。
肉眼で見た光景とそれが写真としてプリントされた時の印象が違って感じることがあります。
これは、ヒトの眼が2眼であり、しかも平面的に両目の位置が離れている事に原因があります。
ヒトの眼は、初めから立体視が可能なようになっているのです。
それに対してカメラのレンズは一眼なのです。
はじめからカメラは立体視出来るようには、なっていない訳です。
ですからカメラで風景を立体的に撮ろうと思えば、それなりの工夫が必要になってきます。
遠近感を出すために工夫を凝らさなければならないのです。
近くにあるものをはっきりとさせ、遠くにあるものをぼんやりと撮るテクニックがそれです。空気遠近法と呼ばれている遠近技法です。
これは、元々は絵画での表現技法のひとつでした。それを写真を撮る人は意識しないで、利用しているのです。
写真展などで風景を撮った作品を見れば、上位に選ばれる作品には意図的に遠近法を取り入れたものが多いのも、納得できるのです。
つたない写真ですが、わたくしが昨年撮った山の写真を見ていただきます。
菜の花畑の向こうに、鳥海山が写っているものです。

撮った本人は好みではないのですが、どうゆう訳かこの写真を地元の観光協会主宰のコンテストに出したところ、入選してしまったのです。
観光ポスターにでも使うことが出来るだろうとの判断なのかも知れませんね。
風景写真は立体的に撮る方法としては、先に述べた遠近法が使えますが、人物写真の場合は簡単にはいきません。
明かりが少ない室内でストロボ光を直接対象の人物に当てると、必ずと言って良いほど平面的な描写の写真になってしまいます。
色んな事を考えるのは、老化の防止にも役立つだろうと始めた写真ですが、何をするにせよ簡単にはいかないものですね。



















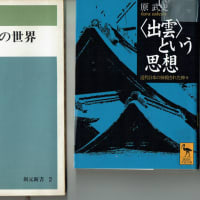








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます