
昨日の陽気に誘われて、畑仕事の準備をしました。まずは耕耘機の整備です。
例年、初めて耕運機を始動させる時には必ずと言って良いほど、不調だったのです。
これは機械が古くなっている為もありますが動かさない期間が数ヶ月もの長期に渡っていることにも原因があるのでしょう。
我が家で使用している耕運機はマメトラと言うメーカーの物です。
マメトラ農機と言う農機具メーカーは一般には馴染みのないメーカー名ですが、かなり前から工場が秋田県南部の象潟にあります。その名のとおり小型の農機具専門メーカーのようです。
この耕運機の整備をしました。一年間もの間オイル交換なしで駆動させていたのでまずはオイル交換と行きましょう。

画像に見える黄色の部品がオイル注入口の蓋です。その左下にオイル排出のドレンプラグがありますので、そこを緩めて取り外しオイルを排出します。
オイル受けの容器には小型の洗面器を使いました。耕運機本体を前かがみに傾けてるとオイルが出てきます。
しばらく放置してオイルが滴り落なくなったならドレンプラグを元に戻し、新しいオイルを入れましょう。
オイルの全容量がどのくらいなのかの記載は機械のどこにもラベルがありません。排気量が100CCほどのエンジンなのでどんなに入ってもオイルの容量は1000CC未満と思われるので、まずは500CCを計量して注入してみます。この時、機械は水平にしておきます。オイル注入口のいっぱいまで入れましたが500CCまでは入りませんでした。約200CCほど余りました。
その後、各部の清掃をしたりVベルトの張りの調整などをして、整備は完了です。
小型耕運機のクラッチの構造はVベルトのテンションで調整するようになっていますので、ベルトの摩耗や、伸びがあると動力がスムーズに伝わりませんのでベルトのテンションも調整しました。テンションの調整はエンジン本体をスライドさせることで行います。微調整はテンションプリーの引き上げ位置をワイヤーの張りでも調整できるようになっています。

テンションローラーが上げると動力が伝わるようになっています。
移動用の車輪もつけました。

畑に耕運機を搬入したついでに畑の様子を見てみました。
次のようでした。

玉ねぎが順調に育っています。

同じネギ科のひろっこが育ちすぎていました。

水仙のつぼみが大きくなっていました。つくしも芽を出しています。ことしもスギナ退治の季節がやってくるのですね。
さて、表題の野菜の画像ですが秋田県ではこの作物を「ふくたち」と言っています。
これは前の年の冬にに収穫しないでおいた白菜の新芽がトウダチしたものなのです。トウダチして花が開花する寸前の物を摘み取り、おひたしや和え物などで食べます。
雪国の春一番の野菜なのです。
 にほんブログ村
にほんブログ村
例年、初めて耕運機を始動させる時には必ずと言って良いほど、不調だったのです。
これは機械が古くなっている為もありますが動かさない期間が数ヶ月もの長期に渡っていることにも原因があるのでしょう。
我が家で使用している耕運機はマメトラと言うメーカーの物です。
マメトラ農機と言う農機具メーカーは一般には馴染みのないメーカー名ですが、かなり前から工場が秋田県南部の象潟にあります。その名のとおり小型の農機具専門メーカーのようです。
この耕運機の整備をしました。一年間もの間オイル交換なしで駆動させていたのでまずはオイル交換と行きましょう。

画像に見える黄色の部品がオイル注入口の蓋です。その左下にオイル排出のドレンプラグがありますので、そこを緩めて取り外しオイルを排出します。
オイル受けの容器には小型の洗面器を使いました。耕運機本体を前かがみに傾けてるとオイルが出てきます。
しばらく放置してオイルが滴り落なくなったならドレンプラグを元に戻し、新しいオイルを入れましょう。
オイルの全容量がどのくらいなのかの記載は機械のどこにもラベルがありません。排気量が100CCほどのエンジンなのでどんなに入ってもオイルの容量は1000CC未満と思われるので、まずは500CCを計量して注入してみます。この時、機械は水平にしておきます。オイル注入口のいっぱいまで入れましたが500CCまでは入りませんでした。約200CCほど余りました。
その後、各部の清掃をしたりVベルトの張りの調整などをして、整備は完了です。
小型耕運機のクラッチの構造はVベルトのテンションで調整するようになっていますので、ベルトの摩耗や、伸びがあると動力がスムーズに伝わりませんのでベルトのテンションも調整しました。テンションの調整はエンジン本体をスライドさせることで行います。微調整はテンションプリーの引き上げ位置をワイヤーの張りでも調整できるようになっています。

テンションローラーが上げると動力が伝わるようになっています。
移動用の車輪もつけました。

畑に耕運機を搬入したついでに畑の様子を見てみました。
次のようでした。

玉ねぎが順調に育っています。

同じネギ科のひろっこが育ちすぎていました。

水仙のつぼみが大きくなっていました。つくしも芽を出しています。ことしもスギナ退治の季節がやってくるのですね。
さて、表題の野菜の画像ですが秋田県ではこの作物を「ふくたち」と言っています。
これは前の年の冬にに収穫しないでおいた白菜の新芽がトウダチしたものなのです。トウダチして花が開花する寸前の物を摘み取り、おひたしや和え物などで食べます。
雪国の春一番の野菜なのです。



















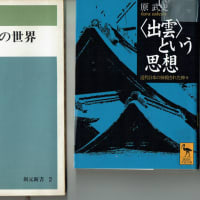









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます