
先日の日曜日に新しいタイヤの乗りごこちとハイドレーションシステムザックなどの使い勝手を試すのも兼ねてミニツーリングに行ってみました。
行った先は秋田県の北部に位置する八峰町(はっぽうちょう)の峰浜(みねはま)という所です。
東能代より八峰町へ向かう広域農道を進みますと峰浜の石川集落へと通ずる交差点があります。
そのあたりは能代市東雲(しののめ)という所で地形は台地になっていますので東雲台地と呼ばれているところです。ここには太平洋戦争中には訓練用の飛行場もあったそうです。戦後、その地区は開拓が進み、今では立派な農地になっています。その農地は水田は少なく、多くの部分は畑となっています。
茗荷やネギやキャベツなどの野菜の栽培が行われています。
この石川へと通ずる交差点のあたりは、一面茗荷畑が広がっていました。


秋田市近郊の農地はほとんどが水田ですので、こんなに広大な畑の景色を見れるのは少し驚きです。
さて、石川地区では以前よりそばを栽培していると聞いてましたので一度それを見たいと思っていたのです。
集落の中ほどに「そば」と名の付く看板を発見。

そばを栽培している農家の看板のようです。このあたりにそば畑があるのかしらとバイクを進めるが見当たりません。
尋ねようにも付近には人影も見えません。もう一箇所、訪ねてみたい所がありましたので先を急ぐことにしました。。石川集落の出口付近には次のような看板もありました。そばの里のかんばんです。

広域農道に戻り少し北上しますと水沢川の上流に「手這坂(てはいざか)」という集落があります
ここには100年以上もの年月を経た「茅葺民家」の集落があります。
かって、江戸時代の紀行家「菅井真澄(すがいますみ)」がここを訪れたときそのあまりに美しい集落のたたずまいに「桃源郷」のようだと評したところだそうです。
手這坂の集落の入り口には次のような案内看板があります。


「手這坂桃源郷」の由来も書かれていました。ここの「手這坂桃源郷」には現在は茅葺民家は4軒ありました。
いずれも築100年を越える旧い茅葺屋根の民家です。
菅井真澄の時代よりほとんど変わることの無いたたずまいで存在する茅葺屋根住居の集落は今まで見たことがありません。秋田県内には保存のために建物を移築した茅葺民家の建築物はいくつかありますが、それらの移築した「茅葺屋根」はその周囲には近代的な管理事務所があったりします。
保存された建物の玄関に通ずる小道がアスファルト舗装だったりするのが普通ですが、「手這坂桃源郷」にはそんなものは何にもありません。建物の窓がアルミサッシだったりとそこに住むための少しばかりの改変が施されてはいますがほとんどが原型を残している茅葺屋根の住居でした。
現在、この集落は元の住人は離村して無人となっています。2000年頃に最後の住民がこの地を離れた後は住民のいない無人地区となっていました。
その後、住居などを保存する方々の働きもあって、民家再生と周辺農地の再生作業も行われたこともあったようですが、今回(2012年7月)訪れたときには周辺農地には耕作された跡も無く草の生い茂るままでした。
しばらく民家を眺めたり写真を取ったりしていました。



このような形で無人の住居だけが残されています。
集落の一番奥にある住居まで来たときです。なにやら人が気配がします。車も留めてあるようです。庭先の木には子犬が繋がれているではありませんか。ここを管理するボランテアの方でも来ているのかなと思いながらその住居に近寄ると中から青年がひとり出てきました。
少し、会話を交わしたところによると、2週間前よりここに住み始めたそうです。これから周辺の耕作地を整備し何か植えてみたいとの話でした。ひとりでやるのは大変でしょう、誰か一緒に作業をする人はいるのかと尋ねたところもう一人来ることになっているとの事。電気や水道もあるそうです。固定電話も設置したそうですので、ここにしばらくは住んで見ようとの心つもりと拝見しました。
雪が降る季節は多分、かなり難儀をすることでしょうががんばってほしいものです。また、後日訪ねて来たい旨をその青年に告げそこを後にしました。
国道101号線沿いに石川集落で採れたそば粉を使用してそばを出している処がありますので、昼食はそこにしました。この場所は「おらほの館」といって旧峰浜村の物産館です。地区で採れた野菜などを主に販売している場所です。中に食堂も併設されています。特産の石川そばをメインにメニューをそろえてありました。
注文したのは「そばメシ定食」です。

出てきたのが上記のもの。
白米にそばの実を炊き込んだご飯とてんぷらそれにそばが付きます。そばは田舎そばそのもので色は黒っぽく太めです。上品な「そば懐石」などというものではありません。あくまで「そば定食」なのです。




メニューの写真と出された現物にはほとんど違いはありませんでした。価格にも納得。腹も納得。
帰りに山本郡、檜山より森岳に向かう羽州街道を通って来ましたがそこでひとつ新しい物を発見。
「大森柏原一里塚跡」というものですが、それについては又後日、「羽州街道」編の記事で紹介したいと思います。
 にほんブログ村
にほんブログ村
行った先は秋田県の北部に位置する八峰町(はっぽうちょう)の峰浜(みねはま)という所です。
東能代より八峰町へ向かう広域農道を進みますと峰浜の石川集落へと通ずる交差点があります。
そのあたりは能代市東雲(しののめ)という所で地形は台地になっていますので東雲台地と呼ばれているところです。ここには太平洋戦争中には訓練用の飛行場もあったそうです。戦後、その地区は開拓が進み、今では立派な農地になっています。その農地は水田は少なく、多くの部分は畑となっています。
茗荷やネギやキャベツなどの野菜の栽培が行われています。
この石川へと通ずる交差点のあたりは、一面茗荷畑が広がっていました。


秋田市近郊の農地はほとんどが水田ですので、こんなに広大な畑の景色を見れるのは少し驚きです。
さて、石川地区では以前よりそばを栽培していると聞いてましたので一度それを見たいと思っていたのです。
集落の中ほどに「そば」と名の付く看板を発見。

そばを栽培している農家の看板のようです。このあたりにそば畑があるのかしらとバイクを進めるが見当たりません。
尋ねようにも付近には人影も見えません。もう一箇所、訪ねてみたい所がありましたので先を急ぐことにしました。。石川集落の出口付近には次のような看板もありました。そばの里のかんばんです。

広域農道に戻り少し北上しますと水沢川の上流に「手這坂(てはいざか)」という集落があります
ここには100年以上もの年月を経た「茅葺民家」の集落があります。
かって、江戸時代の紀行家「菅井真澄(すがいますみ)」がここを訪れたときそのあまりに美しい集落のたたずまいに「桃源郷」のようだと評したところだそうです。
手這坂の集落の入り口には次のような案内看板があります。


「手這坂桃源郷」の由来も書かれていました。ここの「手這坂桃源郷」には現在は茅葺民家は4軒ありました。
いずれも築100年を越える旧い茅葺屋根の民家です。
菅井真澄の時代よりほとんど変わることの無いたたずまいで存在する茅葺屋根住居の集落は今まで見たことがありません。秋田県内には保存のために建物を移築した茅葺民家の建築物はいくつかありますが、それらの移築した「茅葺屋根」はその周囲には近代的な管理事務所があったりします。
保存された建物の玄関に通ずる小道がアスファルト舗装だったりするのが普通ですが、「手這坂桃源郷」にはそんなものは何にもありません。建物の窓がアルミサッシだったりとそこに住むための少しばかりの改変が施されてはいますがほとんどが原型を残している茅葺屋根の住居でした。
現在、この集落は元の住人は離村して無人となっています。2000年頃に最後の住民がこの地を離れた後は住民のいない無人地区となっていました。
その後、住居などを保存する方々の働きもあって、民家再生と周辺農地の再生作業も行われたこともあったようですが、今回(2012年7月)訪れたときには周辺農地には耕作された跡も無く草の生い茂るままでした。
しばらく民家を眺めたり写真を取ったりしていました。



このような形で無人の住居だけが残されています。
集落の一番奥にある住居まで来たときです。なにやら人が気配がします。車も留めてあるようです。庭先の木には子犬が繋がれているではありませんか。ここを管理するボランテアの方でも来ているのかなと思いながらその住居に近寄ると中から青年がひとり出てきました。
少し、会話を交わしたところによると、2週間前よりここに住み始めたそうです。これから周辺の耕作地を整備し何か植えてみたいとの話でした。ひとりでやるのは大変でしょう、誰か一緒に作業をする人はいるのかと尋ねたところもう一人来ることになっているとの事。電気や水道もあるそうです。固定電話も設置したそうですので、ここにしばらくは住んで見ようとの心つもりと拝見しました。
雪が降る季節は多分、かなり難儀をすることでしょうががんばってほしいものです。また、後日訪ねて来たい旨をその青年に告げそこを後にしました。
国道101号線沿いに石川集落で採れたそば粉を使用してそばを出している処がありますので、昼食はそこにしました。この場所は「おらほの館」といって旧峰浜村の物産館です。地区で採れた野菜などを主に販売している場所です。中に食堂も併設されています。特産の石川そばをメインにメニューをそろえてありました。
注文したのは「そばメシ定食」です。

出てきたのが上記のもの。
白米にそばの実を炊き込んだご飯とてんぷらそれにそばが付きます。そばは田舎そばそのもので色は黒っぽく太めです。上品な「そば懐石」などというものではありません。あくまで「そば定食」なのです。




メニューの写真と出された現物にはほとんど違いはありませんでした。価格にも納得。腹も納得。
帰りに山本郡、檜山より森岳に向かう羽州街道を通って来ましたがそこでひとつ新しい物を発見。
「大森柏原一里塚跡」というものですが、それについては又後日、「羽州街道」編の記事で紹介したいと思います。














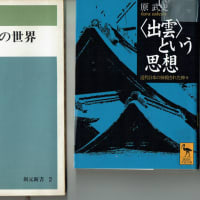






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます