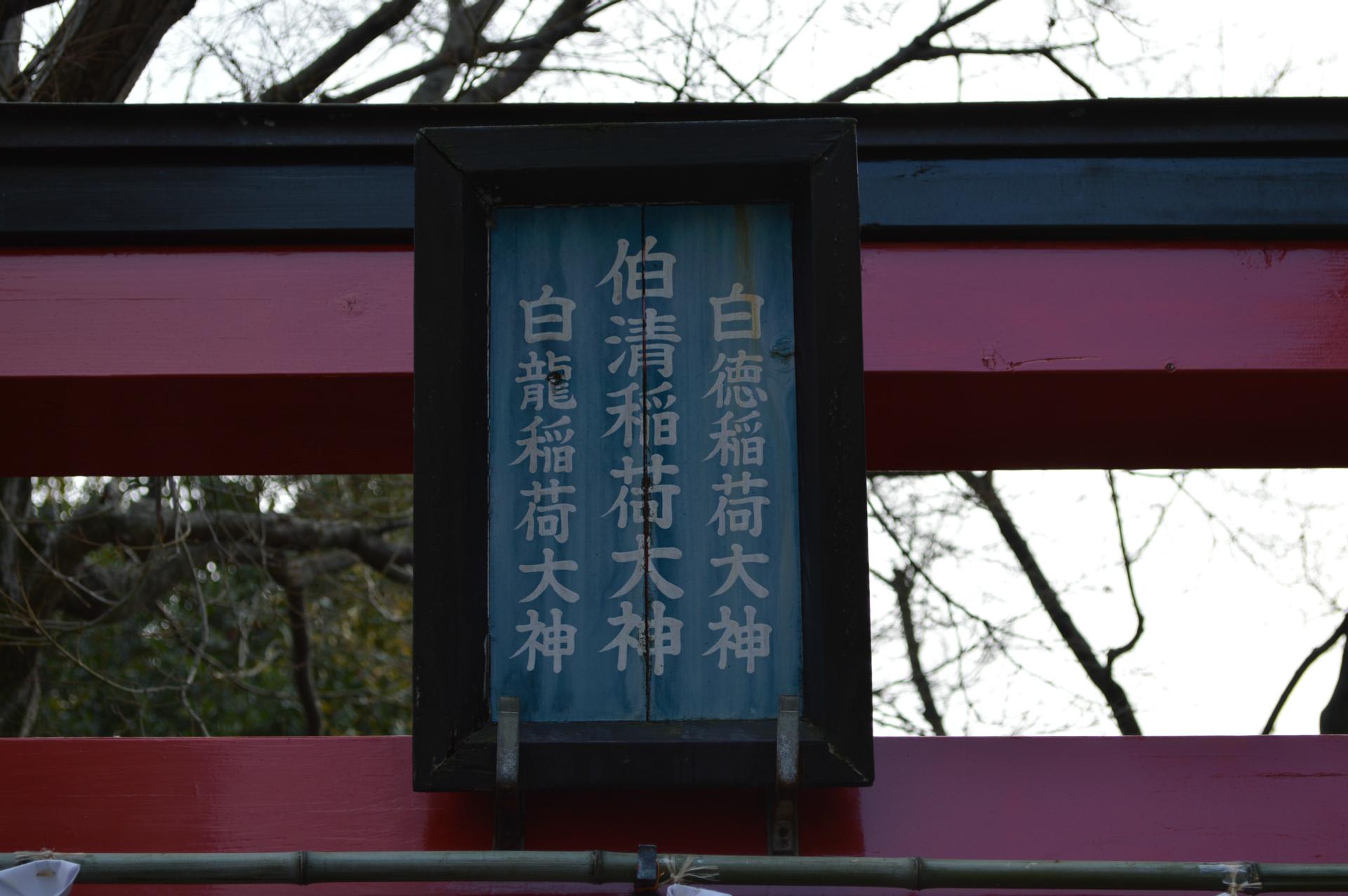クリックでワープします
2月13日 えっ 知らなかった 小野小町・・・
1月13日 梅宮大社 梅が見頃 に画像を追加しました
1月8日 高松神明神社 平清盛・源義朝が保元の乱のときに集まった陣地 その地を訪れました
画像追加しました
1月7日 ユニークなデザインの校舎 画像追加しました
12月13日 閑臥庵 黄檗宗 画像を追加しました
12月10日 三條南殿の遺址 三条烏丸 源頼朝はここで働いていた 建物の画像を追加しました
12月10日 修学院離宮 松の手入れ 画像を追加
12月7日 信行寺 浄土宗 伊藤若冲の天井画 画像を追加
11月23日 若一神社 平清盛ゆかりの地 御神木の楠は 西大路通りを迂回させた 画像を1枚追加
11月19日 蔵のある風景 65回 伊藤仁斎邸 に画像を1枚追加しました
11月8日 空也堂 空也上人ゆかりの寺 に画像を1枚追加しました
11月8日 茶屋四郎次郎邸宅跡 石碑 に記事を追加しました
11月6日 蔵のある風景 4 ビルの中に埋もれるように を画像を1枚追加いたしました
11月3日 天道神社 に秋の例祭の準備の様子を追加しました
11月3日 鹿王院 (ろくおういん) 名勝 鹿王院庭園 を改訂しました
11月1日 10月28日の記事 六条河原 昔は処刑場だった に記事を追加しました
11月1日 10月5日の記事 秦家住宅 明治初期の建物 に画像を追加しました
10月28日 4月7日の記事 椿寺 (地蔵院) 今が見頃 に 画像を追加しました
10月23日 6月9日の記事に 水火天満宮・・・ 登天石と桜 10月23日 追加しました に記事を追加しました
10月17日 8月21日の記事 五条天神社 に記事を少し追加しました
10月17日に 3月30日の記事 神泉苑 に 義経・弁慶・源平物語の記事を追加しました
10月17日 に 4月18日の記事 晴明神社 に 義経・弁慶・源平物語の記事を追加しました
10月5日に 5月21日の記事 智光院 に画像1枚追加しました
10月5日に 4月14日の記事 報土寺 すぐ近くに 重要文化財 に画像3枚追加しました
10月5日に 5月8日の記事 玉蔵院 にお彼岸の画像を1枚追加しました
10月5日に 5月10日の記事 善福寺 戌亥三十三所 第一番 にお彼岸の画像を1枚追加しました
9月24日 に 5月28日の記事 長尾天満宮 を更新しました 頼政の道の記事を追加しました
9月21日 に 6月7日の記事 成願寺 キリシタン墓碑が発見される ミニ三十三間堂を追加しました
8月1日 に 6月17日の記事 勤王画家 森寛斎 宅蹟 を更新しました 直しました
4月4日の記事 石碑 横井小楠 殉節地 を更新しました
8月13日 に 4月30日の記事 聚楽第 上杉家・直江家屋敷跡 を更新しました
8月14日 に 6月10日の記事 御土居堀の深さを感じさせる場所 反対柄からの画像を追加しました
8月20日に 5月9日の記事 光清寺 浮かれ猫、「心和の庭」 (重森三玲 作)
猫の絵馬を追加しましした
8月25日 に 5月13日の記事 妙泉寺 浮世絵師・西川祐信の墓所
墓所の案内
9月10日 に 9月10日の記事 河井寛次郎記念館 を更新しました
9月12日 に 9月10日の記事 河合寛次郎記念館 を更新しました
9月20日 に 5月21日の記事 真如院
9月21日 に 5月21日の記事 本圀寺跡 石碑 を更新しました
9月21日 に 6月5日の記事 朝の二条城前の様子 を更新しました