12月20日 (水曜日)
昨日は日中が晴れてきた。
父親の時代に植えた木々も大きくなって邪魔になった。
50年は経ったものもあって適時カットしてきたが
ここにきて自分の年齢を考えると無理も出来ない。
随分処理してきたがもともと周囲を綺麗にするのが苦手だ「ただ億劫」
困ったのは棕櫚「しゅろ」の木だ。
鳥が運んだ種が沢山芽を出して大きくなってしまった。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
低木は切った、それが狭い場所に重なってあって
枯れて邪魔になってきたので袋に詰め始めたが結構量があって面倒だ。
これがなければ木を植えるのもいいのだが・・
===============================
毎日新聞 余録
勘亭流で書いた看板を下げ、役者の似顔画を描いた大小の羽子板が並んでいる
「1億人の昭和史」に掲載。明治初年とみられる。
~~~~~~~~~~~~~
〇2023年に話題となった人物が描かれた「変わり羽子板」


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〇時代劇では「江戸八百八町」といわれるが、
●18世紀には町が1600以上あった。
●人口100万を上回る大都市。
●町奉行がにらみを利かせる一方、
●共に世襲の町年寄と町名主が「町民自治」で秩序を支えたといわれる
==============
▲斎藤月岑(げっしん)は明治まで生きた神田の名主。
文才にたけていた。
謎の絵師、写楽について「阿波侯の能役者也(なり)」と
唯一の手がかりを残し、
〇江戸市中の年中行事をまとめた「東都歳事記」を出版した。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▲12月18日は「納めの観音」の縁日。
浅草寺では前日から「年の市」が開かれた。
東都歳事記は約2キロ離れた上野の寛永寺まで店が並び、
人であふれたと記す。しめ飾りや破魔弓、羽子板など正月の縁起物が売られた
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▲浅草の羽子板市は江戸の歳末情緒を今に伝える。
明治期に雷門から本堂にかけての目抜き通りに羽子板を売る露店が並ぶ
ようになり、年の市の主役になっていったという
~~~~~~~~~~~~~~~~
▲元々は厄払いの意味を込めた正月の遊び道具。
江戸から明治にかけ、当代人気の歌舞伎役者を取り上げた押し絵羽子板が広まった。
藤井聡太8冠や大谷翔平選手らの「変わり羽子板」はその現代版だろう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今年は外国人観光客向けにQRコード決済も導入されたそうだ。
▲かつては浅草寺の後も神田明神や川崎大師など各地の寺社で年の市が開かれ、
人々が押し寄せた。近所のスーパーで正月飾りが買える現代も年の瀬のせわしなさは同じ。
新年に向けやり残したことがまだまだありそうだ。
<羽子板市 切られの与三は 横を向き>
石原八束(やつか)
================================
昨日は日中が晴れてきた。
父親の時代に植えた木々も大きくなって邪魔になった。
50年は経ったものもあって適時カットしてきたが
ここにきて自分の年齢を考えると無理も出来ない。
随分処理してきたがもともと周囲を綺麗にするのが苦手だ「ただ億劫」
困ったのは棕櫚「しゅろ」の木だ。
鳥が運んだ種が沢山芽を出して大きくなってしまった。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
低木は切った、それが狭い場所に重なってあって
枯れて邪魔になってきたので袋に詰め始めたが結構量があって面倒だ。
これがなければ木を植えるのもいいのだが・・
===============================
毎日新聞 余録

勘亭流で書いた看板を下げ、役者の似顔画を描いた大小の羽子板が並んでいる
「1億人の昭和史」に掲載。明治初年とみられる。
~~~~~~~~~~~~~
〇2023年に話題となった人物が描かれた「変わり羽子板」


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〇時代劇では「江戸八百八町」といわれるが、
●18世紀には町が1600以上あった。
●人口100万を上回る大都市。
●町奉行がにらみを利かせる一方、
●共に世襲の町年寄と町名主が「町民自治」で秩序を支えたといわれる
==============
▲斎藤月岑(げっしん)は明治まで生きた神田の名主。
文才にたけていた。
謎の絵師、写楽について「阿波侯の能役者也(なり)」と
唯一の手がかりを残し、
〇江戸市中の年中行事をまとめた「東都歳事記」を出版した。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▲12月18日は「納めの観音」の縁日。
浅草寺では前日から「年の市」が開かれた。
東都歳事記は約2キロ離れた上野の寛永寺まで店が並び、
人であふれたと記す。しめ飾りや破魔弓、羽子板など正月の縁起物が売られた
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▲浅草の羽子板市は江戸の歳末情緒を今に伝える。
明治期に雷門から本堂にかけての目抜き通りに羽子板を売る露店が並ぶ
ようになり、年の市の主役になっていったという
~~~~~~~~~~~~~~~~
▲元々は厄払いの意味を込めた正月の遊び道具。
江戸から明治にかけ、当代人気の歌舞伎役者を取り上げた押し絵羽子板が広まった。
藤井聡太8冠や大谷翔平選手らの「変わり羽子板」はその現代版だろう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今年は外国人観光客向けにQRコード決済も導入されたそうだ。
▲かつては浅草寺の後も神田明神や川崎大師など各地の寺社で年の市が開かれ、
人々が押し寄せた。近所のスーパーで正月飾りが買える現代も年の瀬のせわしなさは同じ。
新年に向けやり残したことがまだまだありそうだ。
<羽子板市 切られの与三は 横を向き>
石原八束(やつか)
================================




















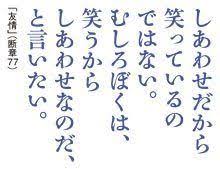

 プロだ!
プロだ!








