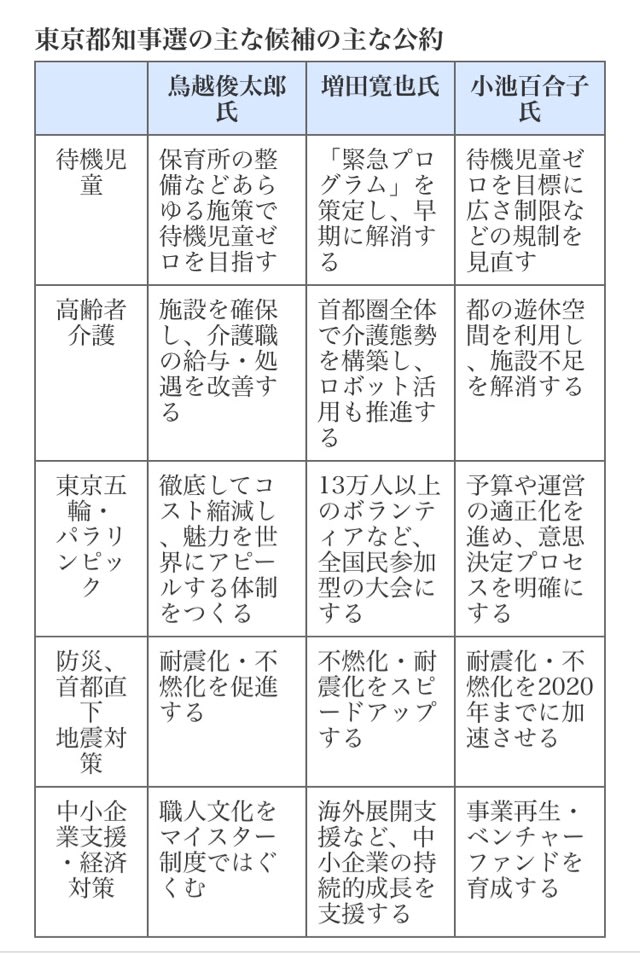脳動脈瘤の破裂 新技術で防ぐ
薄膜ステント治験→大きな瘤の血流遮断 立体画像撮影→患者ごとの効果予測
2016/7/24 3:30 日経朝刊
人間ドックの脳検査が普及し、脳動脈瘤(りゅう)が見つかる人が増えている。瘤(こぶ)が破裂すると、くも膜下出血を起こし命に関わる。治療では瘤への血流を抑える。国立循環器病研究センターは大きな瘤を新型のステント(網状の筒)で治す医師主導の臨床試験(治験)を5月に始めた。東京大学は治療効果を予測する研究に取り組む。脳動脈瘤が原因のくも膜下出血は毎年約2万人に達するとみられ、対策の重要性が増している。

脳動脈瘤は脳の動脈の一部が膨らんで瘤状になる病気だ。瘤ができる詳しい仕組みは不明だが、生まれつき動脈の壁の一部が弱いところに長い間血流が当たり続けてできるとする専門家が多い。「年齢が高いほど患者が増え、ほとんどが人間ドックで見つかる」(国循センター脳神経外科の佐藤徹医長)という。

瘤が破裂するとくも膜下出血を起こし、命を落とすリスクが高い。体のマヒや言語障害、視覚障害などの後遺症で悩む患者もおり、早期発見と治療が大切だ。
当初は脳動脈瘤の入り口の部分を金属のクリップで挟み破裂を防ぐ「クリップ術」が普及したが、頭蓋骨を開く手術が必要で体の負担が大きかった。
1990年代には脚の動脈からカテーテルを入れ、脳動脈瘤の中に細いコイルの束を入れて血栓を作り、破裂を防ぐ「コイル式閉塞治療」が普及した。
2010年代に入ると、コイルを脳動脈瘤内に入れても血流が再開しやすい欠点を克服するために、近くの血管をステントで覆って脳動脈瘤への血流を抑える手法も使うようになった。
それでも直径7ミリを超えるような大きな脳動脈瘤は血液の流入が止まらず、治療効果が上がらなかった。そこで国循センターの医師主導治験では、表面を厚さ20マイクロ(マイクロは100万分の1)メートルのポリウレタンの2枚の薄膜で覆ったステントを使い血流をしっかりと抑える。新型のステントは「多孔化カバードステント」という。
薄膜はレーザーで直径100マイクロメートルの穴を多数開けた。「穴を通じてステントの外の血管壁から栄養が供給され、ステントの内壁を覆うように血管内皮細胞が増える」と佐藤医長は話す。ウサギやイヌの実験では内壁に血管内皮ができ、血栓ができにくい構造になった。
医師主導治験は5月からの2年間で、大きさが7ミリを超える脳動脈瘤を持つ20~75歳の12人が対象だ。物が二重に見える、まぶたが垂れ下がる、額の左右どちらかがしびれるなどの症状を持つ患者にステントを置き、頭の奥深くの内頸(けい)動脈や椎骨(ついこつ)脳底動脈の脳動脈瘤を治療する。180日後までの安全性と性能評価を目指す。治験終了後は速やかに国へ薬事申請して実用化する計画だ。
□ □
脳動脈瘤は破裂してからでは対応が難しく、早めに備えておく必要がある。
東京大学の大島まり教授や庄島正明特任講師は、患部の撮影画像をもとにコンピューターの模擬実験を用い、脳動脈瘤が破裂するリスクの評価方法や治療効果の判定法の研究を進めてきた。
例えば、従来のコイル式閉塞治療で脳動脈瘤に詰めたコイルが定着して血流を滞らせて血栓を作るか、血流に押されてひずみ、血流が再開して治療効果が失われるかを見極めようとしている。
「脳動脈瘤内の血流の速度や、血が固まり血栓ができる仕組みなどを手掛かりに予測する」と庄島特任講師は話す。
5月に東北大学などと臨床研究を始めた。2017年3月末までに約200人で実施する。造影剤を脳動脈瘤へ入れ、その立体画像を撮る。血管や脳動脈瘤のCAD(コンピューターによる設計)データを得て、瘤の中の状態を計算する。
□ □
脳動脈瘤には、放っておいても破裂しないタイプもあるという。従来は脳動脈瘤の大きさや形から治療が必要かどうかを判断するしかなかった。模擬実験が普及すれば最適な治療法を選べる。
庄島特任講師は「治療方法を決めるうえで模擬実験は有力な手立てになると期待する人が多い」と話す。
今後、高齢化の進展に伴い、脳動脈瘤の対策は一段と重要になってくる。いつ破裂するかもわからず、時限爆弾ともいわれる病気に手をこまぬいているわけにはいかない。
(草塩拓郎)