※ジョン・ウー監督ではなく、まちがいなくジョン・ウェットンのサインである
たまたま、いま昔のKing CrimsonのCDを聴いてるのでそれについて書こう。こりゃ、1973年11月23日、アムステルダムで彼らが演奏したときのブートレッグだ。青春である。
とにかくリズムセクションのからみ方がとんでもない。もう、ブイブイいわせてる。もちろんBassは全盛期のジョン・ウェットン、Drumsはビル・ブラッフォードだ。
そこにあやしく乗っかってくるロバート・フリップのGuitarと、デビッド・クロスのViolinがこれまたイカすバンド天国(死語以前の問題)になっている。
こんな攻撃的なリズムセクションは現代でもめったにいないだろう。そんなわけで私の中のジョン・ウェットンは1970年代で完全に時計が止まっている。それ以降の彼はもうはっきり言って「う○こ」だ。(食事中のみなさん失礼します)
で、御多分に洩れず、その当時彼がリリースしたソロアルバムも、フニャフニュした甘ったるいだけの単なるポップスだった。
かといって特筆するほどメロディーラインが美しいわけでもなんでもない。ひとことでいえば、毒にも薬にもならないシロモノだった。
そんな見る影もなくなった彼が、見る影もないつまらないソロアルバムを作り、そのプロモーションのために来日したときの話だ。もう10年位前のことだろう。
あのころの私はまだ若く、ちょうど自分の仕事に対して考えるところがあった時代だ。
それはともかく。
彼は宣伝するために来日したわけだから、いろんなメディアに声をかけて取材を受けている。私はそのとき、ある雑誌の仕事で彼にインタビューした。このブログでは、そのとき記事に書かなかったことを書こう。
私はいちおう基本的に仕事とプライベートを区別している。仕事で会った人間にサインなんてもらったことはない。後にも先にもあれ1度だ。
なのに自分の汗臭いベースギターのストラップを持ってってサインしてもらうわ、「太陽と戦慄(Larks' Tongues in Aspic)」(1973年)、「暗黒の世界(Starless And Bible Black)」(1974年)のレコードをバッグから取り出し「さあここにサインをくれ」とかもうめちゃくちゃ。(もちろんインタビューが終わった後の話ではあるが)。
※「太陽と戦慄」(1973年)、「暗黒の世界」(1974年)とサイン。
やっぱり「ジョン・ウー」監督に見える
おまけに大変申し訳ないことに、彼自身やその取材をセッティングしてくれたレコード会社(だったか音楽事務所だったか? もう忘れた)の意に反し、私はそんなクソみたいなソロアルバムの話なんか聞く気は毛頭ない。
先方がニューアルバムの話を聞いてもらってバンバン書いて(宣伝して)ほしいと思っているのはもちろんだ。なんでも来日した彼は、1日に10本からの取材をこなしてるらしい。
そのとき取材した人たちはみんな一様にソロアルバムについて聞いたはずだ。ウェットンさんも相手が変わるたんびに何度も同じことをみんなに答えて、プロモーションのためとはいえ内心うんざりしていただろう。
が、私にはそんな気はハナからない。なんせ私は怒ってるんだ。「怒ってる」ってのは彼に対してはもちろんだが、当時の自分自身に対してもそうだった。私はとにかく「あてどもなく怒りに行った」のだ。
握手したあと私が聞いたのは、King Crimson時代の話ばかりだった。
「ナーバスな音を使ってたよね?」って聞くと、彼は「その通りだ」とかなんとかいってわざわざ自分のBassをケースから取り出し、フレットを押さえてスケールを教えてくれる。なかなかフランクなおっさんだ。私もいちおう趣味のベーシストなので見ればある程度の意味はわかる。
【ウェットン】
「あのころ僕らが使ってたのは、
『デビルズ・トーン』(だったか『トライトーン』? もう忘れた)
と呼んでたスケールで、教会なんかじゃ絶対使っちゃいけない音なんだよ」
【私】
「ところでブライアン・フェリーのソロアルバムで
あなたがレコーディングした、いくつかの演奏は
個人的にとても気に入っているのだが、どう思うか?」
具体的には、フェリーのアルバム「Another Time, Another Place」(1974年)とか「Let's Stick Together」(1976年)あたりの話だ。これらのアルバムを聞くと彼のルーツがわかる。ジョン・ウェットンの根っこには明らかにR&Bがある。
こういうのはKing Crimsonだけ聴いててもよくわからない。そういう音楽性の話を聞きたかったのだが……。
「そりゃあ、『仕事』だから受けた話もあるさ」
えらくすげない返事だ。通訳を通して質問の意図が正確に伝わってないのだろうか?
しかしフェリーの仕事って、彼は中身に興味はないけど「仕事だから受けた」のかぁ。この時点でウェットンさんは「本音で話す人」だってのが判明したわけだ。彼はツッコめばしゃべるタイプの人間だ。よし、いけるぞ。
で、話はいよいよ核心に向かって行った。
私「ところであなたはなんでいま、あんなつまんない音楽やってるの?」(直訳)
するとウェットンいわく、
「いまは、昔みたいな演奏をしたテープを持ち込んでもどこも使ってくれないよ」
「だいいち私はKing Crimson時代にも、いまと同じようにメロディアスな部分を提供していたさ」
いや酷な話なのはもちろんわかっている。
ミュージシャンだって年を取れば、プレイヤーとして体力的にも技術的にもピークを越える。おまけに市場のニーズに合わせてアルバムをリリースしなきゃビジネスにならない。
そもそもこのインタビュー自体、「いま現在のウェットン」の象徴であるくだんのソロアルバムが売れるような記事を書いてもらうために組まれている。
つまり私の問いに対する答えは、彼にすればこの場で「絶対に言っちゃいけない話」なのだ。そんなことはもちろんわかっている。だがどうしても彼の本音が聞きたかった。というか、私はそれを聞きに行ったのだ。だってもう2度と会えないかもしれないんだから。
記事に書くかどうかは別の話だ。果たしてジョン・ウェットンはいまの自分を「いい」と思っているのか?
それがいちばんの問題なのだ。「ソロアルバムが出た」っていうのは彼に会う口実にすぎない。
CDレビューにからめて本人に話を聞くインタビュー企画だというのに、何が私にそんな逸脱をさせたのか?
こっちは70年代初期に彼が所属した「Family」時代から通してウェットンのベースをずっと聴いている。(私事で恐縮だが)私が高校1年のときBassを始めたのも、中学時代に彼の演奏を聴いてしまったからだ。
実は私はジョン・ウェットンに会いに行ったのではなく、あのとき時間を遡って「自分自身」に会っていたのかもしれない。そして鏡に映ったもうひとりの自分に、答えを言わせようとしている。
彼も話してるうちに、「どうやらコイツはほかのやつとはちがうぞ」と思っただろう。
最後にこんなことを聞いた。
私「じゃあ、いま好きで聴いてる音楽は?」
ウェットン「それは『プライベート』でか?」(彼はもう完全にこっちの意図をわかっている)
私「もちろんそうだ」
ウェットン「スティーリー・ダンとクインシー・ジョーンズだ」
私 (心の中で)「ほうら、あんた仕事でやってることと好みが全然ちがうやん。もっと自分のやりたいことやりなさいよ」
直接的にはウェットンに言っているが、この言葉は当時の私自身にも向いている。で、最後は商業主義と私(青年の主張か?)みたいな流れになって終わった。
「作ってるモンはちがうけど、やっぱりみんな同じなのね」。こんなことを記事にしてもつまらないからもちろん書かなかった。ただの世間話だ。
だが唯一、本物のインタビュー記事の締めでこれだけは書いた。
「好きな音楽はスティーリー・ダンとクインシー・ジョーンズ?
ほうら、やっぱりいまでも好みは私とまったく同じじゃないか」
なのになんでこんなつまらないソロアルバム作ってんの? もちろんシニカルなニュアンスを込めている。インタビューが終わり、通訳の人がこっそり私に耳打ちしてきたのをいまでも覚えている。
「彼は自分の言いたいことを必死でこらえている感じでした」
実はこのインタビューのお題になったソロアルバムの次(?)くらいに彼が出した最新のソロアルバム(確かインタビューから1年後くらい)では、なんでもジョン・ウェットンは「先祖返り」しているらしい。
その最新アルバムがリリースされたとき、たまたま本屋で立ち読みしていて音楽雑誌のCDレビューを見かけたのだ。
他人が書いたレビューを読んだだけだから、そのアルバムの中身がどんなものかはわからない。記事の筆者の言葉を借りればこんなふうだ。(記憶はテキトーなのであしからず)
「まるで20年前に戻ったような音だ。
このアルバムのジョン・ウェットンは、
完全にKing Crimson時代にもどっている」
そういうことらしい。
ひょっとしたらとんでもない失敗作かもしれない。でもいったい彼の中で何が起こったのか? そしてもしそれが私の想像通りだとしたら、私にはアルバムを確かめる義務がある。(こういうのを信者特有の「原理主義的思い込み」と言う)
私の中では彼はもう過去の人だ。本当なら「いまのジョン・ウェットン」を好んで聴く気なんてまったくない。だが問題のアルバムだけはどうしても実際の音を確認しなきゃ、絶対に (だってその盤がそうなったのって私のせいなんだから多分)。
そう強く念じながらも終わりなき「すちゃらかな日常」に押し流され、ズルズルと確認しないまま気がつけばもう10年がたっている。
すちゃらかな日常は誰の心にも忍び寄り、「まあいいや」「世の中、こんなモンさ」とすべてをチャラにしてしまう。
はたして彼はそんなすちゃらかをはね除けて、そのアルバムを作ったのだろうか? 音を聴き、もしそうでなかったら? 私はそれが恐くてどうしてもいまだに音を確認できないでいる。
どうしてるかなあ、ジョン・ウェットンさん。


















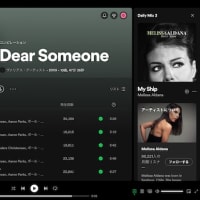









オレにとってジョンウェットンは今も昔も
一番好きなアーティストではありません。
しかしプロのBassist&歌手としては
とてつもなく素晴らしいと思います。
当時のクリムゾンでも一番上手かったのは
彼だと思います。
たくさんのライブ音源を聞きましたが
彼のプレイが音楽の意思を外れた部分は
多分ひとつもなかったか、と。
(他のメンバーはあります笑)
彼のプレイを聞いていつも思うのは
天然には敵わなかったのか?ということかな。
たとえば彼の前任者には
グレッグレイクという天然が居た。
レイクはプロフェッショナル的でもないし
特に卓越したテクニックも持ってなかった。
でも彼の「音楽活動初期」におけるプレイは
ピンポイントでヴィンテージ(笑)ですね。
ジョンウェットンは起用で上手すぎたのかなあ。
そんなことを今なんとなく思います。
饒舌すぎることは、「ロック音楽」にとっては
時に不要となることもあるんだな、と。
そんな気がします。
勝手なことを書いて申し訳ないです。
ウエットンは起用でうまいです、ええ。
たとえば1970年代初頭の
「ファミリー」時代&ブライアン・フェリーのソロでは
R&Bをベースにした同じ傾向の演奏してます。
ところがクリムゾンでの演奏を聞くと
同じ人とはとても思えない。
たぶん彼は発注主からのオーダーに忠実に応え、
それを自分なりにちょっち味付けしてアウトプットする
本当のプロなんだと思います。
想像ですが、後期クリムゾンではロバート・フリップが
こんなコト言い出したんじゃないかな?
「ようし。おれたち、『デビルズ・トーン』使って
人の神経逆撫でするようなナーバスな音楽やろうぜ。
これ、おれらのコンセプトなっ。わかった、みんな?」
だからウェットンは発注主に
忠実に従い、ああいう演奏してたんでは、と思う。
おまけに彼がすごいのは、
歌いながらあんなベース弾いてることですw
しかも歌がまたいいんだなあ、これが。
叙情的で声質にイメージの広がりがあるし、
なによりあの
「ひたすら美しく、ある意味、さわやか」な、
あのボーカルが、
異様にナーバスな演奏の上に乗っかってることの違和感、
ミスマッチが、見事に「混沌の魅力」として昇華してて
とっても効果的に後期クリムゾンの世界を作ってる。
かたや「ファミリー」時代&ブライアン・フェリーのソロって、彼、地でやってるんじゃないかと思います。
うーむ、ウエットンは20才までの私そのものなので
語り出すと思わず長くなっちゃいます(^^;
今日はこのへんで。
それではまた。
TB、コメント、ありがとうございました。
ひょっとしたら当時松岡さんの記事を何かで読んでるかもしれないなぁ、なんて考えるとちょっと楽しくなってしまいました。
また、ちょくちょくお邪魔させていただきますね。よろしくお願いします。
コメントいただいてたんですね。
すみません。気づきませんでした(^^;
ウチのブログは書く対象がハチャメチャなので、
音楽は今度いつ書くかかりませんが、
こんなブログでよろしければぜひまたお越しください♪
よろしくお願いします。
http://www.ongen.net/