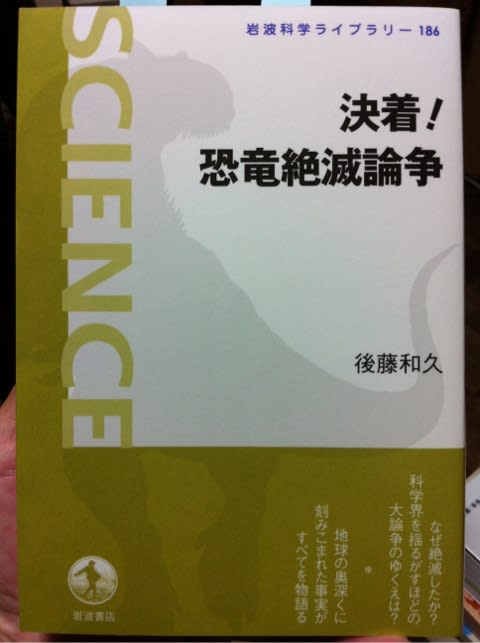
『決着!恐竜絶滅論争』後藤和久著、岩波書店(岩波科学ライブラリー)、2011年
今から6550万年前に起こった、恐竜をはじめとした生物の大量絶滅。
その原因をめぐってはさまざまな仮説が出され、研究や議論が重ねられましたが、1980年に「小惑星衝突による環境変動」が大量絶滅を引き起こしたとする論文が発表されます。その後、メキシコ・ユカタン半島の地下深くで、衝突により生じたと思われる巨大なクレーターが発見されるに及び、小惑星衝突説は多くの研究者に支持され、定説となっていきました。
しかし、火山噴火説などを唱える研究者からの反論が延々と寄せられ続け、それらはマスメディアを通じて一般にも流布されていきました。そのことに危機感を持った衝突説支持の研究者41人が分野を越えて集まり、衝突説への反論を明確に否定し、「論争は決着した」と宣言する論文を共著のかたちで発表するに至りました。本書の著者、後藤和久さんもその共著者の一人です。
本書は、「決着宣言」に至るまでの恐竜絶滅論争史を振り返りながら、なぜ決着したといえるのか、衝突説への反論はどう誤っているのかを解説していきます。
本書において解説されている、小惑星衝突後の劇的な環境変動の凄まじさには、あらためて驚かされるものがあります。が、やはり本書のキモであり、示唆にも富んでいると思ったのは、なぜ衝突説が決定的な定説となった一方で、それに対する異説として提唱された火山噴火説などが定説となれなかったのかを検証していく過程でありました。
ある仮説が提唱され、それに対する反論が出たのであれば、最初に仮説を提唱した側はもっと多くの証拠を提示しなければ、その仮説は支持を失ってしまう。その際、自説に決定的に不利な証拠が見つかった場合にどう対応するかで仮説の運命は大きく変わる。不利な証拠を否定するだけでは、他の研究者や一般社会の支持は得られない•••。著者はそう述べます。衝突説に対する火山噴火説などの異説は、この点においてあまりに不十分であったのです。
「『衝突説では説明できない。だから火山噴火説が正しい』というだけでは、何も説明したことにはなりません。衝突説で定量的または定性的に説明されているあらゆる事象について、同じレベルで科学的に説明がなされないかぎりは、火山噴火説が衝突説を覆すことは難しいでしょう。」 (5「衝突説と反論を検証する」より)
この点、恐竜絶滅論争にとどまらず、様々な科学における論争についても当てはまるのではないでしょうか。
そしてもう一つ考えさせられたのは、研究者とメディアとの関係についてのくだりでした。
メディアにおいては、「定説を支持する」研究成果より「定説を覆す」研究のほうが読者に興味を持たれるということもあり、衝突説に反対する論文の内容が、メディアを通じてたびたび流布されることになり、結果として専門家と一般社会との間にズレが生じることになりました。その責任は、「研究成果の最前線を正しく発信し広く社会に普及させることに対して、十分な努力をしてきたとは言えない」自分たち衝突説支持者にある、と著者は述べます。
メディアが新奇な説に飛びつくのは仕方のないところがありますし、定説を批判的に検証することも大事なことです。しかし、ともすればそのことが、誤った認識を広めてしまい、結果的に混乱を招いてしまうことにもなりかねないのです。これもまた、恐竜絶滅論争に限らず見られることでしょう。われわれ情報の受け手も、そのような側面を頭の中に置いておく必要があるのかもしれません。
恐竜絶滅論争を解説しながら、科学的な議論と研究成果の発信のありかたへの問いかけを込めた本書。コンパクトな小著ながら、教訓に満ちた一冊でありました。









