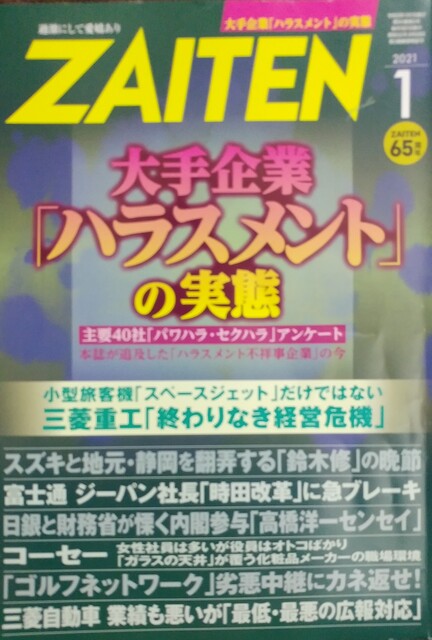自殺志願者たちは、天候が回復して人々が外出するとき、惨めさを思い出して飛び降りるのだ。彼らは金融危機や、学校の休み明けといった、人生の苦しみが大きくなる時期に飛び降りる。
茂幸雄さんの日課が天気に左右されることはない。
ほとんど毎日、約25m下に日本海が波打つ東尋坊の崖の、玄武岩でできた柱をよじ登り、歩き回る。双眼鏡を覗いて、遠くの岩々にうちひしがれた姿がないか探す。話しかけて、彼らを思いとどまらせる心づもりで。
15年間そんな日々を続けた結果、茂さんは609人を命の淵から救った。
「友達に会うときのような感じでやっているんです」と茂さんは語る。くたっとした釣り用の帽子をかぶり、おだやかな物腰の73歳の元警察官である。
「はらはらしたりはしません。こんにちは、お元気ですか、というような感じで話しかけるんですよ。ここでは助けを求めている人たちは、ただ誰かが話しかけてくれるのを待っているんです」
現代日本の「ロマンティック」ではない自殺
日本の自殺死亡率は発展国の中でも最も高い。2016年は10万人に17.3人の割合となり、これは主要先進国の中では韓国に次ぐ2位となった(ちなみに米国は13.5人)。
自殺者の大半は男性だ。銃での自殺が多い米国とは異なり、最も一般的な手法は首吊りである。15歳から39歳の年齢層において、自殺は癌や事故を合わせた死亡数以上に命を脅かす原因となっている。
これらの統計は、経済発展や政府の自殺防止対策により、大幅に改善された結果だ。金融危機後の1990年代後半には、年間の自殺者数は約3万3000人にまで増えたものの、それ以降減少傾向にある。2016年には約2万2000人が自殺をしたが、これは22年間で最少となっている。
日本の国外では、日本の自殺を報道するメディアの表現には、江戸時代の武士による「セップク」──儀式化された自死の刑──から、故意に戦艦にぶつかっていった第二次世界大戦の神風特攻隊まで、「誇り」や「名誉」といった概念が頻出する。
しかし現代の日本人の生活では、経済的な危機や家族の問題、失業、病気、仕事場や学校でのプレッシャーなど、あまりロマンティックではない言葉が多く見られる。東京都は2007年に自殺対策基本法を導入し、その10年後にはより総合的なガイドラインを定め、対策を強化している。
日本政府は「法的、社会的、そして文化的レベルで自殺に取り組んでいる」と、京都府立医科大学の教授で自殺予防研究を行っている本橋豊教授は語る。
教授によれば、政府はうつ病の研究にただ予算をつぎ込むというよりは、自殺の背景にある原因に取り組もうと試みているという。
具体的には、自殺相談窓口の開設、カウンセリングを受けやすくする工夫、自殺を幇助するようなウェブサイトの監視、週ごとの労働時間の削減、そして労働基準法の改正といった対策を重ねている。自殺志願者たちは、天候が回復して人々が外出するとき、惨めさを思い出して飛び降りるのだ。彼らは金融危機や、学校の休み明けといった、人生の苦しみが大きくなる時期に飛び降りる。
しかし、茂幸雄さんの日課が天気に左右されることはない。
ほとんど毎日、約25m下に日本海が波打つ東尋坊の崖の、玄武岩でできた柱をよじ登り、歩き回る。双眼鏡を覗いて、遠くの岩々にうちひしがれた姿がないか探す。話しかけて、彼らを思いとどまらせる心づもりで。
15年間そんな日々を続けた結果、茂さんは609人を命の淵から救った。
「友達に会うときのような感じでやっているんです」と茂さんは語る。くたっとした釣り用の帽子をかぶり、おだやかな物腰の73歳の元警察官である。
「はらはらしたりはしません。こんにちは、お元気ですか、というような感じで話しかけるんですよ。ここでは助けを求めている人たちは、ただ誰かが話しかけてくれるのを待っているんです」
現代日本の「ロマンティック」ではない自殺
日本の自殺死亡率は発展国の中でも最も高い。2016年は10万人に17.3人の割合となり、これは主要先進国の中では韓国に次ぐ2位となった(ちなみに米国は13.5人)。
自殺者の大半は男性だ。銃での自殺が多い米国とは異なり、最も一般的な手法は首吊りである。15歳から39歳の年齢層において、自殺は癌や事故を合わせた死亡数以上に命を脅かす原因となっている。
これらの統計は、経済発展や政府の自殺防止対策により、大幅に改善された結果だ。金融危機後の1990年代後半には、年間の自殺者数は約3万3000人にまで増えたものの、それ以降減少傾向にある。2016年には約2万2000人が自殺をしたが、これは22年間で最少となっている。
日本の国外では、日本の自殺を報道するメディアの表現には、江戸時代の武士による「セップク」──儀式化された自死の刑──から、故意に戦艦にぶつかっていった第二次世界大戦の神風特攻隊まで、「誇り」や「名誉」といった概念が頻出する。
しかし現代の日本人の生活では、経済的な危機や家族の問題、失業、病気、仕事場や学校でのプレッシャーなど、あまりロマンティックではない言葉が多く見られる。東京都は2007年に自殺対策基本法を導入し、その10年後にはより総合的なガイドラインを定め、対策を強化している。
日本政府は「法的、社会的、そして文化的レベルで自殺に取り組んでいる」と、京都府立医科大学の教授で自殺予防研究を行っている本橋豊教授は語る。
教授によれば、政府はうつ病の研究にただ予算をつぎ込むというよりは、自殺の背景にある原因に取り組もうと試みているという。
具体的には、自殺相談窓口の開設、カウンセリングを受けやすくする工夫、自殺を幇助するようなウェブサイトの監視、週ごとの労働時間の削減、そして労働基準法の改正といった対策を重ねている。⇒
続きはコチラ・・・・