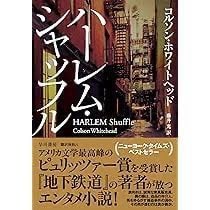「半端者」の侍の生き様
砂原浩太朗『浅草寺子屋よろず暦』
越川芳明
全部で六話ある連作小説集。
すべての作品にでてくるのが、大滝信吾という名の寺子屋の師匠だ。
信吾は宏大な浅草寺(せんそうじ)境内にあるお寺を借りて、子どもたちに読み書きを教えている。
兄は御膳奉行として将軍家に仕えるれっきとした旗本だが、信吾はなぜか町場のほうが性に合うと感じる侍である。
慎吾は妾腹(しょうふく)の子で、武家の人でも町人でもなく、「半端者」でしかないと自覚している。
だが、「半端者」だからこそ、江戸の身分制度のもとで培われた、がんじがらめな常識に対しても「ずいぶん狭い料簡(りょうけん)」だと断ずることができる。
そんな自由な発想ができる信吾のもとに、寺子屋の子どもたちを悩ませる難題が持ち込まれる。
裕福とはいえない親たちが引き起こす厄介ごとだ。
博打で莫大な借金をこしらえてしまう大工や、商売が下手な棒手振(ぼてふ)りの魚屋、賭博場の用心棒を生業(なりわい)にする武士など……。
著者は、信吾が難題をひとつずつ解決していくさまを、人情の機微をまじえてドラマチックに描く。
信吾の関わり合う女性にしても、武家の女性と町人の女性とを魅力的に書きわける。が、どちらかの女性に加担するわけではない。
小説は春の名物・浅草三社祭で幕をあけ、最後は季節が移ろい秋になっている。
タイトルの末尾に「暦」と銘打たれているように、すべての話のなかに季節を象徴するような植物や虫や花がでてくる。
「最終話」で描かれるのは、濃い紫の花をつける竜胆(りんどう)だ。
江戸の闇と真っ向から闘うことになる信吾は進退極まって、苦渋の決断を迫られることに。
だが、信吾のくだす決断は、野に咲く竜胆の花のように清々しい。
それでいて、その花言葉にあるように、「正義」や「勝利」をも連想させるものだ。
続編で、その後の信吾の生き様を読みたくなる、そんな見事な幕切れだ。
『陸奥新報』2024/11/23 ほか。
砂原浩太朗『浅草寺子屋よろず暦』
越川芳明
全部で六話ある連作小説集。
すべての作品にでてくるのが、大滝信吾という名の寺子屋の師匠だ。
信吾は宏大な浅草寺(せんそうじ)境内にあるお寺を借りて、子どもたちに読み書きを教えている。
兄は御膳奉行として将軍家に仕えるれっきとした旗本だが、信吾はなぜか町場のほうが性に合うと感じる侍である。
慎吾は妾腹(しょうふく)の子で、武家の人でも町人でもなく、「半端者」でしかないと自覚している。
だが、「半端者」だからこそ、江戸の身分制度のもとで培われた、がんじがらめな常識に対しても「ずいぶん狭い料簡(りょうけん)」だと断ずることができる。
そんな自由な発想ができる信吾のもとに、寺子屋の子どもたちを悩ませる難題が持ち込まれる。
裕福とはいえない親たちが引き起こす厄介ごとだ。
博打で莫大な借金をこしらえてしまう大工や、商売が下手な棒手振(ぼてふ)りの魚屋、賭博場の用心棒を生業(なりわい)にする武士など……。
著者は、信吾が難題をひとつずつ解決していくさまを、人情の機微をまじえてドラマチックに描く。
信吾の関わり合う女性にしても、武家の女性と町人の女性とを魅力的に書きわける。が、どちらかの女性に加担するわけではない。
小説は春の名物・浅草三社祭で幕をあけ、最後は季節が移ろい秋になっている。
タイトルの末尾に「暦」と銘打たれているように、すべての話のなかに季節を象徴するような植物や虫や花がでてくる。
「最終話」で描かれるのは、濃い紫の花をつける竜胆(りんどう)だ。
江戸の闇と真っ向から闘うことになる信吾は進退極まって、苦渋の決断を迫られることに。
だが、信吾のくだす決断は、野に咲く竜胆の花のように清々しい。
それでいて、その花言葉にあるように、「正義」や「勝利」をも連想させるものだ。
続編で、その後の信吾の生き様を読みたくなる、そんな見事な幕切れだ。
『陸奥新報』2024/11/23 ほか。