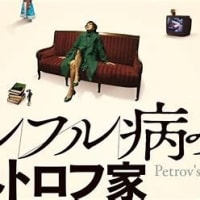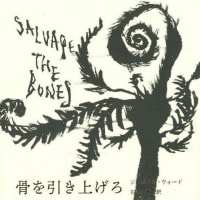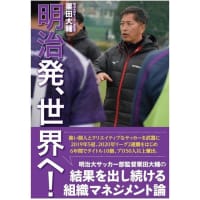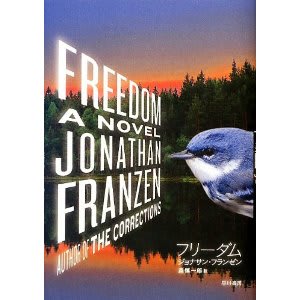
米中西部の中流家族と「自由」ーージョナサン・フランゼン『フリーダム』
越川芳明
フランゼンは恐ろしいほど寡作だが、一冊の長編小説の読み応えが数冊分に相当するような作家である。
アメリカ中西部に住む典型的な白人系の中流家族を登場させるが、十九世紀のイギリス作家ディッケンズのように、人物の心理描写がとても巧い。弁護士の父、専業主婦の母、優等生の娘、親に反逆する息子といったように、家族構成員のそれぞれの視点から互いの愛憎、離別や再会を描きだす。
そのように実にありふれた「家族物語」を装っているが、家庭の外にある「現代政治」を浮かびあがらせる裏技を隠し持つ。
小説で扱われている期間は、八〇年代のレーガン政権以降からほぼ三十年間にわたるが、作家は当代のイデオロギーや価値観を登場人物の描写に巧みに織り込む。
たとえば、八〇年代のいわゆる「新保守主義」(強いアメリカの復活)の時代に二十代を迎える一家の主人ウォルターは、反体制のロッカー、ボブ・ディランと同じミネソタ州の田舎町の出だ。
貧しいながらも弁護士になって、素朴なリベラル派として環境問題に取り組む。どちらかと言えば、富める人の「自由」を制限して、恵まれない人を「平等」に引き揚げる方針をとろうとする立場だ。
しかし、「テロとの戦い」というお題目で、ブッシュ・ジュニアがアメリカの軍事覇権主義(別名、「グローバリズム」)を押し進めたゼロ年代に、四十代になったウォルターは時の政権に強力なコネを持つ新興のトラスト会社の社長に気に入られ、首都ワシントンに移って出世街道を歩み始める。アパラチア山脈の炭坑地の買収をめぐって、自然保護という自分の理想にもかかわらず、富める者を利する「自由」に加担するはめに。
妻パティや息子ジョーイをはじめ、他の登場人物たちの場合も、父ウォルターと同様、普段は押し隠している欲望や無意識が重要な局面で彼らの価値観や意思を裏切り、本人も想定していなかったちぐはぐな行動をとらせることになる。 フランゼンの小説のコミカルな味わいは、アメリカの「自由」をめぐる個人の思想と行動のあいだのそんなギャップから来るようだ。
(『日経新聞』2013年2月17日朝刊)