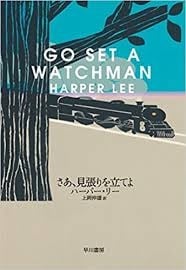サンテリア公式ババラオによるトークと近未来占いデモ体験。 2017年5 月28日 (日)15:00 open。第一部トーク :オリチャとパタキ(神話)。第2部占いデモ。ご予約受付:下北沢 ボデギータ03-5432-9785 詳細はifa-tokyo.jimdo.com
— 越川芳明(ロベルト・コッシー) (@roberto410) 2017年4月29日 - 20:05
二〇一七年度明治大学付属中野中学校・高等学校入学式
祝辞
明治大学学長の土屋恵一郎に代わりまして、祝辞を述べさせていただきます。
新入生の皆さん、ご入学おめでとう。
本校は明治大学の付属校であり、「質実剛毅」「協同自治」を校訓とする学び舎です。学園の合言葉として掲げられている教育方針は、「みんなで、仲良く、正直に、真面目に、精一杯努力しよう」という標語です。
この「みんなで、仲良く、正直に、真面目に、精一杯努力しよう」という標語は、平易な表現でありながら、実は深い意味が宿っている気がします。「みんなで 仲良く」という一語をとってみても、イギリスのEUからの離脱、ヨーロッパにおける極右政党の台頭、米国では「アメリカファースト」を掲げるトランプ大統領の登場など、世界は自国優先主義、自民族優先主義に走ろうとしています。そういう意味で、「他者」を思いやる心を大事にする、この「みんなで 仲良く」というのは、いまこそ、とても価値ある言葉だと思います。
さて、私は十年ほど前に、アメリカとメキシコの国境地帯を放浪しておりました。一九九四年に北米のカナダ、米国、メキシコの三カ国で結ばれた「北米自由貿易協定(NAFTA)」が、国家や企業ではなく、当地の貧困地区やスラムに暮らす低所得者の家族や難民たちに何をもたらしたのかをこの目で見たかったからです。マフィアの暗躍、ドラッグトラフィキングという麻薬の輸送、貧しい家庭の女性への暴力や大量殺人事件、政治家や企業人や警察の腐敗、多国籍企業による労働搾取など、この世界の吹き溜まりのような場所でした。しかし、これは日本とは縁のない、遠い世界の出来事のようでありながら、実はグローバル経済の仕組み中で、日本にも直接的に関係している世界なのです。そこに工場を持つ日本のメーカーのみならず、私たち、日本に暮らす消費者もそうした工場で作られた安い製品や商品を買うという行為によって、知らないうちに世界経済システムの「強者」になっている可能性があるのです。まるで野生のジャングルのように、強い者が容赦なく弱い者を食い殺すような、そんな野蛮な世界だからこそ、本校の教育方針である「みんなで、仲良く」は意味を持ってくると思います。
皆さんは、将来、日本社会のリーダーとして活躍される人材です。実際にリーダーになられた暁には、本校の精神的なモットーである「みんなで、仲良く、正直に、真面目に、精一杯努力しよう」を思い出していただき、世界の中で「弱者」の立場に立って物事を考えてくれる人になってほしいと思います。
このような素晴らしい校訓を掲げた学び舎が、皆さんの将来の「母校」となるわけです。いま私は「母校」という言葉を使いましたが、なぜ「出身校」を表す学び舎が「母」であって、「父」でないのでしょうか?
西洋でも、「母校」という言い方はあります。英語圏では「アルマ・メイタ―alma mater」といいます。その語源は、ラテン語の「アルマ・マーター」だそうです、アルマというのは「栄養を与える/養う」という意味で、マーターは、「母」という意味です。親しみをこめて言えば、マーターとは、「おふくろ」であり「おっかさん」です。
ですから、「アルマ・マーター」を私なりに日本語に意訳してみると、「青少年時代の私たちを育てる母(おふくろ、おっかさん)」です。いま、会場には皆さんをこれまで育ててくださった本物の「お母さん」が大勢いらっしゃっていますが、これからは、明大中野中学校と高校がみなさんのもう一人の「母(おふくろ、おっかさん)」になります。
「アルマ・マーター」とは、人間の精神形成に大きな影響を及ぼす出身校のことです。あるいは、建学の精神を歌詞に落とし込んだ「校歌」も意味するようです。ですから、皆さん、校歌を覚え、大きな声で歌いましょう。いまはわかりませんが、将来、皆さんが大人になったときに、明大中野が「母校」でよかったと、皆さんの精神的な土台を築いてくれたこのもう一つの「母(おふくろ、おっかさん)」に感謝することになるでしょう。
ですが、言うまでもなく「母校」とは、卒業して初めて使えることばです。卒業するまでは、きょうから一日一日を大切にして過ごしてください。私はあるとき、都内の真言宗豊山派のある寺院を訪れたのですが、その正面の壁にこういう箴言(格言)が掲げられていました。「一日を粗末に過ごす。毎日毎日を粗末に過ごす。一生を粗末に過ごすことに通じる」。そう書いてあったのです。
中学生の皆さんはご存知ないかもしれませんが、「カルぺ・ディエム」というラテン語の箴言があります。紀元前一世紀ごろ、古代ローマの詩人ホラティウスの言葉です。「カルぺ・ディエム」とは、平たく言えば、「いまを生きろ」です。
テレビでおなじみの、予備校講師の林修(はやし・おさむ)さんが以前、「いつやるの?いまでしょ」という言葉を流行らせましたね。「いつやるの? いまでしょ」という流行語は、彼のオリジナルではありません。その語の由来は、古代ローマのホラティウスの「カルぺ・ディエム」です。頭のいい林さんは、それを現代ふうの日本語にうまく言い換えたのです。
「一日を粗末に過ごすな」といい、「カルペ・ディエム」といい、「いまでしょ」といい、これらは皆、同じことを言っています。スポーツでも勉強でも大きな目標を立てて、その目標の日から逆算して、じゃあ、今日何をやらなきゃいけないかを自分で考え、実行することにしましょう。そうすれば、「一日を充実して過ごすことができます」。そういう趣旨の標語です。
私たちの生命は有限です。いつか死にます。魂は永遠かもしれませんが、肉体の死の訪れは、確実にやってきます。六十年後か八十年後かもしれませんが、ひょっとしたら明日かもしれません。自分自身の「死」を自覚したとき、「カルぺ・ディエム」という言葉は意味を持ってきます。皆さんも私も墓場に行くまでは、「いまを生きる」を実行することにいたしましょう。
と同時に、ときには墓場に眠る死者たちにも思いを寄せることをお勧めます。皆さんは突然変異でこの世に生まれたのではなく、お父さんお母さんの、さらにお父さんお母さん、さらに、辿れないかもしれませんが、ご先祖のDNA(遺伝子)のリレーでこの世に生きているわけで、そういう意味では、死者は私たちの中に生きている、私たちは死者と共に生きていると言えます。死者に思いを寄せることで、自分の生の意味を再確認することができます。
私の友人で作家の高橋源一郎がすこし前に新聞で、こう言っていました。「健全な社会とは、過去を忘れず、弱者や死者の息吹を感じながら、慎(つつ)ましく、未来へ進んでゆくものではないのはないのか」と。私は高橋さんの「弱者や死者の息吹を感じながら」という点に、深く共感を覚えます。本校の標語で、皆さんが「みんな 仲良く」と述べるときに、「弱者」や「死者」を含めてくださるとうれしく思います。
結びにあたりまして、明治大学付属中野中学校・高等学校の益々のご発展と、中学校二百四十九名、高等学校四百十三名の新入生の皆さんが、この明治大学付属中野中学校・高等学校の生徒としての誇りを胸に、大いに活躍されることを祈念いたしまして、私からのお祝いの言葉とさせていただきます。
本日は、新入生の皆さん、本当におめでとうございます。
平成二十九年四月五日 明治大学副学長 越川芳明
ハイブリッドな工夫を凝らした啓蒙書
四方田犬彦『署名はカリガリーー大正時代の映画と前衛主義』
越川芳明
大正期(1910年代ー20年代)に日本に現れた、映画と演劇をシンクロさせて上演する独特なスペクタル形式を「連鎖劇」と呼ぶが、本書は、複数のテクストを機能的にハイブリッドした一種の「連鎖劇」だ。
例によって「四方田節」としか名付けようのない、個人的な視座に立った饒舌で軽快な語りに導かれてページを括っているうちに、私たちはジェットコースータに乗ったかのように、めくるめく別世界へと旅している。
そうした語りの方法を、著者自身は「迂回のエクリチュール」と告白している。何のことはない、本書自体がポストモダンの「メタフィクション(入れ子細工)」の実践の書だと思えばよい。
とはいえ、難解な研究書ではない。大正期の日本に異常発生した前衛芸術(映画と文学)を題材にしていて、作家周辺のゴシップネタを挟むなど、一流の芸人顔負けのサーヴィス精神が旺盛だ。
例えば、一風変わった芸術家肌の女子大生に導かれて、谷崎潤一郎の『痴人の愛』のモデルと思しき老女と会うくだりはワクワクする。「和嶋せい」という名の、この女性は谷崎の妻千代の実妹であり、一時は愛人として作家と同棲もしていただけでなく、日本映画草創期の「女優」(葉山三千子)でもあったという。これだけでも、読者が思わず身を乗り出す「物語」でないだろうか。
全編は三部からなり、奇しくも十九世紀末生まれの、四人の小説家や映画監督(谷崎潤一郎、大泉黒石、溝口健二、衣笠貞之助)が俎上にあげられている。文章の端々に偶像破壊の意図が見え隠れする。従来の固定的な作家/監督像を打ち壊し、もう一つの作家/監督像を提示しようとする強い意思に貫かれているのだ。
例えば、王朝文学の旗手の谷崎は、ドイツ表現主義の映画に魅せられた野心的な映画人として、あるいは、ぐうたらな浮浪者を主人公にした初期チャップリンの反市民的な映画に魅せられた映画人として、読者の前に立ち現れてくる。身分違いの恋の破滅や女性を社会主義的なリアリズムで描くことに定評がある溝口健二は、実験精神に満ちた映画人として浮かびあがる。
いうまでもなく、ドイツ表現主義の傑作『カリガリ博士』は、夢遊病者を扱い、人間の「不安」や「恐怖」や「悪夢」の表象ーーデフォルメされて歪んだ舞台装置、黒白の衣装や化粧ーーが散りばめられている。この作品に代表されるアヴァンギャルドな作品を生み出した美学運動は、文学、音楽、絵画のみならず、様々な分野にも及んだが、著者によれば、新しいモノ好きの大正モダニスト映画人もいち早くそれに呼応したという。
本書の白眉は、四人の作家や監督の残した前衛的な作品についての丹念な分析にある。それぞれ、「『人面疽』を読む」、「『血と霊』を読む」、「『狂った一頁』を観る」と題されているセクションがそれだ。内外の先行研究はもちろん、当時の映画評の類の小さな文献まで渉猟して、比較検討しながら結論を導き出す。ここは映画研究者の見本である。
『人面疽』は谷崎の幻の映画の原作。怪奇小説の様相を帯びた、「ホフマンやポーに耽溺する悪魔主義的な心身小説家」の前衛作品だ。人面疽というのは、聞き慣れない言葉だが、「人間の腹部や膝に人間の顔に酷似した不気味な腫瘍が生じ、モノを言ったり、寄生主に向かって要求をするという病気」だそうだ。もちろん、これは架空の病気だが、そうした病気に取り憑かれた初期の谷崎のゴシックな想像力は、ただの倒錯的なフェティシズムではなく、秩序転覆の「政治性」も帯びていたに違いない。
大泉黒石は、ロシア人の父と日本人の母との間に生まれた混血作家。孤児としての流謫の生を送った。著者は、長崎の「支那人」居留地を舞台にした犯罪小説『血と霊』を取りあげ、作家の異邦人としての周縁性に焦点を当て、「のがれがたき宿命への洞察とそれを語ろうとする黒石の情熱は・・・ホフマンには、とうてい及びもつかないものであった」と、高く評価する。
とりわけ秀逸なのは、衣笠貞之助による実験映画『狂った一頁』の分析だ。この作品は、精神病院を舞台にしたものだが、「監禁と隠蔽を旨とする近代社会への異議申し立て」であり、すぐれた「近代批判の芸術テクスト」として絶賛される。
著者は、一瞬のきらめきを放つ前衛芸術の宿命を重々承知している。だが、それでも「挫折を余儀なくされた、前衛芸術の試みが万が一成功していたら・・・」といったSF的な想像へと読者を誘う。有り得たかもしれない作家の生(仮想世界)に思いを馳せながら、不朽の名作ではなく、一瞬のきらめきを放った作品に焦点を当てて、蕾から花を咲かせるのだ。本書の最大の功績は、僕のような一般読者に、谷崎の『人面疽』や、溝口/大泉の『血と霊』や、衣笠の『狂った一頁』といった、「小さな巨人」たちの魅力を知らしめたことだろう。そういう意味で、すぐれた啓蒙の書と言わなければならない。
(『図書新聞』2017年4月15日号、1面)
新4年生は、就活がんばっているかな? すでに新学期のオリエンテーションも始まっている。
— 越川芳明(ロベルト・コッシー) (@roberto410) 2017年4月10日 - 17:41
学業と就活の両立は難しいが、そこをあきらめずに挑戦してほしい。
大学倶楽部・明治大:学生の就職活動を応援 「出陣式」を開催 - 毎日新聞 mainichi.jp/univ/articles/…
「死者の世界」を覗き込む 柴崎友香『かわうそ堀怪談見習い』
越川芳明
エドガー・アラン・ポーの「黒猫」や「告げ口心臓」などがいい例だが、怪奇小説やゴシック小説の中には、霊感の強い、「信頼できない語り手」が登場するものがある。真実なのか、それともただの語り手の妄想なのかはっきり判別できない物語を提示することによって、作者は語り手の不安や恐怖を読者にも共通体験させようとするのだ。
だが、「怪談(見習い)」を冠した本作の場合、語り手の「わたし」(谷崎友希=小説家)は、信頼できそうな語り手だ。「感情が乱高下するようなことは、日常生活でも、小説の書き方でも得意ではない」とか、恋愛も怪談も向いていない、と告白する。
そういうわけで、語り手(=作者)は入れ子構造(伝聞形式)の語りを採用することになる。賢明にも、自分より霊感の強い人たちの言葉を「引用」するのだ。
とはいえ、「わたし」自身も、通常「超常現象」と言われる事象に対して鋭い感性がないわけではない。中二の時に、友達と一緒に侵入した謎のマンションで目に見えない存在に気づいてから、「それまで暮らしていた世界と、別の世界との隙間みたいなところに」生きるようになったからだ。
「隙間みたいなところ」とは、わたしたち生者が死者と出会うトポスに他ならない。「わたし」は現世を死者の視線で見ることができるので、「超常現象」に対しても、不安や恐怖を感じることなく、平静でいられるのだ。
かくして、「隙間みたいなところ」ばかりが出てくるが、それは幽霊屋敷のようなおどろおどろしい場所ではなく、街の古本屋だったり公園だったり、漁村の古い家だったり都会の真ん中の奥まった路地だったり、ワケあり物件のアパートだったりビジネスホテルだったり、大阪環状線の電車の中だったり・・・。要するに、わたしたちにとって、身近な生活空間の中の「ちょっと違った世界」なのだ。
それぞれが短い、数多くの物語の中で、「桜と宴」と題された作品は秀逸。「わたし」は、友人のたまみに誘われて商店街の桜見に出かけていく。そこで、ある会社員の若い女性に紹介され、彼女の「幽霊話」を聞く。彼女は中二の頃にいじめに遭い、安らぐ場所がないまま、環状線の電車に乗って過ごす。すると、自分と同じように電車から降りない人たちの存在に気づく。あるとき目をつけた上品な婦人を家まで追いかけ、そこで彼女は自分自身に死者の姿を見抜く能力があることを発見する。
注目すべきは、その話を聞きながら、「わたし」が彼女の眼球にある「穴」を見つけることだ。その「穴」こそ、「どこか遠いところへつながっている暗闇」に通じる入口であり、「死者の世界」の換喩に他ならない。ポーとは違った語り口で、わたしたちのすぐ身近にある「死者の世界」を描いた洗練された「ゴシック小説」だ。
(初出『文學界』2017年5月号)
「肉体」たちの記憶を語る ポール・オースター『冬の日誌』
越川芳明
著者は冒頭で本書を要約する、こんな言葉を発している。
「この肉体の中で生きるのがどんな感じだったか、吟味してみるのも悪くないんじゃないか。五感から得たデータのカタログ」と。
そう、「カタログ」と称するからには、退屈であろうとなかろうと、何から何まで一応網羅しなければならない。例えば、三歳半のとき、デパートで遊んでいて、左頰に長い釘が突き刺さって顔半分が引き裂かれたエピソードから始まり、初老の男の肉体が記憶しているこれまでの怪我や傷の数々。
「君」という二人称で、読者に語りかける記述方法に特徴がある。なぜ自分自身の過去について語るのに「私」でなく、「君」を主語にするのか。
もちろん、それは自分自身の過去の出来事を突き放して見つめるための創作上の工夫に違いない。だが本書のテーマ(身体の記憶カタログ)とも密接に関わっているはずだ。
著者が引き合いに出すイギリス作家ジェイムズ・ジョイスの逸話にヒントがあるかもしれない。ジョイスはパーティの席上で、ある貴婦人から、あの傑作の『ユリシーズ』を書いた手と握手させてくださいと言われ、「マダム、忘れてはいけません。この手は他にもたくさんのことをやってきたのです」と、答えたという。
私たちがこのエピソードから類推できるのは、本書の「君」が、たんに著者の過去の分身というより、むしろ、現在の著者とは別の生き物としての「肉体」たち、過去の様々な瞬間にいろんな反応を見せた「肉体」たちではないだろうか。
たんに執筆に取り組むだけでなく、自我意識に目覚めた三、四歳の頃から、性の虜になる思春期を経て、母の心臓発作による死や、著者の判断ミスによる交通事故で妻や娘を殺しかけた五〇代、そして老いを意識しだした六〇代まで、実に数々な事件や出来事に遭遇した無数の「肉体」たちの物語。
それを掌編小説みたいに巧みに語ったものが本書である。 (「デーリー東北」2017年3月26日朝刊ほか)
50年代の差別問題を見つめる ハーパー・リー『さあ、見張りを立てよ』
越川芳明
米国南部では、十九世紀半ばの奴隷制廃止後も九十年近く、黒人を差別する人種隔離政策(「ジム・クロウ法」)がまかり通っていた。白人たちは、「血が汚れる」ことを恐れ、暴力で黒人の「人権」を押さえつけようとした。一九六三年、二人の黒人学生がケネディ大統領の後押しでアラバマ大学に入学登録しようとした時、ウォレス州知事(もちろん白人)は州兵を繰り出し、それを阻止しようした。
この小説の舞台は、そうした公民権運動が激化する前夜、五〇年代の深南部アラバマだ。二十六歳の女主人公ジーンが二十年ぶりに南部に帰ってくる。いっときは、おてんば娘として今は亡き兄たちと楽しく過ごした過去の思い出にふけることができる。久しぶりに見る弁護士の老父も、株で大儲けして四十代で引退した「学のある変人」の叔父さんも、ズボンをはかない生粋の南部レディの叔母さんも、誰もが健在で、健全に見えた。だが、リビングルームで下劣な黒人差別パンフレットを見つけてから、彼女の牧歌的な世界が崩れ始める。絶対的な信頼と尊敬を寄せていた父が白人優越主義の団体のメンバーであることが発覚するからだ。
社会の周縁に追いやられた「他者」の視点に立つことは、易しいことではない。だが、この女主人公は、子供の頃から観察力が鋭く、そうしたことができたようだ。黒人女性たちがわざと「無知」を装う「知恵」を持っているのを見抜いていたのだ。黒人のメイドは立派な英語をしゃべれるのに、「客人の前では動詞を落として黒人っぽくしゃべったりするのだ」と。
文学的価値では、同じ南部の白人作家であるフォークナーやオコナーの諸作品に敵(かな)わないのに、同じ作者による『アラバマ物語』(1960年)がこれまで圧倒的な人気を誇ってきたのはなぜか。主人公の女の子が「なぜ差別がなくならないの?」という根源的な問いを大人の世界に投げかけ、差別を決して是認しなかったからだ。
だが、もう一つの『アラマバ物語』というべき本書は、差別問題をめぐって主人公を諭す叔父の理屈に見られるように、やや後退してしまっている印象を受ける。
今でも科学的な根拠の欠けた、人種偏見を抱いている人が大勢いる。だから、二つの『アラバマ物語』の果たすべき使命はまだ終わっていない。
(『日経新聞』2017年3月11日朝刊読書欄)
静かな「抵抗」のユーモア ジャファル・パナヒ監督『人生タクシー』
越川芳明
タクシーという密室空間で起こる、人々の出会いや事件をユーモラスに撮った映画だ。静かだが、愉快この上ないブラックユーモアの毒矢が幾つも放たれる。舞台はイランの首都テヘラン。
イランといえば、ドナルド・トランプ米大統領が二〇一七年一月末に、テロリストの排除という名目で下した大統領令の中で、米国への入国を短期間禁じた七カ国のうちの一つだ。ニュースメディアを通じて大統領令が一人歩きして、名指しされたイラン人をはじめ、中東やアフリカのイスラーム教徒をことごとくテロリストと見なすような、極めて単純な思考が世界の隅々にはびこっていく。そんな中で、中東から心理的に遠く離れた日本において、イラン人たちの多様性を打ち出した本作が上映される意義は、決して小さくはない。
とはいえ、この映画を取り上げるのは、そうした政治的、社会的な理由だけではない。むしろ、芸術映画として凝った工夫がなされている点にこそ惹かれたのである。 なぜタクシーなのだろうか。ここに出てくるのは、普通のタクシーではない。目的地が異なる複数の乗客を一緒に運ぶ「乗り合いタクシー」だ。
乗り合いタクシーは、ホテルや駅、空港などと同じように、出自や思想信条の異なる市民が出合う可能性のある一つのトポスである。しかも、小さな密室空間という特徴を有する。見知らぬ人間同士が膝を接して一定の時間を一緒に過ごすことで、まるで元素同士が化学反応を起こすみたいに、個人の感情や思想が露呈しやすい。
例えば、最初に乗ってくる自称「路上強盗」の男は、次に乗り合わせる女教師と「死刑とイスラーム法」をめぐって、熱い議論を繰り広げる。女教師が些細な罪ですぐに死刑にするのはやりすぎだと理性的な意見を述べるのに対して、「路上強盗」は、あなたは本ばかり読んでいる空想家だとバカにして、車のタイヤを盗むような奴は死刑に処すべきだと自説をまくし立てる。タクシー運転手を演じている監督はどちらの側にも与せず、ニコニコしているだけだ。
だが、注目すべきは、このシーンが市民生活を規制するイスラーム法の施行をめぐって、一般市民の間にも異論や反論が存在するという事実を伝えていることだ。労働者階級と知識人、男性と女性といった階級やジェンダーによる意見の食い違いにも細かく目配せしている点も見逃せない。
周知のように、イランでは一九七九年にホメイニー氏によるイラン・イスラーム革命が成就し、宗教指導者が国政の最高指導者を兼ねるイスラーム共和制が樹立された。そのことによって、イランに住むクルド民族や同性愛者など、少数者への「迫害」がイスラーム法のお墨付きを受けやすい。リベラルな映画製作も禁じられ、パナヒ監督自身も、イスラーム法に抵触した作品を作った廉で二十年間の映画製作禁止の処分を受けている。
そうした宗教原理主義による規制拡大への風刺は、本作の終わり近くに登場する女性弁護士の存在に明らかである。女性弁護士はバレーボールの試合を見にいったために拘留されている少女の弁護をして、弁護士会から「活動停止」の憂き目に遭っているという。少女がハンガーストライキという最後の抵抗手段に訴えているというので、応援のためにバラの花束を届けにいくところだ。彼女の言葉によれば、監督自身もまた映画監督協会から「活動停止」の処分を受けており、二人は官憲から「反体制派」の危険分子として目をつけられているのだ。
とはいえ、彼らは非寛容な体制に対して異議申し立てを試みる内部人(ルビ:インサイダー)である。自らの文化とは異なる「他者」(イスラーム教徒)に対して、非寛容に排除を訴えるトランプ大統領のような外部人(ルビ:アウトサイダー)ではない。
そこで、パナヒ監督はイランで生き延びるために実に巧妙な技術を駆使する。直接的に異議を唱える社会主義的リアリズムではなく、自己言及のメタフィクション(入れ子細工)を採用するのである。
例えば、本作はドラマとドキュメンタリーの境界地帯を掘り下げて、ドラマともドキュメンタリーともつかぬ、曖昧な立場を貫く。監督自身が素人のタクシー運転手として出演するというドキュメンタリーの体裁をとるが、ダッシュボードの上の小型カメラに興味を示す自称「路上強盗」によって、監督は「偽の運転手」だとたやすく見破られてしまう。その上、海賊ビデオ売りの小柄な男からは、すべてドラマ映画の演出ではないか、との疑いをかけられる。
さらに、映画撮影をめぐる自己言及は、いたるところに顔を出す。大学で映画学を専攻しているという学生は、製作のための題材をどこから得ているのかを監督に質問する。監督の答えは「自分で見つけるんだ。教えられない」である。言い換えれば、「題材はどこにでもある、この映画のように」と、監督は言いたいかのようだ。
きわめつけは、監督の姪のおしゃべり少女の登場だ。彼女は短編映画を作るという宿題が出たと言い、デジカメで車窓風景を撮り始める。学校の先生から提示された「上映可能な映画」をめぐるルールを監督に告げる。それによれば、「女性はスカーフをかぶり、男女は触れ合わないこと」や「政治や経済に触れないようにすること」などの他に、「俗悪なリアリズムや暴力を避けること」があるという。「俗悪なリアリズム」とは、体制にとって都合の悪い現実を撮ることに他ならず、少女は路上で盗みを働いた少年を偶然撮ってしまったために、それが「上映不可能」になる不安に襲われる。
かくして、声高に時の政権に異を唱えることで欧米の非寛容なキリスト教原理主義に与してしまわないようにする一方、静かにかつユーモラスに、これまた非寛容なイスラーム原理主義に対する「抵抗」を展開するという、高度なテクニックに裏打ちされた傑作である。 (初出『すばる』2017年4月号、395-96頁)