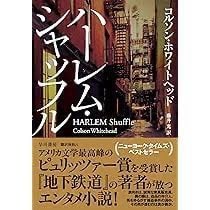なぜ民主主義の国で、いまなお人種差別がなくならないのか? ブレンダ・E・スティーヴンソン『奴隷制の歴史』(所康弘訳、ちくま学芸文庫)
越川芳明
「奴隷制とは何か?」という問題提起で始まる本書は、米国の奴隷制に興味を持つ者にとっては、まるで最新の携帯電話<アイフォン15>みたいに、小ぶりながら膨大な情報量と知的刺激にみちた良書だ。
著者のスティーヴンスンは、「訳者あとがき」によれば、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の歴史学教授だという。
豊富な資料を丹念に読みとき、淡々と「歴史的な事実」を積み重ねるその叙述法には、歴史学を専門とする学者の手堅い姿勢がうかがわれる。
逆に言えば、文学作品のような感情の昂りを表現することを極力抑えている印象だ。
著者のとおい祖先が16世紀から始まる大航海の時代以降にアフリカから新天地に運ばれた奴隷であること、
つまり、自身がアフリカン・ディアスポラの末裔であるということがあえてそうしたスタンスを取らせているのかもしれない。
制度への憤怒は内にとどめておくことによって、逆に読者の中に奴隷制に関する知見だけでなく、そうした制度への憤怒を醸成させることを意図しているかのように。
著者は語る。「奴隷制とは何か?
これは簡単な質問のように思われるかもしれない。ほとんどの人々は、奴隷制とは南北戦争が終わる前にアメリカ合衆国で暮らしていた黒人の状態のことだと信じている。……
(中略)ほとんどの学生が知らないのは、奴隷制が歴史上、最も一般的な制度の一つであるとともに、最も多様な制度の一つであるということだ。
ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、アジア、オーストラリアなど、ほとんどすべての地域の文明で何らかの形の奴隷制が存在していた。
……(中略)さらに奴隷制はほとんどの場所や地域で、今なお存在している。
実際、世界中で推定二〇〇〇〜三〇〇〇万人の人々が債務奴隷、性奴隷あるいは強制労働者として、いまだに奴隷状態にあると考えられている」
確かに第1章で、古代から大航海時代(つまり奴隷貿易)が始まる頃までに世界各地で見られた奴隷制について概説しているが、
本書の真骨頂は、やはり著者の得意分野である北米の奴隷制である。アフリカと大西洋の奴隷貿易(第2章)、北米の植民地(第3章)、
南北戦争以前の米国の奴隷制と反奴隷制(第4章)というように、質量ともにそのことをしめしている。
アフリカン・ディアスポラの歴史
歴史学者ポール・ラヴジョイによれば、アフリカから新天地に連行されたアフリカ人は、推定で1200万人だという。
奴隷貿易にかかわったヨーロッパの帝国は、ポルトガル、スペインのほかに、オランダ、フランス、イギリス、デンマークなどだった。
18世紀にヨーロッパの諸帝国に莫大な富をもたらし、その力で産業革命を成功させ、飛躍的な発展をもたらした影の功労者は「奴隷貿易」であり、植民地での「奴隷制」だったと言っても過言ではない。
アフリカから連行されたディアスポラの民の、血と涙の労苦なくしてはそうした繁栄はなかったに違いない。
本書によれば、アフリカ奴隷の出身地としては、コンゴ・アンゴラなどの中央アフリカが40パーセント、ベニン湾岸の西アフリカが20パーセントと、それだけで全体の60パーセントを占めていたという。
奴隷の到達地としては、ブラジルが400万人、スペイン領植民地が200万で、奴隷の約半数を占めていた。
さらに、奴隷制を経済的な観点からいうと、アメリカ大陸で売られた奴隷の価格は、17世紀後半から18世紀後半にかけて、4倍以上に値上がりし、しかもその数も3倍弱にふくれあがったらしい。
「一般的には、17世紀後半から18世紀を通じて、対外的な労働力需要の増加に伴い、奴隷の価格は上昇した。たとえば、この時期の奴隷の平均価格は4倍から5倍ほど上昇した。これに対し、奴隷の出荷数は二倍から三倍ほど増加している」
要するに、この時期に奴隷貿易は儲かる産業と化していたことがわかる。その産業に加担していたのが、アメリカ建国の父たちとされる偉人だったのいうのもアメリカ史の逆説だ。
たとえば、独立宣言を執筆した大陸会議の委員長を務めたヴィアージニアのリチャード・ヘンリーは五十人以上の奴隷を所有していたし、第二回大陸会議の議長を務め、アメリカ合衆国の独立に尽力したサウス・キャロライナのヘンリー・ローレンスは奴隷商人かつ最大の奴隷所有者だった。
「奴隷体験記」の活用
本書の特色を一、二挙げるならば、まず網羅的であるという点がある。
大西洋奴隷貿易に果たした「中間航路」の役割から、北米における奴隷制反対運動や逃亡奴隷の活動まで、あるいはイギリス植民地時代の奴隷制と経済から独立以降の米南部の奴隷の生活まで、もれなく詳述されている。
さらには、語る主体として表に出てこなかった奴隷自身の「身の上話」もたくさん引用されていることが重要である。
誰もが認めるように、歴史はメディア(活字や伝達媒体)を占有する者によって作られてきた。アフリカ奴隷はつねに歴史の対象となっても、主体にはならなかった。
ここにきてようやく、歴史学者たちがオーラル・ヒストリーの「奴隷体験記」を史料としてつかうことによって、奴隷あるいはその末裔が歴史の主体となることが可能になったのだ。
フレデリック・ダグラスやハリエット・ジェイコブズらの著作は、すでに有名になっている「奴隷体験記(スレイヴ・ナラティヴ)」だが、
本書では、無名の奴隷による「体験記」を数多くつかっていることが注目に値する。
一例を挙げれば、オラウダ・エクイアーノという男の話がとても印象的である。
「……身の上話の中で、ナイジェリア出身のイボ族と名乗っている。
奴隷を所有していた裕福なコミュニティのメンバーの息子だったが、妹と一緒に誘拐され、西アフリカで何度か売られた後に、イギリスの植民地へ送られた。
誘拐された当時、一一歳だったエクイアーノは、自分と妹が二人組の男女に捕えられた瞬間を鮮明に覚えていた。二人組は屋敷の壁を乗り越えてきて、二人を掴まえ、「口を塞いで」、「すぐ近くの森まで」連れて行き、手を木に縛りつけた。
翌日、誘拐犯はエクイアーノと妹を引き離し、それぞれ別の人間に売り渡した。「二人をばらばらにしないように頼んでも無駄だった」。
「妹は私から離され、すぐに連れ去られた。私は言葉では言い表せないほどの混乱状態に陥った。
私は泣き続け、嘆き、数日間、彼らが私の口に無理やり押し込んだもの以外は何も食べなかった。……(中略)オラウダの最初のアフリカ人の主人は金細工職人であった。
そのため昼間はその仕事を手伝い、夜は家事奴隷の女性と一緒に働いていた。その後、一七二個のタカラガイとの交換で再び売られ、同じ年頃の裕福な少年の遊び相手となった。
エクイアーノは西アフリカの奴隷社会の習慣にならって、その家族に養子縁組されることを望んでいたが、再び売りに出された。
「こうして私は時には陸路で、またある時には水路で、様々な国や地域を旅し続け、誘拐されてから六〜七ヵ月が経った頃、海辺に辿り着いた」
すぐさまエクイアーノは大西洋をわたってカリブ海に向かう奴隷船に乗ることになった。
このような無名の奴隷の語られざる「物語」が何百万、何千万とあるに違いない。つまり、人類をめぐる「歴史」は、まだ書き換えられる可能性があるということである。
私のような読者は、このような「物語」をもっと読んでみたいという衝動に駆られる。
そのような読者のために、ありがたいことに巻末に「注」のかたちで出典情報が載っている。さらなる奴隷制をめぐる「読書の森」へと誘うためである。
また、本文中の固有名詞(人名や土地名など)には、原語がカッコで添えてある。
これもまた小さい工夫だが、興味を抱いた読者がネットや図書館で調べる糸口となるはずだ。
訳文は平易でこなれており、読みやすい。
米国の奴隷制に興味がある初心者に基本的な知見をもたらすだけでなく、いまなおどうして民主主義の国で人種差別がなくならないのか、その理由を読者に示唆する優れた図書だ。
越川芳明
「奴隷制とは何か?」という問題提起で始まる本書は、米国の奴隷制に興味を持つ者にとっては、まるで最新の携帯電話<アイフォン15>みたいに、小ぶりながら膨大な情報量と知的刺激にみちた良書だ。
著者のスティーヴンスンは、「訳者あとがき」によれば、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の歴史学教授だという。
豊富な資料を丹念に読みとき、淡々と「歴史的な事実」を積み重ねるその叙述法には、歴史学を専門とする学者の手堅い姿勢がうかがわれる。
逆に言えば、文学作品のような感情の昂りを表現することを極力抑えている印象だ。
著者のとおい祖先が16世紀から始まる大航海の時代以降にアフリカから新天地に運ばれた奴隷であること、
つまり、自身がアフリカン・ディアスポラの末裔であるということがあえてそうしたスタンスを取らせているのかもしれない。
制度への憤怒は内にとどめておくことによって、逆に読者の中に奴隷制に関する知見だけでなく、そうした制度への憤怒を醸成させることを意図しているかのように。
著者は語る。「奴隷制とは何か?
これは簡単な質問のように思われるかもしれない。ほとんどの人々は、奴隷制とは南北戦争が終わる前にアメリカ合衆国で暮らしていた黒人の状態のことだと信じている。……
(中略)ほとんどの学生が知らないのは、奴隷制が歴史上、最も一般的な制度の一つであるとともに、最も多様な制度の一つであるということだ。
ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、アジア、オーストラリアなど、ほとんどすべての地域の文明で何らかの形の奴隷制が存在していた。
……(中略)さらに奴隷制はほとんどの場所や地域で、今なお存在している。
実際、世界中で推定二〇〇〇〜三〇〇〇万人の人々が債務奴隷、性奴隷あるいは強制労働者として、いまだに奴隷状態にあると考えられている」
確かに第1章で、古代から大航海時代(つまり奴隷貿易)が始まる頃までに世界各地で見られた奴隷制について概説しているが、
本書の真骨頂は、やはり著者の得意分野である北米の奴隷制である。アフリカと大西洋の奴隷貿易(第2章)、北米の植民地(第3章)、
南北戦争以前の米国の奴隷制と反奴隷制(第4章)というように、質量ともにそのことをしめしている。
アフリカン・ディアスポラの歴史
歴史学者ポール・ラヴジョイによれば、アフリカから新天地に連行されたアフリカ人は、推定で1200万人だという。
奴隷貿易にかかわったヨーロッパの帝国は、ポルトガル、スペインのほかに、オランダ、フランス、イギリス、デンマークなどだった。
18世紀にヨーロッパの諸帝国に莫大な富をもたらし、その力で産業革命を成功させ、飛躍的な発展をもたらした影の功労者は「奴隷貿易」であり、植民地での「奴隷制」だったと言っても過言ではない。
アフリカから連行されたディアスポラの民の、血と涙の労苦なくしてはそうした繁栄はなかったに違いない。
本書によれば、アフリカ奴隷の出身地としては、コンゴ・アンゴラなどの中央アフリカが40パーセント、ベニン湾岸の西アフリカが20パーセントと、それだけで全体の60パーセントを占めていたという。
奴隷の到達地としては、ブラジルが400万人、スペイン領植民地が200万で、奴隷の約半数を占めていた。
さらに、奴隷制を経済的な観点からいうと、アメリカ大陸で売られた奴隷の価格は、17世紀後半から18世紀後半にかけて、4倍以上に値上がりし、しかもその数も3倍弱にふくれあがったらしい。
「一般的には、17世紀後半から18世紀を通じて、対外的な労働力需要の増加に伴い、奴隷の価格は上昇した。たとえば、この時期の奴隷の平均価格は4倍から5倍ほど上昇した。これに対し、奴隷の出荷数は二倍から三倍ほど増加している」
要するに、この時期に奴隷貿易は儲かる産業と化していたことがわかる。その産業に加担していたのが、アメリカ建国の父たちとされる偉人だったのいうのもアメリカ史の逆説だ。
たとえば、独立宣言を執筆した大陸会議の委員長を務めたヴィアージニアのリチャード・ヘンリーは五十人以上の奴隷を所有していたし、第二回大陸会議の議長を務め、アメリカ合衆国の独立に尽力したサウス・キャロライナのヘンリー・ローレンスは奴隷商人かつ最大の奴隷所有者だった。
「奴隷体験記」の活用
本書の特色を一、二挙げるならば、まず網羅的であるという点がある。
大西洋奴隷貿易に果たした「中間航路」の役割から、北米における奴隷制反対運動や逃亡奴隷の活動まで、あるいはイギリス植民地時代の奴隷制と経済から独立以降の米南部の奴隷の生活まで、もれなく詳述されている。
さらには、語る主体として表に出てこなかった奴隷自身の「身の上話」もたくさん引用されていることが重要である。
誰もが認めるように、歴史はメディア(活字や伝達媒体)を占有する者によって作られてきた。アフリカ奴隷はつねに歴史の対象となっても、主体にはならなかった。
ここにきてようやく、歴史学者たちがオーラル・ヒストリーの「奴隷体験記」を史料としてつかうことによって、奴隷あるいはその末裔が歴史の主体となることが可能になったのだ。
フレデリック・ダグラスやハリエット・ジェイコブズらの著作は、すでに有名になっている「奴隷体験記(スレイヴ・ナラティヴ)」だが、
本書では、無名の奴隷による「体験記」を数多くつかっていることが注目に値する。
一例を挙げれば、オラウダ・エクイアーノという男の話がとても印象的である。
「……身の上話の中で、ナイジェリア出身のイボ族と名乗っている。
奴隷を所有していた裕福なコミュニティのメンバーの息子だったが、妹と一緒に誘拐され、西アフリカで何度か売られた後に、イギリスの植民地へ送られた。
誘拐された当時、一一歳だったエクイアーノは、自分と妹が二人組の男女に捕えられた瞬間を鮮明に覚えていた。二人組は屋敷の壁を乗り越えてきて、二人を掴まえ、「口を塞いで」、「すぐ近くの森まで」連れて行き、手を木に縛りつけた。
翌日、誘拐犯はエクイアーノと妹を引き離し、それぞれ別の人間に売り渡した。「二人をばらばらにしないように頼んでも無駄だった」。
「妹は私から離され、すぐに連れ去られた。私は言葉では言い表せないほどの混乱状態に陥った。
私は泣き続け、嘆き、数日間、彼らが私の口に無理やり押し込んだもの以外は何も食べなかった。……(中略)オラウダの最初のアフリカ人の主人は金細工職人であった。
そのため昼間はその仕事を手伝い、夜は家事奴隷の女性と一緒に働いていた。その後、一七二個のタカラガイとの交換で再び売られ、同じ年頃の裕福な少年の遊び相手となった。
エクイアーノは西アフリカの奴隷社会の習慣にならって、その家族に養子縁組されることを望んでいたが、再び売りに出された。
「こうして私は時には陸路で、またある時には水路で、様々な国や地域を旅し続け、誘拐されてから六〜七ヵ月が経った頃、海辺に辿り着いた」
すぐさまエクイアーノは大西洋をわたってカリブ海に向かう奴隷船に乗ることになった。
このような無名の奴隷の語られざる「物語」が何百万、何千万とあるに違いない。つまり、人類をめぐる「歴史」は、まだ書き換えられる可能性があるということである。
私のような読者は、このような「物語」をもっと読んでみたいという衝動に駆られる。
そのような読者のために、ありがたいことに巻末に「注」のかたちで出典情報が載っている。さらなる奴隷制をめぐる「読書の森」へと誘うためである。
また、本文中の固有名詞(人名や土地名など)には、原語がカッコで添えてある。
これもまた小さい工夫だが、興味を抱いた読者がネットや図書館で調べる糸口となるはずだ。
訳文は平易でこなれており、読みやすい。
米国の奴隷制に興味がある初心者に基本的な知見をもたらすだけでなく、いまなおどうして民主主義の国で人種差別がなくならないのか、その理由を読者に示唆する優れた図書だ。