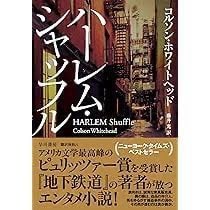制度のゆがみを照らし出す
星野智幸『ひとでなし』(文藝春秋)
越川芳明
この小説を一言であらわすならば、一九七〇年代から現代までのほぼ半世紀を時間軸にして主人公の半生を描き、それと同時に日本の社会制度のゆがみを照らしだす傑作である。
言い換えれば、社会の周縁に追いやられた性的マイノリティや外国人労働者や移民の視点から「常識」を反転させる試みともいえる。
主人公は、作者と同じ一九六五年生まれの鬼村樹(おにむら・いつき)という、アメリカ生まれらしい日本人だ。
そもそも自分の出生地が不明であるという点も、性自認をはじめとする主人公のアイデンティの曖昧さ(多様性)を示唆している。
面白いのは、「架空日記」という着想だ。
主人公は小五のとき、担任の先生から「架空日記」を書くように勧められる。
先生によれば、そうすることで、自分の中の悪い気持ちに「言葉の棲家」を作ってあげることができるからだという。
それ以来ずっと主人公は架空日記を書きつづける。
その中で、イツキはニッキやニッキーやタツキなど、さまざまな分身になり、もうひとつの世界を生きる。
そうすることで、いじめっ子や両親、同級生や同僚などに対する悪感情に「言葉の棲家」を作ることができる。
架空日記とは、先生によれば、自分の中の自分ではわからない意味不明な部分と向き合うことであり、眠っているときに見る「夢」のようなものだという。
この半世紀のあいだに日本はオイルショックによる高度成長の終焉や、「オウム真理教」による騒乱事件、「男女雇用機会均等法」の制定、
アメリカによる湾岸戦争と自衛隊の海外派遣、経済バブル期の到来とその崩壊、東日本大震災とそれに伴う原発事故など、さまざまな想像を絶する歴史的事件に見舞われた。
主人公とその日記の中の分身も、現実か幻想かわからないまま、新興宗教教団らしきものに勧誘されたり、性のゆらぎを体験したり、
日本の家族制度の在り方に疑問を感じたり、在日エクアドル人の女性とのっぴきならない関係になったり、日系ペルー人の経営する会社で働いたりする。
性とは何か、家族とは何か、はたまた日本人とは何かをめぐって、固定観念にがんじがらめになっている日本社会では、夫婦別姓にしろ、同性婚にしろ、根強い反対がある。
主人公はさまざまな失敗や挫折を経て、徐々にそうした制度による「洗脳」から脱していき、制度に縛られない自分、いろいろな自分がいていいのだ、という認識にいたる。
戸籍制度をはじめ、日本の社会制度のいびつさ(ジェンダー格差、外国人差別、婚姻の不平等など)を考えさせる読み物として最適だ。
(『思想運動』2025年1月1日号)
星野智幸『ひとでなし』(文藝春秋)
越川芳明
この小説を一言であらわすならば、一九七〇年代から現代までのほぼ半世紀を時間軸にして主人公の半生を描き、それと同時に日本の社会制度のゆがみを照らしだす傑作である。
言い換えれば、社会の周縁に追いやられた性的マイノリティや外国人労働者や移民の視点から「常識」を反転させる試みともいえる。
主人公は、作者と同じ一九六五年生まれの鬼村樹(おにむら・いつき)という、アメリカ生まれらしい日本人だ。
そもそも自分の出生地が不明であるという点も、性自認をはじめとする主人公のアイデンティの曖昧さ(多様性)を示唆している。
面白いのは、「架空日記」という着想だ。
主人公は小五のとき、担任の先生から「架空日記」を書くように勧められる。
先生によれば、そうすることで、自分の中の悪い気持ちに「言葉の棲家」を作ってあげることができるからだという。
それ以来ずっと主人公は架空日記を書きつづける。
その中で、イツキはニッキやニッキーやタツキなど、さまざまな分身になり、もうひとつの世界を生きる。
そうすることで、いじめっ子や両親、同級生や同僚などに対する悪感情に「言葉の棲家」を作ることができる。
架空日記とは、先生によれば、自分の中の自分ではわからない意味不明な部分と向き合うことであり、眠っているときに見る「夢」のようなものだという。
この半世紀のあいだに日本はオイルショックによる高度成長の終焉や、「オウム真理教」による騒乱事件、「男女雇用機会均等法」の制定、
アメリカによる湾岸戦争と自衛隊の海外派遣、経済バブル期の到来とその崩壊、東日本大震災とそれに伴う原発事故など、さまざまな想像を絶する歴史的事件に見舞われた。
主人公とその日記の中の分身も、現実か幻想かわからないまま、新興宗教教団らしきものに勧誘されたり、性のゆらぎを体験したり、
日本の家族制度の在り方に疑問を感じたり、在日エクアドル人の女性とのっぴきならない関係になったり、日系ペルー人の経営する会社で働いたりする。
性とは何か、家族とは何か、はたまた日本人とは何かをめぐって、固定観念にがんじがらめになっている日本社会では、夫婦別姓にしろ、同性婚にしろ、根強い反対がある。
主人公はさまざまな失敗や挫折を経て、徐々にそうした制度による「洗脳」から脱していき、制度に縛られない自分、いろいろな自分がいていいのだ、という認識にいたる。
戸籍制度をはじめ、日本の社会制度のいびつさ(ジェンダー格差、外国人差別、婚姻の不平等など)を考えさせる読み物として最適だ。
(『思想運動』2025年1月1日号)