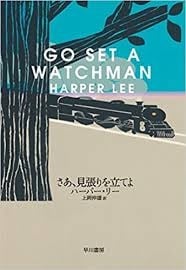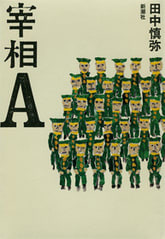「謎」を詰め込んだ「スーツケース」
ファビオ・ヴィスコリオージ『モンブラン』
越川芳明
作家自身を襲ったある出来事が小説の題材になっている。そういう意味では、「ミニマルな宇宙」を書いていると見えなくもない。
語り手の「僕」は、三十一歳のときに突然、両親を失くしてしまう。フランスとイタリアの国境に位置する「モンブラン」のトンネル内で、火災事故に巻き込まれたらしい。
突然、「孤児」になってしまった「僕」は、両親を巻き込んだトンネル事故を追いかける。何の前触れもなく悲劇はやってきたように感じられるが、果たしてその前兆がなかったのかどうか? 事故当日(一九九「九年三月二十四日」のテレビニュースの映像はもちろん、三十九名の死者を出すことになった事故に関するデータを片っ端から集め始める。その資料ファイルは、なんと六十五巻に、資料ナンバーは4559にまで膨れあがる。だが、事件の真相は「探偵小説のように謎めいた展開」を見せていく。
「僕」は、十年間、トンネル事故の真相を探求した結果、ある意味で両親の「墓碑銘」というべき「文学的な記録」を残す。それが本書である。「文学的な」と称するわけは、そのエクリチュールにある。
この「記録」はいくつもの短い断章をつなぎあわせたものだが、一つひとつの断章にはいろいろな「謎」が埋め込まれている。たとえば、両親の葬儀は地域の教会で行われるが、そこで流れるBGMは「僕」がダビングしておいたジャンゴ・ラインハルトの「雲」という曲だったという。ジャンゴ・ラインハルトといえば、知る人ぞ知るジプシーギタの名手である。だが、なぜそのスウィングするジプシージャズを葬儀の曲に選んだのだろうか。「僕」はまるで事実をシンプルに告げただけだというかのように、何の説明も加えない。「僕」が両親の悲劇にまつわる「謎」を追求するように、読者も小説に埋め込まれたいくつもの「謎」について考えざるをえない。
「人は特殊な状況に置かれると、実際にはなんの関係のないもの同士に相関関係を見出して解釈したくなるようだ」(42ページ⇦ゲラでトル)とあるように、やがて「僕」は何を見ても「モンブラン」の事故と結びつけて考えてしまう。「僕」は「モンブラン」に呪縛され、パラノイア(偏執症)患者みたいに、「実際、モンブランはどこでも僕についてきた」と記すまでになる。
さらに、事件の「謎」を追求しているうちに、「僕」はメランコリーに陥る。胸部に痛みを覚えて、循環器内科の診療所を訪れる。そんな場違いな場所で、まともな診断をしてもらえることもなく、「僕」は自分の失望を描く代わりに、診察室にかかっている絵画にさりげなく触れるだけだ。
「医師の左側にはヴァザルリのポスター、反対側にはマティスの複製画ーーちなみにそれは画家一九〇四年に発表したエポックメーキング的作品『豪奢、静寂、逸楽』だったーーがかかっていた」と。
ここにも「謎」が埋め込まれている。ヴァザルリのポスターとマティスの絵画である。私(筆者)が少しだけやってみた「謎解き」によれば、ヴァザルリは一九三〇年代に幾何学的な抽象性を追求したハンガリー系フランス人のアーティスト。六十年代にアメリカで「オプアートの先駆者」として見出されている。理知的な計算にもとづき、錯視効果をもたらす抽象画に特徴があるようだ。
一方、マティスの作品は「野獣派(ルビ:フォーヴィズム)」の出発点とも言われるものだが、一九〇四年に南フランスの保養地コート・ダジュールで製作されている。太陽が燦々と輝く海岸リゾートで楽しむ人々を多彩な原色で描いている。ついでに言えば、その絵画のタイトルは、ボードレールの『悪の華』の一節「旅への誘い」から取られているらしいが、ボードレールは「かの国にては、ものみなは秩序と美、豪奢、静けさ、はた快楽」(堀口大學訳)と書いたが、マティスは最後の部分だけを「引用」して、なぜか「秩序と美」は排除している。それはさらに追求すべき「謎」だ。いずれにしても、診療所に飾ってあった二つのアート作品は、「僕」の暗く混乱した内面のメランコリーとは正反対な世界を表現していると言えそうだ。
そんなメランコリーを癒してくれるのは、文学にほかならない。というのも、「僕」に言わせれば、真に優れた文学は現実の相反する二面性を映し出し、多義的な解釈を許すからで、それによって自分を見つめ直す機会が得られるからだ。
「僕」のお気に入りの文学作品は多国籍にわたっている。ボルヘス、ジョルジュ・ペレック、レーモン・ルーセル、ルイス・キャロル、カフカ、ペソア、ポー、ジャック・ロンドン、ジャック・ケルアック、フィッツジェラルド、小林一茶など・・・。
中でも、注目すべきはスペインの作家エンリーケ・ビラ=マタスであり、その名前は二度登場する。「持ち運びができるスーツケースのように作品を軽量化するというアイディア」こそ、ビラ=マタスが「大切にした精神」だと述べる。いうまでもなく、ビラ=マタスは『ポータブル文学小史』(一九八五年)で、マルセル・デュシャン、マン・レイ、ベンヤミンなどを「ポータブルなもの」を偏愛した作家として取りあげている。
ファビオ・ヴィスコリオージの「小宇宙」を扱った、この小ぶりな作品は、いわば「ポータブル性」を追求した「スーツケース」のような小説の実例なのだ。
「スーツケース」の中に詰め込まれた「謎」は、音楽や文学、芸術、映画、スポーツなどにまつわる固有名詞だが、それらは「僕」の哲学(「小説同様、人生にはつねに笑いと涙が混在する」を暗示するようになっている。しかも、私が一部の箇所で試しにしてみたように、それらの「謎」をリンク機能でデジタル的に追いかけていけば、果てしなく大きな世界を旅することができる。一個のスーツケースを持って大きな宇宙を旅するのは、読者なのだ。(『図書新聞』2018年11月?日号)