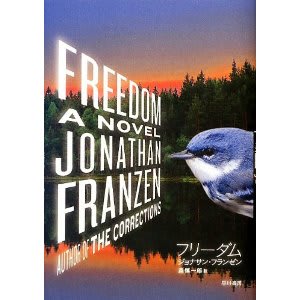小説の「歪曲」 田中慎弥『夜蜘蛛』
越川芳明
田中慎弥にしては、めずらしい書簡体形式の小説である。
しかも、アメリカ作家ジョン・バースの画期的なメタフィクション『やぎ少年ジャイルズ』(一九六六年)のように、
作家である「私」は出版社への仲介者にとどまるという設定だ。
いわゆる「入れ子構造」となっていて、小説家ではない「七十を越えているかどうかの男」(5)が、
小説家の「私」に読んでほしいと書いた(とされる)書簡が作品の中核をなす。
つまり、作家の「私」と書簡の書き手である「私」の、二人の「私」が存在する。
『やぎ少年ジャイルズ』は、アメリカの大学を舞台にしたキャンパス小説で、
その中核は、コンピュータが創作した(とされる)「大学シラバス」。
それが五〇年代から六〇年代にかけての米ソの冷戦構造や学園紛争など、
時代のアクチュアルな実相を比喩的にあぶりだす。
芥川賞を受賞した前作『共喰い』でも、
作家はすでに太平洋戦争のようなアクチュアルな現実と格闘していた。
主人公の母は戦時中の空襲による火事で右手を失い、義手をつけており、
そのことが戦争による「負の遺産」として物語のシルエットをなしている。
だが、そうした歴史の痕跡が、
戦後を生きた一人の女性の生の証として読者の記憶に深く刻まれる逆転劇が用意されており、
不自由な「負の遺産」でしかない義手が血みどろの大立ち回りの主役を演ずるというグロテスクなユーモアが効いていた。
『夜蜘蛛』では、昭和の戦争は最初から前景に配置されている。
書簡の書き手である「私」が語るのは、明治四十三(一九一〇)年生まれの父親の生涯であり、
その父親が三度にわたって出征した戦争についてだ。
そうした「歴史小説」への挑戦には、
これまで作家が書きついできた海峡の街「赤間関」を舞台にした寓話から一歩出ようとする気概が見られる。
だが、作家が得意とする濃密な文体と卓抜なグロテスク・ユーモアを犠牲にしなければならないというマイナスの要素もあり、
そうした試みは両刃の剣だ。
その辺のことは後で述べることにする。
書簡の書き手の「私」の父親は、明治三十四(一九〇一)年の生まれの昭和天皇裕仁より九歳年下だが、
日本が軍国主義路線を敷いて中国をはじめアジアに侵略していくなか、
天皇と同じ時代の空気を吸っていたと言えよう。
たとえば、父親は三度も戦争に召集されたという。具体的に見てみると——
1 昭和六(一九三一)年、満州事変のとき。二十一歳。
2 昭和十二(一九三七)年、盧溝橋事件から日中戦争勃発。二十七歳。
3 昭和十八(一九四三)年、太平洋戦争のとき。三十三歳。召集されたが終戦になり出征せず。
注目すべきは、戦争について普段は語りたがらない父親が「私」に語ってくれた二度目の出征である。
そのとき父親は部隊が全滅するなか、右足を銃弾で撃ち抜かれ、
同僚兵が折り重なっている場所に寄りかかるようにして死んだ振りをして、中国兵の目を欺いて生き延びたという。
ここで、私たちに突きつけられるのは、語りの「主体」の意識の問題である。
先ほど、この小説には二人の「私」がいると述べた。
しかし、「私」の父親もまたもう一人の語り手として少年時代の「私」に二度目の出征時の体験を話したのである。
私たち読者に届けられるのは、父親の言葉そのものではなく、数多くの語り手が介在する口承伝承の物語のごとく、
語り手の「私」による味付けが加えられた父親の戦争体験だ。
実のところ、『夜蜘蛛』は、作家の十八番であるグロテスク・ユーモアを犠牲にしているわけではない。
書簡の書き手の「私」の意識のなかで、荒唐無稽とも言える妄想がおおいに発揮されている。
ちなみに、書き手の「私」は、太平洋戦争開戦の翌年、昭和十七(一九四二)年の生まれで、戦争は体験したものではない。
むしろ、大人の語るものを聴いたものでしかない。
そこに子どもの空想が入りこむ余地が生じる。
父親は「私」に向かって、自分が中国で命拾いした話だけでなく、
『勧進帳』や『忠臣蔵』のような説話や浪花節も語ったらしい。
そのうち、「私」の中で戦争の話と芝居の筋書きが「ごちゃ混ぜになり・・・、ほどけなくなるありさま」(42)となる。
「父が義経、中国兵が富樫という情景が見えてくることもございまして、この場合も、どこからともなく現れます弁慶が、
日本語中国語の区別つけがたい大音声で白紙を読み上げ、あわやというところを父義経は生き延びるのでございます」(59)
極めつきは、昭和七(一九三二)年の関東軍による満州国皇帝溥儀(ルビ:ふぎ)擁立のいきさつが、
「私」の頭の中では、明治十(一八七七)年の「西南戦争」における薩摩と政府の対立と重なってしまうくだりだ。
「これを見た中国兵、まっこと胆の太かお人でごわす、などと言いながら鄭重に(明治帝を)お連れ申しまして、
溥儀を頂く満州国に対抗し、大薩摩中華人民共和国を、文字通りの旗、すなわち天皇を立てることによってまさに旗揚げする」(62)
ここには、二つの歪曲がある。
一つは、西郷隆盛をリーダーとする反乱軍が明治帝を担ぐという点であり、
もう一つは、関東軍による傀儡政府の樹立という作戦に対して、それに抵抗する中華人民共和国のほうに明治天皇が加わるという点。
こうした「私」のとんでもない妄想によって、父親の参加した昭和の戦争がナンセンスなまでに強引に歪曲されている。
バースのメタフィクションは、歴史もまた語られるフィクションにすぎないということを示唆している。
私たちは複雑に絡みあった歴史の事象をまるごと理解することはできずに、
これまでに存在している物語の祖型(ルビ:パターン)を通して理解せざるを得ないからだ。
したがって、いまここで問うべきは、
田中慎弥の『夜蜘蛛』が歴史のアクチュアルな相をあり得ないフィクションの空想で歪めていることの是非ではなく、
むしろ、グロテスク・ユーモアを生じさせるそうした作者の「歪曲」がどれほどの説得力を持って読者に迫ってくるかだ。
だが、そうした「歪曲」が、書簡の書き手の「私」の特殊性に還元されてしまってはいないだろうか。
今後は、田中慎弥にしか書けない濃密かつ執拗な文体で、
周縁者の視座から共同体の“神話”や権力者を笑いのめすようなグロテスク・ユーモアのある「歴史小説」に挑んでほしい。
(『新潮』2013年1月号に、若干手を入れました)