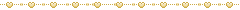やっと出来ました。
今回のは、少々、出来あがりに時間がかかりました。
言葉が降りてきて、一晩ないしは2日もあれば書きあがってしまう小説がある一方で、
不意に浮かんだエピソードが、いつまでたっても動き出さずに、
そのままお蔵入りになってしまうこともあるんです。
今日お届けするお話は、どういうわけか、とてものんびりしていて、
一文ずつ、ゆっくりと繋がっていく感じで仕上がりました。
久しぶりに、
毒にも薬にもならない、いたってフツーな、甘々なカンジになってます。
よろしければ、続きからお付き合いください。
お願いするようで、心苦しいのですが、
もしお気に召したら、小説最後にランキングボタンをぽちっとしていただけると、
とっても嬉しかったりします。
STORY.30 乾いた・花
その夜、外は、何年かぶりの嵐だった。
交通機関は乱れたまんまやし、
街路樹は、強風にさらされて、轟々と音をたてている。
横殴りの雨に、傘はなんの役にもたたず、
俺は、びしょぬれの姿で、どうにか部屋に戻った。
冷たくなった身体を温めようと、
俺はバスルームに向かった。
バスタブに湯を張りながら、俺は濡れたシャツを脱ぐ。
鏡に映った俺。
細い腕。
薄い胸。
もう少し、筋肉があってもええよな。
ここんとこの仕事は、俺には、ハードなシーンが続く。
食べても食べても、動く量には追い付かん。
身体が疲れてる、というより、
連日の緊張感が、俺の神経を昂ぶらせる。
歌うんは、なんでもない。
演じるんも、イヤやない。
ここを抜けたら、また一歩、俺は階段を上がるんやと思う。
ただ、時折、
風が吹き抜けていく気がしてるだけ、や。
うんざりしながら、伸びた髪をかきあげる。
雨に濡れた髪は、重くてわずらわしい。
これ、
この髪、
いつになったら、切れるんやろう。
ちょっと、伸び過ぎたんとちゃうかな。
ちょっとくらい切ってもええかな。
明日は休演日やから、切ってもうたろかな。
「なんで切ったん? 長いほうがええって、言うたのに」
誰かの声が聞こえる気がするな。
もうしばらくは、このままにしとかんと、アカンかな。
湯気のたったバスルームをあとにする。
火照って上気した身体をタオルで包んで、
俺はやっと、深く息をつく。
このままベッドに倒れこんだら、
きっと睡魔が俺を連れ去るだろう。
絶対、風邪ひくけどな。
手近にあったTシャツに袖を通し、
リビングに戻った俺の目に、
携帯の着信を告げる光が、飛び込んできた。
小さな間接照明の中、
それは、
ぽつん、ぽつんと、儚げに瞬いていた。
誰や、こんな夜に。
なんの用やねん。
そう思いながら、俺は携帯を手に取る。
メールの相手は、彼女だった。
『怖い』
たった、ひとこと。
外はものすごい風と雨やからな。
窓閉めてたって、聞こえるやろ。
せやけど、『怖い』って。
大げさなんちゃうん。
どう返事を返したら、安心させられるんか、が、わからへん。
すぐにでも駆けつけて、
そばにおって欲しいんやろけど、
そんなん無理やん。
あいつかて、わかってるはずやのに。
わかってて、ほんでも、このメールなんやったら、
俺、
どないしたらええ?
あいつが望むことやったら、
俺に出来ることやったら、
そら、
叶えてやりたいとは思うてる。
ほんでも。
無理は出来ん。
それだけは、したらアカン。
手づまりのまんま、
ぼんやりとメール画面を見つめてるとこに、
来客を告げるインターホン。
こんな日の、
こんな時間に、客?
ありえへん。
風の悪戯か?
いや、それはないか。
マンション入口は、ちゃんと風除けになってるしな。
「誰?」
小さな画面の向こうに、ずぶ濡れの・・・
待てや、嘘やん。
振り返って窓に目をやる。
遠目にもはっきりと、
窓ガラスを伝うしずくが群れをなす。
俺の指が、慌ててロックを外す。
「早よ、上がって来いッ!」
考えるより先に、叫んでた。
俺の頭ん中では、いろんな疑問符が押し寄せる。
なんでこんなとこにおるん?
どうやって、ここまで?
このメール、いつ、届いたやつや?
『怖い』んとちゃうんかい。
なんぼなんでも・・・!!
無性に腹立たしくなってきてたんを振り切るようにして、
俺は、乾いたバスタオルを手にした。
チャイムを待たずに玄関を出る。
吹き付ける風が、洗ったばかりの俺の髪を乱して視界を遮る。
あかん! やっぱり長いわッ!!!
髪を掻きあげた俺の目に、
たった今、エレベーターホールに辿り着いた彼女の姿が映った。
俺の姿を見て、一瞬だけ、
彼女の身体の動きが止まった。
見え隠れする、躊躇。
それを振り切るかのように、
俺の首すじに抱きつくように手を伸ばし、飛び込んできた。
「おまえは・・・! 何してんねんッ!!」
手にしたタオルで彼女を包みこみながら、俺の語気が荒くなる。
かすかに、小刻みに震える肩。
寒いんか?
それとも・・・?
「怖かった・・・怖かったの。 独りは、イヤなの」
こんな雨風の中、ここまで来る方が怖いやろ。
そう思わんでもなかったが、
とにかく今は、彼女の不安を消してやるんが先か?
震える彼女を抱くようにして、俺は玄関へと彼女を迎えいれた。
風に押されたドアが、大きな音をたてて閉まった。
彼女の体が、おびえたように硬くなる。
バスタオルで彼女の髪を拭いてやりながら、
俺は彼女の体を、俺から離した。
「こんなに濡れて・・・風邪ひいたら、どないすんねん」
彼女の顔を上げさせる。
「俺がおらんかったら、どうするつもりやってん」
「え・・・?」
初めてそれに気づいたかのような彼女の瞳が、俺を見つめた。
気づいて、
彼女の表情が、戸惑っていくのがわかる。
ほんまに、気づかへんかったんやな。
「まあ、ええわ」
俺は彼女をきつく抱き締める。
冷たい彼女の身体の奥に、俺の体温を移してやりたかった。
このまま抱きあって、互いの温もり確かめあうんも、悪くはない。
けど・・・。
俺の胸に顔をうずめる形で、彼女は、安心したように大きく息をした。
「風呂、入って、ちょっとあったまったらええやん。話、それからにしよ」
「いや」
「おい、なんでや。べたついてるやろ、身体」
「離れたくないの、このままがいい。やっと、やっと・・・」
言い淀んだ彼女。
「・・・会えたのに」
俺に抱きつく腕に、決して俺を離すまいとするかのように、力がこもる。
この仕事が始まってからは、確かに忙しいばっかりで、
ろくに会えもせんかったからな。
無理もない、っちゃ、無理もないねんけど。
普段は、さして不満も言わんと、
凛と、自分で自分を支えてる彼女がみせた、小さな、小さなわがまま。
愛しさのかたまりに、出会えた気がして、
俺の中に、ふわりと柔らかな光が差し込んでくる。
風に吹かれて、ささくれ乾いた心に、
温かで穏やかに、差し込む光の渦。
そこで咲く、一輪の花。
俺は、なおも強く彼女を抱きよせて、
彼女の耳元に囁く。
「一緒に、入ろ」
顔をあげた彼女に浮かぶ、とまどいの色。
「そんなん、恥ずかしい・・・」
「よう言うわ。ええやん、たまには」
「でも、着替えもなにも、ないもの」
「大丈夫。洗って乾燥機入れといたら、すぐ乾くわ」
「その間、どうするのよ」
「服、いらへんやろ?」
「え・・・」
「俺が抱いててやるから」
彼女の顔に羞恥の色が浮かぶ。
「怖い、んやろ? ずっと抱いて、傍におったる。
明日の朝には、雨も風も治まってるやろ。
それまで、俺の腕ん中におったらええわ」
「本当に、いいの? 仕事は?」
「そんな心配するくらいなら、来んなや」
「ご、ごめんなさい」
「ええから。怒ったんちゃうって。明日は、休みやから、ええねん」
休み、と聞いて、彼女の顔がほころぶ。
「ずっと、離さないでね。そばにいてね」
「わかってるよ。怖がりやな」
彼女の髪を優しく撫でてやる。
次第に彼女の身体が、俺の腕に、ほどけていった。
風が彼女をさらっていかないように、
俺の腕の中に彼女を、しまいこむ。
雨の音が、彼女の耳に聞こえぬように、
俺は、彼女にささやきつづける。
闇が彼女を襲わぬように、何も考えず眠れるように、
俺の鼓動で、魔法をかけよう。
朝の光が、ふたりを包むまで。
FIN.
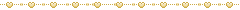
もしお気に召しましたら、
関ジャニWEBランキング
にほんブログ村 男性アイドルグループランキング
ぽちっと押して頂けると、とっても嬉しいです。