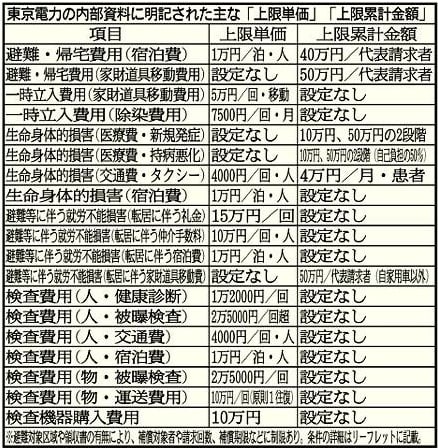がん治療拠点、揺らぐ信頼…東病院で誤検査39項目の事実隠蔽 より転載(産経新聞)
日本のがん治療・新薬研究の最前線に立ち、自らを「がんの専門家集団」と称する組織で、ずさんな検査が行われた上に、問題が隠蔽(いんぺい)されていた。国立がん研究センター東病院(千葉県柏市)の臨床検査部での検査問題。病院関係者によると、腫瘍マーカーの誤使用を含め、大小あわせて39項目もの誤検査などがあったという。医療への信頼を失わせる行為であるだけではなく、日本の新薬戦略を揺るがしかねない行為だ。
◆精度こそ“存在意義”
「臨床検査の世界は『精度ありき』が大前提。正直なところ、こんなことをやっている病院があることに背筋の凍る思いだ」。東京都内のある大学病院の臨床検査技師は今回の問題についてこう印象を語る。
試薬の誤使用以外にも判明した問題の多くは、基準値の誤設定。「基準値」とは一般的に正常な人の約95%がその数値内に当てはまる値で、検査結果が正常か、異常の可能性があるかどうかを示す。
だが、臨床検査部で設定された数値は、「以下」とすべきなのに「未満」とされたものから、単位が本来の100万倍とされたものまであったという。
関係者や院内資料などによると、一連の問題の端緒は平成17年に東病院の臨床検査部で検査機器や試薬が一斉に変更されたことにあるとみられる。
血液検査機器は機械や試薬によって感度や検査法が異なる。しかし、新システムに以前から使っている基準値をそのまま入力・運用したとみられる。
試薬の誤使用もこの時に発生。本来は「βHCG」専用の試薬を使うべきところを、「HCG」と「β」の文字が入っていた別の試薬を、担当者が正しい試薬と誤認した可能性がある。
◆問題をすりかえ
医療関係者の多くは今回の問題について「がん患者の治療に大きな影響はなかった」とみる。
腫瘍マーカーの誤検査で、がんではない人に「がんの疑いあり」という結果が出た可能性があるものの、実際にがんが発生している人を見逃すものではないからだ。基準値の誤設定も、数値の異常が見つかれば、再度別の検査を行うため、患者への影響は回避できたのではないかという。
ただ、がんの専門医は「『疑いあり』とされた人に、本来は必要ない検査を行うなど患者に心理的負担や金銭的な負担を与えた可能性がある」と指摘する。
臨床検査部では問題発覚後、試薬を間違って使っていたことや、誤って基準値を入力していたことを隠蔽。院内には、「機器や試薬の変更で基準値や単位を見直した」と問題をすりかえ、基準値の変更を通知していたという。
同部の関係者は「部内に問題を告発したら処分されるのではないかという雰囲気があった」と隠蔽の事情を説明した。
◆新薬戦略に影響?
問題が与える影響は、一病院の不祥事にとどまらない可能性がある。
厚生労働省は今年7月、世界に先駆けてヒトに初めて新薬や医療機器を投与・使用する初期段階の臨床試験(治験)を実施する国内拠点5施設を選定。東病院は、がん分野の拠点の一つに選ばれた。
治験では、薬の投与が人体にどのような効果や影響を与えるかを正確に読み取る必要があり、血液検査をはじめとした各種検査では厳密なデータ収集が求められている。
医療機関から検査の外部委託を請け負う民間検査会社の幹部は「今回の問題と同じことをわれわれが行ったら、直ちに信用を失い倒産するレベル」と指摘。「同病院に治験の協力を求めることに躊躇(ちゅうちょ)する企業が現れることも考えられる」と憂慮している。
[ 2011年9月28日08時00分 ]
日本のがん治療・新薬研究の最前線に立ち、自らを「がんの専門家集団」と称する組織で、ずさんな検査が行われた上に、問題が隠蔽(いんぺい)されていた。国立がん研究センター東病院(千葉県柏市)の臨床検査部での検査問題。病院関係者によると、腫瘍マーカーの誤使用を含め、大小あわせて39項目もの誤検査などがあったという。医療への信頼を失わせる行為であるだけではなく、日本の新薬戦略を揺るがしかねない行為だ。
◆精度こそ“存在意義”
「臨床検査の世界は『精度ありき』が大前提。正直なところ、こんなことをやっている病院があることに背筋の凍る思いだ」。東京都内のある大学病院の臨床検査技師は今回の問題についてこう印象を語る。
試薬の誤使用以外にも判明した問題の多くは、基準値の誤設定。「基準値」とは一般的に正常な人の約95%がその数値内に当てはまる値で、検査結果が正常か、異常の可能性があるかどうかを示す。
だが、臨床検査部で設定された数値は、「以下」とすべきなのに「未満」とされたものから、単位が本来の100万倍とされたものまであったという。
関係者や院内資料などによると、一連の問題の端緒は平成17年に東病院の臨床検査部で検査機器や試薬が一斉に変更されたことにあるとみられる。
血液検査機器は機械や試薬によって感度や検査法が異なる。しかし、新システムに以前から使っている基準値をそのまま入力・運用したとみられる。
試薬の誤使用もこの時に発生。本来は「βHCG」専用の試薬を使うべきところを、「HCG」と「β」の文字が入っていた別の試薬を、担当者が正しい試薬と誤認した可能性がある。
◆問題をすりかえ
医療関係者の多くは今回の問題について「がん患者の治療に大きな影響はなかった」とみる。
腫瘍マーカーの誤検査で、がんではない人に「がんの疑いあり」という結果が出た可能性があるものの、実際にがんが発生している人を見逃すものではないからだ。基準値の誤設定も、数値の異常が見つかれば、再度別の検査を行うため、患者への影響は回避できたのではないかという。
ただ、がんの専門医は「『疑いあり』とされた人に、本来は必要ない検査を行うなど患者に心理的負担や金銭的な負担を与えた可能性がある」と指摘する。
臨床検査部では問題発覚後、試薬を間違って使っていたことや、誤って基準値を入力していたことを隠蔽。院内には、「機器や試薬の変更で基準値や単位を見直した」と問題をすりかえ、基準値の変更を通知していたという。
同部の関係者は「部内に問題を告発したら処分されるのではないかという雰囲気があった」と隠蔽の事情を説明した。
◆新薬戦略に影響?
問題が与える影響は、一病院の不祥事にとどまらない可能性がある。
厚生労働省は今年7月、世界に先駆けてヒトに初めて新薬や医療機器を投与・使用する初期段階の臨床試験(治験)を実施する国内拠点5施設を選定。東病院は、がん分野の拠点の一つに選ばれた。
治験では、薬の投与が人体にどのような効果や影響を与えるかを正確に読み取る必要があり、血液検査をはじめとした各種検査では厳密なデータ収集が求められている。
医療機関から検査の外部委託を請け負う民間検査会社の幹部は「今回の問題と同じことをわれわれが行ったら、直ちに信用を失い倒産するレベル」と指摘。「同病院に治験の協力を求めることに躊躇(ちゅうちょ)する企業が現れることも考えられる」と憂慮している。
[ 2011年9月28日08時00分 ]