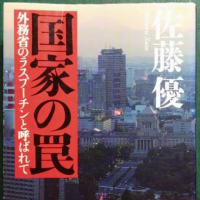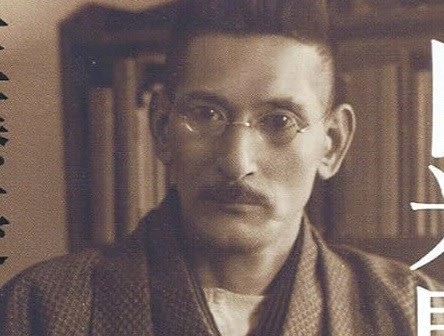
創価学会の「内在的論理」を理解するためといって、創価学会側の文献のみを読み込み、創価学会べったりの論文を多数発表する佐藤優氏ですが、彼を批判するためには、それこそ彼の「内在的論理」を理解しなくてはならないと私は考えます。
というわけで、こんな本を読んでみました。
佐藤優/大川周明「日米開戦の真実-大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く」

興味深い内容でしたので、引用したいと思います。
この本の特徴は、戦前の思想家・大川周明の著書である『米英東亜侵略史』のテキストを2部に分けて再現し、その間に著者・佐藤優氏の解説を挟み込むという形式をとっていることです。
この形式は、佐藤氏が創価学会系の雑誌『潮』に記事を連載するときや、その著書「池田大作研究」を書いた時のスタイルと共通するものです。
さらに言えば、私がいろいろな本を読んでブログで引用する際に、記事の最後に【解説】として私見を述べていますが、そのスタイルにも通じます。
そこで、読者が読みやすく理解しやすいように、あたかも佐藤氏がこのブログを書いているかのように、私のブログのスタイルをまねて、この本の内容を再構成してみました。
必要に応じて、改行したり、文章を削除したりしますが、内容の変更はしません。
なるべく私(獅子風蓮)の意見は挟まないようにしますが、どうしても付け加えたいことがある場合は、コメント欄に書くことにします。
ご理解の上、お読みください。
日米開戦の真実
――大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く
□はじめに
■第一部 米国東亜侵略史(大川周明)
■第二部「国民は騙されていた」という虚構(佐藤優)
□第三部 英国東亜侵略史(大川周明)
□第四部 21世紀日本への遺産(佐藤優)
□あとがき
米国東亜侵略史(大川周明)
第三日 鉄道王ハリマン
太平洋を世界政局の中心たらしめるもの
支那に対するアメリカの門戸開放提唱は、いつもながらのアメリカ流儀で、甚だ堂々たるものではありましたが、内実は昨日申し上げた通り、一つには支那におけるアメリカの利益を保護し、また一つには列強の対支進出を消極的に阻止する目的をもって行われたものであり、その上この提唱によって格別の効果を挙げることも出来なかったのであります。その提唱者である国務長官ジョン・ヘイが、すでに次のように申しております。
「予は支那人に向かって、アメリカに与えておらぬような特権を他国に与えるなと激励した時に、支那人は文字通りこう応えた――もし他国が武力に訴えてきた場合、支那だけではこれに抵抗出来ないが、貴国はその時に支那に味方してくれるかと。予は残念ながら、その通りであると答えることが出来なかった。ここに米国の根本的弱点がある。我らは支那を掠奪しようと思わないが、他国が支那を掠奪する場合、我が国の世論は武力をもってこれに干渉するのを許さない。その上、我らは十分なる兵力をもっていない」
このような次第でアメリカは東亜進出の準備と態度だけは整えましたが、大体立ち遅れていたのでありますから、決して易々と目的を遂げることは出来なかったのであります。
ただし、この頃に至って太平洋の重要性は何人にも明白になり、19世紀における世界政局の中心は大西洋でありましたが、20世紀に入って舞台は明らかに太平洋に移り、従って覇を太平洋に称えることが、取りも直さず世界的覇権を握ることを意味するようになったのであります。
新興アメリカ精神の権化というべきセオドア・ルーズヴェルトは、最も明瞭にこの間の消息を看取し、1905年6月17日付で友人B・I・ホウィーラーに宛てた手紙の中に、アメリカの将来は、ヨーロッパと相対する大西洋上のアメリカの地位によってに非ず、支那と相対する太平洋上の地位によって定まるのだと明言しております。
それならば太平洋をして世界政局の中心たらしめるのは何故であるか。何が太平洋をしてそのように重大なものたらしめるか。実は、その岸に沿って支那満蒙が横たわっているからであります。太平洋を巡る周囲の国々、洋上に浮かぶ大小の島々は、すでに欧米列強の領有するところとなり、または欧米勢力の確立を見たのでありますが、独り東亜だけにおいては、なお未だいずれの国の勢力も、絶対に圧倒的ではなかったのであります。列強がなお競争角逐を試みる余地があり、しかもなお未だ十分に開発されていない厖大な国土あるがゆえに、太平洋は限りなく価値あるものとなっているのであります。ここには列強がその工場を養うべき豊富なる資源が、なお未だ開発されずに埋もれています。たとえ貧乏であるとはいえ、4億の人口を擁することは、欧米列強にとって無二の市場であります。
例えば昭和初年において、日本では毎年一人当たり38円ずつ外国品を買っておりますが、支那ではわずかに3円70銭前後、すなわち我が国の十分の一に足らぬほどしか買っておりません。もし支那人が一人当たり10円ずつ外国品を買うようになれば40億円、20円ずつ買うようになれば実に80億円の大金が、外国商人の懐に落ちるのであります。そればかりでなく、支那の国情が安定すれば、資本を投じてこれほど儲かる国はありません。鉄道一本敷くにしても南米などに敷いたのでは、鉄道沿線一帯が開拓され尽くすまでの何十年間は、猿や鸚鵡でも乗せなければ、荷物も客もないのであります。ところが支那ならば、鉄道開通の明日から、旅客にも貨物にも困らないのであります。
ハリマンの「満鉄買収策」
このような事情でありますから、支那が欧米列強進出の最大目標となったことに、何の不思議もありません。それゆえにアメリカにとっては、太平洋を支配するということは、東亜を支配するという意味であります。東亜を支配するということは、支那満蒙における資源の開発、その広大なる市場の獲得、その高率なる投資利益において、他国よりも優越した地歩を確立するという意味であります。さればこそルーズヴェルトは、先程の手紙の中にただ漠然と太平洋とは申さず、実に「支那と相対する太平洋」と銘打っているのであります。そしてアメリカの太平洋進出、従って東亜進出は、日露戦争直後から初めて大胆無遠慮となってきたのであります。
すべての攻撃または進出は、常に抵抗力の最も薄弱だと考えられる方向に向かって試みられます。そうであるならばアメリカは、多年にわたる東亜進出計画をいよいよ実行に移すに当たって、どこを最小抵抗と睨んだか。それが満蒙であります。日露戦争によって国力を弱めていた日本の勢力圏満蒙が、実にアメリカ進出の目標となったのであります。
ルーズヴェルトの調停によって行われた日露両国の講和談判が、なおポーツマスにおいて進行中のことであります。アメリカの鉄道王と呼ばれたハリマンが、条約によって日本のものとなるべき南満州鉄道を買収するために、1905年8月下旬、秘かに日本に来朝したのでありますが、極力彼に奨めてこの来朝を促したのは、時の東京駐在米国公使グリスカムであります。
ハリマンがいかなる弁舌をふるって日本政府を籠絡したかは詳しく存じませんが、日本は遂に彼の提議を容れて、驚くべき内容を有する覚書が、10月20日付をもって桂首相とハリマンとの間に成立したのであります。その内容とは、満鉄及び満鉄に属する鉱山その他各種事業の権利の半ばを、ハリマンの支配するシンジケートに譲渡し、これに相当する代金を受け取るということであります。そしてハリマンは、この覚書を手に入れたその日の午後に、直ぐさま横浜から船に乗って帰国の途に上りました。
そのちょうど3日後に、ポーツマス条約を携えて帰朝した小村全権が、その覚書を見て驚き、かつ憤り、極力反対を唱えて遂に政府を動かし、これを取り消させたのであります。日本政府が何故に満鉄をアメリカに売る決心をしたかは、我々の今日に至るまで不可解とするところであります。日本は文字通り、国運を賭してロシアと戦い、多大の犠牲を払って勝利を得ましたものの、これによって日本が獲得したところのものは、必ずしも大でなかったのであります。
日本国民はハリマンが秘かに東京に来たころに、講和談判に不平を唱えて焼き打ちの騒動となり、戒厳令まで敷かれたのであります。それなのにその少なき獲物のうちから、満鉄をアメリカに売ってしまえば、勝利の結果を全く失い去るに等しいのであります。当時もし、日本国民がハリマン来朝の真意を知ったならば、その激昂は一層猛烈であったに相違ありません。想うにハリマンは、日本が経済的危機に迫っていたのに乗じ、講和談判斡旋の恩を笠に着て、日本から満鉄利権の半分を見事に奪い取ったもので、もし小村全権が敢然これに反対しなかったならば、おそらく日本の大陸発展が、この時すでにアメリカのために阻止されてしまうはずであったのであります。
このハリマン満鉄買収策は、きわめて大規模なる計画の一部であったのであります。その計画とは、まず第一に満鉄を手に入れ、次いでロシアの疲弊に乗じて東支鉄道を買収し、こうしてシベリア鉄道を経てヨーロッパに至る交通路を支配し、鉄道の終点大連及び浦塩から、太平洋を汽船でアメリカの西海岸と結び、大陸横断鉄道によって東海岸に至り、東海岸から汽船で大西洋をヨーロッパと結ぶ交通系統、すなわち世界一周船車連絡路をアメリカの手に握る第一歩として、満鉄を日本から買収しようとしたのであります。
日本が東亜進出の障碍に
さて、ルーズヴェルトが日露の間に立って講和談判の斡旋をするまでは、これまで申し上げてきたように、アメリカは大体において常に日本に好意を示してきたのであります。しかしハリマンの計画ひとたび失敗するに及んで、日本に対するアメリカの態度は、次第に従前とは違ってきたのであります。それはアメリカが、日本をもってアメリカの東洋進出を遮る大いなる障碍であると考えはじめたからであります。ここにアメリカの甚だしき無反省と横暴とがあります。
東亜発展は日本にとって死活存亡の問題であります。さればこそ国運を賭してロシアと戦ったのであります。ところがアメリカの東洋進出は、持てるが上にも持たんとする贅沢の沙汰であります。アメリカはその贅沢なる欲望を満たさんがために、日露戦争によって日本が東亜に占め得たる地位を、無理矢理奪い去らんとしたのであります。実にこの時より以来、アメリカは日本の必要止むなき事情を無視し、傍若無人の横車を押しはじめたのであります。
横車の第一は、日露戦争の終わった翌年すなわち1906年に、突如当時の東京駐在代理公使ウィルソンをして、下のような提言を日本政府に向かって為さしめたことであります。
「満州における日本官憲の行動は、すべて日本商業の利益を扶植し、日本人民のために財産権を取得せんとするにありて、このため該地の日本軍隊の撤退を了する頃には、他の外国の通商に充つべき余地は希有、もしくは絶無たるに至るべく、世界列国の正当なる企業並びに通商に対する門戸開放に同意すといえども、日本従来の僭越なる専権に鑑み、こうした行動は合衆国政府の甚だ遺憾とするところなり。日本政府は、露国があえて該地方に実質的の国家的統制を為さんとして失敗せるに鑑み、切に反省せん事を望む」
こういう乱暴な文句をつけたのであります。十万の生霊を犠牲にし、二十億の金を使って、満州からロシア勢力を駆逐したのでありますから、ここに日本が商業的発展を試み、あらゆる企業を計画することは、当然至極のことなるにかかわらず、すでに日露戦争の翌年から、アメリカはこのような横槍を入れております。
次には翌1907年のことであります。支那において事業を営むことを主としているイギリスのボーリング商会が、秘かに支那と交渉を進め、京奉線すなわち奉天から北京に至る鉄道の一駅新民屯から、まず北方法庫門に至り、ゆくゆくは北へ北へと延ばしてシベリア鉄道と連絡する斉々哈爾(チチハル)までの鉄道敷設権を獲得したのであります。当時の奉天のアメリカ総領事は、有名なストレートであります。
応諾させられた満州の門戸開放
ストレートは成功しなかった米国のセシル・ローズと言われ、1901年コーネル大学を卒業すると直ちに支那に赴き、ロバート・ハートの下にあって支那海関に3年勤務し、日露戦争の勃発と共に新聞記者となって朝鮮に赴き、ここで京城駐在米国公使に知られ、その私設秘書兼副領事を務め、その時に日本来朝のついでに朝鮮を旅行したハリマンと相識り、大いに鉄道王の尊敬を博したのでありますが、1906年、わずか26歳にして奉天総領事となって赴任したのであります。ひとりハリマンのみならず、ルーズヴェルトもタフトも、皆ストレートを非常に重んじていました。
このストレートは、あらゆる機会を捉えて日本を抑えつけ、アメリカの力を満州に扶植する覚悟で着任したのでありますから、ボーリング商会が法庫門鉄道敷設権を獲得しますと、彼は直ちにアメリカをこれに割り込ませたのであります。この鉄道は満鉄と並行して、シベリア鉄道と渤海湾とを結びつけるものでありますから、この鉄道が敷かれることになると、満鉄は大打撃を受けなければなりません。今日においても満州農産物の最も多いところは北満一帯でありますゆえに、そこから出る農産物が満鉄を経ずに、営口または葫蘆島に出ることになれば、日本は満鉄をもっていても何の甲斐もないことになります。
従って、小村全権が北京において満州善後条約を支那と結んで、次のように約束しております――「支那政府は南満州鉄道の利益を保護する目的をもって、自ら該鉄道を回収する以前においては、該鉄道の付近において、もしくはこれに並行していかなる鉄道をも敷設せず、また該鉄道の利益を害するいかなる支線をも敷設せず」。支那がこういう約束をしておきながら、ボーリング商会に法庫門鉄道の敷設を許可することは、疑いもなく条約違反でありますゆえに、日本は強硬にこれに抗議し、遂に支那をして一旦与えた許可を取り消させたのであります。
さりながら、ストレートは、決してそれくらいのことで思い止むものでありません。彼は翌1908年、支那当局者との間に満州銀行設立の約束を結んだのであります。当時支那の政治の実権を握っていたのは袁世凱であります。袁世凱は、日露戦争前並びに日露戦争中は、我が国に非常なる好意を示していたのであります。それはロシアという共同の敵があったからであります。ところが日露戦争以後、ロシアに代わって日本が満州に勢力を張るに至りますと、今度はアメリカの力を借りて日本の満州における発展を掣肘(せいちゅう)しようという方針に変えたのであります。この袁世凱の親米政策を利用して、ストレートは当時の東三省総督・徐世昌及び奉天督弁・唐紹儀と相図り、満州における鉄道の敷設並びに産業の開発を主目的として、その金融機関たる満州銀行を建てることを承諾させ、2000万ドル借款の仮契約を結んで、よろこび勇んでアメリカに帰っていったのであります。アメリカはこの銀行を機関として、満州において日本と角逐して鉄道並びに事業を始めようとしたのであります。ところが日本にとって幸福であったことには、この年袁世凱が政変のために失脚し、彼の政敵だった醇親王が支那の政治を執るようになりましたので、ストレートの計画は今度も失敗に終わったのであります。
また、この年すなわち1908年11月に、アメリカは時の駐米日本大使高平小五郎に対し、日本は満州において決して他国の事業の邪魔をせぬ、門戸開放・機会均等の主義を忠実に守ると約束せよと提議し、日本をしてこれを応諾させたのであります。このようにしていわゆる高平・ルート協定の成立を見たのであります。
【佐藤氏による解説】
日本に好意的だったアメリカの豹変
アメリカは日露戦争を注意深く観察し、漁夫の利を得ようとしていた。アメリカにとって、太平洋を支配することは、中国、日本、朝鮮を支配し、さらにそこからシベリア経由でロシアに影響を及ぼし、全世界に覇権を及ぼす目的のために不可欠だった。ここに太平洋で日本とアメリカが衝突する根本的な原因が生まれたのである。1905年のポーツマス講和会議で、アメリカが善意の仲介を行ったので、日本は日露戦争を勝利することができたという見方は根強い。確かにアメリカの仲介がなかったら、日本はもっと不利な条件でロシアと平和条約を締結することを余儀なくされたであろう。
しかし、アメリカは善意で仲介活動を行ったのではない。戦争で疲弊した日露両国の状況を冷静に分析した上で、アメリカの利権拡大を図ったのである。ラジオ放送で大川はこの経緯について詳しく説明しているので、少々長くなるが引用しておく。
ルーズヴェルトの調停によって行われた日露両国の講和談判が、なおポーツマスにおいて進行中のことであります。アメリカの鉄道王と呼ばれたハリマンが、条約によって日本のものとなるべき南満州鉄道を買収するために、1905年8月下旬、秘かに日本に来朝したのでありますが、極力彼に奨めてこの来朝を促したのは、時の東京駐在米国公使グリスカムであります。
ハリマンがいかなる弁舌をふるって日本政府を籠絡したかは詳しく存じませんが、日本は遂に彼の提議を容れて、驚くべき内容を有する覚書が、10月20日付をもって桂首相とハリマンとの間に成立したのであります。その内容とは、満鉄及び満鉄に属する鉱山その他各種事業の権利の半ばを、ハリマンの支配するシンジケートに譲渡し、これに相当する代金を受け取るということであります。そしてハリマンは、この覚書を手に入れたその日の午後に、直ぐさま横浜から船に乗って帰国の途に上りました。
そのちょうど3日後に、ポーツマス条約を携えて帰朝した小村全権が、その覚書を見て驚き、かつ憤り、極力反対を唱えて遂に政府を動かし、これを取り消させたのであります。日本政府が何故に満鉄をアメリカに売る決心をしたかは、我々の今日に至るまで不可解とするところであります。日本は文字通り国運を賭してロシアと戦い、多大の犠牲を払って勝利を得ましたものの、これによって日本が獲得したところのものは、必ずしも大でなかったのであります。
日本国民はハリマンが秘かに東京に来たころに、講和談判に不平を唱えて焼き打ちの騒動となり、戒厳令まで敷かれたのであります。それなのにその少なき獲物のうちから、満鉄をアメリカに売ってしまえば、勝利の結果を全く失い去るに等しいのであります。当時もし日本国民がハリマン来朝の真意を知ったならば、その激昂は一層猛烈であったに相違ありません。想うにハリマンは、日本が経済的危機に迫っていたのに乗じ、講和談判斡旋の恩を笠に着て、日本から満鉄利権の半分を見事に奪い取ったもので、もし小村全権が敢然これに反対しなかったならば、おそらく日本の大陸発展が、この時すでにアメリカのために阻止されてしまうはずであったのであります。
このハリマン満鉄買収策は、きわめて大規模なる計画の一部であったのであります。その計画とは、まず第一に満鉄を手に入れ、次いでロシアの疲弊に乗じて東支鉄道を買収し、こうしてシベリア鉄道を経てヨーロッパに至る交通路を支配し、鉄道の終点大連及び浦塩から、太平洋を汽船でアメリカの西海岸と結び、大陸横断鉄道によって東海岸に至り、東海岸から汽船で大西洋をヨーロッパと結ぶ交通系統、すなわち世界一周船車連絡路をアメリカの手に握る第一歩として、満鉄を日本から買収しようとしたのであります。
大川の分析は鋭い。そのポイントを5点に整理して検証しよう。
第一に、アメリカは日本が戦争で疲弊していることを十分見抜いていた。ポーツマスで、セオドア・ルーズヴェルト大統領があたかも日本に対して好意的な仲介をしているような顔をしているその裏で、満鉄とその付属利権の半分をハリマンの鉄道会社に売却する謀略を進めていた。この謀略に日本政府はあやうく乗せられるところで、桂太郎首相は、アメリカ側の提案を受け入れる覚書を作ってしまった。しかし、見事だったのは、小村寿太郎外相がそのようなアメリカの嘘を見抜き、一旦、首相が約束した協定を白紙に戻したことである。
第二に、日本の弱みにつけ込み、アメリカが自己の利権を拡大しようとしたのは、帝国主義国としてごく当たり前のことである。その画策を見抜き、「日本人を騙すことは簡単ではない」ということを覚書の白紙撤回という形で示した当時の日本外交は実にあっぱれなのである。“世界史の時代”においては、このように帝国主義国が相互に裏をかいて自国の利益だけを貪欲に追求していくことが「ゲームのルール」なのである。このようにアメリカ、日本がしのぎを削っていくのも時代の要請なのだ。
第三に、アメリカの満鉄買収計画は、ハリマンという一企業家の思いつきによるものではなく、アメリカの国策に基づいていた。アメリカ大陸横断鉄道で太平洋に出て、そこから汽船で満鉄の終着駅大連とシベリア鉄道の終着駅ウラジオストクをつなぎ、さらにシベリア大陸横断鉄道を経由してヨーロッパ大陸の大西洋に至り、そこから汽船でアメリカ東海岸に至る利権をアメリカが全て独占しようとしたのである。航空路が発展していない当時、この交通網を抑えることは、世界の人的交流、物流の大部分をアメリカが握るということに外ならなかった。軍事力ではなく、経済力でアメリカは世界制覇を狙ったのである。
第四に、日本が満鉄利権の譲渡を拒否した後、アメリカは次の戦略を考える。中国政府を説得し、満鉄に並行して走る鉄道の敷設権を得ることだ。大川はこの計画について、「この鉄道は満鉄と並行して、シベリア鉄道と渤海湾とを結びつけるものでありますから、この鉄道が敷かれることになると、満鉄は大打撃を受けなければなりません」とその危険性を正確に指摘している。日本側の巧みな外交工作が成功し、アメリカは並行鉄道の敷設を実現できなかった。
第五に、ポーツマス講和会議後、日米関係は質的に変化していく。このことが戦略的に最も重要だ。日露戦争までは、アメリカは日本に対して好意的だった。日本の国力を過小評価し、取るに足りない相手と考えていたのであろう。しかし、ハリマンの鉄道買収計画が失敗した後、アメリカの日本に対する目付きが悪くなってくる。日本がアメリカの要求に「ノー」と言ったことに対し、アメリカは苛立ちを強めるのである。そして、日本がアメリカの太平洋制覇と中国進出を妨げる主要な障害と考えるようになってくる。アメリカの帝国主義的野望と後発帝国主義国として国力の強化を図る日本の戦略が軋轢をもたらすようになってきたのである。
構成・文責:獅子風蓮