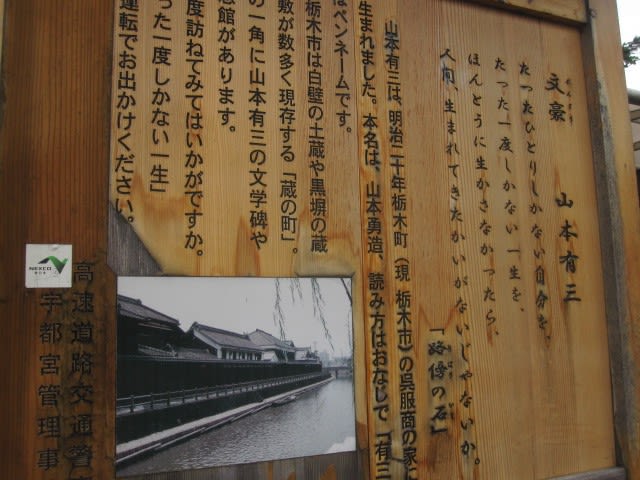「自分史」から
日露戦争から第一次世界大戦を経て、大正12年に関東大震災、大正14年は普通選挙交付またラジオ放送が始まった。
ドイツではヒットラーが『わが闘争』を出版し、世界の情報も急にスピード化してくる。
昭和に入ると、蒋介石の国民党の大改革があり、毛沢東は江西省片岡山に根拠地を構えた。昭和3年、第1次張作林爆死事件発生。蒋介石が前面に出てくる。日本の第一山東出兵が始まった。
昭和6年、満州事変となる。
経済では、昭和4年、ニューヨーク、ウオール街の株価が大暴落し、世界は大恐慌に陥る。
人口ばかりがふえ、資源の乏しい日本への影響は大きかった。オーストリア中央銀行が破産、ドイツに大きく波及、金融恐慌で失業者が町に溢れた。
世界は大変な不況に陥っていく。
第一次世界大戦は、ヨーロッパ中心の民族的対立を背景にした世界戦争であった。
その時の同盟国を見ると、ドイツ、オーストリア、トルコ、ブルガリア4カ国と
イギリス、アメリカ、フランス、ロシア、イタリア、と日本であった。
「第二次世界大戦」は、
経済が絡む世界大恐慌で、世界は再分割されていった。
後進資本国の日本、ドイツ、イタリアは、高い技術を持っていたが資源は無く、先進国イギリス、アメリカなどの経済制裁を受け、国民が食べていけなくなると言う深刻な問題を抱えていたのだ。
昭和6年、犬養首相が暗殺され、世にいう5.15事件がおき、軍部が力をつけていく。
昭和14年、ドイツではヒットラー、アメリカではルーズベルトが政権を握り、これが、やがて始まる第二次世界大戦への導火線となっていった。
“軍人に賜りたる勅論”
一つ 軍人は忠節を尽くすを本分とすべし、
一つ 軍人は礼儀を正しくすべし、
一つ 軍人は信義を重んすべし……。
その頃の歌 “兵隊さんありがとう”
肩を並べて兄さんと、今日にも学校へ行けるのは、兵隊さんのお陰です、
お国のために、お国のために戦った、兵隊さんのお陰です、
私は、その2度とない激動の昭和日本に生まれ育ち、少年時代から平成、現代までの状況を書き残しておきたいと思い立ったのである。
私が生まれたのは、1938年の昭和13年8月15日。
昭和11年、2・26事件が起がおきている。翌年中国盧溝橋において日・中両軍がぶつかり日中戦争が始まった。
昭和13年国家総動員法が公布された。
翌年になるとアメリカが日米通商条約を破棄してきた。ソ連との間でも、ノモンハン事件がおきている。
1939年ヨーロツパでは、ドイツがポーランドに侵攻、ソ連との間で全面戦争となっていった。
第2次世界大戦の火蓋がいよいよ切られたのである。
翌1940年日独伊3国同盟が結ばれ、1941年、昭和16年日本にもついに米英との全面戦争に突入した。
初戦は、優勢だった日本軍は、やがて劣勢となり1944年(昭和19年)サイパン島の日本守備隊が全滅。
それからずるずると後退していくのである。
その頃からアメリカのB29による本土空襲が激しくなってきた。
私たち、一家は父のみを東京に残し埼玉県秩父郡影森村という山奥に疎開した。東京に生活していた者にとっては、それはそれは寒いひもじいつらい疎開生活であった。
昭和20年8月15日終戦。私は村の国民学校1年生だった。
夏休み中であったが其の日、当時国民学校を宿舎として駐留していた兵隊たちと一緒に校庭で玉音放送を聞いた。
当時の教育により、まだ小学一年生だったが、やがては、自分も兵隊さんたちの後をついで、死を覚悟で戦いに行くのだと心に決めていた。
玉音放送はよくわからなかったが、日本が負けたと聞かされ、悔しさと悲しさで胸が張り裂けそうになった記憶がある。
そのときはそのように思いつめたが、早くもその夜、これでやっと東京に帰れるのだ、もう空襲はないのだという安心感、またうれしさで胸が一杯になり眠れなかった。しかし、そのように感じることは何となく罪深いことだと思っていた。
小学生だった私の未熟な頭ではあるがこんなことを考えていた。
・もしドイツが大敗していなければ、
・アメリカにあれだけの資源が無ければ、
・ドイツ、日本に作戦ミスが無かったなら、
・もう一国資源のある大国が同盟であったなら、日本は決して負けなかっただろう。
強兵の掛け声のもと、人間の限界まで鍛えぬかれた日本兵は、世界で1番強い。負けるのはおかしいと疎開から東京に戻るまで信じていた。
この年の9月半ば親とともに帰京。あの荒れ果てた焼け野原を目にしたとき、敗戦という現実を知った。荒廃した東京は表現できないほどであった。
上野駅に着いたのは夕方の4時ごろだったと思う。人、人で駅の構内から駅前、西郷さんの銅像、アメヨコ、ガード下にゲートルを巻いた引揚者がいぱっいであった。親子
ずれの乞食、浮浪児、さらに死んでいる赤ん坊の姿も目にした。
ガード下では死体となって横たわる中年乞食の体には蛆虫がわいていた。
スリをした1人の浮浪児が、大男につかまり殴られ頭から血を出していた。
浮浪児は一生懸命謝ったが、その大男はそれでもやめずに叩き続け、3メートルあまりふっ飛ばした。
少年は私と同年ぐらいと思われた。
周りの大人たちはただ見ているだけだった。・・・・・・。
ここで太平洋戦争のこと。
日本は(1941年)昭和16年12月8日真珠湾奇襲とマレー半島上陸作戦で米・英と戦争に入って真珠湾作戦は宣戦布告が外務省の手落ちにより、アメリカへの通告が遅れ「だまし討ち」といわれている。心ならずも残念なことだ。また、肝心の敵航空母艦が湾に不在だったことが悔やまれる。
マレー半島作戦は2ヶ月で1,100kmを突破、翌年2月15日シンガポールが陥落させた緒戦の勝利には目を見張るものがあった。昭和14年9月欧州でドイツが破竹のいきおいでポーランドを攻め、ドイツ有利に戦いを進めている中、3国同盟を結んだ。 このことが対米戦争にまで至ったのは一部の政治家、一部の軍隊の独走によると言う解釈がよく言われるが、事実は日本国民大半がこの決定には、共感していたのだ。その後の戦いが不利に転じ、ついには負けてしまうが、その主な原因は、ミツドウエイ海戦で戦艦「大和」を活用しなかったなど、むしろ山本五十六の消極的作戦に問題があったと私は思う
俳優の三国連太郎氏があるテレビで「日本に帰ったとき子供たちがアメリカ兵にお菓子を求めている姿を見て悲しかった」と言っていた。大人達も必死だったのはわかる、しかし子供たちには何の力もない、どれだけひもじい思いをして多くの子供が死んでいったか。それを見ていながら、当時の大人たちはいったい何をしてくれたのか。終戦記念日が来るたびに悲しい。
昭和20年3月10日の東京大空襲はB29が334機襲来、焼夷弾総重量1667t投下、一夜で10万人あまりが死亡。4月18日東京を中心に6都市空襲。
多数の犠牲者が出た。・・・・・・・・。
「那須戦争博物館」正面入り口(左に棗の木が、明治38年ロシア司令官ステッカ会見に中国産ナツメの木)

明治の軍服乃木陸軍大将

97式中型戦車

敷地6700坪・建物420坪・総展示数15000点。

住所ー那須町高久(那須街道・御用邸隣接)


陸軍戦闘機

日本軍ロケット砲

砲弾

砲弾

海軍60k爆弾他

大活躍した「ゼロ戦」




昭和6年頃、初の臨時ニュース「満州事変」勃発。・国産映画のトーキー化・内閣は、浜口雄幸から若槻礼次郎(民政党)
16年頃、松岡外相日・ソ中立条約調印・御前会議で日米戦争決定・小学校を国民学校と改称 内閣華族近衛文麿から陸軍東条英機。
日露戦争から第一次世界大戦を経て、大正12年に関東大震災、大正14年は普通選挙交付またラジオ放送が始まった。
ドイツではヒットラーが『わが闘争』を出版し、世界の情報も急にスピード化してくる。
昭和に入ると、蒋介石の国民党の大改革があり、毛沢東は江西省片岡山に根拠地を構えた。昭和3年、第1次張作林爆死事件発生。蒋介石が前面に出てくる。日本の第一山東出兵が始まった。
昭和6年、満州事変となる。
経済では、昭和4年、ニューヨーク、ウオール街の株価が大暴落し、世界は大恐慌に陥る。
人口ばかりがふえ、資源の乏しい日本への影響は大きかった。オーストリア中央銀行が破産、ドイツに大きく波及、金融恐慌で失業者が町に溢れた。
世界は大変な不況に陥っていく。
第一次世界大戦は、ヨーロッパ中心の民族的対立を背景にした世界戦争であった。
その時の同盟国を見ると、ドイツ、オーストリア、トルコ、ブルガリア4カ国と
イギリス、アメリカ、フランス、ロシア、イタリア、と日本であった。
「第二次世界大戦」は、
経済が絡む世界大恐慌で、世界は再分割されていった。
後進資本国の日本、ドイツ、イタリアは、高い技術を持っていたが資源は無く、先進国イギリス、アメリカなどの経済制裁を受け、国民が食べていけなくなると言う深刻な問題を抱えていたのだ。
昭和6年、犬養首相が暗殺され、世にいう5.15事件がおき、軍部が力をつけていく。
昭和14年、ドイツではヒットラー、アメリカではルーズベルトが政権を握り、これが、やがて始まる第二次世界大戦への導火線となっていった。
“軍人に賜りたる勅論”
一つ 軍人は忠節を尽くすを本分とすべし、
一つ 軍人は礼儀を正しくすべし、
一つ 軍人は信義を重んすべし……。
その頃の歌 “兵隊さんありがとう”
肩を並べて兄さんと、今日にも学校へ行けるのは、兵隊さんのお陰です、
お国のために、お国のために戦った、兵隊さんのお陰です、
私は、その2度とない激動の昭和日本に生まれ育ち、少年時代から平成、現代までの状況を書き残しておきたいと思い立ったのである。
私が生まれたのは、1938年の昭和13年8月15日。
昭和11年、2・26事件が起がおきている。翌年中国盧溝橋において日・中両軍がぶつかり日中戦争が始まった。
昭和13年国家総動員法が公布された。
翌年になるとアメリカが日米通商条約を破棄してきた。ソ連との間でも、ノモンハン事件がおきている。
1939年ヨーロツパでは、ドイツがポーランドに侵攻、ソ連との間で全面戦争となっていった。
第2次世界大戦の火蓋がいよいよ切られたのである。
翌1940年日独伊3国同盟が結ばれ、1941年、昭和16年日本にもついに米英との全面戦争に突入した。
初戦は、優勢だった日本軍は、やがて劣勢となり1944年(昭和19年)サイパン島の日本守備隊が全滅。
それからずるずると後退していくのである。
その頃からアメリカのB29による本土空襲が激しくなってきた。
私たち、一家は父のみを東京に残し埼玉県秩父郡影森村という山奥に疎開した。東京に生活していた者にとっては、それはそれは寒いひもじいつらい疎開生活であった。
昭和20年8月15日終戦。私は村の国民学校1年生だった。
夏休み中であったが其の日、当時国民学校を宿舎として駐留していた兵隊たちと一緒に校庭で玉音放送を聞いた。
当時の教育により、まだ小学一年生だったが、やがては、自分も兵隊さんたちの後をついで、死を覚悟で戦いに行くのだと心に決めていた。
玉音放送はよくわからなかったが、日本が負けたと聞かされ、悔しさと悲しさで胸が張り裂けそうになった記憶がある。
そのときはそのように思いつめたが、早くもその夜、これでやっと東京に帰れるのだ、もう空襲はないのだという安心感、またうれしさで胸が一杯になり眠れなかった。しかし、そのように感じることは何となく罪深いことだと思っていた。
小学生だった私の未熟な頭ではあるがこんなことを考えていた。
・もしドイツが大敗していなければ、
・アメリカにあれだけの資源が無ければ、
・ドイツ、日本に作戦ミスが無かったなら、
・もう一国資源のある大国が同盟であったなら、日本は決して負けなかっただろう。
強兵の掛け声のもと、人間の限界まで鍛えぬかれた日本兵は、世界で1番強い。負けるのはおかしいと疎開から東京に戻るまで信じていた。
この年の9月半ば親とともに帰京。あの荒れ果てた焼け野原を目にしたとき、敗戦という現実を知った。荒廃した東京は表現できないほどであった。
上野駅に着いたのは夕方の4時ごろだったと思う。人、人で駅の構内から駅前、西郷さんの銅像、アメヨコ、ガード下にゲートルを巻いた引揚者がいぱっいであった。親子
ずれの乞食、浮浪児、さらに死んでいる赤ん坊の姿も目にした。
ガード下では死体となって横たわる中年乞食の体には蛆虫がわいていた。
スリをした1人の浮浪児が、大男につかまり殴られ頭から血を出していた。
浮浪児は一生懸命謝ったが、その大男はそれでもやめずに叩き続け、3メートルあまりふっ飛ばした。
少年は私と同年ぐらいと思われた。
周りの大人たちはただ見ているだけだった。・・・・・・。
ここで太平洋戦争のこと。
日本は(1941年)昭和16年12月8日真珠湾奇襲とマレー半島上陸作戦で米・英と戦争に入って真珠湾作戦は宣戦布告が外務省の手落ちにより、アメリカへの通告が遅れ「だまし討ち」といわれている。心ならずも残念なことだ。また、肝心の敵航空母艦が湾に不在だったことが悔やまれる。
マレー半島作戦は2ヶ月で1,100kmを突破、翌年2月15日シンガポールが陥落させた緒戦の勝利には目を見張るものがあった。昭和14年9月欧州でドイツが破竹のいきおいでポーランドを攻め、ドイツ有利に戦いを進めている中、3国同盟を結んだ。 このことが対米戦争にまで至ったのは一部の政治家、一部の軍隊の独走によると言う解釈がよく言われるが、事実は日本国民大半がこの決定には、共感していたのだ。その後の戦いが不利に転じ、ついには負けてしまうが、その主な原因は、ミツドウエイ海戦で戦艦「大和」を活用しなかったなど、むしろ山本五十六の消極的作戦に問題があったと私は思う
俳優の三国連太郎氏があるテレビで「日本に帰ったとき子供たちがアメリカ兵にお菓子を求めている姿を見て悲しかった」と言っていた。大人達も必死だったのはわかる、しかし子供たちには何の力もない、どれだけひもじい思いをして多くの子供が死んでいったか。それを見ていながら、当時の大人たちはいったい何をしてくれたのか。終戦記念日が来るたびに悲しい。
昭和20年3月10日の東京大空襲はB29が334機襲来、焼夷弾総重量1667t投下、一夜で10万人あまりが死亡。4月18日東京を中心に6都市空襲。
多数の犠牲者が出た。・・・・・・・・。
「那須戦争博物館」正面入り口(左に棗の木が、明治38年ロシア司令官ステッカ会見に中国産ナツメの木)

明治の軍服乃木陸軍大将

97式中型戦車

敷地6700坪・建物420坪・総展示数15000点。

住所ー那須町高久(那須街道・御用邸隣接)


陸軍戦闘機

日本軍ロケット砲

砲弾

砲弾

海軍60k爆弾他

大活躍した「ゼロ戦」




昭和6年頃、初の臨時ニュース「満州事変」勃発。・国産映画のトーキー化・内閣は、浜口雄幸から若槻礼次郎(民政党)
16年頃、松岡外相日・ソ中立条約調印・御前会議で日米戦争決定・小学校を国民学校と改称 内閣華族近衛文麿から陸軍東条英機。