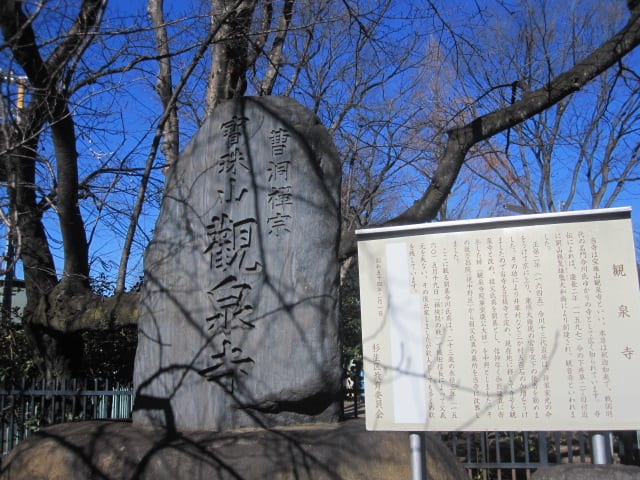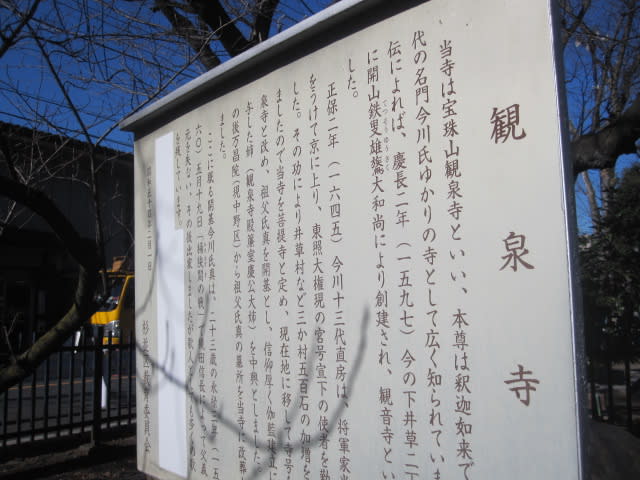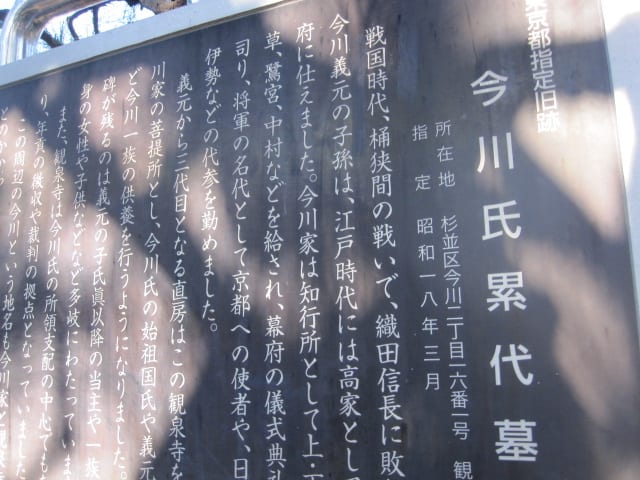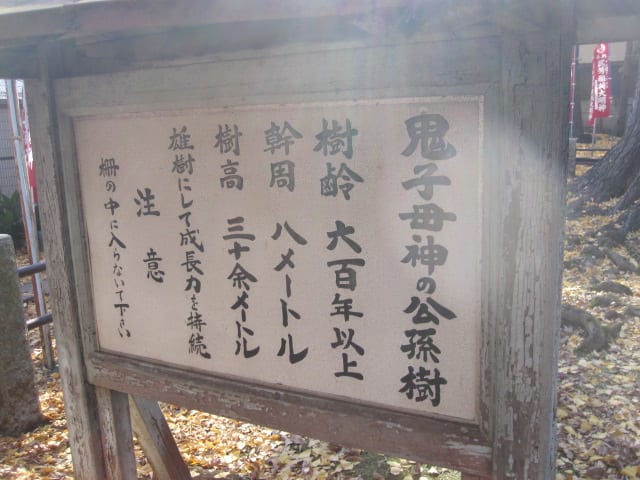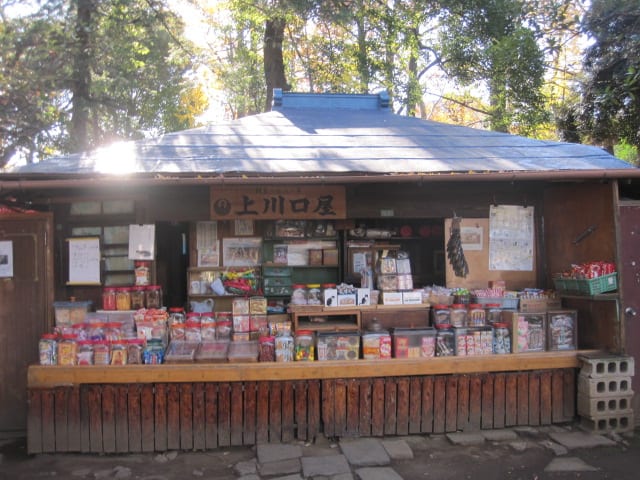「浅野総一郎 1848-1931
越中藪田(現富山県氷見市)に百姓の長子として生まれ、1871年に東京の上京。
お茶の水で水売りを初め、竹の皮商から薪炭商へ転じ、コークスの売り込みに成功。
「渋沢栄一」氏の知遇を得、投機商人から産業資本家への道を開き、官営・深川セメント製造所を貸与。
1884年払い下げを受け、浅野工場ー浅野セメントを設立。
同郷の安田善次郎氏の援助で、1896年ー東洋汽船を創立、太平洋航路を開き、豪華船を就航させたが、第1次大戦後の不況で衰退し、その経営を日本郵船に譲り、1913年には安田氏の協力の下、鶴見・川崎海岸の埋め立てに着手し、16年浅野造船所、18年浅野製鉄所(後に両社とも日本鋼管に吸収合併)を設立するなど、多面的な産業王国を築いた。(平凡社の大百科事典より)
ここ、御茶ノ水で水売りからー浅野総一郎氏。

「駿河台」
元は北の本郷台地の南端に当たる部分が「駿河台」
江戸幕府二代将軍・徳川秀忠の命を受けた仙台藩祖「伊達政宗」が、1620年に、仙台堀ー神田川を開削したことにより湯島台と駿河台とに分離され
孤立した高台となった。
現在、神田川を挟んで北側に位置する湯島台とは、聖橋とお茶の水橋により台地上端の標高で結ばれている。
削って、その土を下町に埋められた。

高層ビルは、東京医科歯科大学と附属病院 (教養学部は千葉県市川市国府台)

朝の御茶ノ水橋(駅拡張工事中)

JR総武線と中央線が平行して。

昌平坂



「湯島聖堂」
江戸時代の元禄3年・1690年、江戸幕府5代将軍徳川綱吉によって建てられた孔子廟であり、後に幕府直轄の学問所となった。
湯島天満宮(湯島天神)とともに、年間(特に受験シーズン)を通して合格祈願のために、参拝に来る受験生が訪れるると云う。
「林羅山」が、上野忍が岡(現在の上野恩賜公園)の私邸内に建てた忍岡聖堂「先聖殿」に代わる孔子廟を造営し、将軍綱吉がこれを「大成殿」と改称して自ら額の字を執筆した。
元禄4年、に神位の奉遷が行われて完成され、「林家」の学問所も当地に移転した。
孔子の聖堂が

今日も若い学生たちが

万世橋付近昔は、東京でも指折りの繁華街で、万世橋駅のある神田須田町は、東京市電の乗り換えターミナル。
大正3年に東京駅が開業し、中央本線が東京駅まで開通すると万世橋駅はターミナルとしての役割を終え、中間駅に。
大正12年ー関東大震災で駅舎が焼失し、大正14年には2代目駅舎が完成したが、非常に質素なものだったと云う。昭和11年に移転してきた
交通博物館と併設する形でホームと直結、昭和18年、不要とみなされ、万世橋駅は役目を終えている。

「昌平橋」は、最初に橋が架設されたのは寛永年間の1624年 - 1645年頃。
橋の南西にある淡路坂の坂上に一口稲荷社があったことから「一口橋」や「芋洗橋」と称したと云う。
「新板江戸大絵図」(寛文五枚図)には、「あたらし橋(新し橋)」、元禄初期の江戸図には「相生橋」とも記されている。
1691年(元禄4年)に徳川綱吉が孔子廟である湯島聖堂を建設した際、孔子生誕地である魯国の昌平郷にちなんで、1691年3月1日に「昌平橋」と命名されたとある。



「都道405号・外濠環状線」
港区新橋一丁目を起点~港区新橋二丁目を終点。
皇居(旧江戸城)外濠に沿った環状の「特例都道」。
本線の通称は「外堀通り」延長12,375m。環状道路、その形は中央通りとの重複を避けるべく少し歪んでいる区間がある。
開通区間の新橋四丁目から虎ノ門二丁目までの支線と、特許庁前付近から昌平橋交差点までの本線は環状第2号線の一部を構成すると云う。


「聖橋」
関東大震災の復興橋梁として昭和2年、完成した橋。
橋長92.47m,幅員22mのアーチ橋で,神田川の景観に美しく溶け込んでいる。
「聖橋」という橋の名前の由来は,北側にある国指定の史跡で江戸幕府の官学所となっていた「湯島聖堂」と,南側にある国指定の重要文化財でビザンチン風建築の「日本ハリストス正教会復活大聖堂(ニコライ堂)」の両聖堂にちなんでいる。
「お茶の水」とは将軍のお茶用の湧き水があったことから名付けられたと云う。

聖橋の朝日


越中藪田(現富山県氷見市)に百姓の長子として生まれ、1871年に東京の上京。
お茶の水で水売りを初め、竹の皮商から薪炭商へ転じ、コークスの売り込みに成功。
「渋沢栄一」氏の知遇を得、投機商人から産業資本家への道を開き、官営・深川セメント製造所を貸与。
1884年払い下げを受け、浅野工場ー浅野セメントを設立。
同郷の安田善次郎氏の援助で、1896年ー東洋汽船を創立、太平洋航路を開き、豪華船を就航させたが、第1次大戦後の不況で衰退し、その経営を日本郵船に譲り、1913年には安田氏の協力の下、鶴見・川崎海岸の埋め立てに着手し、16年浅野造船所、18年浅野製鉄所(後に両社とも日本鋼管に吸収合併)を設立するなど、多面的な産業王国を築いた。(平凡社の大百科事典より)
ここ、御茶ノ水で水売りからー浅野総一郎氏。

「駿河台」
元は北の本郷台地の南端に当たる部分が「駿河台」
江戸幕府二代将軍・徳川秀忠の命を受けた仙台藩祖「伊達政宗」が、1620年に、仙台堀ー神田川を開削したことにより湯島台と駿河台とに分離され
孤立した高台となった。
現在、神田川を挟んで北側に位置する湯島台とは、聖橋とお茶の水橋により台地上端の標高で結ばれている。
削って、その土を下町に埋められた。

高層ビルは、東京医科歯科大学と附属病院 (教養学部は千葉県市川市国府台)

朝の御茶ノ水橋(駅拡張工事中)

JR総武線と中央線が平行して。

昌平坂



「湯島聖堂」
江戸時代の元禄3年・1690年、江戸幕府5代将軍徳川綱吉によって建てられた孔子廟であり、後に幕府直轄の学問所となった。
湯島天満宮(湯島天神)とともに、年間(特に受験シーズン)を通して合格祈願のために、参拝に来る受験生が訪れるると云う。
「林羅山」が、上野忍が岡(現在の上野恩賜公園)の私邸内に建てた忍岡聖堂「先聖殿」に代わる孔子廟を造営し、将軍綱吉がこれを「大成殿」と改称して自ら額の字を執筆した。
元禄4年、に神位の奉遷が行われて完成され、「林家」の学問所も当地に移転した。
孔子の聖堂が

今日も若い学生たちが

万世橋付近昔は、東京でも指折りの繁華街で、万世橋駅のある神田須田町は、東京市電の乗り換えターミナル。
大正3年に東京駅が開業し、中央本線が東京駅まで開通すると万世橋駅はターミナルとしての役割を終え、中間駅に。
大正12年ー関東大震災で駅舎が焼失し、大正14年には2代目駅舎が完成したが、非常に質素なものだったと云う。昭和11年に移転してきた
交通博物館と併設する形でホームと直結、昭和18年、不要とみなされ、万世橋駅は役目を終えている。

「昌平橋」は、最初に橋が架設されたのは寛永年間の1624年 - 1645年頃。
橋の南西にある淡路坂の坂上に一口稲荷社があったことから「一口橋」や「芋洗橋」と称したと云う。
「新板江戸大絵図」(寛文五枚図)には、「あたらし橋(新し橋)」、元禄初期の江戸図には「相生橋」とも記されている。
1691年(元禄4年)に徳川綱吉が孔子廟である湯島聖堂を建設した際、孔子生誕地である魯国の昌平郷にちなんで、1691年3月1日に「昌平橋」と命名されたとある。



「都道405号・外濠環状線」
港区新橋一丁目を起点~港区新橋二丁目を終点。
皇居(旧江戸城)外濠に沿った環状の「特例都道」。
本線の通称は「外堀通り」延長12,375m。環状道路、その形は中央通りとの重複を避けるべく少し歪んでいる区間がある。
開通区間の新橋四丁目から虎ノ門二丁目までの支線と、特許庁前付近から昌平橋交差点までの本線は環状第2号線の一部を構成すると云う。


「聖橋」
関東大震災の復興橋梁として昭和2年、完成した橋。
橋長92.47m,幅員22mのアーチ橋で,神田川の景観に美しく溶け込んでいる。
「聖橋」という橋の名前の由来は,北側にある国指定の史跡で江戸幕府の官学所となっていた「湯島聖堂」と,南側にある国指定の重要文化財でビザンチン風建築の「日本ハリストス正教会復活大聖堂(ニコライ堂)」の両聖堂にちなんでいる。
「お茶の水」とは将軍のお茶用の湧き水があったことから名付けられたと云う。

聖橋の朝日