「江川太郎左衛門」
世直し江川大明神ー享和元年の1801年、江川英毅の次男として韮山で生まれる。幼名は芳次郎。
江川家は、大和源氏の系統で鎌倉時代以来の歴史を誇る家柄である。
代々の当主は太郎左衛門を名乗り、江戸時代には伊豆韮山代官として天領の民政に従事した。
英龍はその36代目の当主・父・英毅が長命だった為に英龍が代官職を継いだのは、1835年、35歳の時とやや遅い。
この間の英龍はやや悠々自適に過ごし、江戸に遊学して岡田十松に剣を学び、同門の斎藤弥九郎と親しくなり、彼と共に代官地の領内を行商人の姿で隠密に歩き回ったりしている。
甲斐国では、1836年、甲斐一国規模の天保騒動が発生し、騒動では多くの無宿(博徒)が参加し、江川は、騒動が幕領の武蔵・相模へ波及することを警戒し、伊豆・駿河の廻村から韮山代官所へ帰還して騒動の発生を知ると、斎藤弥九郎を伴い正体を隠して甲斐へ向かう(甲州微行)。
江川は、甲府代官・井上十左衛門から騒動の鎮圧を知ると韮山へ帰還し、その後も弥九郎との関係は終生続いたと云う。
父・英毅は民治に力を尽くし、商品作物の栽培による増収などを目指した人物として知られるが、英龍も施政の公正に勤め、二宮尊徳を招聘して農地の改良などを行った。
また、嘉永年間に種痘の技術が伝わると、領民への接種を積極的に推進した。
こうした領民を思った英龍の姿勢に領民は彼を「世直し江川大明神」と敬愛、現在に至っても彼の地元・韮山では江川へ強い愛着を持っていると云う。
海防に強い問題意識を。
江川は、民政の改革尽力し、幕府開明派官僚の一人高島流砲術習得し、佐久間象山などの門弟を集めている。・黒船来航2年後に激務過労で病死。
江川は、この地で農民を対象に洋式調錬を行っている。
「韮山反射炉」-幕末期の代官江川英龍が手がけ、後を継いだその子英敏が完成させました。反射炉とは、金属を溶かし大砲などを鋳造するための溶解炉。韮山反射炉は、実際に稼働した反射炉。
「農兵節ー富士の白雪朝日に溶ける 三島女郎衆の化粧水・・・」碑がある。
「小松宮彰仁親王」 1846-1903
安政5年の1858年、仁孝天皇の猶子となり、親王宣下を受け純仁親王を号し、仁和寺第三十世の門跡に就任した。
慶応3年の1867年、復飾を命ぜられ仁和寺宮嘉彰親王と名乗る。明治維新にあっては、議定、軍事総裁に任じられ、戊辰戦争では、奥羽征討総督として官軍の指揮を執った。明治3年の1870年、宮号を東伏見宮に改め、明治7年、勃発した佐賀の乱においては征討総督として、また、同10年、の西南戦争にも旅団長として出征し乱の鎮定に当たった。
明治14年、維新以来の功労を顕彰され、家格を世襲親王家に改められる。
明治15年、宮号を仁和寺の寺域の旧名小松郷に因んで小松宮に改称した。
親王は、ヨーロッパの君主国の例にならって、皇族が率先して軍務につくことを奨励し、自らも率先垂範した。
明治23年に、陸軍大将に昇進し、近衛師団長、参謀総長を歴任、日清戦争では征清大総督に任じられ旅順に出征、明治31年、元帥府に列せられる。
「二宮浅間神社」

「神社」は、三島駅南口の市芝本町にある神社。
「延喜式神名帳」にある「伊賀牟比売命神社(伊豆国・賀茂郡)」に比定される式内社・伊豆国三宮のち二宮に。
三嶋大社の摂社、あるいは別宮だったという。
三嶋大社八所別宮の一つとも。伊豆山神社の本地仏・十一面千手千眼観音の仏名から「浅間」の神名に転訛したとも言われる。
伊豆山神社やその境内社に比定される式内社「火牟須比命神社」の遥拝所、もとは伊豆国三宮であったが、二宮八幡宮が三嶋大社の境内に遷座して後、二宮に昇格、あるいは二宮として扱われるようになったという。
かつては富士登山をする者が必ず当社に詣でるのを常としたという。
境内周辺より湧き出た水は、下流町村の潅概用水、
御祭神は木花開耶姫命・波布比売命。相殿に瓊々杵命・火明命・火蘭降命・彦火々出見命を祀る。例祭は7月15日・16日。
明治10年3月の三島宿の大火に類焼し、明治12年、復興。
御祭神は高産霊神。本殿の下に大きな円形の石があり、霊石と称し、昔から子供の守神として知られている。

社殿

三島市立公園「楽寿園」の庭園と隣接している。

「楽寿園」は、三島駅南口南側に位置する広さ約75,474㎡の市民公園。
今から約1万2千年前に富士山が噴火した時流れ出た、溶岩流の末端にあたると考えられている。この溶岩は、「三島溶岩流」と呼ばれ、現在でも小浜池を中心とする園内各所で見ることができる。
溶岩塚の集合した高まりが小浜山(現三島北高校~楽寿園付近)。
溶岩流の末端にあたるため小浜池、菰池・白滝などの湧水地になる。約1800年前の古墳時代では、耕作に不向きな土地のため居住地としては利用されず墓地として使用された形跡があり、楽寿園西口付近に1基、東口付近に1基古墳が確認されているという。
この地は三嶋大社との関わりも深く、小浜池は神職の「禊みそぎ」の場として使用され、三嶋大社の祭典中、大祭は沼津の千本浜で浜下りが行われ、小祭は小浜で浜下りが行われたことから、この地は「小浜池」と呼ばれるようになったともいう。
江戸時代の小浜池周辺は、数多くの寺社やお堂が建ち並び、農業用水や生活用水に必要な水源地、宿場北の小浜山一帯は、無宿人などのねぐらになったほか、処刑場(現在の三島駅北口新幹線ホームの西端付近)などがあったという。
国の天然記念物及び名勝指定 楽寿園(三島市立公園) 有料

宝永大噴火は、歴史時代の富士山三大噴火の一つであり、他の二つは平安時代に発生した「延暦の大噴火(800年 - 802年)」と「貞観の大噴火(864年 - 866年)」である。宝永大噴火以後、現在に至るまで富士山は噴火していない。
特徴は噴煙の高さが上空20kmと推定される[5]火山爆発指数VEI5[1]のプリニー式噴火と大量の火山灰である。
実際に100 km離れた江戸にも火山灰が積もった。ただし溶岩の流下は見られていない。
地下20km付近のマグマが滞留することなく上昇したため、脱水及び発泡と脱ガスが殆ど行われず、爆発的な噴火となったと云う。
噴火がみられたのは富士山の東南斜面であり、合計3つの火口が形成された(宝永山)。これらは標高の高い順に第一、第二、そして第三宝永火口とよばれ、互いに重なり合うように並んでいる。
1707年宝永大噴火の溶岩

富士山の噴火は、御殿場・三島~駿河湾とかなりの量の溶岩・火山灰・泥流などが堆積したのが判る。
三島駅の中心地に溶岩が今でも

小松宮親王別邸跡 梅御殿

名勝 小浜池



寿橋



霧時雨 富士を見ぬ日ぞ 面白き 芭蕉

三島は終わります。
世直し江川大明神ー享和元年の1801年、江川英毅の次男として韮山で生まれる。幼名は芳次郎。
江川家は、大和源氏の系統で鎌倉時代以来の歴史を誇る家柄である。
代々の当主は太郎左衛門を名乗り、江戸時代には伊豆韮山代官として天領の民政に従事した。
英龍はその36代目の当主・父・英毅が長命だった為に英龍が代官職を継いだのは、1835年、35歳の時とやや遅い。
この間の英龍はやや悠々自適に過ごし、江戸に遊学して岡田十松に剣を学び、同門の斎藤弥九郎と親しくなり、彼と共に代官地の領内を行商人の姿で隠密に歩き回ったりしている。
甲斐国では、1836年、甲斐一国規模の天保騒動が発生し、騒動では多くの無宿(博徒)が参加し、江川は、騒動が幕領の武蔵・相模へ波及することを警戒し、伊豆・駿河の廻村から韮山代官所へ帰還して騒動の発生を知ると、斎藤弥九郎を伴い正体を隠して甲斐へ向かう(甲州微行)。
江川は、甲府代官・井上十左衛門から騒動の鎮圧を知ると韮山へ帰還し、その後も弥九郎との関係は終生続いたと云う。
父・英毅は民治に力を尽くし、商品作物の栽培による増収などを目指した人物として知られるが、英龍も施政の公正に勤め、二宮尊徳を招聘して農地の改良などを行った。
また、嘉永年間に種痘の技術が伝わると、領民への接種を積極的に推進した。
こうした領民を思った英龍の姿勢に領民は彼を「世直し江川大明神」と敬愛、現在に至っても彼の地元・韮山では江川へ強い愛着を持っていると云う。
海防に強い問題意識を。
江川は、民政の改革尽力し、幕府開明派官僚の一人高島流砲術習得し、佐久間象山などの門弟を集めている。・黒船来航2年後に激務過労で病死。
江川は、この地で農民を対象に洋式調錬を行っている。
「韮山反射炉」-幕末期の代官江川英龍が手がけ、後を継いだその子英敏が完成させました。反射炉とは、金属を溶かし大砲などを鋳造するための溶解炉。韮山反射炉は、実際に稼働した反射炉。
「農兵節ー富士の白雪朝日に溶ける 三島女郎衆の化粧水・・・」碑がある。
「小松宮彰仁親王」 1846-1903
安政5年の1858年、仁孝天皇の猶子となり、親王宣下を受け純仁親王を号し、仁和寺第三十世の門跡に就任した。
慶応3年の1867年、復飾を命ぜられ仁和寺宮嘉彰親王と名乗る。明治維新にあっては、議定、軍事総裁に任じられ、戊辰戦争では、奥羽征討総督として官軍の指揮を執った。明治3年の1870年、宮号を東伏見宮に改め、明治7年、勃発した佐賀の乱においては征討総督として、また、同10年、の西南戦争にも旅団長として出征し乱の鎮定に当たった。
明治14年、維新以来の功労を顕彰され、家格を世襲親王家に改められる。
明治15年、宮号を仁和寺の寺域の旧名小松郷に因んで小松宮に改称した。
親王は、ヨーロッパの君主国の例にならって、皇族が率先して軍務につくことを奨励し、自らも率先垂範した。
明治23年に、陸軍大将に昇進し、近衛師団長、参謀総長を歴任、日清戦争では征清大総督に任じられ旅順に出征、明治31年、元帥府に列せられる。
「二宮浅間神社」

「神社」は、三島駅南口の市芝本町にある神社。
「延喜式神名帳」にある「伊賀牟比売命神社(伊豆国・賀茂郡)」に比定される式内社・伊豆国三宮のち二宮に。
三嶋大社の摂社、あるいは別宮だったという。
三嶋大社八所別宮の一つとも。伊豆山神社の本地仏・十一面千手千眼観音の仏名から「浅間」の神名に転訛したとも言われる。
伊豆山神社やその境内社に比定される式内社「火牟須比命神社」の遥拝所、もとは伊豆国三宮であったが、二宮八幡宮が三嶋大社の境内に遷座して後、二宮に昇格、あるいは二宮として扱われるようになったという。
かつては富士登山をする者が必ず当社に詣でるのを常としたという。
境内周辺より湧き出た水は、下流町村の潅概用水、
御祭神は木花開耶姫命・波布比売命。相殿に瓊々杵命・火明命・火蘭降命・彦火々出見命を祀る。例祭は7月15日・16日。
明治10年3月の三島宿の大火に類焼し、明治12年、復興。
御祭神は高産霊神。本殿の下に大きな円形の石があり、霊石と称し、昔から子供の守神として知られている。

社殿

三島市立公園「楽寿園」の庭園と隣接している。

「楽寿園」は、三島駅南口南側に位置する広さ約75,474㎡の市民公園。
今から約1万2千年前に富士山が噴火した時流れ出た、溶岩流の末端にあたると考えられている。この溶岩は、「三島溶岩流」と呼ばれ、現在でも小浜池を中心とする園内各所で見ることができる。
溶岩塚の集合した高まりが小浜山(現三島北高校~楽寿園付近)。
溶岩流の末端にあたるため小浜池、菰池・白滝などの湧水地になる。約1800年前の古墳時代では、耕作に不向きな土地のため居住地としては利用されず墓地として使用された形跡があり、楽寿園西口付近に1基、東口付近に1基古墳が確認されているという。
この地は三嶋大社との関わりも深く、小浜池は神職の「禊みそぎ」の場として使用され、三嶋大社の祭典中、大祭は沼津の千本浜で浜下りが行われ、小祭は小浜で浜下りが行われたことから、この地は「小浜池」と呼ばれるようになったともいう。
江戸時代の小浜池周辺は、数多くの寺社やお堂が建ち並び、農業用水や生活用水に必要な水源地、宿場北の小浜山一帯は、無宿人などのねぐらになったほか、処刑場(現在の三島駅北口新幹線ホームの西端付近)などがあったという。
国の天然記念物及び名勝指定 楽寿園(三島市立公園) 有料

宝永大噴火は、歴史時代の富士山三大噴火の一つであり、他の二つは平安時代に発生した「延暦の大噴火(800年 - 802年)」と「貞観の大噴火(864年 - 866年)」である。宝永大噴火以後、現在に至るまで富士山は噴火していない。
特徴は噴煙の高さが上空20kmと推定される[5]火山爆発指数VEI5[1]のプリニー式噴火と大量の火山灰である。
実際に100 km離れた江戸にも火山灰が積もった。ただし溶岩の流下は見られていない。
地下20km付近のマグマが滞留することなく上昇したため、脱水及び発泡と脱ガスが殆ど行われず、爆発的な噴火となったと云う。
噴火がみられたのは富士山の東南斜面であり、合計3つの火口が形成された(宝永山)。これらは標高の高い順に第一、第二、そして第三宝永火口とよばれ、互いに重なり合うように並んでいる。
1707年宝永大噴火の溶岩

富士山の噴火は、御殿場・三島~駿河湾とかなりの量の溶岩・火山灰・泥流などが堆積したのが判る。
三島駅の中心地に溶岩が今でも

小松宮親王別邸跡 梅御殿

名勝 小浜池



寿橋



霧時雨 富士を見ぬ日ぞ 面白き 芭蕉

三島は終わります。











































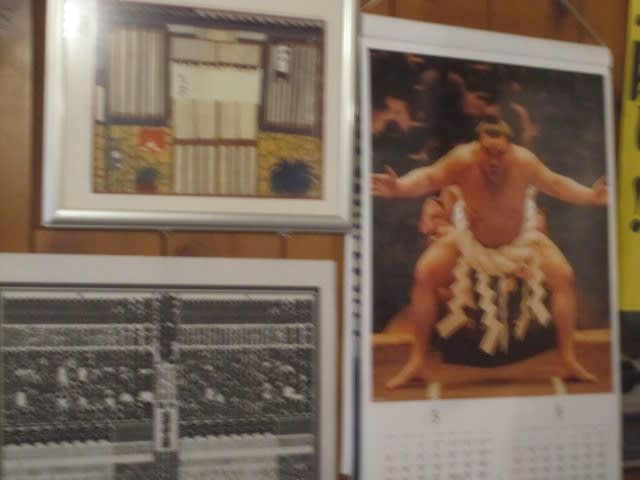
































 「彰義隊」
「彰義隊」









































