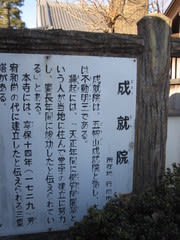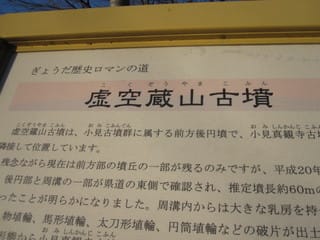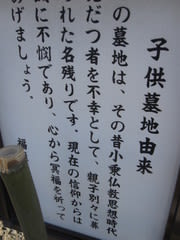「諏訪神社」国道125号線沿い、会の川の南側に位置、自然堤防上に鎮座、鳥居をくぐり石段を登った正面が社務所、
その右に富士浅間大神が祀られている。
社務所の左の小高い所に、諏訪神社の拝殿がある。
拝殿の右側に、11基の石祠が並んでいる。左から5番目に「熊野宮」の石祠。
他の石祠からは、八幡宮、神明社、疱瘡社、天満宮、九頭龍大権現の文字が読み取れる。
明治期に、村内の各地の社が、諏訪神社に合祀されたものと思われる。市は、県の北東部に位置する人口約6万8000人の市。
こいのぼりの生産数が日本一、加須うどんの街としても知られている。武州囃子の流れを汲む「武州加須囃子」がある。
難読地名の一つで「カス」または「カズ」と読み間違えられる事がある。国道沿いには、名物「手打ちうどん」店が目に付く。



「総願寺」不動岡にある真言宗、山号王寿山、関東三代不動尊、円珍作本尊不動王像は、1039年利根川大洪水で武州の吉見から
流れ着いたと云われている。
総願寺(不動ヶ岡不動尊)本堂

1616年高野山総願上人がこの地を訪ね、寺を建立し明王像を安置したのが始まり、本堂は、入母屋造り、節分会は、長さ3m
重さ25kgの燃える松明をもった、赤鬼と剣を持ち振り上げた青鬼と黒鬼が舞う迫力ある行事がある。
不動明王像、倶利迦羅不動剣が不動堂に安置。1739年の作。
「関東三大不動」とは、征夷大将軍が支配していた歴史の有る関八州における高幡山金剛寺、成田山新勝寺、玉山總願寺の3つの不動明王を
本尊とする寺院の総称。
山門



「黒門」行田 忍城の総ヒノキ一枚板の城門を移築された。
「芭蕉の句碑」1843年、松尾芭蕉の150回忌に建てられた句碑。 総願寺の本堂の北側の林の中に位置する、名句「曙ゆくや廿七夜も三日の月」が刻まれている。
境内 芭蕉の碑 忍城の黒門



「鯉のぼりの町」明治から際物屋と呼ばれた提灯、傘の職人が副業で始めたことに端を発し、大正の関東大震災後手書きの鯉のぼりが全国に知られていった。
現在は、一店のみ、毎年ゴールデンウイーク平和祭「ジャンボ鯉のぼり」が利根川広場で泳ぐ
十字路の中央二丁目交差点の一角に、「伝承 問屋場と高札場」と書かれた記念碑が建てられていた。
側面の説明書きによると、問屋場(江戸時代に、商品の積み替えや荷物の集配を行う機能を備えた場所)がこの付近にあり、通達や禁制を掲げた高札場が
あったと伝えられる場所である所。通称で「大辻」とも呼称されてきたというこの交差点が、加須の町の伝統的な中心であった。
付近には、山車と蘭陵王面を保存した蔵もあり、1862年に江戸日本橋田所町・油町・新大坂町の三町合同で制作したものが、明治期に至り電信電話線に
より町内を引き回せなくなってしまい持て余していたものを、1883年に加須町の清水善兵衛が金500円で買い求めたもの、山車の輸送にも水運が活躍し、
江戸川から関宿(千葉県野田市関宿)を経由し、大越河岸(現在の加須市大越)から馬車で運ぶという大掛かりなものであった。
本町交差点から北へ、大越まで伸びる道は、「大越新道」と呼ばれ、街道とその脇往還、水運の拠点たる河岸の中心に位置した加須の町は、
ローカルな物流の拠点として発展し、今日の都市基盤の基礎を築いた。
中央二丁目から駅前通りまでの区間の本町通りは、「ぎんざ通り」として道路が拡幅され、広い歩道も確保、現代的な町並みに整えられた。
次回は羽生へ。
その右に富士浅間大神が祀られている。
社務所の左の小高い所に、諏訪神社の拝殿がある。
拝殿の右側に、11基の石祠が並んでいる。左から5番目に「熊野宮」の石祠。
他の石祠からは、八幡宮、神明社、疱瘡社、天満宮、九頭龍大権現の文字が読み取れる。
明治期に、村内の各地の社が、諏訪神社に合祀されたものと思われる。市は、県の北東部に位置する人口約6万8000人の市。
こいのぼりの生産数が日本一、加須うどんの街としても知られている。武州囃子の流れを汲む「武州加須囃子」がある。
難読地名の一つで「カス」または「カズ」と読み間違えられる事がある。国道沿いには、名物「手打ちうどん」店が目に付く。



「総願寺」不動岡にある真言宗、山号王寿山、関東三代不動尊、円珍作本尊不動王像は、1039年利根川大洪水で武州の吉見から
流れ着いたと云われている。
総願寺(不動ヶ岡不動尊)本堂

1616年高野山総願上人がこの地を訪ね、寺を建立し明王像を安置したのが始まり、本堂は、入母屋造り、節分会は、長さ3m
重さ25kgの燃える松明をもった、赤鬼と剣を持ち振り上げた青鬼と黒鬼が舞う迫力ある行事がある。
不動明王像、倶利迦羅不動剣が不動堂に安置。1739年の作。
「関東三大不動」とは、征夷大将軍が支配していた歴史の有る関八州における高幡山金剛寺、成田山新勝寺、玉山總願寺の3つの不動明王を
本尊とする寺院の総称。
山門



「黒門」行田 忍城の総ヒノキ一枚板の城門を移築された。
「芭蕉の句碑」1843年、松尾芭蕉の150回忌に建てられた句碑。 総願寺の本堂の北側の林の中に位置する、名句「曙ゆくや廿七夜も三日の月」が刻まれている。
境内 芭蕉の碑 忍城の黒門



「鯉のぼりの町」明治から際物屋と呼ばれた提灯、傘の職人が副業で始めたことに端を発し、大正の関東大震災後手書きの鯉のぼりが全国に知られていった。
現在は、一店のみ、毎年ゴールデンウイーク平和祭「ジャンボ鯉のぼり」が利根川広場で泳ぐ
十字路の中央二丁目交差点の一角に、「伝承 問屋場と高札場」と書かれた記念碑が建てられていた。
側面の説明書きによると、問屋場(江戸時代に、商品の積み替えや荷物の集配を行う機能を備えた場所)がこの付近にあり、通達や禁制を掲げた高札場が
あったと伝えられる場所である所。通称で「大辻」とも呼称されてきたというこの交差点が、加須の町の伝統的な中心であった。
付近には、山車と蘭陵王面を保存した蔵もあり、1862年に江戸日本橋田所町・油町・新大坂町の三町合同で制作したものが、明治期に至り電信電話線に
より町内を引き回せなくなってしまい持て余していたものを、1883年に加須町の清水善兵衛が金500円で買い求めたもの、山車の輸送にも水運が活躍し、
江戸川から関宿(千葉県野田市関宿)を経由し、大越河岸(現在の加須市大越)から馬車で運ぶという大掛かりなものであった。
本町交差点から北へ、大越まで伸びる道は、「大越新道」と呼ばれ、街道とその脇往還、水運の拠点たる河岸の中心に位置した加須の町は、
ローカルな物流の拠点として発展し、今日の都市基盤の基礎を築いた。
中央二丁目から駅前通りまでの区間の本町通りは、「ぎんざ通り」として道路が拡幅され、広い歩道も確保、現代的な町並みに整えられた。
次回は羽生へ。