「伊東温泉・七福神巡り」御利益宜しくお願いします。
中世鎌倉時代以降、水墨画の発達に伴って、禅画の画題で親しまれる布袋和尚(契此)や福禄寿・寿老人も福の神に加えられ、室町中期には、
恵比寿と大黒が一対の神として併せ祀られ、福の神の中心となり、次第に、幾つかの福の神が合祀されるようになる。
禅宗の僧侶が中国の「竹林の七賢」に倣い、半分冗談で作ったのが七福神と言われる。
別の説では、同じく室町時代に「仁王般若経」や「薬師経」にある「七難即滅、七福即生」という言葉に基づき、考え出されたという説もある。
どちらにしても、中世室町後期までに福なる神々が組み合わされてできたのが、「七福神」。
七福神は、瑞祥の象徴とみなされ、広く絵画や彫刻の題材に採られるようになった。なお、七福神の中に、布袋・福禄寿・寿老人という日本ではほとんど七福神意外になじみのない道教系の神々が含まれるのは「中国の知識に偏った禅僧が考えたから」という裏事情によるとの説がある。
となると禅僧の遊びで考えだされ、「七難即滅、七福即生」という言葉との融合で、確立された信仰というところが、本当のところ。
大室山

「福禄寿」。
道教で強く希求される3種の願い、すなわち幸福(現代日本語でいう漠然とした幸福全般のことではなく血のつながった実の子に恵まれること)、
封禄(財産のこと)、長寿(単なる長生きではなく健康を伴う長寿)の三徳を具現化したものである。
宋の道士・天南星の化身や、南極星の化身(南極老人)とされ、七福神の寿老人と同体、異名の神とされることもある。
福禄人とも言われる。
福禄寿を祀る山号ー水東山・林泉寺を参拝する。

「東郷平八郎」 1847-1934 ロシアバルチック艦隊を全滅させたー海軍元帥。
薩摩藩出身、戊辰戦争で、軍艦春日に乗り海戦に参加している。1871年イギリス留学し帰国後海軍中尉任官、日露戦争では連合艦隊司令長官
世界最強のバルチック艦隊を対馬沖で、T 字先鋒で殲滅させ、一躍世界にその名が知られた。
晩年は、ここ伊東で過ごしている。
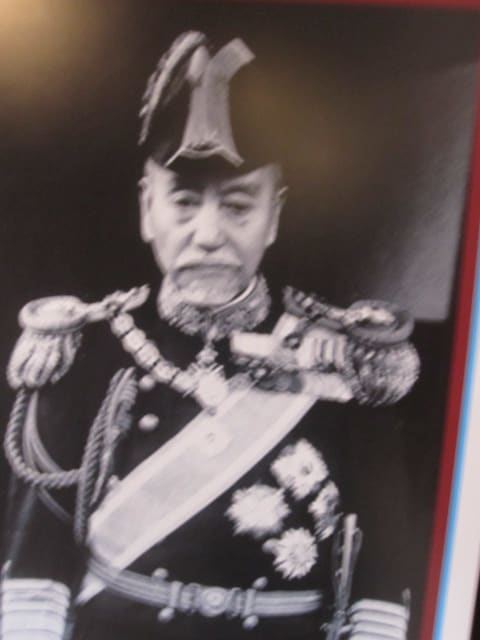
「三笠・戦艦」
大日本帝国海軍の戦艦で、敷島型戦艦の四番艦。
奈良県にある三笠山(若草山)にちなんで命名。船籍港は京都府舞鶴市の舞鶴港。同型艦に敷島、初瀬、朝日。1904年からの日露戦争では連合艦隊旗艦を務め、連合艦隊司令長官の東郷平八郎大将らが座乗した。
現在は神奈川県横須賀市の三笠公園に記念艦として保存されている。
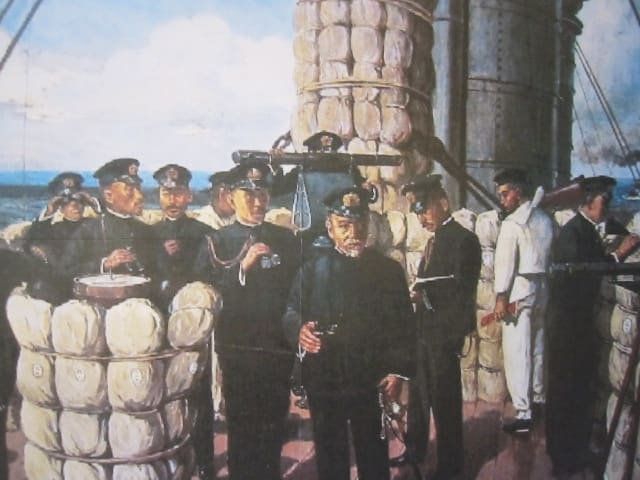
日露戦争の日本海海戦当時の連合艦隊司令長官だった東郷平八郎元帥が晩年を過ごした夫人療養の別荘が、
伊東市渚・松川河口近くの「東郷小路」と呼ばれる露地の中ほどに当時のままの姿で保存され、記念館になっていると云う。

「林泉寺」は、曹洞宗、水東山と号し本尊ー釈迦如来
1545年僧「覚隣」改宗・開山

本堂に向かって左に薬師如来像・月光菩薩像を祀る。

33体観世音・薬師如来は文化年間作で一刀彫と云う(県指定文化財)



境内の「藤」は、県指定文化財の樹齢200年余の大木2株ある、つるが境内いっぱいに広げて、5月上旬花で見ごろになると云う。


いろいろな表情の顔をした石仏


次回は、毘沙門天の仏現寺へ。
中世鎌倉時代以降、水墨画の発達に伴って、禅画の画題で親しまれる布袋和尚(契此)や福禄寿・寿老人も福の神に加えられ、室町中期には、
恵比寿と大黒が一対の神として併せ祀られ、福の神の中心となり、次第に、幾つかの福の神が合祀されるようになる。
禅宗の僧侶が中国の「竹林の七賢」に倣い、半分冗談で作ったのが七福神と言われる。
別の説では、同じく室町時代に「仁王般若経」や「薬師経」にある「七難即滅、七福即生」という言葉に基づき、考え出されたという説もある。
どちらにしても、中世室町後期までに福なる神々が組み合わされてできたのが、「七福神」。
七福神は、瑞祥の象徴とみなされ、広く絵画や彫刻の題材に採られるようになった。なお、七福神の中に、布袋・福禄寿・寿老人という日本ではほとんど七福神意外になじみのない道教系の神々が含まれるのは「中国の知識に偏った禅僧が考えたから」という裏事情によるとの説がある。
となると禅僧の遊びで考えだされ、「七難即滅、七福即生」という言葉との融合で、確立された信仰というところが、本当のところ。
大室山

「福禄寿」。
道教で強く希求される3種の願い、すなわち幸福(現代日本語でいう漠然とした幸福全般のことではなく血のつながった実の子に恵まれること)、
封禄(財産のこと)、長寿(単なる長生きではなく健康を伴う長寿)の三徳を具現化したものである。
宋の道士・天南星の化身や、南極星の化身(南極老人)とされ、七福神の寿老人と同体、異名の神とされることもある。
福禄人とも言われる。
福禄寿を祀る山号ー水東山・林泉寺を参拝する。

「東郷平八郎」 1847-1934 ロシアバルチック艦隊を全滅させたー海軍元帥。
薩摩藩出身、戊辰戦争で、軍艦春日に乗り海戦に参加している。1871年イギリス留学し帰国後海軍中尉任官、日露戦争では連合艦隊司令長官
世界最強のバルチック艦隊を対馬沖で、T 字先鋒で殲滅させ、一躍世界にその名が知られた。
晩年は、ここ伊東で過ごしている。
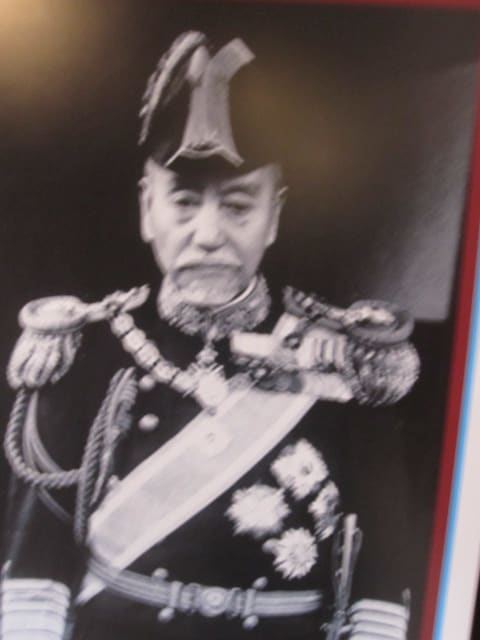
「三笠・戦艦」
大日本帝国海軍の戦艦で、敷島型戦艦の四番艦。
奈良県にある三笠山(若草山)にちなんで命名。船籍港は京都府舞鶴市の舞鶴港。同型艦に敷島、初瀬、朝日。1904年からの日露戦争では連合艦隊旗艦を務め、連合艦隊司令長官の東郷平八郎大将らが座乗した。
現在は神奈川県横須賀市の三笠公園に記念艦として保存されている。
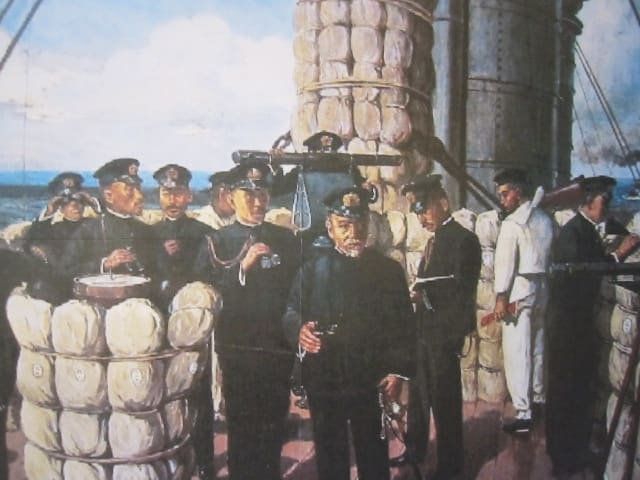
日露戦争の日本海海戦当時の連合艦隊司令長官だった東郷平八郎元帥が晩年を過ごした夫人療養の別荘が、
伊東市渚・松川河口近くの「東郷小路」と呼ばれる露地の中ほどに当時のままの姿で保存され、記念館になっていると云う。

「林泉寺」は、曹洞宗、水東山と号し本尊ー釈迦如来
1545年僧「覚隣」改宗・開山

本堂に向かって左に薬師如来像・月光菩薩像を祀る。

33体観世音・薬師如来は文化年間作で一刀彫と云う(県指定文化財)



境内の「藤」は、県指定文化財の樹齢200年余の大木2株ある、つるが境内いっぱいに広げて、5月上旬花で見ごろになると云う。


いろいろな表情の顔をした石仏


次回は、毘沙門天の仏現寺へ。
























































