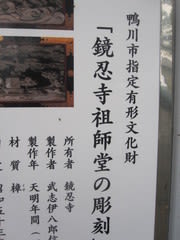「清澄寺を訪ねてー2009-12-12 07:40:27 | 気まま旅」すでに掲載したのですが今回再掲載です。
「清澄寺」
清澄山参道、65号線を清澄養老ライン81号線で鴨川に下る途中に、日蓮が入門し出家した清澄寺がある。
この道は険しくカーブ多し狭い、
境内中央の大杉は、樹齢1000年をこえる清澄寺の歴史を物語る霊木とされている。根回り17、5m 樹高47m。
771年天台宗の寺として開創、三大虚空蔵尊の一つとして、深く信仰されている。
日蓮宗の開祖「日蓮聖人」は1233年12歳のときに、小湊からこの寺に入り、道善法師に師事し、出家得度した。
JR外房線上総一の宮駅、一時間1本「清澄寺」まで、直行便マイクロバスが出ている。(時間の関係で参拝しません)

「安房国」「房総」は、房総半島東西に連なる「上総丘陵の南斜面」に位置、海岸線に沿う狭い台地、黒潮の影響を受け、冬は暖かく・夏は涼しい。
最近は花卉・枇杷栽培が盛んに、平安時代初期の「古語拾遺」によると、「阿波の斎部(いんべ)の居る所、安房と名づく、太玉命を祀り安房の社
と云う」とあり、阿波(徳島県)の人々が移住したところから「安房郡」と名付けたと云う。
「続日本紀」718年「上総国、安房等の4郡を割き・安房国を置く」とある。4郡は、平郡・安房・朝夷・長狭である。国府は三芳村府中付近
その後武士団丸氏が活躍し、源頼朝の再起の地。
15世紀の滝沢馬琴「南総里見八犬伝」で知られた「里見氏」が勢力を張っていく。
豊臣秀吉時代「里見氏」江戸期「後北条氏」-幕府領・旗本領などに分割されていく。元禄期の浮世絵師「菱川師宣」は、鋸南町の出身
「天津小湊町」は、鯛の浦の面した漁港地区、日蓮聖人生誕地で「誕生寺」の門前町。
ー上総国一之宮玉前神社ー



永禄年間(1558年-1570年)の戦火により社殿および古記録等が焼失したため、創建年代は不明。他の文献等により、少なくとも鎮座以来1,200年以上経過していることは間違いないとされる。
祭神ー玉依姫命 ・海からこの地に上がり、豊玉姫命に託された鵜葺草葺不合命を養育し、のち玉依姫命と鵜葺草葺不合命は結婚し
初代「神武天皇ら」を産んだとされる。
「延喜式神名帳」を始めとして文献上は祭神は一座とされているが、古社記には鵜茅葺不合命の名が併記されている。そのほか、「大日本国一宮記」
では前玉命、また天明玉命とする説。
平安時代中期、927年、の「延喜式神名帳」では「上総国埴生郡 玉前神社」として、名神大社に列し、上総国一宮として崇敬されたとある。
江戸時代、1687年、に現在の社殿が造営、1871年の明治4年、近代社格制度において国幣中社に列し、1900年と1923年の大正12年、に社殿等の改修。
一宮町は、房総半島九十九里浜の最南端に位置し、一年を通して寒暑の差が少なく温暖な気候に恵まれた土地で、縄文弥生の頃から人々の営みがあったことが遺跡や貝塚などによって明らかに。 歴史の古いこの一宮町の名称の由来となった「玉前神社」は、上総国にまつられる古社である。
平安時代にまとめられた「延喜式神名帳」では名神大社としてその名を列し、全国でも重きをおくべき神社として古くから朝廷・豪族・幕府の信仰を集め、「上総国一之宮」の格式を保っていた。
永禄年間の大きな戦火にかかり、社殿・宝物・文書の多くを焼失しており、ご創建の由来や年数また名称についてなど明らかにされていませんが、
毎年9月10日から13日に行われるご例祭には少なくとも1200年の歴史がある。
「上総の裸まつり」「十二社まつり」と称されるこのお祭りは房総半島に多く見られる浜降り神事の代表として広く知られ、壮大な儀礼をひと目見ようと、
大勢の人々が。
名称の由来ー祭神に由来するという説と九十九里浜を古くは「玉の浦」とたたえ太東崎を南端とするところから玉崎(前)となったと云う説など。
手洗鉢 本殿 献上樽酒



末社 舞殿



境内には,芭蕉の句碑ー「たかき屋にの 御製の有難を今も猶」、「 叡慮にて賑ふたみや庭かまど」の二首。



落ち着いた境内

毎年7月・中旬に一宮海岸海開き、
宮薙祭~あんどん祭りが、 裏千家中村社中の「くらやみ茶菓接待」館広間・ 玉前神社総代会ー甘酒ふるまい・神楽殿脇、囃子奉納・神楽殿
点灯式・ 県指定無形文化財上総神楽奉納 …神楽殿ー 消灯。
田植えの無事終了を感謝し、ひと休みのこの時期に神社に詣で境内の草薙ぎ(草刈り)や神賑行事を行うもので、神社ではこの日、新麦の御飯と麦濁酒を供えて祭儀を、早盆の時期にあたることから夕刻より先祖迎えの行灯まつりが行われ、境内を彩る500基余りの行灯や地口行灯と呼ばれる大行灯が幽玄な風景を醸し出し、初夏の風物詩となっている。



神代の昔、天孫降臨に当って国譲りした事代主神が海路当地に移り東方鎮護の神として鎮座し、これを『庤明神』と崇敬したことが当社の始まりと伝えられている。
その後、治承4年(1180年)石橋山の戦いに敗れ安房に逃れた源頼朝が源氏の再興を伊勢神宮に祈願し、御厨一処の寄進を祈誓したという[1]。また、寿永元年(1182年)に、頼朝の妻政子の安産祈願の祈祷のため、奉幣使として三浦義村が当社へ遣わされた[2]。頼朝は一ノ谷の戦いの後、寿永3年(1184年)[3]安房国に東条御厨(白浜御厨、阿摩津御厨)を設け、伊勢より神霊を勧請し以前より鎮座の『庤明神』とともに祀ったのが当社である。文治元年(1185年)には生倫神主が参籠したところ、霊夢の奇端があったので頼朝から飛龍と号する馬が奉納され[4]、以降も関東武家の崇敬を受け「房州伊勢の宮」と仰がれ今日に至ってる。
当社の境内にある「まるばちしゃの木」は、中国大陸南部や海南島、台湾などに生育している亜熱帯性の落葉喬木であり、その北限として価値が高く千葉県の天然記念物に指定されている。境内東側の山にはすぐれた極相林があり「神明神社の林」として鴨川市の天然記念物に指定され、山頂には伊邪那岐大神・伊邪那美大神を祀る諾冉神社が鎮座する



境内・「まるばちしゃの木」
中国大陸南部や海南島、台湾などに生育している亜熱帯性の落葉喬木であり、その北限として価値が高く千葉県の天然記念物に指定。
境内東側の山にはすぐれた極相林があり「神明神社の林」として鴨川市の天然記念物に指定された。
山頂には伊邪那岐大神・伊邪那美大神を祀る諾冉神社が鎮座する。
「両親閣・小湊妙蓮寺」ー誕生寺と逆方向すぐー
御廟堂の中にお大きな宮殿があり、その宮殿の中に日蓮父母の御廟があると云う。
宮殿後ろ左には妙日、右には妙蓮の石像が安置され、宮殿の真後ろには棟板本尊。
日蓮聖人の両親のご廟所・1253年、清澄寺のお山で立教開宗・山から降りた聖人は、父母を教化し、 父に妙日、母に妙蓮寺



孝養父母第一に、小湊妙蓮寺 本堂

「日蓮の母感謝の心・ 誕生寺」 ー県鴨川市小湊ー
母は、病気の平癒祈願を感謝し信仰に励まれた地が誕生寺の所と云う 生まれた地は今は海となって居ると云うが海には大鯛が踊り岸には蓮華が咲き丘には清水が湧き出したと三奇瑞を今に傳えられて居ると云う。
山内には、幼少期の日蓮像

1276年、日蓮の弟子の「日家」が日蓮の生家跡に、高光山日蓮誕生寺として建立。(1498年・1703年、2度の大地震、大津波に遭い、現在地に移転)
(生家跡伝承地は沖合いの海中にあると云う。)
26代、「日孝」が「水戸光圀」の外護を得て七堂伽藍を再興し、小湊山誕生寺と改称したが、1758年、仁王門を残して焼失し、
1842年、に49代「目闡」が現存する祖師堂を再建。
近代に入り、大正天皇の病気平癒の廟所が建立され、その後、昭和から平成にかけて、50万人講を発願して諸堂を復興、
1992年の平成4年、落慶法要が行われた。平成13年、風景100選に選定。
佛教の研鑽を逐え故郷に帰り父に妙日 母に妙蓮の法号を贈り自らは一字づつとり日蓮と改めたと云う。



御影体内文書(日静筆・室町期)
江戸時代の不受不施派(悲田宗)禁政のため幕命により天台宗に改宗するところだったが身延山が日蓮誕生地の由緒で貰いうけ一本山に格下げ(悲田宗張本寺の谷中感応寺、碑文谷法華寺は天台宗に改宗された。現谷中天王寺、碑文谷円融寺)。昭和21年大本山に復帰。
現住は84世石川日命貫首(本山水戸久昌寺より晋山)。潮師法縁。
「文化財」-大壁画 散華霊鷲山(石川響作)・富木殿女房御返事 (日蓮真蹟)・薬王丸画像・誕生寺古図・ 御影体内文書(日静筆・室町期)



「仁王門」
1706年、建立ー平成3年大改修。
入母屋造二重門、間口8間、宝暦の大火の際焼け残った誕生寺最古の建造物。
金剛力士(仁王)像は松崎法橋作。楼上の般若の面は左甚五郎作とされる。(千葉県指定有形文化財)
「本堂」
1991年、建立。間口7.8間、奥行き8.8間の単層入母屋造り本瓦葺。
水戸光圀の寄進による十界本尊木像(大仏師左京康裕作)がある。天井に仏教植物の天井画(石川響筆)82枚。
日家、日保像等が安置される。
「祖師堂」
1842年、建立。入母屋造、総欅造り雨落ち18間4面、高さ95尺。建材は江戸城改築用として、伊達家の藩船が江戸へ運ぶ途中遭難し、譲りうけたもの。
日蓮像が安置され、聖人像が安置される御宮殿は明治皇室大奥の寄進による。
堂内右側の天井には南部藩の相馬大作筆による天女の絵が描かれ、堂内の天蓋等の仏具類は明治天皇の生母である中山慶子一位局や、大正天皇の生母・柳原愛子一位局による寄進。
「本師殿宝塔」
1988年、完成。総高26m、塔体印度砂岩切石貼。釈尊像(西村房蔵作)を安置。
「宝物殿」
1989年、に新築開館。面積366m²、日蓮真筆、歴代の墨蹟、里見家、加藤清正、水戸光圀等の遺墨、明治皇室よりの拝領品、日蓮聖人御一代伝記画十八枚等を展示。
「客殿」
1933年、建造。総檜造りで宮家の接待所として造られ、貴賓殿と称した。
「誕生堂、鐘楼堂、大田堂、竜王堂など」



「願満の鯛」
1991年、祖師堂の日蓮像を修理するため解体したところ、胎内から4代日静筆の古文書と薬草が発見。
古文書には「生身の祖師」の名と宗祖誕生の時と所が記され、日蓮が母を蘇生させた伝説から、当山の日蓮像は「蘇生願満の祖師」と呼ばれる。
この願満の祖師のお使いとして鯛が使われており、山内では鯛のお守り「願満の鯛」が売られている。
日蓮宗信徒に限らず、周辺地域では鯛を食べる事を嫌う人が多いと云う。(願満の鯛は近所にある清澄寺の五角の合格枡と共に有名な縁起物)
「立正安国論」(1260年)
鎌倉での日蓮は、松葉ヶ谷に草庵を結び、小町大路を中心に辻説法を行い、「念仏無間・禅天魔・真言亡国・律国賊」として、他宗を厳しく批判。
(妙法寺、安国論寺、長勝寺が日蓮の旧跡に建てられたとしているが、その場所は定かではない。)。
1260年の文応元年、立正安国論を著し、宿谷光則を通じて、時の権力者「北条時頼」に提出した。
立正安国論では、天変地異や疫病は、法然の念仏宗や禅宗などの邪宗を信仰するからであるとし、法華経を信じなければ、「他国の侵攻も受ける」などの批判を行っている。



「鯛の浦遊覧船」
海面に群がる特別天然記念物の「鯛」。小弁天と大弁天の二つの島を周遊する遊覧船、船上・船内から水深10~20mに天然鯛の群れを眺められる。
今日は、天候不順で欠航。
誕生寺の前が遊覧船乗り場

次回は、勝浦朝市から。