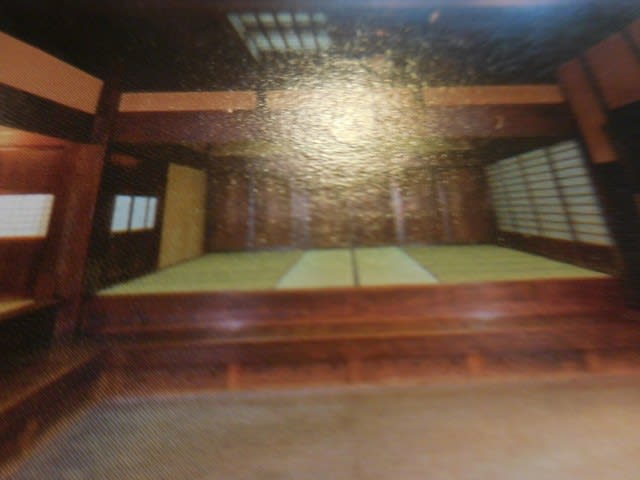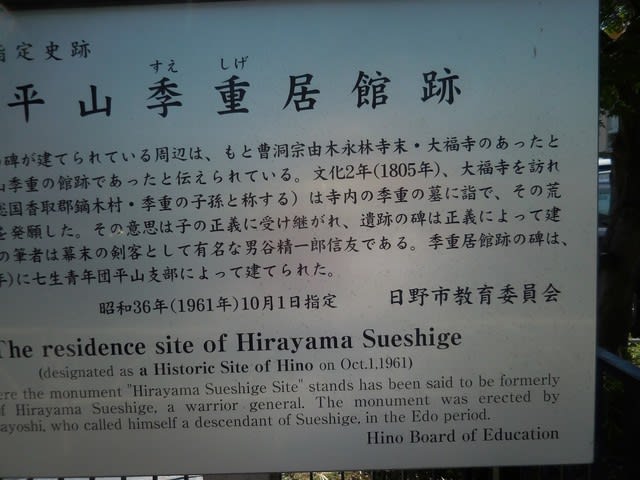東京都日野市、都の南西、多摩川の沖積低地と日野台地と多摩川丘陵で、奈良時代の烽火台「飛日野」・武蔵七党「日奉氏」を祀った「日野宮権現」
に由来するなどの諸説有。
江戸時代、多摩川渡船場・日野の渡し。大戦中は軍関連工場。戦後工業団地。今は、住宅・工業都市、JR中央本線、日野・豊田。
東京の酒「多摩自慢」石川酒造の歴史は
文久3年の1863年明治13年・福生の熊川の地に酒蔵を建ててから現在まで130年余りと云う。
土蔵にさまざまな歴史を刻んみ、「清酒多満自慢と地ビール」を生産。
多摩地域最古のビール・山口麦酒」-山口平太夫は明治6年清酒醸造を始めた。明治19年に、「山口麦酒醸造所」創業した。
明治20年「天狗」マークのビールは、ドイツのラガータイプ、八王子宿・府中宿・日野宿等と遠く群馬県まで広げていたが明治28年廃業。
当時のビール釜は石川酒造内展示している。日野市は、山口ビールをモデルに平成27年本格的に石川酒造に依頼し「豊田ビール・日野産大麦」の販売を行い今に。
「伊部猪三郎」清国上海で、洋酒の瓶・空樽の値段を調べ、ビールの詰め替え作業など書かれた手紙が展示されている。
当時の日本では、まだガラス瓶の製造は出来なかったため、伊部氏達は買い付け再利用したとある。日野市郷土資料館にて。
「甲武鉄道・中央本線」
明治22年、小金井ー立川間開通し多摩川・浅川に鉄橋工事を経て、その年の8月にー八王子まで開通した。翌年の23年に「日野停車場」が出来た。

「豊田の七森」
若宮神社ー東豊田・「新編武蔵風土記稿」のある豊田村鎮守・地頭大久保勘三郎棟札がある。祭神9月9日(千貫神輿一基)
八幡神社ー祭神応神天皇
白髭明神社・天満社・山王社・三嶋社・・矢崎弁天
「宝泉禅寺」日野駅前
本尊は、釈迦如来、脇侍に文珠菩薩普、賢菩薩。
「持ち上げ観音」の名で知られ、持ち上げた時に感じる重さによって吉凶を占う、約36cmの馬頭観音の石像がある。
「持ち上げ観音」は鐘付き堂の隣にある観音堂の本尊・本堂と客殿との間に安置している。
宝泉禅寺に参道

墓所内に,新選組六番隊長・副長助勤井上源三郎の墓碑が建てられている。
墓誌には、源三郎と共に兄松五郎(戒名:清松軒仁□智勇居士)、源三郎の 死をみとった泰助(戒名:泰岳宗保居士)の名も。
旧甲州道に面した山門・六脚ヒノキ造りー1853年

宝泉禅寺の本堂

大権現 鳥居

社殿


「日野ふるさと館」 無料

日野宿江戸時代の絵


「山口ビール」


山口ビールの前進は、山口氏がタイのバンコックに作った会社「山口洋行」
仁丹・蚊取り線香などを扱う会社ビル

「日野宿本陣」は、1849年主屋焼失ー1863年上棟、1864年住み始めている。
日野宿本陣には、「佐藤彦五郎が周助に師事して開いた「佐藤道場」、後に新選組 近藤勇・土方・沖田・井上達が稽古場に励んだところ。