釧路から十勝支庁にはいる。道中央部から南部に渡る道最大の支庁で所在地は帯広市になる。十勝流域の十勝平野が大半を占め、日高山脈
石狩山地、
白糠丘陵を境界にしている。
道内最大の畑作地帯、小豆、大豆、ジャガイモ、小麦で北部は酪農が中心で十勝川・利別川の合流に水田がある。内陸部の開拓1900年植民区画し発展している。
東部の雌阿寒岳西麓(1476m)に形成する堰止湖、アイヌ語で、年老いた沼・大きい沼「オンネトー」がある。周囲から小河川に流入し南岸柄蝶湾川となる。
「オンネトー」は、たかさ623m、深さ3.8m、阿寒富士とサンショウウオの生息地で知られている。

「サンショウウオ」は、皮膚は鱗がなく粘膜におおわれる。呼吸の大半を皮膚呼吸に頼っていて、皮膚が湿っていないと生存できない。
渓流に生息するハコネサンショウウオは肺を持っていない。また、前足は4本、後足は5本の指を持つ。
オオサンショウウオは繁殖期に川を遡上するとき以外はほとんど水中から出ることはないが、他の種類は陸上生活を送ることが多く、森林の落ち葉の下や
モグラやネズミが掘った穴の中や、川近くの石の下などに生息する。繁殖期以外はあまり人の目にはふれることはない。

オンネトー湯の滝は、湖の南東方向にある2つの滝。天然記念物、日本の地質百選の1つである。
雌阿寒岳からの温泉水(水温43度)が湧き出て、直後に安山岩溶岩の崖を流れ落ちる滝である。
かつては滝上の池で入浴ができたが、ここに生息する微生物によって酸化マンガンを生成する現象が発見され、保護のため入浴禁止となった。
熱帯魚を持ち込んだ者がおり、それが繁殖し生態系を乱すという問題も起き、駆除中との事。


オンネトーの魅力は、湖面の美しさ。見る角度や空模様によって、色が変わっていく。コバルトブルー、エメラルドグリーンと。
湖面の美しさと湖を取り囲む原生林、そびえ立つ雌阿寒岳・阿寒富士の眺望も見事。道三大秘湖のひとつ、静かにこの美しいオンネトー。
湖の周りを1周する遊歩道は、約1時間半程度。残念ながらその時間はと取れない。

大型バスは、ユータン出来ないので(道幅が狭い)途中下車した。

オホツク海から知床、根室、釧路と摩周湖、阿寒湖を挟んで十勝の太平洋と見てきた。少々疲れが出た。

石狩山地、
白糠丘陵を境界にしている。
道内最大の畑作地帯、小豆、大豆、ジャガイモ、小麦で北部は酪農が中心で十勝川・利別川の合流に水田がある。内陸部の開拓1900年植民区画し発展している。
東部の雌阿寒岳西麓(1476m)に形成する堰止湖、アイヌ語で、年老いた沼・大きい沼「オンネトー」がある。周囲から小河川に流入し南岸柄蝶湾川となる。
「オンネトー」は、たかさ623m、深さ3.8m、阿寒富士とサンショウウオの生息地で知られている。

「サンショウウオ」は、皮膚は鱗がなく粘膜におおわれる。呼吸の大半を皮膚呼吸に頼っていて、皮膚が湿っていないと生存できない。
渓流に生息するハコネサンショウウオは肺を持っていない。また、前足は4本、後足は5本の指を持つ。
オオサンショウウオは繁殖期に川を遡上するとき以外はほとんど水中から出ることはないが、他の種類は陸上生活を送ることが多く、森林の落ち葉の下や
モグラやネズミが掘った穴の中や、川近くの石の下などに生息する。繁殖期以外はあまり人の目にはふれることはない。

オンネトー湯の滝は、湖の南東方向にある2つの滝。天然記念物、日本の地質百選の1つである。
雌阿寒岳からの温泉水(水温43度)が湧き出て、直後に安山岩溶岩の崖を流れ落ちる滝である。
かつては滝上の池で入浴ができたが、ここに生息する微生物によって酸化マンガンを生成する現象が発見され、保護のため入浴禁止となった。
熱帯魚を持ち込んだ者がおり、それが繁殖し生態系を乱すという問題も起き、駆除中との事。


オンネトーの魅力は、湖面の美しさ。見る角度や空模様によって、色が変わっていく。コバルトブルー、エメラルドグリーンと。
湖面の美しさと湖を取り囲む原生林、そびえ立つ雌阿寒岳・阿寒富士の眺望も見事。道三大秘湖のひとつ、静かにこの美しいオンネトー。
湖の周りを1周する遊歩道は、約1時間半程度。残念ながらその時間はと取れない。

大型バスは、ユータン出来ないので(道幅が狭い)途中下車した。

オホツク海から知床、根室、釧路と摩周湖、阿寒湖を挟んで十勝の太平洋と見てきた。少々疲れが出た。













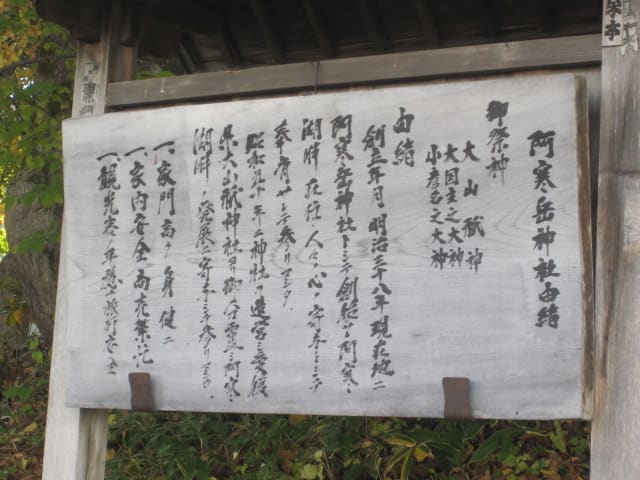










 「♪霧の摩周湖」作詞 水島 哲作曲 平尾 昌晃。
「♪霧の摩周湖」作詞 水島 哲作曲 平尾 昌晃。





















