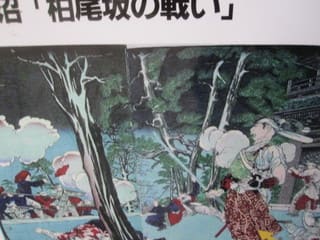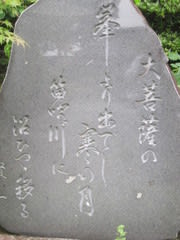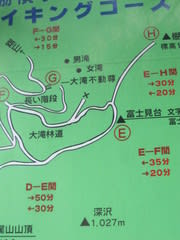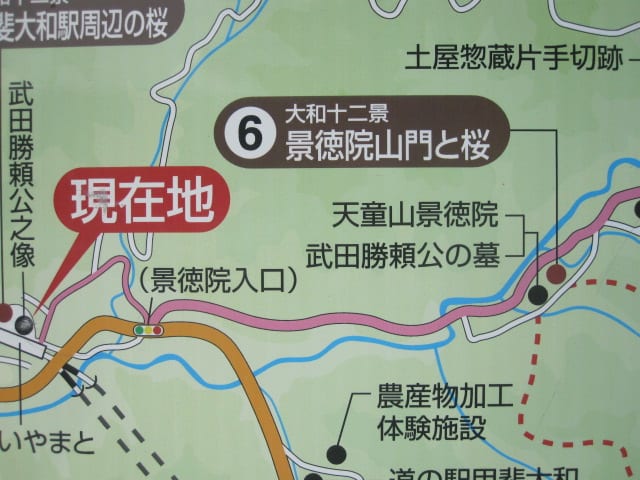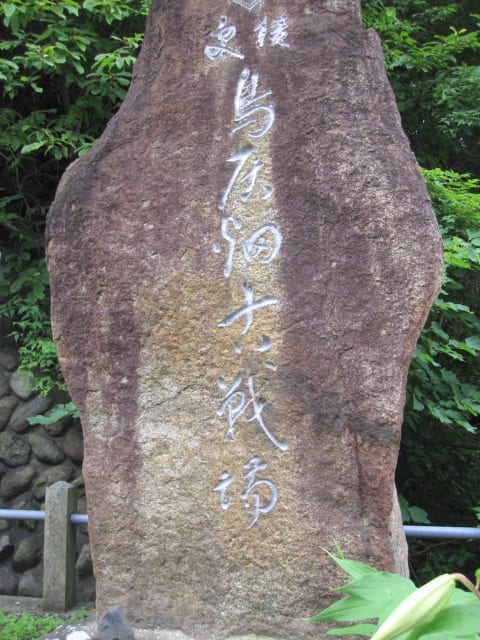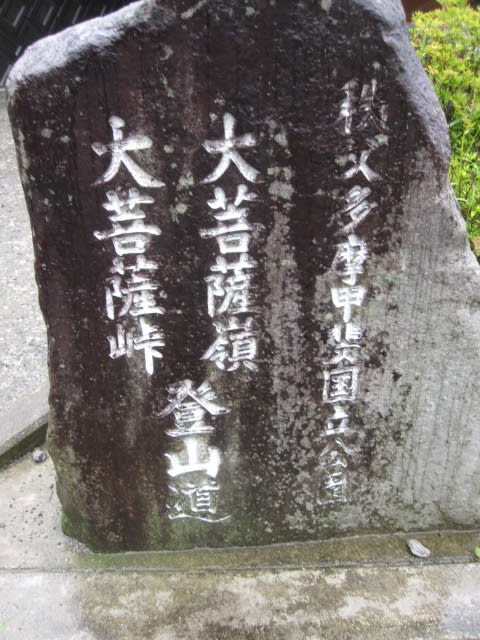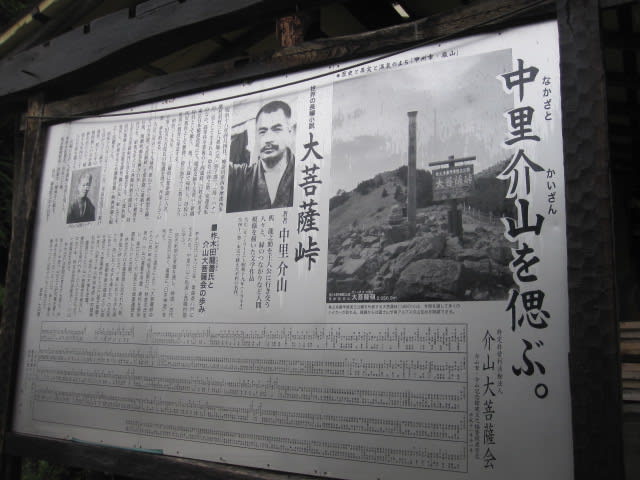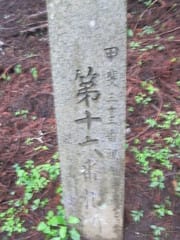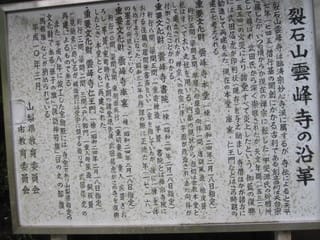今回震災後の東北を旅することににしました。
私が仙台に単身で赴任した(仙チョン族といっていた)昭和末頃は、仙台ー上野東北本線所要時間4時間強、
座席も90度直角で車内は常に大混雑で苦労して月に一回東京に帰京していた。
明治9年に、「奥羽巡幸」において明治天皇が馬車で各地を回り、明治16年、仙台 - 福島の運行を開始したと云う。
当時は、都市間乗合馬車を乗り継くことで、東京 - 仙台の所要時間は3泊4日に短縮された。
1887年の明治20年、日本鉄道の駅として仙台駅が。上野駅から宮城県・塩竈駅まで通じ、上野 - 仙台間の所要時間は12時間20分の記録がある。
「仙台駅」初代の駅舎は木造平屋建ての小さな建物で線路の西側に位置し、馬車を回すロータリーがあったと云う。
昭和20年、仙台空襲により焼失した。
1906年に日本鉄道は国有化され、国鉄東北本線・1925年に仙台地区では初の直流電化路線である宮城電気鉄道(後の仙石線)が西塩釜駅まで開業し、
1929年には仙山東線(後の仙山線)が愛子駅まで敷かれ、所要時間は1926年に上野 - 仙台間が8時間弱。
この頃の仙台駅は東北地方で最多の旅客数であったが、貨物では青森駅・塩竈駅(旧駅)などに引き離されている。
1926年の大正15年、仙台市電が仙台駅前駅 - 荒町日赤病院前駅において開業し、駅前広場に隣接する駅前通りに仙台駅前停留所が設けられた。



岩出山町「座散乱木遺跡」・古川市「馬場壇遺跡」は旧石器時代の」遺跡で、縄文時代では小牛田町の「素山貝塚」・石巻の「沼津貝塚」・七ヶ浜町の
「大木囲貝塚」等。弥生時代では仙台市の「小泉遺跡」・塩釜の「崎山囲遺跡」・多賀城の「枡形囲遺跡」等が知られている。
古墳時代では、名取市「雷神山古墳」・丸森町の「台町古墳」・「京銭塚古墳」等がある。
724年には、多賀城に「陸奥国府、鎮守府」が置かれている。その80年後「坂上田村麻呂」が鎮守府を胆沢城に移す。
1051年、「前九年の役」が起こる。1083年、「後三年の役」が、1170年「藤原秀衡」が鎮守府将軍となる。
1189年、源頼朝の奥州征伐で「藤原氏」は滅ぶ。1333年、北畠顕家が陸奥守~1591年天正19年、「伊達正宗」米沢より岩出山に移っている。1601年、正宗は、仙台城築城し移る。3年後、松島に「五大堂」が完成。
仙台湾には、北上川・阿武隈川・名取川が注ぎ沖積平野を形成し、水田面積は、他県に劣らない「東北地方第一位」。
古代から、東北地方の海の玄関口、陸奥国府「多賀城」(現多賀城市)に設置されている。
三陸南部はリアス海岸で、天然の良港ー寒流の親潮と暖流の黒潮がまじわる漁場と云う。石巻・気仙沼が知られている。
杜の都「仙台・青葉通り」

「仙台七夕」ー約3000本の七夕飾りがアーケード街を埋めつくす。
古くは、藩祖「伊達政宗公」の時代から続く伝統行事として受け継がれ、 日本古来の星祭りの優雅さと飾りの豪華絢爛さを併せ持つお祭りとして全国に名を 馳せており、旧暦7月7日の行事として全国各地に広まっている。
短冊ー学問や書の上達を願う。紙衣ー病や災いの身代わり、または、裁縫の上達を願う。折鶴ー長寿を願う。巾着ー富貴と貯蓄、商売繁盛を願う。
投網ー豊漁を願う。くずかごー飾り付けを作るとき出た裁ち屑・紙屑を入れる。清潔と倹約を願う。吹き流しー織姫の織り糸を象徴する。
戦後の昭和21年、仙台空襲で焼け野原となった街に52本の竹飾りで仙台七夕は復活・ここ商店街で、、。



「穴蔵神社」
鎮座地ー・青葉区霊屋下(瑞鳳寺参道横) 主祭神ー宇迦之御魂神 祭日ー9月19日

元米沢に御鎮座。
伊達氏の守護神として奉斎、藩祖政宗伊達郡梁川に遷し、、後、青葉城を築くのとき鈴の沢の地を選び城に向けて遷し祀るとある。
「夕日明神」と称あり。天保6年ー広瀬川の氾濫と崖崩れの災をおそれ遂に川下の現在の地に鎮められた。
藩祖の信仰あつく社殿の修復のことは勿論、本社に三貫文の地を寄進し、更に年一石の饌米を奉献するを例とし、歩卒172家をもって祭事が、
公の奥方・愛姫(陽徳院)は安産の守護神として深く信仰したと伝えられている。
(社伝、稲荷神祠頌)大正11年八木山の越路神社(山神)を合祀。平成15年参道修復工事、平成17年本殿改築。



「瑞鳳寺」
広瀬川右岸の丘陵経ヶ峰のある臨済宗妙心寺派 山号ー正宗山 開山ー清岳宗拙。
本尊ー釈迦三尊 伊達正宗の遺言ー二大藩主「伊達忠宗」が1636年に創建・三代藩主「伊達綱宗」



三大の霊廟が「瑞鳳殿」-伊達正宗・「感仙殿」ー伊達忠宗・「善応殿」-伊達綱宗がある。
「瑞鳳殿」は、桃山時代の建築様式をつたえる豪華な霊廟建築と云う。1979年復元(国宝指定)



「伊達正宗」1567-1636 東北の猛者、独眼竜と恐れられた。
仙台藩主・伊達輝宗の長男、蘆名義広を破り「会津」掌握。
小田原征伐で遅参し、豊臣秀吉から領国一部没収されている。「関ヶ原の戦い」東軍に与する。-62万石大名に。
スペイン通訳「シピオーネ」(支倉常長)-正宗は、奥州を植民地としてスペインへ献上し、次期皇帝の最高実力者と記した宣教師「ソテロ」の書簡
が残っている。正宗は、天下を狙っていた証拠度と云われている。独眼竜正宗、片目を苦にし、自分の像には両目を添えよと遺言している。
「人そめて くにゆたかなる みぎりとや 千代とかぎらじ 仙台のまつ」伊達正宗・和歌ー仙台の名はここから



米沢城主伊達輝宗(1544-85)-出羽半国・最上義光(1546-1614)の妹・義姫保春院(1548-1623)-最上氏の宿敵。
長男「伊達正宗」(1567-1636)-妻は、愛姫・陽徳院(1568-1653)陸奥三春城城主の一人娘ー3男1女をもうけた。小次郎ー1590正宗毒殺未遂事件で
正宗に斬殺 井伊直政(1561-1602)亀姫徳川家康の命で「伊達秀宗ー政宗庶長子」に嫁ぐ。
政宗の三男飯坂宗清(1600-34)母の実家飯坂氏養子へ。 宗勝十男末子(1621-80)一関藩主
松平忠輝(家康6男)ー越後高田藩75万石太守となるが大坂の陣遅参で改易。 五郎八姫(天麟院)忠輝改易と共に離縁・仙台で暮らす
伊達忠宗(政宗次男嫡男)政宗死後家督継承陸奥仙台藩二代藩主ー長男宗綱(1603-18)、正宗の5男16歳で早世
忠宗の正室は、徳川家康外孫姫路藩主池田輝政の娘、徳川秀忠養女が嫁いでいる。その次男嫡男が伊達光宗(1627-45)19歳で病没。
田村宗良(1637-78)忠宗の三男ー愛姫遺言で田村家の名跡を継いだ。
綱宗(1640-1711)忠宗の六男ー19歳で家督を継ぐが酒色に溺れ2年で隠退
宗房(1646-86)忠宗の八男が五代藩主に。
「秀宗と亀姫」
宗実(1612-44)は、病弱で地位を同母弟「宗時」に譲っている。 宗時(1615-53)実質的藩主とし活躍したが襲封前に死去
宗利(1635-1709)秀宗の三男は、伊予宇和島藩二代藩主に。 宗純(1636-1708)秀宗の五男は、父から3万石分与、伊予吉田藩主に。
「涅槃門」
樹齢数100年の青森檜葉に飾り彫刻ー涅槃とは、煩悩を取り払った悟りの境地となる状態を云う。
資料館には、副葬品等が展示されている。金製飾り・大刀・兜・手箱など。



参道は、石造り階段と左右に杉並木(樹齢380年余り)が、、、。
「瑞鳳殿」
1636年政宗70歳の生涯を閉じ遺命により、その翌年造営された霊屋ー墓所。桃山文化を伝える豪華絢爛な廟建築。
柱には、彫刻ー獅子頭・屋根には竜頭瓦が


「感仙殿」-二代将軍 伊達忠宗(1599-1658)
政宗の治世を引き継ぎ、新田開発、港湾整備と産業・経済の復興を図り領内の安定に尽力し、基礎固めを成し遂げている。
瑞鳳殿と同様、豪華なもの。


「善応殿」-三代藩主 伊達綱宗(1640-1711)
芸術的才能にたけ、隠居後は、書画・蒔絵などで余生を送っている。水墨画などは、江戸期東北を代表する作品を残している。
墓室からは、香道具や文具など多数副葬品が出土。



妙雲界廟・御子様廟
感仙殿北・東正面に九代藩主 伊達周宗公・南正面に十一代藩主 伊達斎義夫妻の妙雲世廟が。
参道手前に五代藩主 伊達吉村公・歴代子公女の墓域になている。



美食大名と云えば、徳川家康・伊達正宗、政宗は、意外なことに料理が趣味。
もともと兵糧開発だったのが平和な世になるや美食を極める為に料理研究し、仙台に美味いものが多いのはその名残か。
政宗談ー「馳走とは旬の品をさり気なく出し、主人自ら調理して、もてなす事である」と云う。
広瀬川で自ら魚を釣り客にふるまったとある。酒に弱かったとある。



次回は、青葉城へ。
私が仙台に単身で赴任した(仙チョン族といっていた)昭和末頃は、仙台ー上野東北本線所要時間4時間強、
座席も90度直角で車内は常に大混雑で苦労して月に一回東京に帰京していた。
明治9年に、「奥羽巡幸」において明治天皇が馬車で各地を回り、明治16年、仙台 - 福島の運行を開始したと云う。
当時は、都市間乗合馬車を乗り継くことで、東京 - 仙台の所要時間は3泊4日に短縮された。
1887年の明治20年、日本鉄道の駅として仙台駅が。上野駅から宮城県・塩竈駅まで通じ、上野 - 仙台間の所要時間は12時間20分の記録がある。
「仙台駅」初代の駅舎は木造平屋建ての小さな建物で線路の西側に位置し、馬車を回すロータリーがあったと云う。
昭和20年、仙台空襲により焼失した。
1906年に日本鉄道は国有化され、国鉄東北本線・1925年に仙台地区では初の直流電化路線である宮城電気鉄道(後の仙石線)が西塩釜駅まで開業し、
1929年には仙山東線(後の仙山線)が愛子駅まで敷かれ、所要時間は1926年に上野 - 仙台間が8時間弱。
この頃の仙台駅は東北地方で最多の旅客数であったが、貨物では青森駅・塩竈駅(旧駅)などに引き離されている。
1926年の大正15年、仙台市電が仙台駅前駅 - 荒町日赤病院前駅において開業し、駅前広場に隣接する駅前通りに仙台駅前停留所が設けられた。



岩出山町「座散乱木遺跡」・古川市「馬場壇遺跡」は旧石器時代の」遺跡で、縄文時代では小牛田町の「素山貝塚」・石巻の「沼津貝塚」・七ヶ浜町の
「大木囲貝塚」等。弥生時代では仙台市の「小泉遺跡」・塩釜の「崎山囲遺跡」・多賀城の「枡形囲遺跡」等が知られている。
古墳時代では、名取市「雷神山古墳」・丸森町の「台町古墳」・「京銭塚古墳」等がある。
724年には、多賀城に「陸奥国府、鎮守府」が置かれている。その80年後「坂上田村麻呂」が鎮守府を胆沢城に移す。
1051年、「前九年の役」が起こる。1083年、「後三年の役」が、1170年「藤原秀衡」が鎮守府将軍となる。
1189年、源頼朝の奥州征伐で「藤原氏」は滅ぶ。1333年、北畠顕家が陸奥守~1591年天正19年、「伊達正宗」米沢より岩出山に移っている。1601年、正宗は、仙台城築城し移る。3年後、松島に「五大堂」が完成。
仙台湾には、北上川・阿武隈川・名取川が注ぎ沖積平野を形成し、水田面積は、他県に劣らない「東北地方第一位」。
古代から、東北地方の海の玄関口、陸奥国府「多賀城」(現多賀城市)に設置されている。
三陸南部はリアス海岸で、天然の良港ー寒流の親潮と暖流の黒潮がまじわる漁場と云う。石巻・気仙沼が知られている。
杜の都「仙台・青葉通り」

「仙台七夕」ー約3000本の七夕飾りがアーケード街を埋めつくす。
古くは、藩祖「伊達政宗公」の時代から続く伝統行事として受け継がれ、 日本古来の星祭りの優雅さと飾りの豪華絢爛さを併せ持つお祭りとして全国に名を 馳せており、旧暦7月7日の行事として全国各地に広まっている。
短冊ー学問や書の上達を願う。紙衣ー病や災いの身代わり、または、裁縫の上達を願う。折鶴ー長寿を願う。巾着ー富貴と貯蓄、商売繁盛を願う。
投網ー豊漁を願う。くずかごー飾り付けを作るとき出た裁ち屑・紙屑を入れる。清潔と倹約を願う。吹き流しー織姫の織り糸を象徴する。
戦後の昭和21年、仙台空襲で焼け野原となった街に52本の竹飾りで仙台七夕は復活・ここ商店街で、、。



「穴蔵神社」
鎮座地ー・青葉区霊屋下(瑞鳳寺参道横) 主祭神ー宇迦之御魂神 祭日ー9月19日

元米沢に御鎮座。
伊達氏の守護神として奉斎、藩祖政宗伊達郡梁川に遷し、、後、青葉城を築くのとき鈴の沢の地を選び城に向けて遷し祀るとある。
「夕日明神」と称あり。天保6年ー広瀬川の氾濫と崖崩れの災をおそれ遂に川下の現在の地に鎮められた。
藩祖の信仰あつく社殿の修復のことは勿論、本社に三貫文の地を寄進し、更に年一石の饌米を奉献するを例とし、歩卒172家をもって祭事が、
公の奥方・愛姫(陽徳院)は安産の守護神として深く信仰したと伝えられている。
(社伝、稲荷神祠頌)大正11年八木山の越路神社(山神)を合祀。平成15年参道修復工事、平成17年本殿改築。



「瑞鳳寺」
広瀬川右岸の丘陵経ヶ峰のある臨済宗妙心寺派 山号ー正宗山 開山ー清岳宗拙。
本尊ー釈迦三尊 伊達正宗の遺言ー二大藩主「伊達忠宗」が1636年に創建・三代藩主「伊達綱宗」



三大の霊廟が「瑞鳳殿」-伊達正宗・「感仙殿」ー伊達忠宗・「善応殿」-伊達綱宗がある。
「瑞鳳殿」は、桃山時代の建築様式をつたえる豪華な霊廟建築と云う。1979年復元(国宝指定)



「伊達正宗」1567-1636 東北の猛者、独眼竜と恐れられた。
仙台藩主・伊達輝宗の長男、蘆名義広を破り「会津」掌握。
小田原征伐で遅参し、豊臣秀吉から領国一部没収されている。「関ヶ原の戦い」東軍に与する。-62万石大名に。
スペイン通訳「シピオーネ」(支倉常長)-正宗は、奥州を植民地としてスペインへ献上し、次期皇帝の最高実力者と記した宣教師「ソテロ」の書簡
が残っている。正宗は、天下を狙っていた証拠度と云われている。独眼竜正宗、片目を苦にし、自分の像には両目を添えよと遺言している。
「人そめて くにゆたかなる みぎりとや 千代とかぎらじ 仙台のまつ」伊達正宗・和歌ー仙台の名はここから



米沢城主伊達輝宗(1544-85)-出羽半国・最上義光(1546-1614)の妹・義姫保春院(1548-1623)-最上氏の宿敵。
長男「伊達正宗」(1567-1636)-妻は、愛姫・陽徳院(1568-1653)陸奥三春城城主の一人娘ー3男1女をもうけた。小次郎ー1590正宗毒殺未遂事件で
正宗に斬殺 井伊直政(1561-1602)亀姫徳川家康の命で「伊達秀宗ー政宗庶長子」に嫁ぐ。
政宗の三男飯坂宗清(1600-34)母の実家飯坂氏養子へ。 宗勝十男末子(1621-80)一関藩主
松平忠輝(家康6男)ー越後高田藩75万石太守となるが大坂の陣遅参で改易。 五郎八姫(天麟院)忠輝改易と共に離縁・仙台で暮らす
伊達忠宗(政宗次男嫡男)政宗死後家督継承陸奥仙台藩二代藩主ー長男宗綱(1603-18)、正宗の5男16歳で早世
忠宗の正室は、徳川家康外孫姫路藩主池田輝政の娘、徳川秀忠養女が嫁いでいる。その次男嫡男が伊達光宗(1627-45)19歳で病没。
田村宗良(1637-78)忠宗の三男ー愛姫遺言で田村家の名跡を継いだ。
綱宗(1640-1711)忠宗の六男ー19歳で家督を継ぐが酒色に溺れ2年で隠退
宗房(1646-86)忠宗の八男が五代藩主に。
「秀宗と亀姫」
宗実(1612-44)は、病弱で地位を同母弟「宗時」に譲っている。 宗時(1615-53)実質的藩主とし活躍したが襲封前に死去
宗利(1635-1709)秀宗の三男は、伊予宇和島藩二代藩主に。 宗純(1636-1708)秀宗の五男は、父から3万石分与、伊予吉田藩主に。
「涅槃門」
樹齢数100年の青森檜葉に飾り彫刻ー涅槃とは、煩悩を取り払った悟りの境地となる状態を云う。
資料館には、副葬品等が展示されている。金製飾り・大刀・兜・手箱など。



参道は、石造り階段と左右に杉並木(樹齢380年余り)が、、、。
「瑞鳳殿」
1636年政宗70歳の生涯を閉じ遺命により、その翌年造営された霊屋ー墓所。桃山文化を伝える豪華絢爛な廟建築。
柱には、彫刻ー獅子頭・屋根には竜頭瓦が


「感仙殿」-二代将軍 伊達忠宗(1599-1658)
政宗の治世を引き継ぎ、新田開発、港湾整備と産業・経済の復興を図り領内の安定に尽力し、基礎固めを成し遂げている。
瑞鳳殿と同様、豪華なもの。


「善応殿」-三代藩主 伊達綱宗(1640-1711)
芸術的才能にたけ、隠居後は、書画・蒔絵などで余生を送っている。水墨画などは、江戸期東北を代表する作品を残している。
墓室からは、香道具や文具など多数副葬品が出土。



妙雲界廟・御子様廟
感仙殿北・東正面に九代藩主 伊達周宗公・南正面に十一代藩主 伊達斎義夫妻の妙雲世廟が。
参道手前に五代藩主 伊達吉村公・歴代子公女の墓域になている。



美食大名と云えば、徳川家康・伊達正宗、政宗は、意外なことに料理が趣味。
もともと兵糧開発だったのが平和な世になるや美食を極める為に料理研究し、仙台に美味いものが多いのはその名残か。
政宗談ー「馳走とは旬の品をさり気なく出し、主人自ら調理して、もてなす事である」と云う。
広瀬川で自ら魚を釣り客にふるまったとある。酒に弱かったとある。



次回は、青葉城へ。