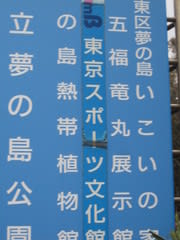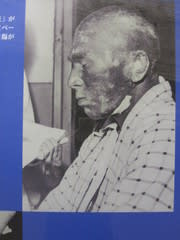お休みの間、大勢の皆様にご訪問いただき有難うございました。パソコンも復活しました。日光の続きを掲載いたします。
大猷院は徳川三代将軍家光の廟所です。境内には、世界遺産に登録された22件の国宝・重要文化財が、杉木立の中にひっそりとたたずんでいます。
特に雪の舞う中、境内に林立する315基の灯籠と共に、美しくも印象的です。
先祖である家康公の廟所(東照宮)をしのいではならないという家光公の遺命によって、彩色や彫刻は、控え目に造られましたが、
かえってそれが重厚で落ち着いた雰囲気を醸し出しています。
入り口の「仁王門」にはじまり、家光公墓所の入り口に当たる「皇嘉門」まで、意匠の異なる大小6つの門で、境内が立体的に仕切られており、
門をくぐるたびに景色が転換して、あたかも天上界に昇っていくような印象を受けます。

「徳川家光」1604-51 三代将軍、二代秀忠の長男、両親は弟忠長を偏愛、家康が裁定し二十歳で将軍に就任。
酒井忠世、土井利勝、松平信綱等の指導で強力な政治力を発揮した。家光は、幼少時から言語障害があったという。家康を終世敬愛した。

お清め所

仁王門







ご廟所

燈籠と扉





大猷院は徳川三代将軍家光の廟所です。境内には、世界遺産に登録された22件の国宝・重要文化財が、杉木立の中にひっそりとたたずんでいます。
特に雪の舞う中、境内に林立する315基の灯籠と共に、美しくも印象的です。
先祖である家康公の廟所(東照宮)をしのいではならないという家光公の遺命によって、彩色や彫刻は、控え目に造られましたが、
かえってそれが重厚で落ち着いた雰囲気を醸し出しています。
入り口の「仁王門」にはじまり、家光公墓所の入り口に当たる「皇嘉門」まで、意匠の異なる大小6つの門で、境内が立体的に仕切られており、
門をくぐるたびに景色が転換して、あたかも天上界に昇っていくような印象を受けます。

「徳川家光」1604-51 三代将軍、二代秀忠の長男、両親は弟忠長を偏愛、家康が裁定し二十歳で将軍に就任。
酒井忠世、土井利勝、松平信綱等の指導で強力な政治力を発揮した。家光は、幼少時から言語障害があったという。家康を終世敬愛した。

お清め所

仁王門







ご廟所

燈籠と扉