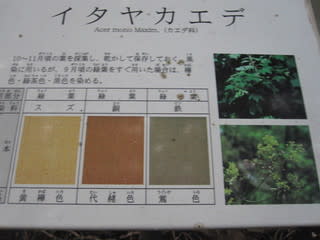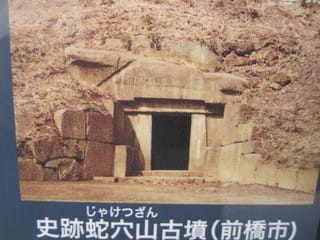新潟南魚沼から、群馬渋川へ。
旧石器時代の岩宿遺跡で、赤城山噴火・縄文、月夜野大原遺跡・弥生、子持村押手遺跡(前期)・前橋天神山古墳・741年に国分寺・939年
平将門上野国を襲う・1108年浅間山が大噴火・1333年「新田義貞」挙兵・1335年「上杉憲房」以降上杉氏・足利基氏が上杉憲顕を
関東管領に任じ、守護代に「長尾景忠」としている。
1552年関東管領「上杉憲政」、「北条氏康」小田原に平井城追われ上杉謙信を頼る。
1582年織田信長、滝川一益を関東管領に任している。1949年昭和24年国立群馬大学開学、「相沢忠洋」岩宿のローム層で旧石器発見。
日本全体から見ると、北海道・九州から群馬県は直線で約1000km、日本列島の中央部に位置、気候も太平洋型と日本海型気候の境界である。
その為、「雷とからっ風」で知られ、雷を祀る神社が多い。
練馬ICから本庄児玉ICまで国道254号、本庄児玉ICから長岡JCTは国道17号がほぼ並行,三国山脈を貫いて東京と新潟県を結ぶ高速道.
上越新幹線とともに首都圏と日本海側を結ぶ高速交通網として重要な機能を持ち、藤岡JCTから上信越自動車道(関越自動車道上越線)が分岐。
首都圏と長野県北信地方・東信地方を結ぶ高速交通網の一部。

「前橋市」は、利根川の沖積平野を中心に、北赤城山麓広がり、東山道の駅家(碓氷峠、上野国府ー下野国府を結ぶ)所在地。
利根川に架かる橋名「厩橋」-「前橋」に、上野国府指定地があり、戦国時代は、厩橋城が築かれ、後酒井氏の厩橋藩が成立している。その時厩橋から
前橋城と名を変えている。幕末には21万国の城下町であった。
糸の町として発展、横浜港海港が1859年、以降最大の出荷地であった。世界恐慌まで糸の町として栄えた。
「吉岡町」は、関越自動道渋川・伊香保ICで、県のほぼ中央に位置し、榛名山の南東の山麓と利根川地域に町域がある。
西半分は榛名山の裾野の一部で、標高200~900mの傾斜地。一方東半分は、標高100~200mの洪積層からなる台地となっている利根川沿いの町。
「村社・赤城神社」
御祭神、赤城大明神、大国主神、磐筒男神、磐筒女神、經津主神、豐城入彦命。相殿、徳川家康公、大山祇神等、
赤城山の赤城神社の分社・群馬県の赤城山を祭る赤城神社の支流で、旧社格は村社。



「大胡城」は、大胡氏の居城。(赤城山・赤城神社・16号線・大胡町)
大胡氏は藤原秀郷の子孫であり、東毛地方で勢力を扶植していた豪族。
「吾妻鏡」の1190年、の記事には大胡太郎の名前が見える。
鎌倉時代の初期にはすでにこの地域の有力な支配者であったと思われるが、大胡氏の居館は、現在の大胡城ではなく、城の西300mほどの所にある養林寺
の辺りであったのではないかと推定。
現存の城趾には近世大名牧野氏の城主時代の縄張りや構造が認められている。
城は、前橋市河原浜町・中世の日本の城(平山城跡)、大胡氏・上泉氏の居城、後に近世初頭に徳川氏の臣・牧野氏が入り城主。
1532年 - 1555年に築城されたとされ、1616年廃城となった。
前橋市河原浜町にあった中世の日本の城(平山城跡)


南北朝時代、観応の擾乱に際して大胡氏は山上氏らと共に足利尊氏に与し、足利直義方の桃井直常、長尾景忠と笠懸野で戦って敗れたが、
やがて尊氏は勢力を回復し直義を自害に追い込んだ。
その後しばらく大胡氏の動静はつかめないが、「享徳の乱」のさなかに古河公方足利成氏は配下の岩松持国に赤堀・大胡・深津氏を攻撃させているので、この大乱において大胡氏は上杉方に加担していたものと思われる。
1469年に川越城で行われた太田資清主催の連歌会に大胡城主とみられる大胡修茂の名が見えていると云う。
大胡氏・上泉氏の居城。後に近世初頭に徳川氏の臣・牧野氏が入り城主に なった。



1582年、武田氏も織田信長に攻められて滅亡し、その後信長の家臣「滝川一益」が厩橋城(前橋城)に入りこの地方を支配したが、本能寺の変で信長が殺害されると織田氏の勢力も一掃されるというように、めまぐるしく事態は展開した。
滝川氏が去った後はこの地方は完全に北条氏の支配下に置かれることとなる。
関東地方で最大勢力を誇った北条氏も1590年、小田原征伐で没落し、変わって関八州の支配者となったのは徳川家康。
大胡城には徳川氏家臣の「牧野康成」が2万石で大胡城に入城した。
しかし、入城後約25年の1616年、牧野氏は越後長峰に5万石で転封され、大胡領は前橋城主酒井氏の管轄となり、それにより上部構造物が撤去されて大胡城は廃城となった。
天文年間、1532年 - 1555年に築城されたとされ、元和2年、1616年廃城と。



城の古絵図によると、
細長い小丘陵地の南北を堀切で仕切り、土塁・枡形門を備えた本丸・二ノ丸は大胡氏時代の城郭構造であると推定される。
このほかに三ノ曲輪・四ノ曲輪(以上南側)・西曲輪・玉蔵院(西側)・根小屋(東側)・越中屋敷(北側)が位置する。
城北部に近接の近戸神社があるがこれも城郭の一部とされ近戸曲輪という。
複郭構造には牧野氏が拡充した近世城郭の様相も見て取れる。現在見られる石垣構造などはこの牧野氏時代に構築されたのでは。


渋川・伊香保IC、国道17号線・吉岡町に近い、「箱田城」は、
白井長尾氏の居城である白井城の出城として戦国時代に箱田地衆によって築かれたという。
箱田地衆というのは土地の地侍のことで、半農半士のような存在である。箱田地衆は木曽義仲に仕えた郎党の末裔を称する今井氏、高梨氏、小野沢氏ら
で形成されていたとされる。
前橋城から白井城へと続く利根川沿いの道には箱田城の他にも等間隔で砦が並んでいるが、戦国時代の上州は、北条氏と武田氏に上杉氏らが絶えず領土を奪い合っていた激戦地である。
箱田城も戦国時代末期まで使用されていたと思うが、落城伝説等は伝わっていない。
箱田城は白井長尾氏の居城である白井城の出城。利根川沿いの道には箱田城の他にも等間隔で砦が。北条氏と武田氏に上杉氏らが領土を奪い合っていた。


「岩神稲荷神社」(前橋市)
祭 神ー倉稲魂命 木花咲耶姫命。
神社裏に巨岩があり、往昔この巨岩を拝祭して岩神。
酒井河内守重忠公が領主とな、稲荷大神を勧請祭祀としている。
古くより岩神村の地名の起こりとして学術研究上貴重存在で、巨岩は「天然記念物指定」
県庁から北へ進んだ群馬大学医学部付属病院の隣に鎮座している。
鳥居を潜るとすぐに拝殿、短い参道には幟が立てられて境内は狭い。社殿は比較的新しく、土台もコンクリートに。
大学交差点・朱い鳥居と岩神稲荷神社と書かれた赤い幟が 見える



「岩神の飛石」
10万年以上前の赤城山の爆発により噴出した溶岩であり、約2万年前の浅間火山の爆発 によって生じた火山泥流によってここまで運ばれたと考えられていた(案内板)。
これに対し、浅間山研究の第一人者・群馬大学の早川由起夫氏は、
浅間山の噴火に伴うものとする新説を出し、今からおよそ2万4000年前の浅間山の噴火で起きた山体崩壊による泥流が吾妻川に流入し、利根川を流れ下ってこの場所で止まったのだとするものである。
赤城山から噴出した火山岩といい国指定天然記念物。



2万4000年前のこの時代、東日本の年平均気温は今より7~8度も低く、氷河の発達と後退がくり返されていたと云う。
海面は現在よりも約100mも低下し、日本列島の南北は陸橋により大陸とつながっていたと推定されている。
この岩塊に、何万年にもわたる太古の記憶が刻み込まれる。
地球上で最も古い岩石は、カナダ北西部で見つかった火成岩で40億3000万年前までさかのぼるという。
御神体は周囲60m、地表に出ている高さは約10m、さらに地下に数mは埋もれ ているという巨岩。

「国指定天然記念物 岩神の飛石」
周囲が約60m、高さは地表に露出した部分だけで9.65m、さらに地表下に数mは埋もれている。
昔、石工がノミをあてたところ、血が流れ出したという伝説があり、岩は赤褐色の火山岩で、地表には縞のような構造も見えると云う。
大きさのそろった角ばった火山起源の岩や石が多い部分もあります。この岩の火口から溶岩として流れ出したものではなく、火口から噴出した高温の火山岩や火山灰などが冷えて固まってできたものと考えられている。
岩を石材利用しようとノミを入れたら血が噴出して災いを起こしたという伝説が。

「国立群馬大学」
1949年に設置、大学の略称は群大ーぐんだい。
国立群馬大学教養部校入口

1873年に 群馬師範学校創設され、1915年 桐生高等染織学校として創設、1918年に、 群馬青年師範学校創設・1920年 桐生高等染織学校から桐生高等工業学校に改称され、1943年 前橋医学専門学校創設し、1944年 桐生高等工業学校から桐生工業専門学校へ改称をたどり、1949年に 新制群馬大学に。
群大校庭



「敷島公園」
90年以上の歴史、昭和4年「日本の公園の父」と呼ばれる「本多静六博士」(1866~1952)が敷島公園の改良設計。
博士は、日比谷公園をはじめ日本各地を代表する数百にもおよぶ公園の設計に携わっている。
公園を街づくりの中心施設として考え、
「公園を地域の情報発信基地にすれば人も集まりお金も動く、お金が動けば地域経済も豊かになり文化の向上につながる」という当時としては大変新しい考え方で公園を設計されたと云う。
敷島公園

「本多静六」1866ー1952年(満85歳没)
明治17年・1884年、東京山林学校(後に東京農林学校から東京帝国大学農科大学)に入学し、卒業時には首席。
卒業1年前の1889年、元彰義隊隊長、本多敏三郎の娘・詮子と結婚し婿養子。
東京農林学校(現在の東京大学農学部)を卒業とともに、林学を学ぶためドイツへ留学、ドイツでは、2つの学校に学び、最初はドレスデン郊外にあるターラントの山林学校(現在はドレスデン工科大学林学部)で半年、この後ミュンヘン大学へ転校し、更に1年半学問を極めた。ドクトルの学位を取得、欧米を視察した後帰国し、母校の助教授、教授に。
日比谷公園を皮切りに、北海道の大沼公園や福島県の鶴ヶ城公園、埼玉県の羊山公園、東京都の明治神宮、長野県の臥竜公園、石川県の卯辰山公園、福岡県の大濠公園ほか、設計・改良に携わった公園多数。
東京駅丸の内口駅前広場の設計も行っているほか、行幸通りも本多氏が担当、関東大震災からの復興に。
敷島公園


利根川東岸の市街地にある公園、旧河川敷の松林と池沼が中央に、運動公園が並んでいる。1912年旧国立蚕種試験場を移築した。
敷島公園



敷島公園


ばら園は、平成20年3月にオープン.
ばら園は、敷島公園の松林をぬけた西奥に600種のバラ7,000株が植栽され,平成20年の「全国都市緑化ぐんまフェアの総合会場」にもなっている。
園内には、郷土の詩人・萩原朔太郎の生家を移築した「萩原朔太郎記念館」や、「糸の町」前橋をしのぶ「蚕糸記念館」などがある。
敷島公園



「萩原 朔太郎」1886 - 1942年、日本の詩人。大正時代に近代詩の新しい地平を拓き「日本近代詩の父」。
前橋中学卒業後、第5高等学校・第6高等学校・慶応義塾で、最終学歴、慶應義塾大学予科中退 活動期間は、1917年 - 1942年
詩・随筆・評論・小説・短歌 ・文学活動ー象徴主義・芸術詩派・アフォリズム・口語自由詩・神秘主義
代表作ー「月に吠える」(1917年)・「青猫」(1923年)・「純情小曲集」(1925年)・「氷島」(1926年)・「猫町」(1935年、小説)
受賞歴ー第8回文学界賞(1936年)・ 第4回透谷文学賞(1940年)
処女作ー「ひと夜えにし」(1902年、短歌)・「みちゆき」(1913年、詩)。
昭和16年「樋口一葉全集5巻」刊行し、翌年肺炎、自宅で死亡している。
敷島公園バラ園と萩原 朔太郎旧宅(無料)


次回も前橋市内。