胎内市中条町は鎌倉時代、荘園奥山庄の中心部を示す地名、「越後国奥山庄波月絵図」は、当時の荘園のようすを伝えている。
江戸に入ると。米沢街道の宿場町、近郷農村部相手の「六斉市」知られている。幕末から明治では、桃崎浜が西廻海軍の寄港地として栄えた。
胎内川の湧水と天然ガスを利用したガス化学コンビナートで大工場が次々進出された。
JR中条駅は、県胎内市 東日本旅客鉄道(JR東日本)、日本貨物鉄道(JR貨物)、羽越本線 39.1km(新津起点)、1,236人/日 -2010年-
1914年(大正3年)開業、
駅は、胎内市の中心駅で、特急「いなほ」の全列車が停車する。
中条駅 村松浜


日本書紀には、越後国より天智天皇に「燃ゆる水(燃水)」が献上されたという記述がある。胎内市より産したものであるとされる。
自然にわき出た原油は「臭水、草水(くそうず)」などと呼ばれた。国内油田の本格的な利用は明治時代以降のことである。
「黒川油田」北西部、下館に、明治に手掘り井戸による石油の油坪群が見つかっている。現在シンクルトン記念公園になっている。
坪跡には手掘り跡と上総掘り跡、明治6年、英国人シンクルトン指導のたて穴掘りの異人井戸跡が残っている。
カクマ(シダ類)ですくう昔の採油から、機械採油までの様子を見ることが出来る。
我が国初の黒川油田


「湖彦山・廣厳寺」は、曹洞宗の開創、1389年頃、胎蔵界大日如来を本尊とする真言宗のお寺が建立されていたと伝えられている。
本尊は京都の大仏師定朝法印の作でその当時のものと思われる。世源康伝によって修復されている。
曹洞宗開創当時 天正16年は、戦国時代であり、戦乱の世の中でお寺も非常に荒廃し、住職もいなかったと思われる。
本殿 末社



「熊野・若宮神社」は、中条駅の北東500メートルに鎮座。旧中条町の産土神で, かつては川下(西本町)に鎮座したが1797年に現在地遷座した。
古くは「若一王子」としたが,1872年に村社となり「熊野若宮神社」と改められた。
祭神は饒速日命,事解男命,速玉男命,伊邪那岐神,天目一箇神,神功皇后,武内宿禰。饒速日命・神武天皇より前に降臨していたが,神武天皇に従ったとされる神。
拝殿と本殿は弊殿によってつながっており,いずれも規模が大きい。残された棟札に1789年の記載があり,建立の時期もそのころだと考えられる。
本殿内に安置されている宮殿は,1690年の作で,県の文化財指定。
境内の大木 本殿



「黒川郷土文化伝習館」は、縄文時代の遺跡資料から、近世の民俗資料まで胎内市の歴史資料を収蔵・展示。展示品は、遺跡の資料、民俗の資料、胎内の動植物、
郷土芸能など。「中条駅」より車で10分。入館料¥200、
伝習館正面 展示場


「黒川城」は、1277年、高井道円(奥山庄と本領相模国津村の所領、阿波国・讃岐国・出羽国の所領を茂連・茂長・義基の3人の孫に譲与する。
三代の茂実は、南北朝時代に足利氏に従い北条氏を打ち、越後守護長尾邦景を勝利に導くなど活躍し、1423年には、6代基実が守護側に背反し300騎で、黒川城に籠ったが、
逆に中条房資、上杉頼勝、伊達持宗ら5000騎に攻められ降伏した。さらに黒川館も滑沢何某に夜打ちをかけられ黒川基実は切腹し、その子弥福丸(氏実)が中条房資に
救出されて、再興を果たす。
大きく分けて2か所の曲輪群があり標高203.9m地点(赤坂山砦=黒川城前要害)と、本城に相当する標高462m付近に赤坂山砦がある。
展示場館内 正面赤坂山・黒川城跡がある



「無形文化財保持 瞽女・ごぜ、小林ハルさん」
盲目の女性が3~4人で組を作り、農山村の奥地まで訪ね、三味線芸を披露して歩く旅芸人たちを云う。室町時代の「看聞御記」の
盲女絵巻「七十一番職人歌合」にみられる「鼓打ちで歌う女盲」を瞽女とも言われていた。
引退直後の小林ハル



「越後胎内観音」は、 昭和41年7月16日に新潟県下越地方を襲った集中豪雨は、3日間にわたって降り続いた。そのため胎内川は毎秒100トンを超す濁水が激流し、
中小河川がいたるところで氾濫するに至り、新潟県北蒲原郡黒川村は水攻めの大被害を受けた。
昭和42年8月28日には集中豪雨により土石流が発生し死者・行方不明32名、家屋の倒壊・埋没・流失121棟、田畑の流埋冠水5,000ha、道路・橋梁の決壊流失など、
郷土史上いまだかつてない惨事となり、黒川村は壊滅的な打撃を受けた。
この2年連続の大水害に対し、村長を先頭に「災を転じて福となす」を合言葉に再建に取り組むとともに、殉難者の冥福と災害復興を願って昭和45年日本一の大観音像を建立した。
越後胎内観音像 楼門

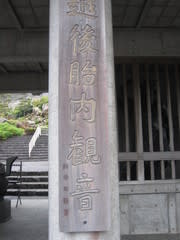

「42年水害」は、胎内川流域では上流の、胎内第一ダムで一日総降水量が645ミリ、同胎内第一発電所で542ミリを記録。
北蒲原郡中条町と黒川村(いずれも現在の胎内市)では胎内川中流部の赤川と下流部の熱田坂で堤防が決壊、家屋の浸水が2,170戸、農地などの浸水が2,330haに及んだ。
六角堂 境内


胎内の歴史は古く、桓武平氏の一族、城氏が平安末期に「奥山荘」周辺を支配した。
1201年、城資盛は平氏復興のため鳥坂城で挙兵、幕府は佐々木盛綱を越後御家人の総大将として追討軍を派遣、城氏は事実上滅亡した。
その後幕府は木曽義仲追討の恩賞として、三浦和田氏の和田義茂に「奥山荘」地頭職を与えた。
三浦和田氏は土着して中条氏を名乗り、黒川氏、関沢氏、築地氏、金山氏など多くの庶流を生み出した。
中条氏と黒川氏は波月条や金山郷などの周辺の所領をめぐり度々紛争を起こした。江上館は越後三浦和田氏の宗家・中条氏の15世紀の居館と見られている。
戦国期の後半は中条氏は庶流の羽黒氏の居館を接収し、鳥坂城南麓にも居館を構え、居館と要害を一体化した根古屋式城郭とした。
1598年の上杉景勝の会津移封により、中条氏もこの地を離れ、奥山荘における三浦和田氏の支配は終わったと云われている。


波乗り観音・越後胎内観音は、総丈7.3m、重量4t、鳥坂山を背に蓮華台で合唱姿は波の上に載っているように見えるところから、波乗り観音とも言われている。
羽越水害で、犠牲になって亡くなった32名の人達の供養する観音像である。
薬師堂など、ボランティアの掃除の小母さんと話が出来た。
胎内観音供養堂内


「酒造りの話」第三仕込「溜」
約仕込んで温度が7~8℃が、醗酵熱で15~16℃にあがる。醪を検査する。比重計(ボーメ)で酸度分析
溜後2~3日で泡が出だす。筋泡、水泡、岩泡、高泡、落泡、玉泡、最後が「地」で終わる。
醪をもう一度加えるのを「四段仕込み」 アルコール分は、18~19℃になっている。
味を調えるため、アルコールを添加、これは国で定めれている清酒のみ、(純米酒はアルコールを添加しない)
次回は、笹川流れ。
江戸に入ると。米沢街道の宿場町、近郷農村部相手の「六斉市」知られている。幕末から明治では、桃崎浜が西廻海軍の寄港地として栄えた。
胎内川の湧水と天然ガスを利用したガス化学コンビナートで大工場が次々進出された。
JR中条駅は、県胎内市 東日本旅客鉄道(JR東日本)、日本貨物鉄道(JR貨物)、羽越本線 39.1km(新津起点)、1,236人/日 -2010年-
1914年(大正3年)開業、
駅は、胎内市の中心駅で、特急「いなほ」の全列車が停車する。
中条駅 村松浜


日本書紀には、越後国より天智天皇に「燃ゆる水(燃水)」が献上されたという記述がある。胎内市より産したものであるとされる。
自然にわき出た原油は「臭水、草水(くそうず)」などと呼ばれた。国内油田の本格的な利用は明治時代以降のことである。
「黒川油田」北西部、下館に、明治に手掘り井戸による石油の油坪群が見つかっている。現在シンクルトン記念公園になっている。
坪跡には手掘り跡と上総掘り跡、明治6年、英国人シンクルトン指導のたて穴掘りの異人井戸跡が残っている。
カクマ(シダ類)ですくう昔の採油から、機械採油までの様子を見ることが出来る。
我が国初の黒川油田


「湖彦山・廣厳寺」は、曹洞宗の開創、1389年頃、胎蔵界大日如来を本尊とする真言宗のお寺が建立されていたと伝えられている。
本尊は京都の大仏師定朝法印の作でその当時のものと思われる。世源康伝によって修復されている。
曹洞宗開創当時 天正16年は、戦国時代であり、戦乱の世の中でお寺も非常に荒廃し、住職もいなかったと思われる。
本殿 末社



「熊野・若宮神社」は、中条駅の北東500メートルに鎮座。旧中条町の産土神で, かつては川下(西本町)に鎮座したが1797年に現在地遷座した。
古くは「若一王子」としたが,1872年に村社となり「熊野若宮神社」と改められた。
祭神は饒速日命,事解男命,速玉男命,伊邪那岐神,天目一箇神,神功皇后,武内宿禰。饒速日命・神武天皇より前に降臨していたが,神武天皇に従ったとされる神。
拝殿と本殿は弊殿によってつながっており,いずれも規模が大きい。残された棟札に1789年の記載があり,建立の時期もそのころだと考えられる。
本殿内に安置されている宮殿は,1690年の作で,県の文化財指定。
境内の大木 本殿



「黒川郷土文化伝習館」は、縄文時代の遺跡資料から、近世の民俗資料まで胎内市の歴史資料を収蔵・展示。展示品は、遺跡の資料、民俗の資料、胎内の動植物、
郷土芸能など。「中条駅」より車で10分。入館料¥200、
伝習館正面 展示場


「黒川城」は、1277年、高井道円(奥山庄と本領相模国津村の所領、阿波国・讃岐国・出羽国の所領を茂連・茂長・義基の3人の孫に譲与する。
三代の茂実は、南北朝時代に足利氏に従い北条氏を打ち、越後守護長尾邦景を勝利に導くなど活躍し、1423年には、6代基実が守護側に背反し300騎で、黒川城に籠ったが、
逆に中条房資、上杉頼勝、伊達持宗ら5000騎に攻められ降伏した。さらに黒川館も滑沢何某に夜打ちをかけられ黒川基実は切腹し、その子弥福丸(氏実)が中条房資に
救出されて、再興を果たす。
大きく分けて2か所の曲輪群があり標高203.9m地点(赤坂山砦=黒川城前要害)と、本城に相当する標高462m付近に赤坂山砦がある。
展示場館内 正面赤坂山・黒川城跡がある



「無形文化財保持 瞽女・ごぜ、小林ハルさん」
盲目の女性が3~4人で組を作り、農山村の奥地まで訪ね、三味線芸を披露して歩く旅芸人たちを云う。室町時代の「看聞御記」の
盲女絵巻「七十一番職人歌合」にみられる「鼓打ちで歌う女盲」を瞽女とも言われていた。
引退直後の小林ハル



「越後胎内観音」は、 昭和41年7月16日に新潟県下越地方を襲った集中豪雨は、3日間にわたって降り続いた。そのため胎内川は毎秒100トンを超す濁水が激流し、
中小河川がいたるところで氾濫するに至り、新潟県北蒲原郡黒川村は水攻めの大被害を受けた。
昭和42年8月28日には集中豪雨により土石流が発生し死者・行方不明32名、家屋の倒壊・埋没・流失121棟、田畑の流埋冠水5,000ha、道路・橋梁の決壊流失など、
郷土史上いまだかつてない惨事となり、黒川村は壊滅的な打撃を受けた。
この2年連続の大水害に対し、村長を先頭に「災を転じて福となす」を合言葉に再建に取り組むとともに、殉難者の冥福と災害復興を願って昭和45年日本一の大観音像を建立した。
越後胎内観音像 楼門

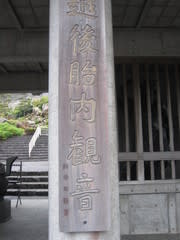

「42年水害」は、胎内川流域では上流の、胎内第一ダムで一日総降水量が645ミリ、同胎内第一発電所で542ミリを記録。
北蒲原郡中条町と黒川村(いずれも現在の胎内市)では胎内川中流部の赤川と下流部の熱田坂で堤防が決壊、家屋の浸水が2,170戸、農地などの浸水が2,330haに及んだ。
六角堂 境内


胎内の歴史は古く、桓武平氏の一族、城氏が平安末期に「奥山荘」周辺を支配した。
1201年、城資盛は平氏復興のため鳥坂城で挙兵、幕府は佐々木盛綱を越後御家人の総大将として追討軍を派遣、城氏は事実上滅亡した。
その後幕府は木曽義仲追討の恩賞として、三浦和田氏の和田義茂に「奥山荘」地頭職を与えた。
三浦和田氏は土着して中条氏を名乗り、黒川氏、関沢氏、築地氏、金山氏など多くの庶流を生み出した。
中条氏と黒川氏は波月条や金山郷などの周辺の所領をめぐり度々紛争を起こした。江上館は越後三浦和田氏の宗家・中条氏の15世紀の居館と見られている。
戦国期の後半は中条氏は庶流の羽黒氏の居館を接収し、鳥坂城南麓にも居館を構え、居館と要害を一体化した根古屋式城郭とした。
1598年の上杉景勝の会津移封により、中条氏もこの地を離れ、奥山荘における三浦和田氏の支配は終わったと云われている。


波乗り観音・越後胎内観音は、総丈7.3m、重量4t、鳥坂山を背に蓮華台で合唱姿は波の上に載っているように見えるところから、波乗り観音とも言われている。
羽越水害で、犠牲になって亡くなった32名の人達の供養する観音像である。
薬師堂など、ボランティアの掃除の小母さんと話が出来た。
胎内観音供養堂内


「酒造りの話」第三仕込「溜」
約仕込んで温度が7~8℃が、醗酵熱で15~16℃にあがる。醪を検査する。比重計(ボーメ)で酸度分析
溜後2~3日で泡が出だす。筋泡、水泡、岩泡、高泡、落泡、玉泡、最後が「地」で終わる。
醪をもう一度加えるのを「四段仕込み」 アルコール分は、18~19℃になっている。
味を調えるため、アルコールを添加、これは国で定めれている清酒のみ、(純米酒はアルコールを添加しない)
次回は、笹川流れ。



















