
関宿場町がけっこうよかった
まず奇跡と言うほど町並みがよく保存されている。当時の東海道に立って街道沿いに見ると、旧東海道の道筋とそれに沿った宿場町の町屋の町並みが、がうねうねと、曲がりながら続いている。定規で引いたような直線の街路に慣れている私たちには本当に新鮮で珍しい風景だ。


そういや、なんか彦根城の自然木をそのまま使った梁の木組みを思い出した。現代社会ではすべてが規格品で、同じような製品や町並みが全国にあふれているのに対して当時は違ったのだ。日本中の町並みがこのように優しいフリーハンドで描かれた町並みだったわけだから逆に平安京や平城京の町並みが如何に衝撃的だったかがわかると言うもの。当時は自然に人間が合わせていたのですね。
町を歩くとゆうに2kmちかくの街並が往時をしのばせる。これは関が江戸時代は交通の要衝だったのに、鉄道や、国道などの後世の交通機関と程よく距離を置き開発が進まなかったことが大きい。歴史を調べると最初の町並み保存の意見が出されたのは昭和5年 つまり1930年と言うのだから驚く。関宿旅籠玉屋歴史資料館・関まちなみ資料館は本当に保存状態もよく、当時のままの建物が参観することができる。

思うに江戸時代はわれわれが想像する以上に豊かで、熟成された時代だったのではないのだろうか?
まず奇跡と言うほど町並みがよく保存されている。当時の東海道に立って街道沿いに見ると、旧東海道の道筋とそれに沿った宿場町の町屋の町並みが、がうねうねと、曲がりながら続いている。定規で引いたような直線の街路に慣れている私たちには本当に新鮮で珍しい風景だ。


そういや、なんか彦根城の自然木をそのまま使った梁の木組みを思い出した。現代社会ではすべてが規格品で、同じような製品や町並みが全国にあふれているのに対して当時は違ったのだ。日本中の町並みがこのように優しいフリーハンドで描かれた町並みだったわけだから逆に平安京や平城京の町並みが如何に衝撃的だったかがわかると言うもの。当時は自然に人間が合わせていたのですね。
町を歩くとゆうに2kmちかくの街並が往時をしのばせる。これは関が江戸時代は交通の要衝だったのに、鉄道や、国道などの後世の交通機関と程よく距離を置き開発が進まなかったことが大きい。歴史を調べると最初の町並み保存の意見が出されたのは昭和5年 つまり1930年と言うのだから驚く。関宿旅籠玉屋歴史資料館・関まちなみ資料館は本当に保存状態もよく、当時のままの建物が参観することができる。

思うに江戸時代はわれわれが想像する以上に豊かで、熟成された時代だったのではないのだろうか?










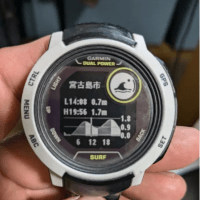









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます