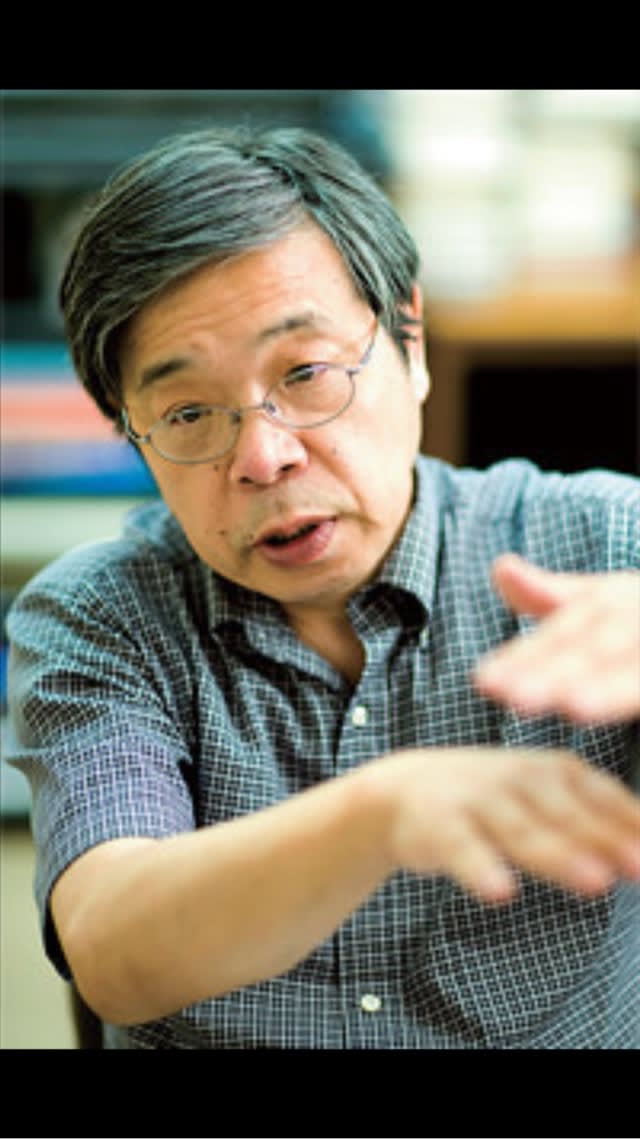【ハフポまんまコピー】----------------------
「ネット上の争いでは、リベラルは99%負ける」 津田大介さんが訴える政治運動の姿とは

■「ネットは裏社会」という発言が出る背景
――鳥越さんは、私たちのインタビューの中で「ネットは裏社会だと思っている」という発言しました。これについて、どう感じましたか?
それについては「残念」の一言に尽きますね。元々、鳥越さん自身が2006年に、ネットを使ったジャーナリズムの先駆けだった「オーマイニュース」日本版の創刊編集長をやっていたわけですから。当時はブログがブームで、ネットを使うことで「ブログ論壇」なんていう言葉も出ていたし、「マスメディアとは違うジャーナリズムをやろう」という機運が盛り上がっていた時期でした。
もちろん、鳥越さんの中にはオーマイニュースが思うように行かなかったことに対する絶望があるのかもしれないですが、他ならぬ鳥越さんの口から、ああいう発言が出てきたことは、自分自身、ネットを使って報道に携わるようになった人間として、すごく寂しいものがありました。
――鳥越さんの考え方は、彼がテレビに長く属していたことが関係していると思いますか?
毎日新聞の記者としてスタートして、「ザ・スクープ」などテレビ朝日のニュース番組の司会者になるなど、既存のメディアとの関係は長かったですよね。2000年以降のトレンドとして、ネットはマスメディアから常に厳しい目に晒されていました。もちろん僕も、Twitterなどで「この報道はおかしいんじゃないか」と言うこともあるし、今の炎上を加速させる装置となったネットに対して思うところもたくさんあります。
ただ、確実に言えるのは、両者の差は年々少なくなってきているということです。マスコミの中にもひどい報道もあるし、全てのネットメディアが駄目なわけでもない。マスコミからヤフーニュース、ドワンゴ、ハフィントンポスト、Buzzfeed、NewsPicksといったネットメディアに転職する人もここ数年で圧倒的に増えましたし、ようやくこの業界の人材の流動性が高まってきている。そうなると、「マスコミはこうだから」「ネットはこうだから」と語ることが難しくなっています。それが現在のメディアを巡る状況ですね。
僕自身はマスコミやメディアに関わっている人は、やはり新しい情報技術を使ってみるべきだし、仕事に活かすべきだと思っています。ところが、ある世代を超えた人……具体的には50代後半から70代くらいで、古いマスコミで仕事をしてきた人は、ネットを一刀両断に全部切り捨てる傾向がありますね。だからシンプルに言えば、鳥越さんもそういう思考から脱しきれていないということなんだろうなと思います。
■なぜ「リベラルは負けている」のか?
――同じインタビューの中で、鳥越さんは「日本のリベラルは現実に
負けている」と指摘しました。これについては、津田さんはどう感じましたか?
これについては同感です。一言でいうと、保守の人のほうがマメなんですよ。保守系団体の「日本会議」もそうですが、とにかく参加者たちが地に足のついた活動を継続的にしているし、筆まめなんです。自分達はどういう思想で、何を目指しているのかをちゃんと主張する。自民党も野党時代にマスメディアに相手にされなくなったからネット戦略というのを重視するようになって、マメになりました。ネットを活用して、自分達の主張を訴えている。
その点については確実にリベラル側は怠けていると思いますね。ネット選挙が解禁され、ネットと政治の関係についてほぼ全ての党から呼ばれて講演してきました。その際、「これからの時代は、マスメディアが個別の候補についてほとんど報道しなくなる。選挙期間中にTwitterやFacebookで情報発信することが大事だ。それらの発信源となるスマホを使うことが重要になる」と説明したあとに、「現在スマホを使っている方は?」と、会場の方に手を挙げてもらうと、リベラルな党の方がスマホ率やSNS利用率が低いんですよね。ガラケー率8割みたいな。
本来は「革新」であるにも関わらず、新しいものに対する好奇心が薄いことが一番の問題かもしれません。それが結果的に「自分たちの理念を左でも右でもない一般の人に、わかりやすく説明する努力を放棄してきた」こととも繋がっているんじゃないかと思います。
つまり、なんでこれだけネットを中心とした保守層が浮上しているかというと、やっぱりそういう人達のほうが勉強をしている……あるいは外から見たときに勉強しているように見えるということだと思います。
彼らは少なくとも自分たちの興味関心があるトピックについては勉強しているし、これまで「世間から迫害されてきた」という意識があるから、自分達の主張をちゃんと世の中に広めようと努力する。だから筆まめになるんです。一方でリベラルの側は、ある時期から最新の状況を追いかけなくなり、一般人に広める努力も怠ってきた。そのツケが出てきていますね。
■テクノロジーを敵視してきた「リベラル」
――リベラルの人が、スマホを初めとしたITが苦手なのはなぜでしょうか?
それはかなり深い背景がありそうです。最近は、アメリカの新しい保守層と呼ばれるネット発の「alt-right」もしくは「オルタナ右翼」という層と、シリコンバレー的な思想の相性の良さが表面化してきました。一般的なイメージでは、シリコンバレーといえば西海岸で「民主党の牙城でしょ?」と思ってしまう。「多文化共生でリベラルなのがいい」という風土だから、政治的にも左だと世間では思われている。
でも共和党の大統領候補であるドナルド・トランプの支持者の一人は、シリコンバレーで絶大な影響力を持つ投資家のピーター・ティールです。さらにはVR(仮想現実)技術での最先端企業である「オキュラスリフト」創業者のパルマー・ラッキーも、トランプを支持するオルタナ右翼の団体に約1億円の資金援助をしています。
今やシリコンバレーの経営者たちからトランプを支持する動きが出ている。それは思想的に「転向」したわけじゃなくて、テクノロジーやデータを積み重ねたテックユートピアみたいな技術信仰とトランプの全体主義的な思想の相性が良いからなんです。オルタナ右翼とシリコンバレーの親和性については、経営学者の八田真行(はった・まさゆき)さんが自身のブログで様々な論考を掲載して分析されています。なぜ近年のネットで保守層が台頭しているのか理解に苦しむ方は、その論考を一通り読むことをオススメします。
その一方、日本の労働運動は、テクノロジーを敵視してきた一面がありました。たとえば郵便局に郵便番号が導入された際には、すごい反対運動が起きました。「機械は人間を堕落させる」もしくは「合理化して人減らし」になるという理由で、機械の導入や、テクノロジー信仰に対する反発が、リベラル勢力の中に根付いているように感じます。日本でIT業界が勃興してきたときに、堀江貴文さんが日本に遅れて登場した新自由主義者として、象徴的にメディアで扱われたこととも無縁ではないかもしれません。そうした背景もあって、日本の旧来型リベラル層は、ITを否定する人が多いように思います。
――そうですね。管理社会のイメージがあるのか、人工知能を全否定するような主張もありますね。
そうそう。で、結局「人間が大事なんだ」となる。でもこれも考え方次第なんです。人工知能やテクノロジーが進むことで、全ての職が奪われるわけじゃない。「人間がロボットみたいに働かされていること」がそもそもの問題であって、それをロボットに代替させることによって、より創造的でやりがいのある「人間的」な仕事に配置転換していくことも可能になる。
ロボットや人工知能は振興するが、人減らしの契機としてロボットを導入することには一定の制限を設けようという議論をするだけで建設的な話ができるはずなのに、そういう話にはならずに、「職が奪われる」で止まってしまう。それはひとえに未来技術に対する想像力の欠如が問題で、そうした知的怠慢はリベラル側に顕著だったと思いますね。それは、シリコンバレーの少なくない経営者が、トランプを支持していることとも繋がっていると思います。
――日本のネットでも、いわゆる「ネトウヨ」と言われる保守的な主張が幅を利かせていますね。
逆に「ネットリベラル」の人って、そんなにいないですよね。ヘイトスピーチへのカウンターは一定勢力になっていますが、あれは反差別運動だからリベラルとは違いますし、彼らはヘイトだけでなく、旧リベラル勢力や朝日新聞なども苛烈な言葉で攻撃しています。そうした状況も含め、情報発信の勢力がアンバランスになっているというのがいまの日本の現状なんでしょう。
たまに中道左派やリベラルの人が情報発信をしても、保守系の人たちが数の力で押さえこむことができる。ツイッターは140字しか書けないのでどうしても言葉足らずになってしまいますし、いくらでも発言の不備をついて揚げ足取りできる。攻撃をする側も議論しようとは思っていないから、相手が黙るまで集団で攻撃を続ける。
中道的な意見は左右両方から叩かれ、過激な意見を持つ人に支持が集まっていくので、その結果、普通の人が発言をしなくなっていく……。このあたりは山口真一さんと田中辰雄さんが著書『ネット炎上の研究』で示されていますね。そういう情報環境になった結果、ネット上では保守層の対抗勢力が、数的になくなりつつあるという状況なんじゃないでしょうか。
■「ネット上の争いになると、リベラルは99%負ける」
――そもそも保守系の人が筆まめで、SNSを通してガンガン意見を発信するのに比べて、リベラルの人が消極的な理由とは?
個人的には、まだまだマスメディアの影響力が大きいことと無関係ではないと思っています。だってなんだかんだで日本のマスメディアは総じてリベラルですから。だから、保守的な考えを持っている人達は「マスメディアでは自分達の考え方が限られたことしか報道されていない」と日々痛感している。
そうなると彼らの中に「俺達がネットを使ってやるしかない」という当事者意識が生まれます。そういう当事者意識は、リベラルには少ないんじゃないですか。だって、テレビをつけて「報道ステーション」や「サンデーモーニング」を見れば、自分たちの考えと同じ論調のニュースが流れているわけだから、わざわざネットを使ってやる必要もない。
――リベラルがマスメディアで多数派になったことが、ネット上で情報発信が少ない背景にあると?
そうです。リベラルが既得権益化したとも言えます。戦後の日本は民主主義がインストールされていく過程でリベラルが台頭し、知識人も含めて標準的な日本の思考になっていった。でも、それが既得権益化したことで彼らに対する反動が押し寄せているようにも思えます。
「日本会議」関連の本もこの夏にたくさん発売されましたが、リベラルの人は「こんなひどい人たちがいるんだ」と読むのではなく、彼らの「草の根的な運動論」を見て、自分たちの反省材料にすべきじゃないでしょうか。
韓国の社会運動もそうですよね。すごく地道に拠点を作ってやっていく。最後にものを言ってくるのは、継続すること。組織があること。拠点があること。それらを長い間やっていくことで草の根で広がっていく。市民運動というと、これまでリベラルのものだと思われていたけれども、実はそんなことはなかったという単純な話かもしれません。
情報化社会が進展したことで、情報発信力が勢力拡大に大きな影響を与えるようになりました。SEALDsは、情報発信が重要という点に自覚的で、その意味ではとても上手くやったと思いますが、あれは安保法反対というワンイシューだから可能だったし、左派系マスメディアが好意的に取り上げたということで「ゲタ」も履かされましたよね。それが反発を招いたし、対案を出す形での運動ではなかったため、広がりに限界がありました。
僕はSEALDsを応援していましたし、若者が政治的な問題に対して声を挙げてもいいんだと思わせたことは大きな功績があったと思います。その一方で、彼ら若者を旗印にして協働しなければならなかった日本の左派市民運動の限界も示したと思います。
――脱原発であったり、反安保であったり、争点によってはリベラルな勢力が健闘しているのでは?
存在感は一時的に示せたかもしれませんが、結果は出せてませんよね。脱原発は実現するどころか政府は推進に向けて舵を切っているし、安保法案も通ってしまったし、今夏の参院選では3分の2も取られてしまった。
政治学者の山口二郎さんと先日、東浩紀さんが運営するゲンロンカフェで話したんですが、その際山口さんは「歴史的に見てリベラルは不満を糾合しブームを起こすところまでは行くけれど、統治の論理を持っていない。時間軸で見ると政治は多くの時間保守が担当して、たまにリベラルが担当する。リベラルの天下は長くは続かないので、その短い期間にどれだけ物事を変えられるかが重要だ」ということをおっしゃってました。
そして、ネット上の争いになると、リベラルは99%負けるんです。リベラルが「多様であることがいい」「多文化であることがいい」と訴えると、保守派の言っていることも「そういう言論もありだ」と認めなきゃいけないから。でも、保守派はリベラルの主張を認めないですから、その点がそもそも非対称なんです。それをわかった上で保守派と同じ土俵で真っ向から対決すると、今度は「リベラルの欺瞞」と責められる。対等な土俵が存在しないという意味で、よほどのことがない限り、ネット上の論争で勝つことは難しい。
――勝ち目がない戦いは、どう戦えばいいんでしょう?
やっぱり「こういう考え方が正しいんだよ」ということを地道に訴えていくほかはないと思いますね。数の論理が押しつぶされそうになったときに、冷静な言葉でファクトを出し、「こういう理念を守ることが大事なんです」と、一般人が共感を持てる言葉で発信する人を増やす。
情報発信を厭わない層のバランスが左右で取れるようになれば、今よりかはTwitter上の議論も建設的になるんじゃないでしょうか。あとはTwitterとも、テレビの討論番組とも違う、意見が違う人同士の意味のある対話の機会や場所をどうネットで作れるかでしょうね。でも、それは1〜2年とかの短いスパンで結果が出るものじゃないので、5年、10年、20年かけてやっていくしかない。
でも、世の中が保守とか、右のほうに行きすぎたら、その反動もいずれやってくると僕は思いますけどね。山口さんの話にもあったように、「いざそうなったとき」のために心折れずにきちんと準備をしておくことが大事だと思いますね。
僕自身も自分の立ち位置を巡ってこの1~2年、ずっと悩んできました。カッとなって書いたツイートで炎上することも多かったですし(笑)、「あいつは変わった」なんて言われることも増えましたが、そういう経験も含めて糧にしないといけないなと。結局自分ができることは「メディアづくり」しかないので、改めて自分を見つめ直し、自分が現在の能力でできることを地道に積み上げていくしかないのだなと思っています。
(聞き手:竹下隆一郎、安藤健二)
--------------------------------------------
話の冒頭に鳥越俊太郎氏を持ってくるあたりは、言わば鳥越氏の惨敗をリベラルの顔としてハフポも津田大介氏も距離を置くことで自分達はあくまでも俯瞰で観察している風を装うことでリベラルに張り付いていたジャーナリズムとは一線を画したいのだろう。生き残りに必死さを感じる。
保守とリベラルの情勢に保守層が台頭してきたことの理由も『保守の人のほうがマメなんですよ』
や、リベラルは『ガラケー率8割』というように短絡的な標準値からの理由付けにすぎない。
結局保守層の台頭がその者の心象が『世間から迫害されてきた』という一方的で身勝手な想像しか出来ず、『テクノロジーを敵視してきた』のはなにもリベラルや保守といったイデオロギーで色分けされるのでなく、完全に読み間違えている。
または、意図的に中立を維持しょうとしての虚言かもしれない。
その疑義の根本が津田氏がシールズを応援し、鳥越氏に投票し、山口二郎を持ち上げる、散々リベラルに媚びを売り、安倍政治を許さないジャーナリストを気取っていたことに他ならない。
その男が舌の根の乾かないうちにリベラルが99%負ける、つまり保守層が99%勝つと歯の浮くようなコメントをハフポに載せても十把一絡げにした
"敗北宣言"にしか聞こえない。
敢えてあげるなら、リベラルの多様性が保守も認めざるを得ないというそもそも論だけは評価出来る。
あえてこの私、つまり素人の私に言わせて頂ければリベラルもそれに加担し煽ってきたメディア、ジャーナリズム、ジャーナリストはとっくに終焉を迎えている。
メディアとネットの汽水域の風雲児津田大介が、金髪を辞める時が見ものであり、個人的な楽しみでもある。