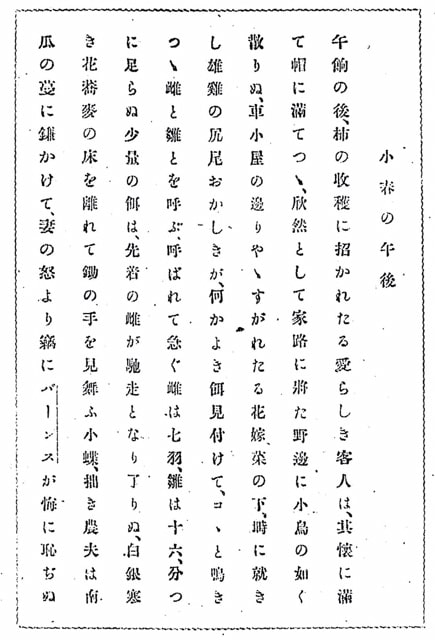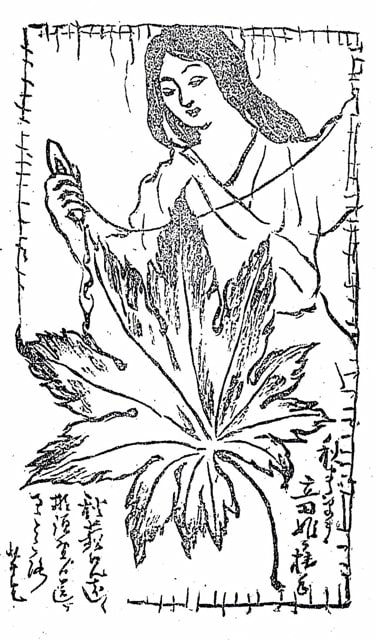芋銭の短文「小春の午後」(短文の内容を示す画像は前の記事を参照されたい)と「柿の秋」図とは、<柿の収穫>に多少の関連性が認められるとはいうものの、主題に関しては、ほとんど共通点を見出し難い。
柿の収穫に招かれた「愛らしき客人」が、猿である可能性も考えたが、それでは、その後の文章との繋がりもうまくいかないし、蟹に相当する者も見当たらない。
だから、ここでは「小春の午後」は、全く独立した短文として読んでみる他はない。
しかし、それにしても、この短文の意味を理解するのはかなり難しいのではないか。
柿の収穫に招かれた客人は、貰った柿を持って小鳥のように嬉々として家路や野辺に帰る。
次に雄鶏が登場し、餌を見つけて雌鶏と雛とを呼ぶ。
雌鶏は7羽、雛は16羽で、なぜか見つけた餌は、先着の雌鶏が喰べてしまうが、これは何か比喩的な意味があることなのだろうか。
そして場面は変わり、今度は小蝶が「拙き農夫」の手元に飛んできたようだ。が、この農夫はなぜか「南瓜の蔓に鎌かけて、妻の怒りよりひそかにバーンスが悔い」に恥じている。
これだけの筋書きだが、小蝶や農夫やバーンスの互いの関係も何だか解らないし、農夫の妻もどうして怒っているのか曖昧だ。
「バーンスが悔い」を農夫もしでかしたから妻の怒りを買ったようなのだが…それにしてもかなり唐突な展開だ。
そもそも、この短文に突如出てくる「バーンス」とはいったい誰なのか。
私には、芋銭の時代にはよく知られていたスコットランドの国民的詩人ロバート・バーンズ のことが思い当たる。
彼は「農民詩人」とも評されることがあるようだから、これは当時の芋銭の注意を引いたかもしれない。
芋銭は田舎に住んではいても、日頃、農業に従事したわけではない。ただ彼も田舎に住んで俳句などを嗜んでいたわけだから、「農民詩人」の面はある。
芋銭がロバート・バーンズに関心を抱いていても不思議はない。
バーンズは、「蛍の光」や「故郷の空」などの原曲の詞を書いた詩人として最も有名だが、一方、奔放な女性関係でも知られている。
寺西範恭氏の論文(「ダンフリースでのロバート・バーンズと女性たち」)によると、バーンズの妻は、彼が37歳で亡くなった直後、第7子を産んでいるが、彼は他に「5人の女性に5人の私生児を産ませた」ともいう。
すると単純計算でもバーンズは12人の子をもうけたことになろう。
さらに彼が愛し、その詩の創作に多大な影響を与えたことで、その名が知られている女性も相当数いるから、短い生涯ながら、18世紀の詩人バーンズが思いを寄せた女性の数は正確に数えることが難しいほどである。だが、10人ほどはいたと考えてもよいのではなかろうか。
その彼が女性を愛することについて何らかの「悔い」を残したかと言えば、どうもそうではない。むしろ反対に、自己の詩作の源泉として必要なことだと主張している。
だが妻はそれをどう見ていたか…嫉妬や怒りがなかったとは、あまり想像できない。
しかし、これだけ自己の内面における恋愛の欲求に忠実であるなら、現実の生活ももちろんただでは済まなかった。
子どもの養育費などはやはり大変だったらしく、彼は収税吏の仕事に就いて、家庭の生活を破綻させることなく維持していく現実感覚も一方で持っていた。
さて、ここまでバーンズの伝記的事実を見ていくと、ここで思い出されるのは、芋銭の短文における、妙に数字に拘る雌鶏7羽、雛16羽などというフレーズではなかろうか。
芋銭がバーンズの恋愛相手が何人いて、何人の子を妻や女性たちに産ませたと考えていたかは今のところ分からないが、明治時代の文化人から見てもいかにバーンズが多くの女性たちと交際し、多くの子どもたちを産ませたかはやはり驚きの数字であったのではなかろうか。
しかも、それでも彼は生活を破綻させずに名を成した。それもいっそうの驚きであったろう。
もちろん、1羽の雄鶏が見つけた「分つに足らぬ少量の餌は先着の雌が馳走になり了りぬ」という家庭の状況ではあったろう。餌は雛にも充分、行き渡らない。
先着の雌鶏だけが馳走にあずかる。これは、すべて比喩的な表現だが、比較的早期に先着した雌鶏は妻のことだろうか。
こうしてこの芋銭の短文を読んでいくと、その内容は、スコットランド18世紀の国民的詩人、ロバート・バーンズの伝記的事実に重ねられ、いくぶん皮肉を交えて、ここに紹介されているように思える。
してみると、「花蕎麦の床を離れた」小蝶も「拙き農夫」も、実はバーンズ自身のことを指しているのかもしれない。
このように読むかどうかは、もちろん読む人次第だ。だが、バーンズは明治の多くの文化人にかなり早くから知られていた。
夏目漱石や国木田独歩もバーンズについて書いている。
それについては、例えば難波利夫氏の「明治期のバーンズ流入」といった論文があるので参照されたい。
この難解な芋銭の短文をどう読むか、もっと筋の通った読み方があるのかもしれない。
上記の仮説は、あくまで現時点での私の読み方に過ぎない。