1月31日、しばた100選を見てみよう!船岡(2)コースのバスツアーを
行ないました。
前回、広報館について書きました。
広報館の後方にあった、「旧工兵第2連隊門柱及び哨舎」の説明を受けたので
その報告です。

旧工兵第2連隊門柱及び哨舎、後方に広報館が見えます。
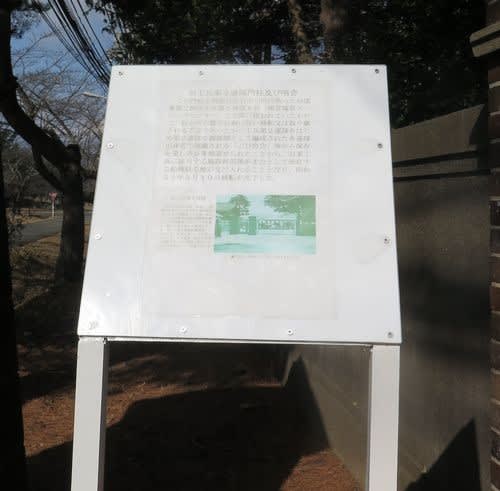
説明板
旧工兵第2連隊門柱及び哨舎
この門柱と哨舎は仙台市川内にあった旧陸軍第2師団工兵第2連隊本部(現宮城県
スポーツセンター)で実際に使われていたもので、仙台市の都市計画に伴い移転又は
取り壊される予定であったが、工兵第2連隊をはじめ第2連隊を親部隊として編成さ
れた各連隊出身者で組織される「とび色会」等から保存を望む声が多数寄せされたこ
とから、旧軍工兵に該当する施設科部隊が主力として所在する船岡駐屯地が受け入れ
ることとなり、昭和52年3月10日移転を完了した。
旧工兵第2連隊
明治16年の創設、日清、日露戦争を経て、日華事変、満州動乱、そして太平洋戦
争のインパール作戦まで戦史に残る数々の逸話を生んだ。旧工兵第2連隊を親部隊と
して誕生した部隊も多く、工兵第13、33、48連隊、独立工兵第3連隊など、主
に宮城、福島、新潟県出身者によって組織された部隊である。
写真の説明、昭和5年頃の工兵第2連隊本部正面

右の門柱

哨舎、この前に哨番がたち、入退出の人、車両等をチェックした。

船岡駐屯地の広報担当者が説明してくれた。
行ないました。
前回、広報館について書きました。
広報館の後方にあった、「旧工兵第2連隊門柱及び哨舎」の説明を受けたので
その報告です。

旧工兵第2連隊門柱及び哨舎、後方に広報館が見えます。
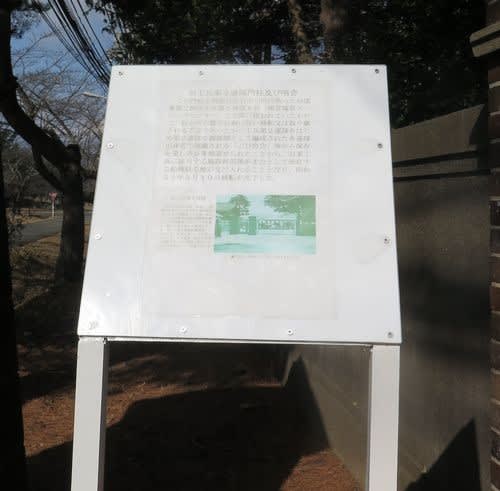
説明板
旧工兵第2連隊門柱及び哨舎
この門柱と哨舎は仙台市川内にあった旧陸軍第2師団工兵第2連隊本部(現宮城県
スポーツセンター)で実際に使われていたもので、仙台市の都市計画に伴い移転又は
取り壊される予定であったが、工兵第2連隊をはじめ第2連隊を親部隊として編成さ
れた各連隊出身者で組織される「とび色会」等から保存を望む声が多数寄せされたこ
とから、旧軍工兵に該当する施設科部隊が主力として所在する船岡駐屯地が受け入れ
ることとなり、昭和52年3月10日移転を完了した。
旧工兵第2連隊
明治16年の創設、日清、日露戦争を経て、日華事変、満州動乱、そして太平洋戦
争のインパール作戦まで戦史に残る数々の逸話を生んだ。旧工兵第2連隊を親部隊と
して誕生した部隊も多く、工兵第13、33、48連隊、独立工兵第3連隊など、主
に宮城、福島、新潟県出身者によって組織された部隊である。
写真の説明、昭和5年頃の工兵第2連隊本部正面

右の門柱

哨舎、この前に哨番がたち、入退出の人、車両等をチェックした。

船岡駐屯地の広報担当者が説明してくれた。
























