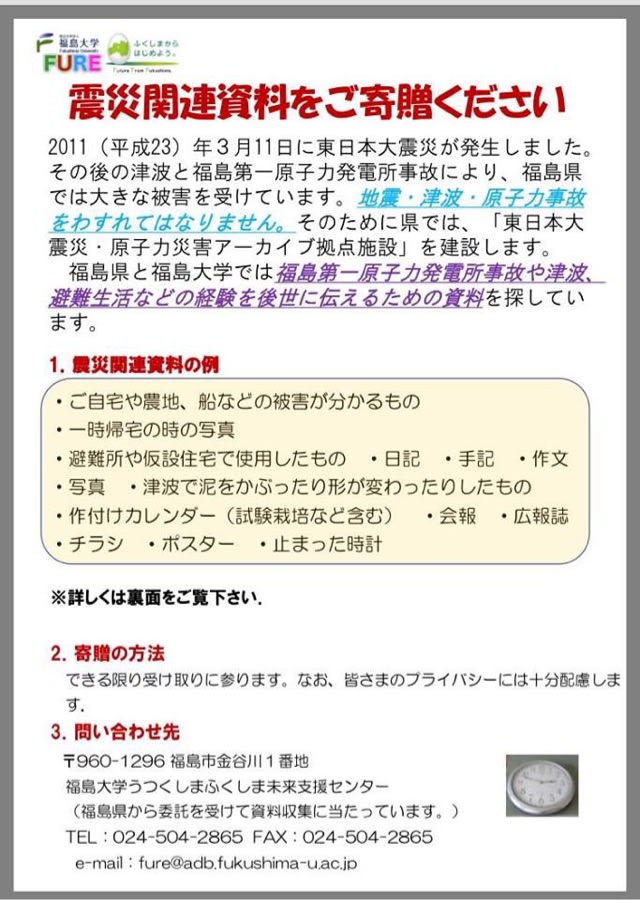第3回全国史料ネット研究交流集会が近づいてきました。一昨年は神戸、昨年度は福島郡山、今年度は愛媛松山での開催です。(昭和南海地震70年《本年12月21日》の直近の週末開催)
参加費:無料(事前申し込み不要、懇親会のみ要申込)
************************
【開催日時】
12月17日(土)13:00~18:00
12月18日(日)9:00~13:00
【会場】
愛媛大学南加記念ホール
1995 年の阪神・淡路大震災を機に設立された歴史資料ネットワークを皮切りに、全国各地で20 以上の史料ネットが立ち上がり、災害から歴史資料を保全し、災害の記録を保存する活動に取り組んでいます。
2011 年3 月の東日本大震災では、国の被災文化財等救援本部の活動とともに、史料ネット同士の連携と協力によって、地域に伝えられた多くの歴史・文化遺産が救出されました。2014 年10 月には国立文化財機構内に「文化財防災ネットワーク推進本部」が設置され、本年4 月に発生した熊本地震を経て、歴史・文化遺産の防災に向けた全国的な連携体制づくりの強化が望まれています。
2015 年2 月、阪神・淡路大震災と歴史資料ネットワークの活動開始20 年の節目に、神戸市で開催された第1回集会では「『地域歴史遺産』の保全・継承に向けての神戸宣言」が採択されました。東日本大震災5 年の節目にあたる2016 年3 月には、被災地の一つである福島県内で第2回集会が開催され、被災地で取り組まれてきた活動から得られた経験を共有し、大規模災害に対する日常的な備えのあり方を展望しました。
昭和南海地震70 周年の本年12 月、愛媛県松山市において第3 回集会が開催されるはこびとなりました。
本会では「神戸宣言」をふまえ、地域の歴史資料を保全する実践に向けての連携を発展させるとともに、保全した資料を活用して、災害に強い地域社会をどのように創っていくかについても考えてみたいと思います。
●1日目(12 月17 日)
13:00~13:15 開会
13:15~14:15 基調講演
髙妻洋成 氏(奈良文化財研究所保存修復科学研究室長)
「文化財防災ネットワークの構築について」
森伸一郎 氏(愛媛大学防災情報研究センター准教授)
「南海地震に備える史料学と防災減災学の連携」
14:15~14:30 休憩
14:30~16:30 各地からの報告(1) 報告時間15 分×8 本
「特集 南海地震を伝え、備える」
16:30~16:45 休憩
16:45~17:15 各地からの報告(2) 報告時間15 分×2 本
17:15~18:00 意見交流
18:15~20:00 懇親会*
●2日目(12 月18 日)
9:00~11:00 各地からの報告(3) 報告時間15 分×8 本
11:00~11:15 休憩
11:15~12:00 各地からの報告(4) 報告時間15 分×3 本
12:00~12:45 意見交流
12:45~13:00 閉会
【報告団体】
歴史資料ネットワーク、岩手歴史民俗ネットワーク、茨城文化財・歴史資料救済・保全ネットワーク、岡山史料ネット、鹿児島歴史資料防災ネットワーク、神奈川地域資料保全ネットワーク、熊本被災史料レスキューネットワーク、こうちミュージアムネットワーク、小豆島史料調査団、地域史料保全有志の会、千葉歴史・自然資料救済ネットワーク、長野被災建物・史料救援ネットワーク、新潟歴史資料救済ネットワーク、ふくしま歴史資料保存ネットワーク、NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワーク、宮崎歴史資料ネットワーク、山形文化遺産防災ネットワーク、NPO 法人歴史資料継承機構じゃんぴん、歴史資料保全ネットワーク・徳島、歴史資料保全ネット・わかやま、愛媛資料ネット
主催 愛媛資料ネット、独立行政法人国立文化財機構
問合先:愛媛資料ネット事務局
Tel:089-927-9316
E-mail:ebesu.hikaru.me●ehime-u.ac.jp(●を@に置換)
なお、17日18時からの懇親会は事前申し込みが必要です。参加希望の方は、下記のページよりお申込みください。
http://kokucheese.com/event/index/433489/