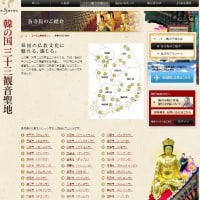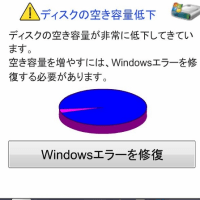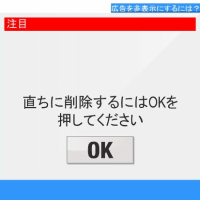CO2削減のために石油ストーブや電気式空調機から、たっぷり冬着を着込んで昔のように「こたつ」に戻るのも一つの方策かも知れぬと思い調べてみた。
「炬燵に似た暖房器具はイランやアフガニスタンにも存在する」とWikipediaに書いてあった。
ついでに歴史の項を見ると、「禅宗の僧侶により中国からもたらされたとされるあんか(「行火」「安価」と表記)が起源といわれている。当時は掘り炬燵であった。
日本では火鉢とともに冬には欠かせない暖房器具として発達した。 寺院や武家では火鉢が客向けの暖房器具で炬燵は家庭用であった。そのため「内弁慶」という言葉から、家庭向けの炬燵から出ようとしない引っ込み思案なことを表すのに「炬燵弁慶」という言葉が派生した。
江戸時代中期には、置き炬燵が登場した。」とあった。 おき‐ごたつ【置き火燵・置き炬燵】 自由に移動できるこたつ。底板のあるやぐらの中に、炭火をいける陶器を置いたもの。切り火燵・掘り火燵に対していうと辞書にあった。
炬燵は冬の季語である、歳時記をめくってみると、次のような句に目を惹かれた。
住みつかぬ旅のこころや置火燵 芭蕉真
夜中や炬燵際まで月の影 去来
みな違うことをしており炬燵の間 藤岡 幸子 (昔の暮らしを思い出した)
炬燵には、いろいろ風情を感じるのである。
また、関連項目として、次の二品が示されていた。
* 湯たんぽ
* 懐炉
炬燵と共に、湯たんぽ懐炉などが将来も暖房器具として脚光を浴び続けるような気がしている。