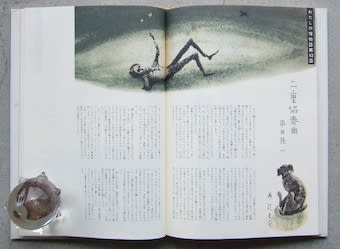文春文庫 (2010/02).読み出したら止められず,寝不足を新幹線で回復するという目論見が外れてしまった.
丸谷 才一, 三浦 雅士, 鹿島 茂の三人で文学全集を作るとすれば誰のどんな作品を入れるかを議論するという趣向.全300巻とする.世界文学約130巻,残りが日本文学.うち言文一致以降が約80巻.日本文学の部では司会(もと文春勤務氏)もかなり積極的に発言.
男の井戸端会議といった,下世話なおもしろさは最後の80巻に集中している.
「村上春樹はモダニズム,井上ひさしはプロレタリア文学,大江健三郎は私小説」とか
「死霊は滑稽小説として読んだらけっこう面白いな」「でもそうは読めないよ」とか
「白樺派は全部ストーカー」とか
芥川賞作家の丸谷が「芥川は外してもいい」というが,結局菊池寛とふたりで1巻に決着.漱石3巻.谷崎3巻.意外なところでは,宮沢賢治,斎藤茂吉,内田百﨤などがひとり1巻.
世界文学では
「嵐が丘はセックスを知らないで書く,元祖少女マンガ」
「ジェーン・エアで主人公をブスに設定してあるのは,勝ち組だからできること」
ここでは,ブラッドベリ・バラード・ウォネガット・ディックで1巻というのがぼく的にはヒット.
ここに挙げられた本を,語り手3人がすべて読破しているわけではないようだ.自分はといえば,ここに出てくる本の1割も読んでいないし,読んでないものをこれから読もうとも思わない.にもかかわらずおもしろい.金がないのに「特選街」や「暮らしの手帖」の商品テストを読む感覚である.
巻立て一覧として,世界文学のほうは作者とともに作品名もまとめてあるのに,日本文学は作者だけというのが不満.
丸谷 才一, 三浦 雅士, 鹿島 茂の三人で文学全集を作るとすれば誰のどんな作品を入れるかを議論するという趣向.全300巻とする.世界文学約130巻,残りが日本文学.うち言文一致以降が約80巻.日本文学の部では司会(もと文春勤務氏)もかなり積極的に発言.
男の井戸端会議といった,下世話なおもしろさは最後の80巻に集中している.
「村上春樹はモダニズム,井上ひさしはプロレタリア文学,大江健三郎は私小説」とか
「死霊は滑稽小説として読んだらけっこう面白いな」「でもそうは読めないよ」とか
「白樺派は全部ストーカー」とか
芥川賞作家の丸谷が「芥川は外してもいい」というが,結局菊池寛とふたりで1巻に決着.漱石3巻.谷崎3巻.意外なところでは,宮沢賢治,斎藤茂吉,内田百﨤などがひとり1巻.
世界文学では
「嵐が丘はセックスを知らないで書く,元祖少女マンガ」
「ジェーン・エアで主人公をブスに設定してあるのは,勝ち組だからできること」
ここでは,ブラッドベリ・バラード・ウォネガット・ディックで1巻というのがぼく的にはヒット.
ここに挙げられた本を,語り手3人がすべて読破しているわけではないようだ.自分はといえば,ここに出てくる本の1割も読んでいないし,読んでないものをこれから読もうとも思わない.にもかかわらずおもしろい.金がないのに「特選街」や「暮らしの手帖」の商品テストを読む感覚である.
巻立て一覧として,世界文学のほうは作者とともに作品名もまとめてあるのに,日本文学は作者だけというのが不満.