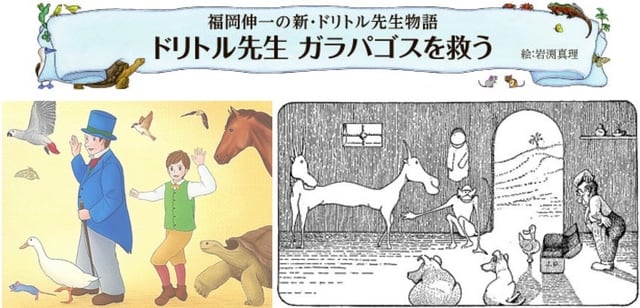特別展「大正ロマンの画家 小林かいち&竹久夢二」は有料.木版絵師 小林かいち 1896-1968 は初体験.大正後期から昭和初期にかけて,京都で制作された絵はがき・絵封筒など.見慣れれば (そして忘れなければ) 一眼でこの人のものと分かりそうな作風.トランプに題材をとった作品が多いが,どうせなら53枚をデザインしてくれればよかったのに.
日曜日だし,美術館は多少混んでいた.竹久夢二 1884-1934 は日光の美術館の収蔵品が中心らしい.こちらを目当ての方が多かったかもしれない.展示壁の前にガラス室を作って,小さい作品をf離れて見ろ,に不満.
市民ギャラリー「麻野瞳・上田一歩二人展」.トップ画像は
麻野さんの Facebook からいただいた.
麻野さんには J 子が二紀会でお世話になっている.毎年作品を拝見しているのだが,こうしてずらりと並ぶと,モデルさん (お子さん) も絵も変わっていくのが見えた.
麻野さんから御案内をいただいたとき,書の一歩さんにオッサンを想像してしまったが,実際は見目麗しく「素直で可愛くてキラキラした」方だった.おふたりの高校時代の作品も中央のテーブルにあった.二人展に来た高校生へのプレゼントかな ?
今を去ること六十余年,自分が高校で書道ではなく「書」をとったときの先生は前衛書家だった.良い生徒ではなかったが,「好きな言葉があったら好きなように書け」と言われたのを覚えていて,
年に1-2回は実行している.
書の個展 (ではなく二人展の半分だったが) は今回が初めて.画家の場合は画風が固定しているようだが,書では個人でいろんな書風 ? をこなすのだな.
千字文とやらに挑戦してみようかと,自分の好きなお手本を漁ったら,
早稲田大学古典籍総合データベースに池大雅の楷書千字文があったので,ダウンロードした.
京都文化博物館とは違うバージョンだ.ちなみに上田さんの作品は日下部鳴鶴の臨書だった.