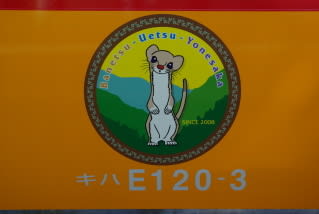海老江駅から2分ほど乗車しただけで、御幣島駅に足を記します。スタンプの表題は、「野里や大浦の渡し跡が残る駅」です。地下なので実感ないですが、淀川の西側に出たことになります。

私が最初に出た2号出口は、歌島橋バスターミナルに隣接し、バスの出入りが多数見られます。

しばらくそぞろ歩きすると、面白い陸橋を発見しました。一見して普通の橋ですが、跨いでいる対象は川ではなく、歩道と自転車道(大野川緑陰道路)です。 向こうにはミテジマ化学の工場が見えますが、このあたりは平成不況で中小工場の多くが撤退してマンションに生まれ変わったところです。
向こうにはミテジマ化学の工場が見えますが、このあたりは平成不況で中小工場の多くが撤退してマンションに生まれ変わったところです。

西淀川区役所が近接する1号出口を通過し、暫く歩くと3号出口に出ました。2号出口とは道路を挟んで近接していますが、このあたりには工場が残っています。

3号出口から改札をくぐります。申し遅れましたが、構内は島式ホームの1面2線です。11時20分発の5453M(207系S3編成+H3編成)にてJR東西線最後の未訪問駅へ。

11時22分に加島駅に到着。構内は島式ホームの1面2線で、結局のところ、JR東西線の駅は全てこれでした。
加島駅のスタンプの表題は、「都と西国を結ぶ歴史の残る地の駅」です。改札をくぐり、1号出口から出たところでJR東西線全駅下車達成 です。午前中だけでも1つやっておけばすっきりします。
です。午前中だけでも1つやっておけばすっきりします。

1号出口から道なりに歩くと駅舎らしい建物とロータリーが現れます。これには駅機能がなく、単なる出入り口(2号出口)です。このあたりはJR東西線の開業まで駅が皆無で「陸の孤島」といわれていた地区なので、これだけのロータリーが必要だったのでしょう。

駅構内にもう1度入り、竹島西口に出ました。JR神戸線の列車が走る姿を間近に見ることが出来ます。この駅は、JR東西線の開業前の段階(仮称)では「竹島駅」とされていました。

竹島地区は阪神工業地帯の一角にあり、如何にも労働者の町という佇まいで、まっすぐ歩いていくとプリマハムの工場と佐川急便のステーションにぶち当たりました。
竹島東口から今一度改札をくぐり、11時45分発の4497B(207系S67編成+Z12編成)で尼崎に出た後、11時53分発の新快速3238M(223系W39編成+V59編成)に乗り継いで新大阪へ。

12時5分に新大阪駅に到着。ほっとして束の間、「トワイライトエクスプレス」が入線してきました。時刻表に載っていないので団体列車です。新潟でコンサートがあるため、今回の旅はこれにて終了。せめてJL2247便が利用できれば桂川駅を訪問できたのに。

改札前の喫茶店で昼食を終えた後、リムジンバスで伊丹空港に向かい、ANA1659便にて新潟空港に帰還します。悪名高きDHC-8-Q400(JA841A)で且つ優先搭乗者が何人も居たので、搭乗開始は定刻の10分遅れの14時20分。新潟空港に着陸したのは15時30分。機体が小さく荷物を預けたのでホント焦りました。
おわり

私が最初に出た2号出口は、歌島橋バスターミナルに隣接し、バスの出入りが多数見られます。

しばらくそぞろ歩きすると、面白い陸橋を発見しました。一見して普通の橋ですが、跨いでいる対象は川ではなく、歩道と自転車道(大野川緑陰道路)です。
 向こうにはミテジマ化学の工場が見えますが、このあたりは平成不況で中小工場の多くが撤退してマンションに生まれ変わったところです。
向こうにはミテジマ化学の工場が見えますが、このあたりは平成不況で中小工場の多くが撤退してマンションに生まれ変わったところです。
西淀川区役所が近接する1号出口を通過し、暫く歩くと3号出口に出ました。2号出口とは道路を挟んで近接していますが、このあたりには工場が残っています。

3号出口から改札をくぐります。申し遅れましたが、構内は島式ホームの1面2線です。11時20分発の5453M(207系S3編成+H3編成)にてJR東西線最後の未訪問駅へ。

11時22分に加島駅に到着。構内は島式ホームの1面2線で、結局のところ、JR東西線の駅は全てこれでした。
加島駅のスタンプの表題は、「都と西国を結ぶ歴史の残る地の駅」です。改札をくぐり、1号出口から出たところでJR東西線全駅下車達成
 です。午前中だけでも1つやっておけばすっきりします。
です。午前中だけでも1つやっておけばすっきりします。
1号出口から道なりに歩くと駅舎らしい建物とロータリーが現れます。これには駅機能がなく、単なる出入り口(2号出口)です。このあたりはJR東西線の開業まで駅が皆無で「陸の孤島」といわれていた地区なので、これだけのロータリーが必要だったのでしょう。

駅構内にもう1度入り、竹島西口に出ました。JR神戸線の列車が走る姿を間近に見ることが出来ます。この駅は、JR東西線の開業前の段階(仮称)では「竹島駅」とされていました。

竹島地区は阪神工業地帯の一角にあり、如何にも労働者の町という佇まいで、まっすぐ歩いていくとプリマハムの工場と佐川急便のステーションにぶち当たりました。
竹島東口から今一度改札をくぐり、11時45分発の4497B(207系S67編成+Z12編成)で尼崎に出た後、11時53分発の新快速3238M(223系W39編成+V59編成)に乗り継いで新大阪へ。

12時5分に新大阪駅に到着。ほっとして束の間、「トワイライトエクスプレス」が入線してきました。時刻表に載っていないので団体列車です。新潟でコンサートがあるため、今回の旅はこれにて終了。せめてJL2247便が利用できれば桂川駅を訪問できたのに。


改札前の喫茶店で昼食を終えた後、リムジンバスで伊丹空港に向かい、ANA1659便にて新潟空港に帰還します。悪名高きDHC-8-Q400(JA841A)で且つ優先搭乗者が何人も居たので、搭乗開始は定刻の10分遅れの14時20分。新潟空港に着陸したのは15時30分。機体が小さく荷物を預けたのでホント焦りました。
おわり



























 )
)















 でした。
でした。









 の営業所があり、1台客待ちしています。
の営業所があり、1台客待ちしています。


 を敢行します。
を敢行します。




 で上着が邪魔なくらい暑いです。
で上着が邪魔なくらい暑いです。