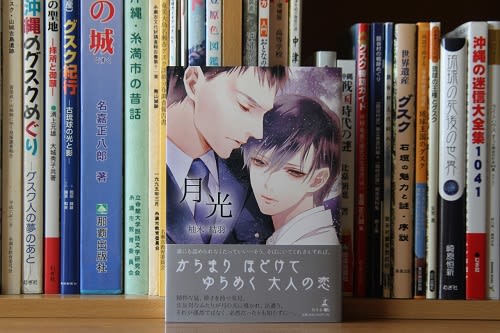福井川橋梁 ( ふくいがわきょうりょう ) は、
長崎県佐世保市吉井町直谷と
同市江迎町田ノ元の境界 ( 松浦鉄道西九州線の潜竜ヶ滝駅~吉井駅間 ) となる
福井川 ( 佐々川支流 ) に架かる単線鉄道橋である。

福井川橋梁から400mほど離れた場所に架かる 「 吉井川橋梁 」
福井川橋梁は、2006年 ( 平成18年 ) 9月に、
同駅間にある吉井川橋梁とともに国の登録有形文化財になった。
また、長崎県のまちづくり景観資産にも指定されている。
当時の国鉄伊万里線 ( 現松浦鉄道西九州線 ) の建設に伴い架橋されたもので、
1942年 ( 昭和17年 ) に竣工、
1944年 ( 昭和19年 ) 4月13日の潜竜 ( 現潜竜ヶ滝 ) から
肥前吉井 ( 現吉井 ) 間の開業に伴い供用開始された。
コンクリート製3連アーチ橋で、
橋梁の長さは79m ( うちアーチ部67.06m ) 、アーチ半径は10m。
当橋梁が架橋された時期は戦時中で鉄材の不足していた時期であることから、
架橋時の骨組みに鉄筋ではなく、
竹を用いた竹筋コンクリートだという地元住民の証言があった。
事実だとすれば日本国内の現用鉄道橋としては他に類例がないため
松浦鉄道が2002年 ( 平成14年 ) から調査を開始。
2006年 ( 平成18年 ) 2月には
工学院大学に依頼して橋梁内部の調査を行った。
その結果、竹筋使用については確認ができなかったが、
使用された可能性は残されているという。
スパンドレルに連続アーチを穿ち、躯体軽量化と資材減量化を図る、
官設鉄道時代の貴重な遺構である。