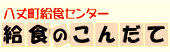みなさま、こんにちは!海風おねいさんです。
ここ数日、冷え込みが厳しくなってきましたね。灯油の減りが早いこと!
八丈島もいよいよ冬本番というかんじです。
しかし、ひと足早い春をみなさまに感じていただく


「ヘルシーフェスタ」が、本日より元気に始まっています
会場は、中之郷、地熱利用農産物直売所「えこ・あぐりまーと」です。
このイベントに関しましては、おねいさんが取材に行ってまいりますので、
また詳しく内容をお伝えいたしますね♪
本日は、地元小学校で行われた「食育講習会」の内容をご紹介いたします。
この講習会に関する記事は、昨日発売の南海タイムスにも掲載されていました。
ご覧になりましたか?
子どもを心身ともに健康に育てることは、すべての母の願いだと思います。
食育に関心のおありになるお母様も多いことでしょう。
でもきっとこのような講習会には、なかなか参加できないかたが多いのですよね?
小学校の「食育講習会」ではどんなことが話されているのでしょうか。
おねいさんが代わりによく聴いてきましたので、ご紹介しますね。

講師は、食育コーディネーターで、フェリス女学院非常勤講師の大村直己先生です。
大村先生は、子どもの食と育を考えるインターネットサイトも主宰しておられます。
 ほねぶとネット
ほねぶとネット  クリック
クリック
大村先生は、「食の3つの基本ポイント」として、
(1)ご飯と1汁2菜(主食+主菜+副菜+汁物)
(2)地産地消と旬産旬消
(3)食べ物への感謝の気持ち「いただきます」と「ごちそうさま」
の3点を提唱されています。
(1)の主食は、白いご飯のことです。
白いご飯とおかずを口の中で食べ合わせることを「口内調味」といいます。
ご飯とほどほどの塩分のあるおかずを口の中で食べ合わせて調味することは、
子どもの味覚の形成と健康のためにとてもよろしいと仰っています。
これは、日本人の食生活が最も理想的な形で完成されていた昭和40年代の食べ方。
おかずは、焼き魚を中心にして、なるべく丸のままの素材をシンプルに使う。
子どもに食材を教え、農業・漁業の大切さや環境を考えることにも繋がります。
大村先生は、食と自立に向う人の意欲は繋がると仰います。
「元気」「根気」「やる気」_「気」=生きる力のある人を育てる食事をしようと。
いま、日本人は、「ちょっとおかしな食べ方をしている」と感じている人が多い。
でも、食生活をはじめとする生活習慣は、なかなか直りませんね。
いつの間にか悪循環に身を投じ、生活習慣病に陥る人も多いです。
もう少しきちんと自分たちの食生活を見直さないと、
食生活の乱れが「気」のない子どもたちを育てています。
また、様々な自然体験なく育った子どもたちの「いいこ」による非行という
おかしな現象も増えています。
「食べ方論以前に、暮らし方論なんです」と、大村先生は仰います。
子どもの成長ホルモンが促されるピークは、夜の10~11時だそうです。
その時間に起きているような暮らしをさせていたのでは、いい成長は望めません。
「家庭が子どもの暮らしを守るんです」親の自覚が問われますね。
「子どもの早寝を重視して、夜食などを食べなくてすむ生活スタイルにすること」
「子どもには腹ペコを体験させ、お腹を空かせて食事をさせれば偏食はなくなる」
この点にも、おねいさんは深く共感します。
「食べてくれない」「うちの子は偏食」と悩む家庭は、
たいてい子どもや親の好きな食生活に偏っています。
食事は、子どもの食べたいものを食べさせるのでなく、
親が考えて、子どもに食べさせたいものを与えなければいけません。
わが家では、食べなければ食べさせない方針を貫きましたので、
(代わりのものを与えない、という意味ですよ)
うちの子どもはなんでも食べるようになったのだと思っていますよ。
お腹を空かせる経験は、かわいそうなことではなく、必要な経験だと思います。
「程よい食べ方、節度のある食べ方が、欲望のコントロールも教えます」
耳の痛いかたも多いでしょう。わたしも同じですよ。
おいしいと、ついつい食べ過ぎちゃいますもんね。
ですが、ネズミを使った実験で、満腹ネズミくんと腹八分ネズミくんでは、
寿命がぜんぜん違うと聞いたら、どうします?
もちろん早死には、満腹くんのほうなんですよ。


長生きしたいなら、あまり食べすぎはいけませんね。
日本では、3年前に「食育基本法」が新たに成立し、この1月にも文部科学省は、
学校給食法の目的を大幅に見直し、これに「食育」明記して、
給食を通じて「食への感謝や地域文化の理解、郷土への愛着などを育む」
といった理念を盛り込む考えであることを発表しています。
(2)の地産地消、旬産旬消は、これに同じ意味ですね。
郷土を愛し、郷土の産業や食材に関心を持ち、これを旬の時期にいただく
地産地消や旬産旬消の考え方は、地球にも優しいスローライフです。
(3)の食べ物への感謝の気持ちも、食育法の第三条にうたわれています。
(食に関する感謝の念と理解) 第三条
食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、
また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、
感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。
なんだか当たり前すぎることのようですね。
でも、できない人も多いのかもしれません。
地元で作られた商品でなくても、必ず生産者のいることです。
いまは、スーパーでも商品に産地を明記するようになりましたし、
「あさぬま」でも昨年は、桃の産直販売セールなどで、
店内モニターに生産者の姿や生産現場を映すなどの試みをしております。
わたしたちの口に入るものには、必ず多くの方々の苦労や努力が陰にあります。
いつも感謝していただく気持ちを忘れたくないですよね。
さて、ずいぶん長くなりまして、更新時刻も遅くなりました。
本日は、地元小学校で行われた「食育講習会」の内容をお届けいたしました。
いかがでしょうか?日々の食生活の参考にしていただけたら幸いです。
有意義なお話を聴かせていただいた大村直己先生と
小学校の校長先生はじめ関係者各位にお礼申し上げます。

 今週末の特売チラシは、こちらです。
今週末の特売チラシは、こちらです。
ここ数日、冷え込みが厳しくなってきましたね。灯油の減りが早いこと!

八丈島もいよいよ冬本番というかんじです。

しかし、ひと足早い春をみなさまに感じていただく



「ヘルシーフェスタ」が、本日より元気に始まっています

会場は、中之郷、地熱利用農産物直売所「えこ・あぐりまーと」です。
このイベントに関しましては、おねいさんが取材に行ってまいりますので、
また詳しく内容をお伝えいたしますね♪

本日は、地元小学校で行われた「食育講習会」の内容をご紹介いたします。
この講習会に関する記事は、昨日発売の南海タイムスにも掲載されていました。
ご覧になりましたか?
子どもを心身ともに健康に育てることは、すべての母の願いだと思います。
食育に関心のおありになるお母様も多いことでしょう。
でもきっとこのような講習会には、なかなか参加できないかたが多いのですよね?
小学校の「食育講習会」ではどんなことが話されているのでしょうか。
おねいさんが代わりによく聴いてきましたので、ご紹介しますね。

講師は、食育コーディネーターで、フェリス女学院非常勤講師の大村直己先生です。
大村先生は、子どもの食と育を考えるインターネットサイトも主宰しておられます。
 ほねぶとネット
ほねぶとネット  クリック
クリック
大村先生は、「食の3つの基本ポイント」として、
(1)ご飯と1汁2菜(主食+主菜+副菜+汁物)
(2)地産地消と旬産旬消
(3)食べ物への感謝の気持ち「いただきます」と「ごちそうさま」
の3点を提唱されています。
(1)の主食は、白いご飯のことです。
白いご飯とおかずを口の中で食べ合わせることを「口内調味」といいます。
ご飯とほどほどの塩分のあるおかずを口の中で食べ合わせて調味することは、
子どもの味覚の形成と健康のためにとてもよろしいと仰っています。
これは、日本人の食生活が最も理想的な形で完成されていた昭和40年代の食べ方。
おかずは、焼き魚を中心にして、なるべく丸のままの素材をシンプルに使う。
子どもに食材を教え、農業・漁業の大切さや環境を考えることにも繋がります。
大村先生は、食と自立に向う人の意欲は繋がると仰います。
「元気」「根気」「やる気」_「気」=生きる力のある人を育てる食事をしようと。
いま、日本人は、「ちょっとおかしな食べ方をしている」と感じている人が多い。
でも、食生活をはじめとする生活習慣は、なかなか直りませんね。
いつの間にか悪循環に身を投じ、生活習慣病に陥る人も多いです。
もう少しきちんと自分たちの食生活を見直さないと、
食生活の乱れが「気」のない子どもたちを育てています。
また、様々な自然体験なく育った子どもたちの「いいこ」による非行という
おかしな現象も増えています。
「食べ方論以前に、暮らし方論なんです」と、大村先生は仰います。
子どもの成長ホルモンが促されるピークは、夜の10~11時だそうです。
その時間に起きているような暮らしをさせていたのでは、いい成長は望めません。
「家庭が子どもの暮らしを守るんです」親の自覚が問われますね。
「子どもの早寝を重視して、夜食などを食べなくてすむ生活スタイルにすること」
「子どもには腹ペコを体験させ、お腹を空かせて食事をさせれば偏食はなくなる」
この点にも、おねいさんは深く共感します。
「食べてくれない」「うちの子は偏食」と悩む家庭は、
たいてい子どもや親の好きな食生活に偏っています。
食事は、子どもの食べたいものを食べさせるのでなく、
親が考えて、子どもに食べさせたいものを与えなければいけません。
わが家では、食べなければ食べさせない方針を貫きましたので、
(代わりのものを与えない、という意味ですよ)
うちの子どもはなんでも食べるようになったのだと思っていますよ。
お腹を空かせる経験は、かわいそうなことではなく、必要な経験だと思います。
「程よい食べ方、節度のある食べ方が、欲望のコントロールも教えます」
耳の痛いかたも多いでしょう。わたしも同じですよ。
おいしいと、ついつい食べ過ぎちゃいますもんね。

ですが、ネズミを使った実験で、満腹ネズミくんと腹八分ネズミくんでは、
寿命がぜんぜん違うと聞いたら、どうします?
もちろん早死には、満腹くんのほうなんですよ。



長生きしたいなら、あまり食べすぎはいけませんね。

日本では、3年前に「食育基本法」が新たに成立し、この1月にも文部科学省は、
学校給食法の目的を大幅に見直し、これに「食育」明記して、
給食を通じて「食への感謝や地域文化の理解、郷土への愛着などを育む」
といった理念を盛り込む考えであることを発表しています。
(2)の地産地消、旬産旬消は、これに同じ意味ですね。
郷土を愛し、郷土の産業や食材に関心を持ち、これを旬の時期にいただく
地産地消や旬産旬消の考え方は、地球にも優しいスローライフです。
(3)の食べ物への感謝の気持ちも、食育法の第三条にうたわれています。
(食に関する感謝の念と理解) 第三条
食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、
また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、
感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。
なんだか当たり前すぎることのようですね。
でも、できない人も多いのかもしれません。
地元で作られた商品でなくても、必ず生産者のいることです。
いまは、スーパーでも商品に産地を明記するようになりましたし、
「あさぬま」でも昨年は、桃の産直販売セールなどで、
店内モニターに生産者の姿や生産現場を映すなどの試みをしております。
わたしたちの口に入るものには、必ず多くの方々の苦労や努力が陰にあります。
いつも感謝していただく気持ちを忘れたくないですよね。
さて、ずいぶん長くなりまして、更新時刻も遅くなりました。
本日は、地元小学校で行われた「食育講習会」の内容をお届けいたしました。
いかがでしょうか?日々の食生活の参考にしていただけたら幸いです。
有意義なお話を聴かせていただいた大村直己先生と
小学校の校長先生はじめ関係者各位にお礼申し上げます。


 今週末の特売チラシは、こちらです。
今週末の特売チラシは、こちらです。