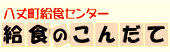みなさま、こんにちは!海風おねいさんです。
いい日曜日をお過ごしですか?
今日の八丈島は風はさほど強くないものの、海は時化ているようです。
本日の船便は欠航しております。朝、「あさぬま」へ行きましたら、
生鮮品が少なくなっておりました。どうぞご理解の程お願いいたします。
今日は息子のバスケの試合でしたが、朝から仕事が立て込んでいました。
試合を少しだけでも観たいし、打ち合わせの時間もあるし、
バタバタ走り回りながら15分で作った息子のお弁当です。

・ポークソテー
・ブリの塩焼き
・小松菜ソテー
・セリのお浸し
・ミートソーススパゲティ(あさぬまのお惣菜)
・甘塩筋子
・ミニトマト・きんかん
・ご飯
・ホットレモンジュース

[ポークソテーの作り方]
◎時間のないときには、必殺裏技で作ります。
フライパンにサラダ油とバターを熱し、豚ロース肉をソテーします。
片面を焼きながら、片面にクレイジーソルトとコンソメ顆粒を振りかけます。
片面に焼き色がついたら、ひっくり返して同じことをします。
焼きあがる前に、もう一度ひっくり返してコンソメを絡めます。
肉に火が通ったらフライパンから取り出し、食べやすい大きさに切ります。
その間に、フライパンの肉汁を煮詰めます。
切ったお肉に、ほどよく煮詰めた肉汁をかけて完成です。
これでけっこうおいしいポークソテーができるんですよ。

ポークソテーは、この端の脂のちょっとあるところがおいしいですよね。

この間に、塩を振りかけたブリをグリルで焼きながら、
別のガスコンロでセリをサッと湯がき、小松菜を胡麻油でササッと炒めます。
※セリを湯がくお湯は、湯沸かし器から熱湯を小鍋にとると早いです。
小松菜の味付けは塩胡椒のみ。セリは絞っておかかと醤油をかけます。
小松菜は2株分、セリは1/2束入っています。

ポークソテーの付け合せには、小松菜とミートソーススパを詰めます。
このスパは、「あさぬま」お惣菜コーナーの商品です。
ちょっと懐かしい味で、おいしいですよ。時間のないとき利用しています。
子どもの好きな筋子も端に詰めて、空いたスペースにきんかんとミニトマト。
お弁当箱に詰める時間も含めて、15分で完成です。
バスケの試合は、半分だけ見ることができました。
試合は惜しいところで負けてしまったけど、みんなずいぶん上手くなっていました。
いい日曜日をお過ごしですか?

今日の八丈島は風はさほど強くないものの、海は時化ているようです。
本日の船便は欠航しております。朝、「あさぬま」へ行きましたら、
生鮮品が少なくなっておりました。どうぞご理解の程お願いいたします。

今日は息子のバスケの試合でしたが、朝から仕事が立て込んでいました。
試合を少しだけでも観たいし、打ち合わせの時間もあるし、
バタバタ走り回りながら15分で作った息子のお弁当です。

・ポークソテー
・ブリの塩焼き
・小松菜ソテー
・セリのお浸し
・ミートソーススパゲティ(あさぬまのお惣菜)
・甘塩筋子
・ミニトマト・きんかん
・ご飯
・ホットレモンジュース

[ポークソテーの作り方]
◎時間のないときには、必殺裏技で作ります。
フライパンにサラダ油とバターを熱し、豚ロース肉をソテーします。
片面を焼きながら、片面にクレイジーソルトとコンソメ顆粒を振りかけます。
片面に焼き色がついたら、ひっくり返して同じことをします。
焼きあがる前に、もう一度ひっくり返してコンソメを絡めます。
肉に火が通ったらフライパンから取り出し、食べやすい大きさに切ります。
その間に、フライパンの肉汁を煮詰めます。
切ったお肉に、ほどよく煮詰めた肉汁をかけて完成です。
これでけっこうおいしいポークソテーができるんですよ。


ポークソテーは、この端の脂のちょっとあるところがおいしいですよね。

この間に、塩を振りかけたブリをグリルで焼きながら、
別のガスコンロでセリをサッと湯がき、小松菜を胡麻油でササッと炒めます。
※セリを湯がくお湯は、湯沸かし器から熱湯を小鍋にとると早いです。
小松菜の味付けは塩胡椒のみ。セリは絞っておかかと醤油をかけます。
小松菜は2株分、セリは1/2束入っています。

ポークソテーの付け合せには、小松菜とミートソーススパを詰めます。
このスパは、「あさぬま」お惣菜コーナーの商品です。
ちょっと懐かしい味で、おいしいですよ。時間のないとき利用しています。
子どもの好きな筋子も端に詰めて、空いたスペースにきんかんとミニトマト。
お弁当箱に詰める時間も含めて、15分で完成です。

バスケの試合は、半分だけ見ることができました。

試合は惜しいところで負けてしまったけど、みんなずいぶん上手くなっていました。

















 クリック
クリック












 こんなこともいつかきっといい思い出です。
こんなこともいつかきっといい思い出です。



 だから、「みぞれ鍋」を作りました。
だから、「みぞれ鍋」を作りました。