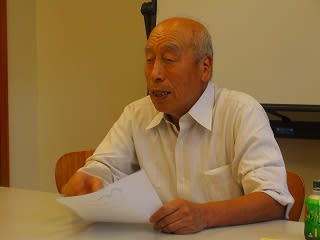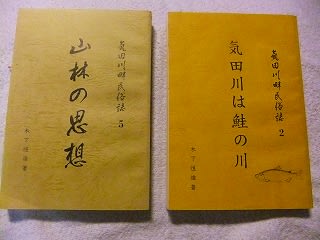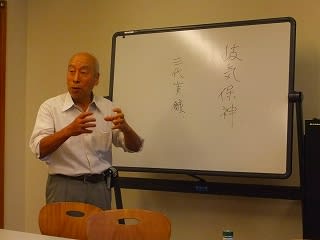昨夜の山車は昨年より子どもが少なく閑散としている。
青年たちも出番では活躍しているが、これが過疎の現実でもある。
祭りのために帰郷する若人も少なくなっている。


しかしながら、洗練した都会の祭りより、お互いがみんな知っている山里の祭りらしさは親しみやすい。
小学生も夏休みごろから太鼓の練習をしてきたという。


午前中に道草山の隣のお宮の幟を仕舞ってから、お昼ごろ地区の神社に行く。
廃校の校庭に屋台がつつましく配置されているが、空白が目立つ。
その隣が境内となっている。
宮司たちが神社本殿に向かって歩き出すと祭りのクライマックスとなる。
甘酒・ビールを飲んだり、焼き鳥・おでんなどを食べながら集落の世間話が延々と続く。
山里の祭りは日本が年々失っていくコミュニティーが健在する場でもある。
青年たちも出番では活躍しているが、これが過疎の現実でもある。
祭りのために帰郷する若人も少なくなっている。


しかしながら、洗練した都会の祭りより、お互いがみんな知っている山里の祭りらしさは親しみやすい。
小学生も夏休みごろから太鼓の練習をしてきたという。


午前中に道草山の隣のお宮の幟を仕舞ってから、お昼ごろ地区の神社に行く。
廃校の校庭に屋台がつつましく配置されているが、空白が目立つ。
その隣が境内となっている。
宮司たちが神社本殿に向かって歩き出すと祭りのクライマックスとなる。
甘酒・ビールを飲んだり、焼き鳥・おでんなどを食べながら集落の世間話が延々と続く。
山里の祭りは日本が年々失っていくコミュニティーが健在する場でもある。