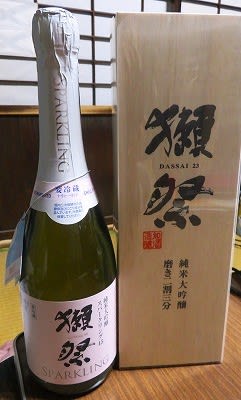年末から年始にかけて、庭にあった植木鉢に防寒対策をする。オラんちの庭は冬には陽が全く当たらなくなる。そこで、畑の隣で陽当たりがよさそうな所に植木鉢を移動して防寒対策をしようとしたわけだ。地上から10~20cmほどの所に厚い板をかけ、そこに植木鉢を運搬する。つい水やりを忘れ枯らしてしまった失敗も重ねている。

次は、支柱をX状に打ち込んでから寒冷紗を被せるが、そこにグラスファイバーの支柱を入れてパッカーで縦横に補強する。これは失敗の試行錯誤から産み出した創作作業だ。この作業は風が強い時を避けないとふりだしに戻される。 
しかも、寒冷紗の上にビニールを被せるから余計だ。ビニールシートに穴あけもしてあるので喚起や雨浸透もなんとかクリアする。強風をさらに緩和するために竹を伐ってきて両側に補強する。内側には刈り取ってきた枯れ草をたっぷり配置してあるので霜よけにもなる。年末はこの作業だけでずいぶん時間がかかってしまった。現代俳句「竹垣の青き切り口年明ける」と詠んだ 高野清美さんに共感のエールを送りたい。

上から見ると、雨が入るようにしてあるのがミソだ。これを全面的にビニールで覆ってしまうと突風ですべてを失ってしまう。山と川に挟まれたこの地は風の谷のナウシカならぬジェット気流地帯となってしまう。さらに、この上にべた掛けのシートを掛けて完成へ。

植木鉢が多すぎて移転できなかった庭には、防寒のための枯れ草を被せた上にシートを覆う。ビニールでないので雨でもOKだ。それでも、防寒は植物にとっても人生??の一大危機でもある。バタフライガーデンの枯れ草がここでやっと活躍する。

裏側の庭にあった植木鉢は山の枯葉を撒いてシートは使っていない。枯葉は意外に防寒対策にアイテムとなる。ただし、突風があると無くなってしまうので補充を常に考えなければならない。畑の野菜もべた掛けと寒冷紗でなんとか寒さをしのげそうな状態で、このところ、ルッコラ・大根・ニンジン・ネギ・キャベツ・白菜などを少しだが収穫できている。この防寒対策をやっていないと野菜は全滅になるのが今までの教訓だ。