31日(火)。早いもので7月も今日で最後ですね。月日の流れの速さを感じます
日曜日の日経朝刊最終面に西洋史家の樺山紘一さんが「欧人異聞」というコラムを連載していますが、先日は「ふたりのグスタフ、世紀末の不満」と題して書いていました 二人のグスタフとは「グスタフ・マーラー」と「グスタフ・クリムト」です。ともに100年前の”ウィーン世紀末”をリードした芸術家です
二人のグスタフとは「グスタフ・マーラー」と「グスタフ・クリムト」です。ともに100年前の”ウィーン世紀末”をリードした芸術家です 樺山氏は書きます。
樺山氏は書きます。
「マーラーは1897年には37歳でもうウィーン宮廷歌劇場の芸術監督、ついでは、ウィーン・フィルの指揮台に。のちに招かれて、ニューヨークのメトロポリタン・オペラ座の指揮者への道をたどる。栄光そのものだ だが不満だった。マーラー本人は、正道を行く作曲家と自認していた。けれどもウィーンでは、あくまでも指揮者としてのみ尊重された
だが不満だった。マーラー本人は、正道を行く作曲家と自認していた。けれどもウィーンでは、あくまでも指揮者としてのみ尊重された 」
」
そう、その通り。マーラーはウィーンで成功するため、ユダヤ教からキリスト教に改宗までしています。それでも作曲家として正当な評価を受けることはありませんでした
「クリムトはある年、ウィーン大学講堂を飾る天井画の委嘱を受ける。この作品はあまりにラディカルで挑発的だとしてスキャンダルを巻き起こす 酷評に嫌気がさしたクリムトは、これを撤回し、仲間に呼びかける。”分離派”の出発である
酷評に嫌気がさしたクリムトは、これを撤回し、仲間に呼びかける。”分離派”の出発である 」
」
クリムトは”ウィーン分離派”で活躍したものの、やがて同志と諍いをして脱退します。彼の不平不満はいつまでも収まらなかったようです 樺山氏は次のように結んでいます。
樺山氏は次のように結んでいます。
「クルムトはマーラーより2つ年下だった。ウィーンっ子の二人が親しく語り合った形跡はない。だが、百年後となってみれば、不平不満足も人生の隠し味といえようか。仲間らしい連帯感さえもほのみえる 」
」
マーラーは当時、こう言ったといわれています。
「やがて私の時代が来る 」
」
その通り、100年後の今、マーラーの時代が続いています

 閑話休題
閑話休題 

三上延著「ビブリア古書堂の事件手帖《2》~栞子さんと謎めく日常」(メディアワークス文庫)を読み終わりました 第1巻に続いて北鎌倉の老舗古本屋「ビブリア古書堂」の女主人・篠川栞子(しおりこ)とアルバイト店員・五浦大輔が主人公となり,古書にまつわる謎を解いていくミステリー小説です
第1巻に続いて北鎌倉の老舗古本屋「ビブリア古書堂」の女主人・篠川栞子(しおりこ)とアルバイト店員・五浦大輔が主人公となり,古書にまつわる謎を解いていくミステリー小説です
この巻で収録されているのは①坂口三千代「クラクラ日記」,②アントニイ・バージェス「時計じかけのオレンジ」,③福田定一「名言随筆 サラリーマン」,④足塚不二雄「UTOPIA 最後の世界大戦」の4冊です
「時計じかけのオレンジ」はレーザー・ディスクで観たことがあります.一人の若者が麻薬,暴力をやりたい放題やるストーリーで,どこが面白いのか,と疑問に思いながら観た記憶があります この本を読んで初めて「時計じかけのオレンジ」には結末の違う2つのバージョンがあることを知りました
この本を読んで初めて「時計じかけのオレンジ」には結末の違う2つのバージョンがあることを知りました
福田定一と言われても小説に縁のない人には誰だかさっぱり分からないと思いますが,デビュー前の司馬遼太郎だと言われれば,なるほどと思うのではないでしょうか 彼はデビュー当時,産経新聞大阪本社の文化部次長でした
彼はデビュー当時,産経新聞大阪本社の文化部次長でした
古書をテーマにミステリーを展開する珍しい手法ですが,なかなか読ませます.取り上げられている本を読んでみたくなります

司馬遼太郎さんと一度だけ話したことがあります もう30年以上も前,元の職場の国際部にいた時のことです.約10名のアメリカの新聞記者団に同行して大阪に出張した際,司馬遼太郎さんを囲む会(要するに司馬さんに自由に話をしてもらい,通訳を通して聴く会)を開きました.司馬さんと大阪ロイヤルホテルのロビーで待ち合わせをしたのですが,司馬さんは約束の時間よりも前にお見えになっていてコーヒーを飲んでいらっしゃいました
もう30年以上も前,元の職場の国際部にいた時のことです.約10名のアメリカの新聞記者団に同行して大阪に出張した際,司馬遼太郎さんを囲む会(要するに司馬さんに自由に話をしてもらい,通訳を通して聴く会)を開きました.司馬さんと大阪ロイヤルホテルのロビーで待ち合わせをしたのですが,司馬さんは約束の時間よりも前にお見えになっていてコーヒーを飲んでいらっしゃいました 伝票を取って「これは当方でお支払いさせていただきます」と言うと,「それ,私が払いますわ」と関西弁でおっしゃいました.そういう訳にもいかないので「いや,こちらで・・・」と言ってレジに持っていきました.その時の司馬さんの話しぶりや仕草などから、気さくな人なんだな,と思いました
伝票を取って「これは当方でお支払いさせていただきます」と言うと,「それ,私が払いますわ」と関西弁でおっしゃいました.そういう訳にもいかないので「いや,こちらで・・・」と言ってレジに持っていきました.その時の司馬さんの話しぶりや仕草などから、気さくな人なんだな,と思いました 「囲む会」は日本の昔の話で歴史の専門用語が頻繁に出てきたせいか通訳がうまく記者団に通じなかったようでした.日本人の私にも相当難しい内容だったので無理もありません。たった10人足らずのために司馬遼太郎さんの話を聴くという贅沢な企画だったのですが、残念なことをしました
「囲む会」は日本の昔の話で歴史の専門用語が頻繁に出てきたせいか通訳がうまく記者団に通じなかったようでした.日本人の私にも相当難しい内容だったので無理もありません。たった10人足らずのために司馬遼太郎さんの話を聴くという贅沢な企画だったのですが、残念なことをしました












 プログラムは2部構成で、第1部が「熱い夏」、第2部が「涼む夏」となっています。指揮は小松長生、曲の合間のナレーションは堀江一眞です
プログラムは2部構成で、第1部が「熱い夏」、第2部が「涼む夏」となっています。指揮は小松長生、曲の合間のナレーションは堀江一眞です コントラバスの村松裕子さんの姿が見えないのはちょっと寂しいかな
コントラバスの村松裕子さんの姿が見えないのはちょっと寂しいかな
 さっそく,第1曲めのガーシュイン「キューバ序曲」の演奏に入ります.オープニングに相応しい”ノリのいい”ラテン・ミュージック”です
さっそく,第1曲めのガーシュイン「キューバ序曲」の演奏に入ります.オープニングに相応しい”ノリのいい”ラテン・ミュージック”です マラカスの音が何ともいい感じです.管楽器も弦楽器も,もちろん打楽器群もノリノリの演奏です
マラカスの音が何ともいい感じです.管楽器も弦楽器も,もちろん打楽器群もノリノリの演奏です






 兄弟そろって後世に残るたくさんのワルツやポルカを作曲しました
兄弟そろって後世に残るたくさんのワルツやポルカを作曲しました
 この曲は,クラシック音楽のパロディー名演集といった感じの曲で,メンデルスゾーンの結婚行進曲で始まり,モーツアルトの「ト短調交響曲」の有名なテーマ,リストの「ラ・カンパネラ」,ウェーバー「魔弾の射手・序曲」,モーツアルト「魔笛~パパゲーノのアリア」などがメドレーで演奏されます.初めて聴きましたが,とても楽しい曲でした
この曲は,クラシック音楽のパロディー名演集といった感じの曲で,メンデルスゾーンの結婚行進曲で始まり,モーツアルトの「ト短調交響曲」の有名なテーマ,リストの「ラ・カンパネラ」,ウェーバー「魔弾の射手・序曲」,モーツアルト「魔笛~パパゲーノのアリア」などがメドレーで演奏されます.初めて聴きましたが,とても楽しい曲でした




 かつて電気街で有名だった街が,今やアニメとAKB48の街にすっかり変身しています(今さら何を,という声あり).メイド姿の女性が道の両サイドでチラシやティッシュを配ったりしています
かつて電気街で有名だった街が,今やアニメとAKB48の街にすっかり変身しています(今さら何を,という声あり).メイド姿の女性が道の両サイドでチラシやティッシュを配ったりしています なぜか分からないのですが,あちこちで若い男の子が行列を作っています
なぜか分からないのですが,あちこちで若い男の子が行列を作っています こういう所へはあまり行きたくないですね.息切れしそうで・・・・・・
こういう所へはあまり行きたくないですね.息切れしそうで・・・・・・ なにしろ256席しかないので聴きたいコンサートがある時は早めに手配しないとすぐにソルド・アウトになってしまいます
なにしろ256席しかないので聴きたいコンサートがある時は早めに手配しないとすぐにソルド・アウトになってしまいます




 ベトナム・ビールやベトナム焼酎(ココナッツの味がした.非常に美味しかった
ベトナム・ビールやベトナム焼酎(ココナッツの味がした.非常に美味しかった
 飯野海運のKさん,Tさんは絶好調でハイスコアを記録,W夫人はいつものように得意の演歌で周囲の聴衆を歓喜の渦に巻き込んでトップ・スコアを出していました
飯野海運のKさん,Tさんは絶好調でハイスコアを記録,W夫人はいつものように得意の演歌で周囲の聴衆を歓喜の渦に巻き込んでトップ・スコアを出していました W夫人はカラオケの世界ではエンターティナーの向こうを張って”演歌ティナー”と呼ばれています.当社の4人(約1名は初登場
W夫人はカラオケの世界ではエンターティナーの向こうを張って”演歌ティナー”と呼ばれています.当社の4人(約1名は初登場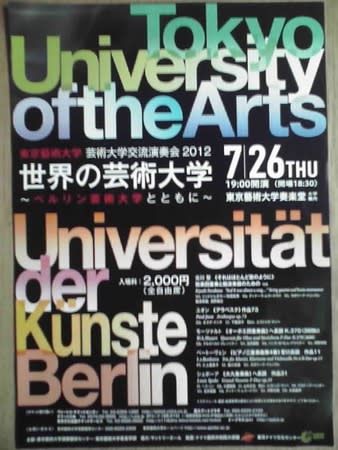
 どういう曲か誰も分からないので,作曲者自らが解説しました
どういう曲か誰も分からないので,作曲者自らが解説しました 誤解を恐れずに要約すると,
誤解を恐れずに要約すると, 聴衆は2つのスクリーンに映し出された脳波の波などの映像を観て過ごします(シーン1).そしてシーン2に移り,8つの小さなスピーカーからそれぞれコンピュータを通して解析された脳波の音楽が流れてきます
聴衆は2つのスクリーンに映し出された脳波の波などの映像を観て過ごします(シーン1).そしてシーン2に移り,8つの小さなスピーカーからそれぞれコンピュータを通して解析された脳波の音楽が流れてきます 大きな花模様の髪留めがひっきりなしに揺れていました.一種の演奏連動型シンドロームかもしれません.そんなの無いですが
大きな花模様の髪留めがひっきりなしに揺れていました.一種の演奏連動型シンドロームかもしれません.そんなの無いですが

 」と腹が立ちましたが,そんなことにもめげずに結果を出して関係者を見返してやればいいと思います.ガンバレ・ニッポン
」と腹が立ちましたが,そんなことにもめげずに結果を出して関係者を見返してやればいいと思います.ガンバレ・ニッポン


 日本のプロ野球では有り得ないことです。イチローの凄いところは他の日本人メジャーリーガーが移籍のたびにランクを落としていくのに,上位のチームに移籍していくところです.今でも超一流ですが,さらに進化を続け,その上を目指してチームの優勝に貢献してほしいと思います
日本のプロ野球では有り得ないことです。イチローの凄いところは他の日本人メジャーリーガーが移籍のたびにランクを落としていくのに,上位のチームに移籍していくところです.今でも超一流ですが,さらに進化を続け,その上を目指してチームの優勝に貢献してほしいと思います
 茂木さんに聞いてみたい気がします
茂木さんに聞いてみたい気がします
 ビールやお酒の一気飲みが良くないのは誰でも知っていますが,まさかウーロン茶の”一時集中摂取”が健康に良くないと言うのは初めて聴きました
ビールやお酒の一気飲みが良くないのは誰でも知っていますが,まさかウーロン茶の”一時集中摂取”が健康に良くないと言うのは初めて聴きました



 コンマスは女性です.そういえば,先日のアマ・オケ「ザ・シンフォニカ」も女性のコンマスでした.アマチュア・オーケストラは女性上位なのでしょうか
コンマスは女性です.そういえば,先日のアマ・オケ「ザ・シンフォニカ」も女性のコンマスでした.アマチュア・オーケストラは女性上位なのでしょうか まったく異議ありません
まったく異議ありません




