31日(日)。月末兼年末を迎えたので、3つの目標の実績をご報告します 最初に12月の実績は①クラシック・コンサート=13回、②映画鑑賞=10本、③読書=3冊でした
最初に12月の実績は①クラシック・コンサート=13回、②映画鑑賞=10本、③読書=3冊でした
次に2023年のトータルの実績は①クラシック・コンサート=180回(前年比 36回 増)、②映画鑑賞=130本(前年比 43本 増)、③読書=49冊(前年比 21冊 減)でした コンサートと映画が増えた一方、読書が減りました。①のコンサートは、N響はCプロに代えてAプロ、Bプロの会員になり、読響は定期に加え名曲も会員になり、シティ・フィルは定期に加えティアラも会員になったこと、また5月の「ラ・フォル・ジュルネ音楽祭」が復活したことが大く影響しています
コンサートと映画が増えた一方、読書が減りました。①のコンサートは、N響はCプロに代えてAプロ、Bプロの会員になり、読響は定期に加え名曲も会員になり、シティ・フィルは定期に加えティアラも会員になったこと、また5月の「ラ・フォル・ジュルネ音楽祭」が復活したことが大く影響しています なお、②映画鑑賞にはNetflixで観た10数本の作品は含めていないので、トータルでは140本以上になると思います
なお、②映画鑑賞にはNetflixで観た10数本の作品は含めていないので、トータルでは140本以上になると思います
また、健康面の1年間を振り返ってみると、2月には「鼡径ヘルニア手術」で3拍4日の入院があり、4月には「前立腺癌検査」のため1泊2日の入院がありました また、9月には酔って玄関で転倒しオデコに瘤を作り、右手の甲を打撲しました
また、9月には酔って玄関で転倒しオデコに瘤を作り、右手の甲を打撲しました お酒には気をつけなきゃアカンと思った出来事でした
お酒には気をつけなきゃアカンと思った出来事でした 皆さまの1年はいかがでしたでしょうか
皆さまの1年はいかがでしたでしょうか
ということで、わが家に来てから今日で3273日目を迎え、カナダに事実上の亡命をした香港の民主活動家・周庭さんについて、香港警察は「一生追跡する」などと警告して逮捕する方針を示し、近く指名手配されると見られている というニュースを見て感想を述べるモコタロです

言論の自由の根絶を目指す 中国・習近平の傀儡政権の 執拗な追及に対し抗議する!





昨日は娘が仕事休みだったので、帰省した息子を交えて巣鴨駅 atre の「OTTIMO KITCHEN」でランチしました 白ワインを片手にオードブル(4種)、ピザ(2種)、パスタ(2種)とデザート(ジェラート&コーヒー)をいただきました
白ワインを片手にオードブル(4種)、ピザ(2種)、パスタ(2種)とデザート(ジェラート&コーヒー)をいただきました 撮り忘れた料理が2種類あります
撮り忘れた料理が2種類あります 白ワインもしこたま飲んだので満腹です
白ワインもしこたま飲んだので満腹です












今年聴いた180回のクラシックコンサートの中から「マイ・ベスト3」を選びました 私は音楽評論家ではありませんので、あくまでも「今年聴いた最も印象に残ったコンサート」という観点で独断と偏見により選びました
私は音楽評論家ではありませんので、あくまでも「今年聴いた最も印象に残ったコンサート」という観点で独断と偏見により選びました
最初に手帳の日程表を見ながらパッと直感的に演奏を思い出した次の10公演を候補として選びました この時点で「マイ・ベスト10」と言えます
この時点で「マイ・ベスト10」と言えます 演奏月日順に次の通りです
演奏月日順に次の通りです
Ⅰ。井上道義指揮 音楽大学フェスティバルオーケストラ(3月26日:ミューザ川崎) ①ヨーゼフ・シュトラウス「天体の音楽」、②伊福部昭「シンフォニア・タプカーラ」、③ストラヴィンスキー「春の祭典」※何と言っても井上道義の十八番「シンフォニア・タプカーラ」です

Ⅱ。大野和士指揮 東京都交響楽団、(3月27日:サントリーホール) ①リゲティ「ヴァイオリン協奏曲」、②同「マカーブルの秘密」(以上Vn:パトリツィア・コパチンスカヤ)、③バルトーク「中国の不思議な役人」※コパチンスカヤの超個性的な演奏が光ります

Ⅲ。東京・春・音楽祭「郷古廉&加藤洋之 ~ 横坂源を迎えて」(4月11日:東京文化会館小ホール) ①ブロッホ「パール・シェム」より「ニーグン」、②ショスタコーヴィチ「ヴァイオリン・ソナタ」、③シルヴェストロフ「ヴァイオリン・ソナタ”追伸”」、④ショスタコーヴィチ「ピアノ三重奏曲第2番」※ピアノ・トリオにおける3人のグルーブ感に満ちたアグレッシブな演奏が印象的です

Ⅳ。新国立オペラ:ヴェルディ「リゴレット」(5月18日:オペラパレス) マウリツィオ・ベニーニ指揮東京フィル。ロベルト・フロンターリ、ハスミック・トロシャン他 ※指揮者も歌手陣も最高レベルでした

Ⅴ。梅田俊明指揮 東京交響楽団「モーツアルト・マチネ」(5月27日:ミューザ川崎) ①モーツアルト「セレナータ・ノットゥルナ」、②同「フルート協奏曲第2番」(Fl:高木綾子)、③同「交響曲第40番」※セレナータ・ノットゥルナにおけるウィットに満ちた演奏が楽しく魅力的でした

Ⅵ。チョン・ミョンフン指揮 東京フィル:ヴェルディ「オテロ」演奏会形式(7月31日:サントリーホール) グレゴリー・クンデ、小林厚子、ダリボール・イェニスほか ※終始、暗譜によるチョン・ミョンフンの指揮のもと、オペラの魅力が十二分に伝わってきました

Ⅶ。上岡敏之指揮 読売日響:ブルックナー「交響曲第8番」(8月31日:サントリーホール) ローター・ツァグロゼクの代役 ※集中力に満ちた気迫の演奏でした

Ⅷ。高関健指揮 東京シティ・フィル:プッチーニ「トスカ」演奏会形式(11月30日:東京オペラシティ) 木下美穂子、小原啓楼、上江隼人、妻屋秀和ほか ※高関健の渾身の指揮と歌手陣が素晴らしい

Ⅸ。フォーレ四重奏団(12月10日:横浜みなとみらい小ホール) ①マーラー「ピアノ四重奏断章」、②フォーレ「ピアノ四重奏曲第1番」、③ブラームス「ピアノ四重奏曲第1番」※ブラームスにおける迫真の演奏が凄かった

Ⅹ。ファビオ・ルイージ指揮 NHK交響楽団:マーラー「交響曲第8番”一千人の交響曲”」(12月17日:NHKホール) ジャクリン・ワーグナー、ヴァレンティーナ・ファルシュカ、オレシア・ペトロヴァほか ※大管弦楽と合唱とソリストとルイージの完璧な統率力に脱帽






さて、いよいよ「マイベスト3」の発表です
上記10公演の中で最も印象に残ったのは、大野和士指揮 東京都交響楽団(3月27日:サントリーホール) ①リゲティ「ヴァイオリン協奏曲」、②同「マカーブルの秘密」(以上Vn:パトリツィア・コパチンスカヤ)、③バルトーク「中国の不思議な役人」の公演です 特に「マカーブルの秘密」は奇抜な衣装といい、鋭角的なヴァイオリン独奏といい、何を言っているのか分からない叫び声といい、パトリツィア・コパチンスカヤの独演会の様相を呈していました
特に「マカーブルの秘密」は奇抜な衣装といい、鋭角的なヴァイオリン独奏といい、何を言っているのか分からない叫び声といい、パトリツィア・コパチンスカヤの独演会の様相を呈していました これほど強烈な個性は現代では天然記念物的存在です
これほど強烈な個性は現代では天然記念物的存在です しかし、アドリブ満載のように思えて彼女はほとんど楽譜通りに演奏しているのが驚きです
しかし、アドリブ満載のように思えて彼女はほとんど楽譜通りに演奏しているのが驚きです

次に印象に残ったのは梅田俊明指揮 東京交響楽団「モーツアルト・マチネ」(5月27日:ミューザ川崎)①モーツアルト「セレナータ・ノットゥルナ」、②同「フルート協奏曲第2番」(Fl:高木綾子)、③同「交響曲第40番」の公演です 特に「セレナータ・ノットゥルナ」におけるユーモア溢れる演奏スタイルはモーツアルトの本質を突いており、指揮者・梅田俊明のセンスの良さを再認識しました
特に「セレナータ・ノットゥルナ」におけるユーモア溢れる演奏スタイルはモーツアルトの本質を突いており、指揮者・梅田俊明のセンスの良さを再認識しました

3番目に印象に残ったのは、高関健指揮 東京シティ・フィル:プッチーニ「トスカ」演奏会形式(11月30日:東京オペラシティ)木下美穂子、小原啓楼、上江隼人、妻屋秀和ほかの演奏です 木下美穂子をはじめ「オール・ジャパニーズ」でこれほど高水準のパフォーマンスが達成できるのは素晴らしいことです
木下美穂子をはじめ「オール・ジャパニーズ」でこれほど高水準のパフォーマンスが達成できるのは素晴らしいことです

上記の通り、今年は3点ともオーケストラの「定期演奏会」とそれに準ずるコンサートから選んでいます 特に強調したいのは、チケット代の高低とコンサートの印象度とは必ずしも比例しないということです
特に強調したいのは、チケット代の高低とコンサートの印象度とは必ずしも比例しないということです 低料金のコンサートでも、企画次第で強く印象付けることが出来ることを「モーツアルト・マチネ」は証明しています
低料金のコンサートでも、企画次第で強く印象付けることが出来ることを「モーツアルト・マチネ」は証明しています
昨年の年末にも書きましたが、私はもともとオペラが好きで「新国立オペラ」を中心に鑑賞し、映画でも「METライブビューイング」や「同アンコール上映」を毎年欠かさず鑑賞しているのですが、最近の円安を背景に高騰する海外オペラ劇場来日公演のチケット代に、二の足を踏んでいるのが実情です もっと安価な料金で鑑賞できるようにならないか、といつも思っています
もっと安価な料金で鑑賞できるようにならないか、といつも思っています
さて、皆さまの「2023年のマイベスト」はいかがだったでしょうか
今年1年間、toraブログをご訪問いだだきありがとうこざいました 来年も1日も休まず書き続けて参りますので、モコタロともどもよろしくお願いいたします
来年も1日も休まず書き続けて参りますので、モコタロともどもよろしくお願いいたします





【忘備録】
2023年12月31日におけるtoraブログのトータル・アクセス数とランキング
①トータル 閲 覧 数 8,438,675 PV(前年末は 7,487,082 PV)※ +951,593PV
②トータル訪問者数 2,667,959 IP (前年末は 2,313,157 IP) ※ +354,802 IP
③gooブログ全体におけるランキング 3,176,944ブログ中184位(前年末は 3,140,875 ブログ中245位)
④日本ブログ村「コンサート・演奏会感想」におけるラキング 57ブログ中 1位(前年末は54ブログ中1位)
⑤フォロワー数 2026人( X分73人を含む)※前年末は2001人( ツイッター分47人を含む)













 私も全くその通りだと思います
私も全くその通りだと思います
 「手羽元とソボロと五穀米のサムゲタン風」と「生野菜サラダ」です。「サムゲタン風」は本格的な調味料が足りないので「風」と呼んでいますが、味は本格的でとても美味しかったです
「手羽元とソボロと五穀米のサムゲタン風」と「生野菜サラダ」です。「サムゲタン風」は本格的な調味料が足りないので「風」と呼んでいますが、味は本格的でとても美味しかったです



 そして、観客はトラヴィスとともに、独り、夜の街を彷徨うことになる
そして、観客はトラヴィスとともに、独り、夜の街を彷徨うことになる
 これは今年の分だけではなく 昨年からの蓄積です
これは今年の分だけではなく 昨年からの蓄積です





 ジョナサンの婚約者であるミナは、ジョナサンとドラキュラ伯爵の間で揺れ動く
ジョナサンの婚約者であるミナは、ジョナサンとドラキュラ伯爵の間で揺れ動く 徐々に心身ともに衰弱していくルーシーの様子を心配した婚約者であるアーサー(ケイリー・エルウィス)は、友人のジャックとクィンシーからこのことを形而上学者のヴァン・ヘルシング(アンソニー・ホプキンス)に相談するよう勧められる
徐々に心身ともに衰弱していくルーシーの様子を心配した婚約者であるアーサー(ケイリー・エルウィス)は、友人のジャックとクィンシーからこのことを形而上学者のヴァン・ヘルシング(アンソニー・ホプキンス)に相談するよう勧められる それからしばらく経ち、ドラキュラ城から脱出したジョナサンはロンドンに戻るが、そこでドラキュラ伯爵もロンドンに渡ってきていたことを知る
それからしばらく経ち、ドラキュラ城から脱出したジョナサンはロンドンに戻るが、そこでドラキュラ伯爵もロンドンに渡ってきていたことを知る


 禁酒はもう完全になし崩しです
禁酒はもう完全になし崩しです

 車好きやスピード狂には堪らない映画でしょう
車好きやスピード狂には堪らない映画でしょう 全国公立文化施設協会(公文協)の22年度の調査によると、公立の劇場や音楽ホールで働く人材は、正規雇用が41.3%、非正規は58.5%だった
全国公立文化施設協会(公文協)の22年度の調査によると、公立の劇場や音楽ホールで働く人材は、正規雇用が41.3%、非正規は58.5%だった


 宛名印刷は数年前からCD-ROMのソフト(住所録を登録済み)を使用しているのでパソコン+プリンタで簡単に出来ます
宛名印刷は数年前からCD-ROMのソフト(住所録を登録済み)を使用しているのでパソコン+プリンタで簡単に出来ます

 先月、長蛇の列に並んで予約を取っておいたものです
先月、長蛇の列に並んで予約を取っておいたものです



 」と言われそうですが、タイガースの日本一に免じてお許しください
」と言われそうですが、タイガースの日本一に免じてお許しください

















 ゲイの友人バース(モンゴメリー・クリフト)も加わり、一行は砂漠へ野馬狩りに出発する
ゲイの友人バース(モンゴメリー・クリフト)も加わり、一行は砂漠へ野馬狩りに出発する 馬と人間の壮絶な闘いを見たロザリンはそれを止めようとする
馬と人間の壮絶な闘いを見たロザリンはそれを止めようとする



 よく考えたら昨夜はクリスマス・イブでした
よく考えたら昨夜はクリスマス・イブでした ちなみに今日=25日が娘の誕生日なので今夜誕生祝いをやります
ちなみに今日=25日が娘の誕生日なので今夜誕生祝いをやります
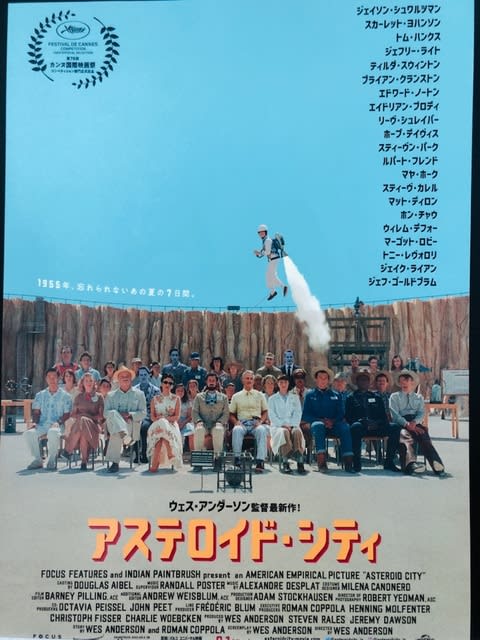








 彼は1990年10月14日に肺癌のため72歳で亡くなりましたが、過度な喫煙が少なからず影響したのは間違いないのではないかと思います
彼は1990年10月14日に肺癌のため72歳で亡くなりましたが、過度な喫煙が少なからず影響したのは間違いないのではないかと思います






 」と思いましたが、確信が持てません
」と思いましたが、確信が持てません 合唱や4人のソリストの歌唱が終わった後の終結部では、弦楽セクションを中心に”死に物狂い”とでも言いたくなるような壮絶な演奏が繰り広げられ、圧倒的なフィナーレを迎えました
合唱や4人のソリストの歌唱が終わった後の終結部では、弦楽セクションを中心に”死に物狂い”とでも言いたくなるような壮絶な演奏が繰り広げられ、圧倒的なフィナーレを迎えました 」ということです
」ということです




