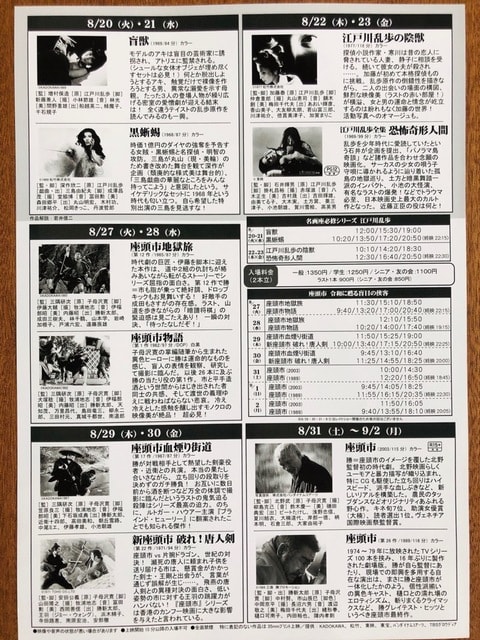9月1日(日)。今日から月9月です。8月にツキがなかった人はツキが変わります。希望を持ちましょう
さて、昨日は久しぶりに陽が射したので、午前中 網戸とガラス戸の清掃をしました 百円ショップで買っておいたミニ箒と網戸用ブラシを活用して外側をきれいにしました
百円ショップで買っておいたミニ箒と網戸用ブラシを活用して外側をきれいにしました 内側はあまり汚れていないので乾拭きで済ませました
内側はあまり汚れていないので乾拭きで済ませました いつもなら徹底的に清掃するのですが、午後にコンサートがあるので体力を温存せねば、と思いセーブしたわけです
いつもなら徹底的に清掃するのですが、午後にコンサートがあるので体力を温存せねば、と思いセーブしたわけです
話は180度変わりますが、昨日からツイッターを始めました ツイッターについてはあまりよく分かっていないのですが、早速「いいね」を一ついただきました
ツイッターについてはあまりよく分かっていないのですが、早速「いいね」を一ついただきました しかし、当然ながら 現在フォロワーはゼロです
しかし、当然ながら 現在フォロワーはゼロです 現在 toraブログのフォロワーは2030人ですが、私がこのブログを立ち上げた8年前の2011年2月15日の時点もゼロでした。何でも最初はゼロからのスタートです
現在 toraブログのフォロワーは2030人ですが、私がこのブログを立ち上げた8年前の2011年2月15日の時点もゼロでした。何でも最初はゼロからのスタートです
ツイッターのアカウント名は tora @tora76730618 です。toraブログ同様よろしくお願いいたします
ということで、わが家に来てから今日で1673日目を迎え、宿題や課題の「読書感想文」について、タブレット端末やスマートフォンなどで電子書籍を読んで書いた場合は、コンクールによっては「紙媒体に限る」と電子書籍の感想文を受け付けないので注意が必要である という記事を読んで感想を述べるモコタロです

そもそも宿題や課題で読書感想文を書かせることが若者の読書離れを促進してる





昨日、東京オペラシティコンサートホールで「アジア・ユース・オーケストラ東京公演2019」第2日目を聴きました プログラムは①リムスキー=コルサコフ「スペイン奇想曲 作品34」、②ブルッフ「ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調」、③リムスキー=コルサコフ:交響組曲「シェヘラザード」です
プログラムは①リムスキー=コルサコフ「スペイン奇想曲 作品34」、②ブルッフ「ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調」、③リムスキー=コルサコフ:交響組曲「シェヘラザード」です 演奏は②のヴァイオリン独奏=服部百音、指揮=リチャード・パンチャスです
演奏は②のヴァイオリン独奏=服部百音、指揮=リチャード・パンチャスです
リチャード・パンチャスは1987年に名ヴァイオリニスト、ユーディ・メニューインと共にアジア・ユース・オーケストラを立ち上げ、1990年から指揮をとってきました ツアーの最終公演はパンチャスが指揮をとることが伝統になっています
ツアーの最終公演はパンチャスが指揮をとることが伝統になっています

自席は1階28列11番、センターブロック左通路側です。会場は前日よりも埋っています
オケは前日同様、左奥にコントラバス、前に左から第1ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、第2ヴァイオリンという対向配置をとります。コンミスは前日の後半と同じ日本人と思われる女性です
1曲目はリムスキー=コルサコフ「スペイン奇想曲 作品34」です この曲はリムスキー=コルサコフ(1844-1908)が1887年に作曲した作品です
この曲はリムスキー=コルサコフ(1844-1908)が1887年に作曲した作品です
パンチャスの指揮で演奏に入りますが、冒頭のクラリネットの演奏が素晴らしかったのが印象に残りました また、コンマスによるヴァイオリン・ソロ、チェロ首席による独奏が冴えていました
また、コンマスによるヴァイオリン・ソロ、チェロ首席による独奏が冴えていました 全体としてはロシア人から見たスペインが色彩感溢れる音楽で表現されていました
全体としてはロシア人から見たスペインが色彩感溢れる音楽で表現されていました
2曲目はブルッフ「ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調」です この曲はマックス・ブルッフ(1838-1920)が1866年に作曲した作品です。第1楽章「前奏曲:アレグロ・モデラート」、第2楽章「アダージョ」、第3楽章「終曲:アレグロ・エネルジコ」の3楽章から成ります
この曲はマックス・ブルッフ(1838-1920)が1866年に作曲した作品です。第1楽章「前奏曲:アレグロ・モデラート」、第2楽章「アダージョ」、第3楽章「終曲:アレグロ・エネルジコ」の3楽章から成ります
ヴァイオリン・ソロを弾く服部百音は1999年生まれの弱冠20歳 内外のコンクールでグランプリを受賞している実力者です
内外のコンクールでグランプリを受賞している実力者です 現在はザハール・ブロン・アカデミー(スイス)に在籍、桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコースに在学中です
現在はザハール・ブロン・アカデミー(スイス)に在籍、桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコースに在学中です
グリーン系の銀のラメ入り衣装で登場した服部百音がステージ中央にスタンバイし、さっそく演奏に入ります 演奏を聴く限り、高音も低音も音がとても綺麗で技術的には完璧です
演奏を聴く限り、高音も低音も音がとても綺麗で技術的には完璧です その上、聴く者を惹きつける力を持っています
その上、聴く者を惹きつける力を持っています 思わず前のめりになって耳を傾けている自分に気が付きます
思わず前のめりになって耳を傾けている自分に気が付きます もし初めてこの曲を彼女の演奏で聴く人がいたら、きっとブルッフのこの曲が好きになることでしょう
もし初めてこの曲を彼女の演奏で聴く人がいたら、きっとブルッフのこの曲が好きになることでしょう
満場の拍手とブラボーに、エルンストの「夏の名残りのバラ」(日本では「庭の千草」として知られている)を、ヴァイオリンを自由自在に操りながら 超絶技巧であっけらかんと演奏し、泣く子を黙らせました 客席の聴衆に止まらず、舞台上の若者たちからもやんややんやの喝采を浴びました
客席の聴衆に止まらず、舞台上の若者たちからもやんややんやの喝采を浴びました 鳴りやまない拍手に、イザイの「無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番」という これまた超絶技巧曲を涼しい顔で演奏し、再び満場の拍手とブラボーを浴び、会場の温度を上昇させました
鳴りやまない拍手に、イザイの「無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番」という これまた超絶技巧曲を涼しい顔で演奏し、再び満場の拍手とブラボーを浴び、会場の温度を上昇させました この際、地球温暖化の問題は無視することにします
この際、地球温暖化の問題は無視することにします とにかく凄い演奏でした
とにかく凄い演奏でした 服部百音は、名前の通り百の音を奏でるアーティストなのではないか、と思ったくらいです
服部百音は、名前の通り百の音を奏でるアーティストなのではないか、と思ったくらいです

プログラム後半はリムスキー=コルサコフ:交響組曲「シェヘラザード」です この曲はリムスキー=コルサコフが1888年に作曲した作品です
この曲はリムスキー=コルサコフが1888年に作曲した作品です 彼は最初、海軍の軍人でした。その経験が海にまつわる作品を作るうえで参考になったと思われます
彼は最初、海軍の軍人でした。その経験が海にまつわる作品を作るうえで参考になったと思われます 第1曲「海とシンドバッドの船」、第2曲「カランダール王子の物語」、第3曲「王子と王女」、第4曲「バグダードの祭り、海、青銅の騎士の立つ岩での難破、終曲」の4曲から成ります
第1曲「海とシンドバッドの船」、第2曲「カランダール王子の物語」、第3曲「王子と王女」、第4曲「バグダードの祭り、海、青銅の騎士の立つ岩での難破、終曲」の4曲から成ります
この曲の大きな特徴は、独奏ヴァイオリンによるシェへラザードのテーマが全曲を統一しており、オリエンタリズムと管弦楽法の妙味が発揮されていることです 独奏ヴァイオリンはコンミスが務めましたが、全体を通して曲趣を弾き分けながら素晴らしい演奏を展開しました
独奏ヴァイオリンはコンミスが務めましたが、全体を通して曲趣を弾き分けながら素晴らしい演奏を展開しました 独奏チェロも良かったと思います
独奏チェロも良かったと思います また、木管楽器が素晴らしく、ファゴットをはじめクラリネット、フルート、オーボエ、ピッコロが冴えた演奏を展開しました
また、木管楽器が素晴らしく、ファゴットをはじめクラリネット、フルート、オーボエ、ピッコロが冴えた演奏を展開しました また第3曲「王子と王女」における弦楽器によるアンサンブルはとても美しく響きました
また第3曲「王子と王女」における弦楽器によるアンサンブルはとても美しく響きました 何より、100人規模によるオケの音は迫力満点で、大きな音の波が客席に押し寄せてくる感じがしました
何より、100人規模によるオケの音は迫力満点で、大きな音の波が客席に押し寄せてくる感じがしました
満場の拍手にパンチャス ✕ AYOはアンコールにリムスキー・コルサコフの「熊蜂の飛行」(オペラ「サルタン皇帝」第3幕に登場する曲)を高速で演奏しましたが、演奏の最中、打楽器の男子数名が蜂を追いかける小芝居を仕掛け、最後に手打ち式ムチ(2枚の板でパチンと音を出す)で蜂を仕留めた音で締め、聴衆の笑いを誘いました
次いで、パンチャスが例年通り、ステージ上のオケのメンバー105人を国別に紹介、国を呼ばれた人はその場で立ち上がり、大きな拍手を受けました 一番多いのは台湾の30人、次いで中国と日本の各14人、香港12人、韓国とフィリピンの各10人という順で、他にインドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナムから参加していました
一番多いのは台湾の30人、次いで中国と日本の各14人、香港12人、韓国とフィリピンの各10人という順で、他にインドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナムから参加していました 政情不安を抱える香港、韓国そして日本のメンバー紹介の時はひときわ大きな拍手が送られました
政情不安を抱える香港、韓国そして日本のメンバー紹介の時はひときわ大きな拍手が送られました コンマスを務めた女子は日本の14人(うち女子13人)の一人でした
コンマスを務めた女子は日本の14人(うち女子13人)の一人でした プログラム冊子に掲載のメンバー表によると、オオキ・ユキコさん、オオツカ・サトリさん、サカモト・リサさんのいずれかです
プログラム冊子に掲載のメンバー表によると、オオキ・ユキコさん、オオツカ・サトリさん、サカモト・リサさんのいずれかです
最後にパンチャスが「AYOのメンバーが香港でのリハーサル・キャンプで最初に取り組んだのはエルガー『エニグマ変奏曲』の『ニムロッド』でした ツアーの最終公演の本日、アンコールにこの曲を演奏します」と説明し、演奏に入りました
ツアーの最終公演の本日、アンコールにこの曲を演奏します」と説明し、演奏に入りました 今や この曲はAYOのテーマミュージックのような存在になっています
今や この曲はAYOのテーマミュージックのような存在になっています つくづく良い曲で、この演奏を最後に 離れ離れになって それぞれの国に帰って行く若者たちの心情を思いながら聴いていたら、思わず熱いものが込み上げてきました
つくづく良い曲で、この演奏を最後に 離れ離れになって それぞれの国に帰って行く若者たちの心情を思いながら聴いていたら、思わず熱いものが込み上げてきました
AYOの皆さん、素晴らしい演奏をありがとう 来年も厳しいオーディションを通過して、この会場に戻ってきてください。必ず聴きに行きます
来年も厳しいオーディションを通過して、この会場に戻ってきてください。必ず聴きに行きます













 月日の流れの速さを感じる昨今です
月日の流れの速さを感じる昨今です







 というのは、彼が帽子を脱いで被り直したのが目に入ったからです
というのは、彼が帽子を脱いで被り直したのが目に入ったからです このホールに限らず、どこの会場でも演奏前に帽子を被っている人がいると、会場の係員が傍まで行って帽子を脱ぐように注意しています
このホールに限らず、どこの会場でも演奏前に帽子を被っている人がいると、会場の係員が傍まで行って帽子を脱ぐように注意しています 幸いなことに、爺さんは7~8月の「フェスタサマーミューザ」にはお越しにならなかったようで、一度もお会いしませんでした
幸いなことに、爺さんは7~8月の「フェスタサマーミューザ」にはお越しにならなかったようで、一度もお会いしませんでした







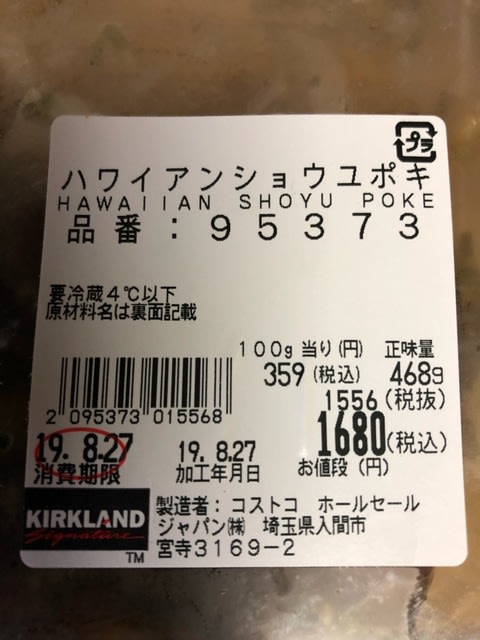


 清水氏が佐々木氏をつかまえて、「私はどうもバッハが苦手で、弾いているうち心が不安定になってくるんですよ
清水氏が佐々木氏をつかまえて、「私はどうもバッハが苦手で、弾いているうち心が不安定になってくるんですよ 私のように感情の起伏が激しい者にはバッハは向かないのかも知れないですね
私のように感情の起伏が激しい者にはバッハは向かないのかも知れないですね

 1964年の東京オリンピックの開会式では、この基地から飛び立った「ブルーインパルス」が5色の煙で東京の空に五輪のマークを描きました
1964年の東京オリンピックの開会式では、この基地から飛び立った「ブルーインパルス」が5色の煙で東京の空に五輪のマークを描きました


 中山七里の本は文庫化されるたびに当ブログで紹介してきました
中山七里の本は文庫化されるたびに当ブログで紹介してきました



 果たして山ちゃんはボクシングではしずちゃんに勝てなくても 文章力では勝てるでしょうか
果たして山ちゃんはボクシングではしずちゃんに勝てなくても 文章力では勝てるでしょうか
 もはやこれまでか となったところで、善吉が助け舟を出す(第1章)。中学2年の雅彦は太一とは正反対で、暴力には暴力で対抗するため、いつしか最強の一匹狼的な存在になっていた
もはやこれまでか となったところで、善吉が助け舟を出す(第1章)。中学2年の雅彦は太一とは正反対で、暴力には暴力で対抗するため、いつしか最強の一匹狼的な存在になっていた それから8年後、史親と善吉が眠る墓の前で太一と刑事・宮藤が顔を合わせる。太一は宮藤に、8年前の火災の原因は何だったのかを語る(第5章)
それから8年後、史親と善吉が眠る墓の前で太一と刑事・宮藤が顔を合わせる。太一は宮藤に、8年前の火災の原因は何だったのかを語る(第5章) 毎日最低8000歩 歩くことを目標にしてから自転車に乗る機会がめっきり減り、この1年間は一度も乗りませんでした
毎日最低8000歩 歩くことを目標にしてから自転車に乗る機会がめっきり減り、この1年間は一度も乗りませんでした




 すると、第2、第3の犠牲者が発生し、町はたちまちパニックに陥る
すると、第2、第3の犠牲者が発生し、町はたちまちパニックに陥る



 一方、「いいえ」の理由は「調理作業が面倒」(496人)、「料理が下手」(316人)、「他の人が作ってくれる」(273人)、「献立を考えるのが面倒」(254人)、「食材をそろえるのが面倒」(219人)がトップ5になっています
一方、「いいえ」の理由は「調理作業が面倒」(496人)、「料理が下手」(316人)、「他の人が作ってくれる」(273人)、「献立を考えるのが面倒」(254人)、「食材をそろえるのが面倒」(219人)がトップ5になっています


 」と非難されそうですが、あらためて自分の無知蒙昧さに呆れています
」と非難されそうですが、あらためて自分の無知蒙昧さに呆れています

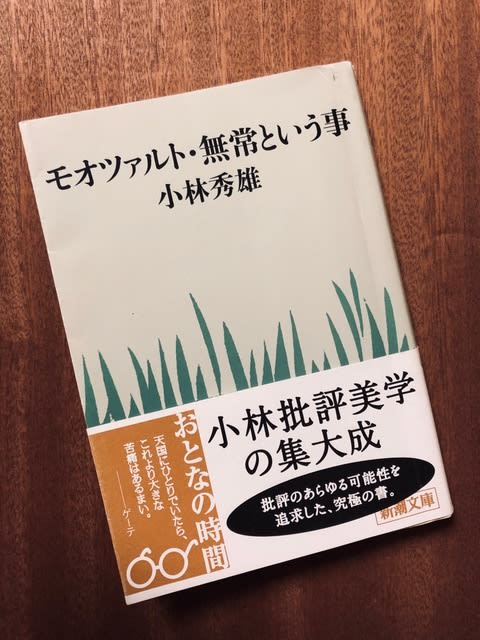




 タロイモを採り、丸木舟で海に出て魚を獲る、のどかな島の暮らしがある
タロイモを採り、丸木舟で海に出て魚を獲る、のどかな島の暮らしがある




 静子が物音がしたという小山田邸の天井裏を探ってみると誰かが這いまわったような跡があり、飾りボタンが一つ落ちていた。寒川は春泥の足取りを探る。そして、寒川の担当編集者で一度だけ春泥と面識のある本田(若山富三郎)は浅草でピエロ姿の春泥を見たと言い出したが、全く彼の足取りはつかめなかった
静子が物音がしたという小山田邸の天井裏を探ってみると誰かが這いまわったような跡があり、飾りボタンが一つ落ちていた。寒川は春泥の足取りを探る。そして、寒川の担当編集者で一度だけ春泥と面識のある本田(若山富三郎)は浅草でピエロ姿の春泥を見たと言い出したが、全く彼の足取りはつかめなかった