30日(月)。月日の流れは速いもので今日で11月も終わりです。ということで、昨夜もゲージからなかなか出てこず自分の陣地に立てこもる、わが家に来てから429日目を迎えたモコタロです

モコタロ~ 周りは警察官に囲まれている 観念して出てこ~い

 閑話休題
閑話休題 

昨日、上野の東京藝大奏楽堂で東京藝大「ブラームス室内楽の喜び 第4回」公演を聴きました プログラムはブラームスの①ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調、②チェロ・ソナタ第2番ヘ長調、③ハンガリー舞曲集第1集から第17番~第21番、④ピアノ五重奏曲ヘ短調です
プログラムはブラームスの①ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調、②チェロ・ソナタ第2番ヘ長調、③ハンガリー舞曲集第1集から第17番~第21番、④ピアノ五重奏曲ヘ短調です

午後3時開場ですが、全自由席のため1時間前の2時に会場に着きました。楽勝で1番乗りか、と思いきや、何とすでに80人くらいの人が並んでいました それでも1階7列13番、センターブロック左通路側席を押さえることが出来ました。会場はほぼ満席です
それでも1階7列13番、センターブロック左通路側席を押さえることが出来ました。会場はほぼ満席です
最初の「ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調」はヴァイオリン=東京藝大演奏藝術センター准教授の野口千代光、ピアノ=東京藝大准教授の東誠三です 第1楽章「アレグロ」、第2楽章「アダージョ」、第3楽章「ウン・ポコ・プレスト・エ・コン・センティメント」、第4楽章「プレスト・アジタート」から成りますが、第1楽章の冒頭が演奏されたとき「ああ、ブラームスは良いなあ
第1楽章「アレグロ」、第2楽章「アダージョ」、第3楽章「ウン・ポコ・プレスト・エ・コン・センティメント」、第4楽章「プレスト・アジタート」から成りますが、第1楽章の冒頭が演奏されたとき「ああ、ブラームスは良いなあ 」と思いました。ヴァイオリンは美しい音で旋律を奏でています
」と思いました。ヴァイオリンは美しい音で旋律を奏でています ピアノもぴったり付けています。ブラームスはこの曲をスイスのトゥーン湖畔で作曲に着手したそうです。プログラムにその湖の写真が載っていますが、非常に美しいところです
ピアノもぴったり付けています。ブラームスはこの曲をスイスのトゥーン湖畔で作曲に着手したそうです。プログラムにその湖の写真が載っていますが、非常に美しいところです こういう場所でブラームスは名曲を作ったのだな、と感じ入りました
こういう場所でブラームスは名曲を作ったのだな、と感じ入りました
2曲目の「チェロ・ソナタ第2番ヘ長調」はチェロ=藝大教授の河野文昭、ピアノ=同じく藝大教授でソリストとしても活躍している伊藤恵です この曲は第1楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」、第2楽章「アダージョ・アッフェットゥーソ」、第3楽章「アレグロ・パッショナート」、第4楽章「アレグロ・モルト」から成ります
この曲は第1楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」、第2楽章「アダージョ・アッフェットゥーソ」、第3楽章「アレグロ・パッショナート」、第4楽章「アレグロ・モルト」から成ります
第1楽章冒頭は伊藤恵のピアノから入りますが、気合が入っています すぐに河野文昭のチェロが入りますが、このチェロが素晴らしい
すぐに河野文昭のチェロが入りますが、このチェロが素晴らしい 何回かこの人の演奏を奏楽堂で聴いていますが、明るく明快なチェロで、演奏に安定感があります
何回かこの人の演奏を奏楽堂で聴いていますが、明るく明快なチェロで、演奏に安定感があります 伊藤恵との相性もぴったりです。こういう演奏でブラームスを聴くと、「やっぱりブラームスは室内楽だよね
伊藤恵との相性もぴったりです。こういう演奏でブラームスを聴くと、「やっぱりブラームスは室内楽だよね 」と言いたくなります。第3楽章が終わると、曲全体が終わった印象があるので、普通のコンサート会場だと、間違えてフライングの拍手が起こるところですが、藝大奏楽堂でのコンサートは耳の肥えた聴衆が揃っているのか、席が早い者勝ちのため早めに来てプログラムを読んでこの曲が4楽章から成ることを”予習”しているせいか、ただの一人もフライングがありません
」と言いたくなります。第3楽章が終わると、曲全体が終わった印象があるので、普通のコンサート会場だと、間違えてフライングの拍手が起こるところですが、藝大奏楽堂でのコンサートは耳の肥えた聴衆が揃っているのか、席が早い者勝ちのため早めに来てプログラムを読んでこの曲が4楽章から成ることを”予習”しているせいか、ただの一人もフライングがありません そのあとの第4楽章のフィナーレは圧巻でした
そのあとの第4楽章のフィナーレは圧巻でした

休憩後の最初は、「ハンガリー舞曲集」から第17番~第21番が、藝大非常勤講師の伊藤わか奈と同じく佐々木崇のピアノ連弾で演奏されました ブラームスの時代には、コンサート会場で演奏される交響曲などの大曲よりも、このような家庭で演奏できる小曲が人気を博したようですね
ブラームスの時代には、コンサート会場で演奏される交響曲などの大曲よりも、このような家庭で演奏できる小曲が人気を博したようですね
さてコンサートを締めくくるのは「ピアノ五重奏曲ヘ短調」です。演奏は第1ヴァイオリン=藝大准教授で紀尾井シンフォ二エッタでも活躍中の玉井菜採、第2ヴァイオリン=藝大大学院在学中の三輪莉子、ヴィオラ=藝大准教授の市坪俊彦、チェロ=河野文昭、ピアノ=ザルツブルク・モーツアルテウム大学教授のジャック・ルヴィエです
この曲は、最初は弦楽五重奏曲として作曲されましたが、破棄され、2台のピアノ版に改訂されました。そして、最終的にピアノ五重奏曲として完成されたものです ブラームス自身がこの曲を「演奏が難しい作品の一つ」と述べているとおり、かなりの実力者ぞろいでないと弾きこなせない曲です
ブラームス自身がこの曲を「演奏が難しい作品の一つ」と述べているとおり、かなりの実力者ぞろいでないと弾きこなせない曲です 第1楽章「アレグロ・ノン・トロッポ」、第2楽章「アンダンテ・ウン・ポコ・アダージョ」、第3楽章「スケルツォ」、第4楽章「フィナーレ」から成ります。第1楽章の有名なテーマが演奏されると、「ああ、ブラームスだなあ
第1楽章「アレグロ・ノン・トロッポ」、第2楽章「アンダンテ・ウン・ポコ・アダージョ」、第3楽章「スケルツォ」、第4楽章「フィナーレ」から成ります。第1楽章の有名なテーマが演奏されると、「ああ、ブラームスだなあ 」と思います。そして第3楽章のスケルツォを聴くと、すごい推進力だなあと感心します
」と思います。そして第3楽章のスケルツォを聴くと、すごい推進力だなあと感心します もちろん第4楽章のフィナーレは感動的です
もちろん第4楽章のフィナーレは感動的です
これだけの演奏が3,000円で聴けるのですから東京藝大の一連のコンサートはありがたいです とにかく生演奏至上主義の私にとってはコストパフォーマンスの高いコンサートです。これからも安くて質の高いコンサートに期待したいと思います
とにかく生演奏至上主義の私にとってはコストパフォーマンスの高いコンサートです。これからも安くて質の高いコンサートに期待したいと思います














 来週水曜日(2日)午前10時からの部です。左ブロック後方の右通路側席を押さえました
来週水曜日(2日)午前10時からの部です。左ブロック後方の右通路側席を押さえました


 楽器編成を見るとヴィオラのほかに、ヴァイオリン、チェロ、フルート、クラリネット、ティンパ二、スネア・ドラム、テナー・ドラム、カスタネット、マラカス、チェレスタと、合計11の楽器があります。6つの楽器というのはティンパ二以外の打楽器をまとめて1つとして数えているのではないかと思われます
楽器編成を見るとヴィオラのほかに、ヴァイオリン、チェロ、フルート、クラリネット、ティンパ二、スネア・ドラム、テナー・ドラム、カスタネット、マラカス、チェレスタと、合計11の楽器があります。6つの楽器というのはティンパ二以外の打楽器をまとめて1つとして数えているのではないかと思われます 音楽評論家の奥田佳道氏の解説によると「限定された音素材を弱音で奏し、それらを編み合わせ、反復させるスタイル」という音楽で、耳を澄ませて聴いたところでは、「四谷怪談」とでもタイトルを付けたくなるような、静かで、ちょっとゾッとするような曲想です
音楽評論家の奥田佳道氏の解説によると「限定された音素材を弱音で奏し、それらを編み合わせ、反復させるスタイル」という音楽で、耳を澄ませて聴いたところでは、「四谷怪談」とでもタイトルを付けたくなるような、静かで、ちょっとゾッとするような曲想です
 印象に残るのは第2楽章「アレグロ」で、全体的に民族的とでもいうような曲想ですが、ときにストラヴィンスキーの「春の祭典」のようなバーバリズムが聴こえてきます
印象に残るのは第2楽章「アレグロ」で、全体的に民族的とでもいうような曲想ですが、ときにストラヴィンスキーの「春の祭典」のようなバーバリズムが聴こえてきます そして第4楽章のアレグロ・モルトは弦楽器、打楽器、チェレスタが民族的な舞曲を賑やかに繰り広げ、圧倒的なフィナーレに突入します
そして第4楽章のアレグロ・モルトは弦楽器、打楽器、チェレスタが民族的な舞曲を賑やかに繰り広げ、圧倒的なフィナーレに突入します
 このブログの読者・ゆえさんはこの曲が大好きですが、私も昔から、あまりにも有名な第9番”新世界より”よりもこの第8番の方が好きでした
このブログの読者・ゆえさんはこの曲が大好きですが、私も昔から、あまりにも有名な第9番”新世界より”よりもこの第8番の方が好きでした
 ときに弦楽器の美しいメロディーを消してしまうことがあり、もう少し管楽器を抑え気味にした方が良いのではないかと思いました
ときに弦楽器の美しいメロディーを消してしまうことがあり、もう少し管楽器を抑え気味にした方が良いのではないかと思いました
 この日はオペラシティ地下1階のロッテリアで250円のコーヒーをテイクアウトして会場に持ち込みました
この日はオペラシティ地下1階のロッテリアで250円のコーヒーをテイクアウトして会場に持ち込みました 休憩時間はチラシの選別に忙しいので飲みません
休憩時間はチラシの選別に忙しいので飲みません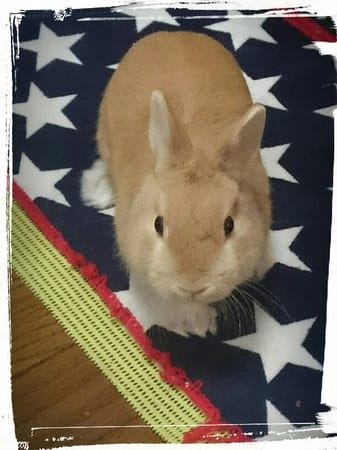





 プログラムは①メンデルスゾーン「弦楽のためのシンフォニアより」、②モーツアルト「フルート協奏曲第1番k.313」、③メンデルスゾーン「交響曲第4番”イタリア”」です
プログラムは①メンデルスゾーン「弦楽のためのシンフォニアより」、②モーツアルト「フルート協奏曲第1番k.313」、③メンデルスゾーン「交響曲第4番”イタリア”」です






 深代惇郎は1929年東京生まれ。東大法学部卒業後、53年に朝日新聞社入社。ロンドン、ニューヨーク各特派員、ヨーロッパ総局長などを経て、73年に論説委員となる。同年2月15日から75年11月11日、入院するまで朝日新聞1面コラム「天声人語」を執筆、同年12月17日に急逝骨髄性白血病のため死去。享年46.
深代惇郎は1929年東京生まれ。東大法学部卒業後、53年に朝日新聞社入社。ロンドン、ニューヨーク各特派員、ヨーロッパ総局長などを経て、73年に論説委員となる。同年2月15日から75年11月11日、入院するまで朝日新聞1面コラム「天声人語」を執筆、同年12月17日に急逝骨髄性白血病のため死去。享年46.







 女の正体をつかむため彼女の郷里に赴くが、女は何者かによって殺されている。今度は殺人犯として追われる立場になる
女の正体をつかむため彼女の郷里に赴くが、女は何者かによって殺されている。今度は殺人犯として追われる立場になる

 最後には追う側と追われる側とが手を組んで真犯人を追い詰めることになりますが、新宿の街を馬で疾走するシーンを見て、いったいどこからあんなに多くの馬が出てきたんだろうか、と考えてしまいました
最後には追う側と追われる側とが手を組んで真犯人を追い詰めることになりますが、新宿の街を馬で疾走するシーンを見て、いったいどこからあんなに多くの馬が出てきたんだろうか、と考えてしまいました



 」と言います。お皿に盛りつける時にどうやら鶏肉だけが偏ってしまったようです。今回の教訓は”料理は盛り付けが終わるまで続く”ということです
」と言います。お皿に盛りつける時にどうやら鶏肉だけが偏ってしまったようです。今回の教訓は”料理は盛り付けが終わるまで続く”ということです






 息子はいつもよりワインを飲みすぎて、ろうそくの火を消して、ケーキを食べずベッドで寝入ってしまいました。おいおい、誰の24歳の誕生日だよ
息子はいつもよりワインを飲みすぎて、ろうそくの火を消して、ケーキを食べずベッドで寝入ってしまいました。おいおい、誰の24歳の誕生日だよ 

 」と思うのは第4楽章のアレグロ・アラ・ポラッカです。舞曲ですね
」と思うのは第4楽章のアレグロ・アラ・ポラッカです。舞曲ですね



















